traces





|
|---|
| �p����5�l�̌��z�Ɓ|�n���I�ȗ��j�� Five British Architects �g�����������i�[�̌ǓƁh�g�y�j�̖�Ɠ��j�̒��h�g�g���E�W���[���Y�̉ؗ�Ȗ`���h�g�~�]�h�A �f����ώn�߂�����̂��̂���A�C�M���X�f�悪���炭���͓I�������B �g�~�]�h�� �ē̓C�^���A�l�̃~�P�����W�F���E�A���g�j�I�[�j�����A����̓C�M���X�A�o�D���C�M���X�l�������B ���̂R�̊ē̓g�j�[�E���`���[�h�\���ŁA���̒��̓�Ɏ剉���Ă����A���o�[�g�E�t�B�j�[�����ɍD���������B �f��̒��̃C�M���X�́A�Ɠ��̕��i���A�����Đl���A�V�N�ɖ��͓I�ɉf�����B ��w�ɓ����āA�������z�̂��Ƃ�m��n�߁A�����o�������A�C�M���X����W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�Ƃ������z�Ƃ��䓪���Ă��āA �ǂ������E�̌��z���ς�낤�Ƃ��Ă���炵���A�Ƃ������Ƃ��킩���Ă����B��������A�A�����J����̓��C�X�E�J�[�����䓪���Ă��Ă����B �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�̔����I�O�̉p���ɂ́A���ă}�b�L���g�b�V���A���b�`�F���X�����āA�����Ă���ɔނ��100�N�O�ɂ̓\�[���A �܂�����100�N�O�ɂ̓z�[�N�X���[�A�Ƃ�����ɁA�Ƒn�I�Ȍ��z�Ƃ��ق�100�N�����Ɍ���A���ꂼ����ʂ̌�����A���قȌ��z�������Ă����B | �X�^�[�����O�A���b�`�F���X�A�}�b�L���g�b�V���A�\�[���A�z�[�N�X���[�A�̂T�l�́A ���̐���������w�i�ɋ����e�����A���̃R���e�N�X�g�̓��ɂ��Ȃ���A�����̉e���̒�����ł��l�I�ŁA �Ƒn�I�ȃX�^�C���W�����A���ꂼ��̎���̘g��傫�����������z�Ƃ������B ����͊u�����Ă��Ă��A�ނ�ɋ��ʂ��Ă���̂́A���z�̌`�Ԃ̃Q�[�����y���ޏ_�炩���m�I�Ȏp���ł���A ���ɔ�߂��G�N�Z���g���V�e�B�ŁA���̌��z�͍������ʂȌ�������Ă���B �ނ�݂͂ȁA�`�ԂɊւ��錚�z�̗��j�ɂ��Ă̋��{��������A �g�n���I�ȗ��j�Ɓh�ł������B����́A�܂������ɂ߂ăC�M���X�I�ŁA���[���b�p�̑��̍�����͂����������z�Ƃ����͏o�Ȃ������̂ł͂Ȃ����Ǝv����B �p���̂S�l�̌��z�Ƃɂ��āA1976�N�`2006�N�� ���\�����L�����A�Ę^���A���M�A�ҏW�A�����Ă���ɉp���֍s�������Ǝv�����|���ɂȂ����W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�ɂ��āA �V���ɏ����������B -���z�Ƃ̏ё����N���b�N����Ƃ��̌��z�Ƃ̍��ɃW�����v���܂��B- |

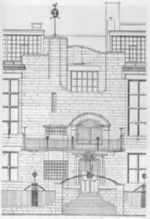


|
|
|---|---|
�W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�����{�ɗ����Ƃ��A�V���|�W�E���̂��Ƃ̃p�[�e�B�[�ł̎���ɓ����āA �p�����z�̓������g�G�N�Z���g���V�e�B�h�Ƃ������t�ŗv�����Ƃ��������B �ނ��z�肵�Ă��錚�z�Ƃ́ARIBA�̃S�[���h�E���_�������ŁA�e�������ƌ������Ă���A ���@���u���A�z�[�N�X���[�A�A�\�[���A�����ă}�b�L���g�b�V���� �A�ł��p���I�Ȍ��z�Ƃ������낤�B�X�^�[�����O�̃��X�g�ɂ͂Ȃ��A���b�`�F���X���A�����ɓ��R�܂߂����Ƃ��낾�B ���Ƃ��z�[�N�X���[�A�̃X�s�g���t�B�[���Y�̃N���C�X�g�`���[�`�B�i���}���j���̋���́A�����h���̑��̋���̃X�P�[���� ���S�ɒ��z���A�펯�I�Ȕ�ኴ�o�����킹��A�֑�ϑz���I�t�@�T�[�h�����Ă���B������ ���j�I���̌`�ԃ��`�[�t���A�܂������Ɠ��̑g�ݍ��킹�ň�ɂȂ��Ă���B ����ȃ��F�l�c�B�A���E�E�C���h�E��S�V�b�N�̐듃�����p����A�X�^�[�����O�̌����A�h�z�b�N�ȃe�N�j�b�N�B ���邢�͂܂��W�����E�\�[�������ق̓����́A�����ȃX�P�[���̂�������l�܂����A�����|�ǓI��ԍ\���B�i���}���j | ���A�ʖʋ��A�X�J�C���C�g�A�K���X�u���b�N�̏��A���܂�����ꂽ���A�l�X�Ȏd�|�������ݏo���A��Ԃ̍����I���ʁB �s�[�^�[�E�N�b�N�͉p���̌��z�Ƃ̓������g�N�E�F�C���ƃl�X�h�ƌ������t�Ō`�e���A�g�������A��{�I�ȃA�C�f�B�A����������܂킵�A ���̒����疳���ׂ̍������@���G�[�V�������Ђ˂�o���A���l�Ȏ}�t��n��o�����Ƃ��y���ށB���̓����������̕��ʍ\���� ���p�����Ƃ��A�����ɐ��܂��̂́A�f�B�e�[���ɂ�����ɓx�̍I�����ł���\���Ƃ��S�̂͒��̂܂܂ł������Ƃ��Ă��h�Ƃ����B �e�B���H���̃��F�X�^�̐_�a�ƌĂ��Ñネ�[�}�̉~�`�_�a�����p���āA�����}���e�̓T���E�s�G�g���E�C���E�����g���I�̑m�@�� �P�T�O�Q�N�g�e���s�G�b�g�h�����Ă��B����͈��p�ƌ����Ă��T�}�[�\�����ɂ��Ƃނ��냍�[�}����ؗp�������O�́g�g���h�ł���A ���ꎩ�́A�Ǝ��̊����i�ł���B ���̃e���s�G�b�g�́A�p���f�B�I�̌��z�l����ʂ��Ĉ��̌ÓT���`�[�t�ƂȂ�A�p���̌��z�Ƃ����Ɏg��ꂽ�B |



|
|
|---|---|
|
�Ⴆ�I�b�N�X�t�H�[�h�ɂ���W�F�[���Y�E�M�b�u�X��
���h�N���t�E�L�������A�N���X�g�t�@�[�E�����ɂ��Z���g�E�|�[���吹���̃h�[���ɂ����p����Ă���B
�\�[���̃C���O�����h��s�̈ꕔ�ɂ����̃��`�[�t���g�����A�e�B���H���E�R�[�i�[�Ƃ�����p������B
�����ăz�[�N�X���[�A�́A���̃��`�[�t���g���āA���[�N�ߍx�̃L���b�X���E�n���[�h�ɓƑn�I�ȗ�_���[�\���E����v�����B
���̊Ԋu�͖��ɂȂ�A�h�[���͎��k����ĒႭ�}�����Ă���A��d�����������ɍL�����ĒႭ�����B �ÓT�����p���Ȃ�������ȑ���������A�Ǝ��̌��z�ɂ܂ō��߂Ă���B �V�����`�Ԃ̑n�o�Ƃ������A�V���Ȍ`�Ԃ̗p�@�̑n�o�Ƃ����A�T�}�[�\���̌������z�Ƃ̖����B�Ɏ����Ă���B ���̐▭�̃v���|�[�V�������A�f���炵���L��ȕ~�n�̗ƁA���[�N�x�O�̋�̍L����̒��ŁA��捂ɉ�������Ă���B�i��}�E�j | ���F�X�^�̐_�a�̑��ɂ��p���f�B�I�̃��`�[�t�̌��z���A�p���ɂ͂���������B �A���O���E�p���[�f�B�A���E���B���ƌĂ��1700�N��ɗ��s���������������B���̒��ŁA���E���g���_�����`�[�t�ɂ����A �����h���̃`�Y�E�B�b�N�E�n�E�X���܂��s�v�c�ȕ��͋C�������Ă��Ĉ�ۓI�������B �m�I�ȗV�т��������A����炻���͂��ƂȂ��ςŁA�p���I�G�N�Z���g���V�e�B�̓������ł������o�Ă���B �ÓT�����`�[�t�ɂ��Ă��Ȃ���A�C��n���ĉp���Ō��z�����ƁA�Ɠ��̖��t�����Ȃ���A���T�Ƃ͏������ꂽ���͋C��g�ɒ�����A�N���� ������g�V�[�E�`�F���W�h�ƌ`�e���Ă����B ���ꂪ�s�[�^�[�E�N�b�N�̌����g�N�E�F�C���g�l�X�h�Ƃ����`�e�ɓ��Ă͂܂�A���邢�͂܂��X�^�[�����O�̌��� �g�G�N�Z���g���V�e�B�h���߂��▭�̌`�ԑ���ł���A�V���Ȍ`�Ԃ̗p�@�̑n�o�Ƃ������Ƃ�������Ȃ��B |
 | ||
|---|---|---|
|
�W�F�[���Y�E�X�^�[�����O���A�S���Ȃ鏭���O�ɐv���A����5�N��Ɋ�������������No.1�|�E���g���[�Ƃ����̂�����B �I�t�B�X�ƓX�܁A���X�g�����������������r���ŁA�����h���̒��S�A�o���N�w�̐^��Ɍ����Ă���̂����A �������������ɂ́A���b�`�F���X�̃~�b�h�����h��s�A���̐�̓\�[���̃C���O�����h��s�A ��������ăz�[�N�X���[�A�̃Z���g�E���A���[�E�E�[���m�X����o���Ă���B �O���X�S�[�Ŋ����}�b�L���g�b�V���������A�Ȃ�ƃz�[�N�X���[�A�A�\�[���A���b�`�F���X�A�X�^�[�����O�̌��z�������ɑ����Ă���B |
���ꂼ��̊����N�́A�Z���g�E���A���[�E�E�[���m�X��1724�N�A�C���O�����h��s��40�N�߂���������1826�N���A�~�b�h�����h��s�͂����炭1920�N��A
�Ƃ��傤�ǖ�100�N���̊Ԋu�A������No.1�|�E���g���[���A��70�N�̊Ԋu�̌�A1997�N�Ɋ������Ă���B ����ɁA�z�[�N�X���[�A�̎t�������̃Z���g�E�X�e�t�@���E�E�H���u���b�N����A �\�[�����傫�ȉe�������F�l�̃_���X2���̕��_���X�P���ɂ��}���V�����n�E�X�܂ł������߂ɂ���B �p���̌��z�̗��j�̏k�}���A���������ɑ��݂��Ă���Ƃ����A�Ȃ�Ƃ��s��Ȃ��ƂɂȂ��Ă���ꏊ�ł���B | |
| �ڎ� �T.SIR JAMES FRAZER STIRLING�@(1926�`1992) �X�^�[�����O�\�u���e�B�b�V���E���_�����삯���������z�Ɓ\ �P�D�X�^�[�����O�̃X�^���X �Q�D�r�[�g���Y�ƃX�^�[�����O �R�D��w�V���[�Y�R���� �S�D�����^�[�W���H�@ �T�D����Ɍb�܂�Ȃ����� �U�D�h�C�c�̔��p�كV���[�Y�R���� �V�D�R���e�N�X�g�� �W�D�V���g�D�b�g�K���g���p�وȍ~ �X�D�e���������z�� �U.SIR EDWIN LANDSEER LUTYENS(1869-1944) ���b�`�F���X�̃J���g���[�E�n�E�X�\�����ƉI��\ �P�D���@�i�L�����[�E�A�v���[�` �Q�D�ΏƓI�ȓ�l �R�D�}���X�e�b�h�E�E�b�hMUNSTEAD WOOD�@1893-1897 �S�D���E�{���E�f�E���`�GLE BOIS DE MOUTIERS 1898 �T�D�S�_�[�YGODDARDS 1898-1899 �U�D�e�B�O�{�[���E�R�[�gTIGBOURNE COURT 1899-1901 �V�D�f�B�[�i���[�E�K�[�f��Deanary Garden 1899-1902 �W�D�O���C�E�E�H�[���Y GREYWALLS 1901 �X�D�z�[���E�b�h Homewood 1901 �P�O�D���g���E�Z�C�J��Little Thakeham 1902 �P�P�D�����f�B�X�t�@�[���E�L���b�X��Lindisfarne Castle 1903 �P�Q�D�p�s�����E�z�[��Papilon Hall 1903-1904 �P�R�D�q�[�X�R�[�gHeathcote 1905-1907 �P�S�D�U�E�T���e�[�V����THE Salutation 1911 �P�T�D�O���[�g�E�f�B�N�X�^�[Great Dixter 1912 �P�U�D�v�����v�g���E�v���[�XPlumpton Place 1928 �P�V�D���b�`�F���X�̐v��@ �V.CHARLES RENNIE MACKINTOSH(1868�`1928) �}�b�L���g�b�V���\���㐸�_�̎�@���\ �P�D�����̂ւ̎��� �Q�D�`�Ԃ̗p�@ �R�D�O���X�S�[���p�w�Z�R���y �S�DLet function dictate �T�D���p�w�Z2���H���� �U.�P��I�ȋ��x�� �V�D�}���� |
�W.SIR JOHN SOANE(1753�`1837) �W�����E�\�[���������ف\����܂ʈ�E�\ �P�D�����h���̊X���� �Q�D�W�����E�\�[���������� �R�D���z�ƃ\�[���̌`���ߒ� �S�D���H��-the poetry of architecture �T�D�_���b�`�E�A�[�g�E�M�������[-lumiere mysterieuse �U�D�h�[���|�\�[�����Ǝ��̑��� �V�D�\�[������w�Ԃ��Ɓ|���I�v���|�[�V���� �X.NICHOLAS HAWKSMOOR(1661�`1736) �j�R���X�E�z�[�N�X���[�A�\���[�}�ւ̓��ہ\ �P�D�L���b�X���E�n���[�h �Q�D�u���j���E�p���X �R�D�����h���̂U�̋��� �S�D�L���b�X���E�n���[�h�̃��[�\���E�� �ԊO-Carlo Scarpa�i1908-1978�j �N�F���[�j�E�X�^���p�[���A�̕��� ���o ��NICE SPACE �O���X�S�[���p�w�Z�`�����̂ւ̎����`�@ SD1976.3 ���p����3�l�̌��z�Ƒ� �`�z�[�N�X���[�A�A�\�[���A�}�b�L���g�b�V���̋��߂���ԁ`�J����62�� 1976.10 �����㐸�_�̎�@���i�}�b�L���g�b�V���@��Ԃ̎��w�j�@���p�蒠 �@ 1979.5 �����z�ƃ}�b�L���g�b�V���@���͏��[ 1980.10 �����b�`�F���X�̌��z�@�J����88�� 1983.4 ���W�����E�\�[���������ف`����܂ʈ�E�`�@�J����98�� 1985.10 ���j�R���X�E�z�[�N�X���[�A�`���[�}�ւ̓��ہ` �J����110�� 1988.10 ���S�Ɏc��܂��Ȃ�23�@�����h���@�ƂƂ܂��Ȃ݂T�S���@2006.9 |
| �T.JAMES STIRLING(1926�`1992) �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�|�u���e�B�b�V���E���_�����삯���������z�Ɓ\ �P�D�X�^�[�����O�̃X�^���X �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�́A�T�[�̏̍������^���ꂽ12����A�P�X�X�Q�N�U���Q�T���A��Î��̂łɖS���Ȃ����B�U�U�������B �v��U�N�o���āA�ނ̒���W���C�^���A�ŏo�ł��ꂽ�̂����A�����o�ʼn�̋g�c����̈˗��ŁA�|��@����B ���̖{�́g�W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�|�u���e�B�b�V���E���_�����삯���������z�Ɓh�Ƃ����^�C�g���łQ�O�O�O�N�X���ɏo�ł��ꂽ�B �]�k�����A�C�^���A�̖{�Ɠ����N�A�X�L�����_���X�Șb����܂�"�r�b�O�E�W��"�Ƃ����`�L�{���C�M���X�ŏo�ł���Ă���B ����W��|�Ă݂āA�R�U�N�ɂ킽�錚�z�ƂƂ��Ă̊������Ԃ̂��ɁA��i����ȊO�̕��͂́A�ӊO�ɏ��Ȃ��������B ������قƂ�ǂ����g�̌��z�ɂ��āA�ׂ��ȃv���O�����A�R���e�N�X�g�A�ǂ������������Ƃ����悤�Ȑ����ɏI�n���Ă���B �܂�́A�X�^�[�����O���O�ꂵ���g�����̐l�h�ł��������������Ă���B 
|
���ł́A�R�O��O���ɏ����ꂽ �g���B���E�K���V�F����W���E�[���@�� �|�P�X�Q�V�N�ƂP�X�T�R�N�̏Z���� ���E�R���r���W�G�h(1955) �g�����V�����| ���E�R���r���W�G�̗�q���ƍ�����`�̊�@�h(1956) �Ƃ������E�R���r���W�G�ɂ��Ă̓�̃G�b�Z�C���炢����O�ŁA���̓�́A �����@�v�[����w�̎��̎t�ł���A�F�l�ł�����R�����E���E�́g���z�I���B���̐��w�h��f�i�Ƃ�����B ����Ƀ��X�^�[��w�H�w�����Ő��E�I�ɃX�^�[�����O�̖��O���m��n��O�́g�t�@���N�V���i���E�g���f�B�V�����ƕ\���h�܂ł́A �R�O��ɏ����ꂽ���͂�ǂނƁA �X�^�[�����O�Ƃ������z�Ƃ̍���ɂ���������S�̃X�^���X�́A�Ⴂ�����玀�ʂ܂łقƂ�Ǖς���Ă��Ȃ��̂��悭������B ���̃X�^���X�́A��{�I�Ƀt�@���N�V���i���X�g�Ƃ��Ẵ��_�j�X�g�ł���B�����ĉ������A�����ɂ��Ƃ肠�����A�p���̌��z�j�ɓ_�݂���A ���l���̕s�v�c�ɕȂ̂���A��B�������p�����z�Ƃł���Ƃ������Ƃł���B 
|
|
�Q�D�r�[�g���Y�ƃX�^�[�����O �C�M���X�̓c�ɒ����X�^�[�ɍH�w���̌��������������̂�1963�N�ł������B ���X�^�[�̏o���́A���C�X�E�J�[���̃��`���[�Y����f�B�J���������i1961�N�j�Ƌ��ɁA �����̎��オ�I����ă��_�j�Y�����V�����t�F�[�Y�ɂ͂������������Ӗ����Ă����B ����͂܂��C�M���X���A�v���Ԃ�Ɍ��z�̕\����Ɉ�������o���L�O���ׂ����z�ł��������B ����͉��y�̐��E�Ńr�[�g���Y���ʂ����������Ɏ��Ă���B ���X�^�[��w�H�w�������������̂Ɠ����N�A1963�N�ɂ́A�r�[�g���Y�̍ŏ��̃q�b�g��A���o���g�v���[�Y�E�v���[�Y�E�~�[�h�������[�X����A �c�ɒ������@�v�[�����琢�E�ɍL�����Ă������B ���X�^�[��w�H�w�����u���Ԃɐ��E���ɍL�����āA �X�^�[�����O�̖��͒m��n�����B����ȍ~��10�N�ԈʁA�C�M���X���V��������𐢊E�ɔ��M��������͂Ȃ��̂ł͂Ȃ����B ���X�^�[�ȍ~�A�X�^�[�����O�̐V�������z���G���Ō���Ƃ��ɂ́A�r�[�g���Y�̐V�����A���o�����̂Ɠ����悤�ȁA �҂��ł���Ă������̂�ڂɂ���A�V�N�Ȋ������������B |
�P���u���b�W��w���j�w���̊�������1967�N�͂܂��ɁA �g�T�[�W�F���g�E�y�p�[�Y�E�������[�E�n�[�c�E�N���u�E�o���h�h�̃����[�X���ꂽ�N�����A ����Ƀr�[�g���Y�����U���A �Ō�̃I���W�i����A���o���g���b�g�E�C�b�g�E�r�[�h�������[�X���ꂽ1970�N�A����͏������ꂽ���A ���̗��N�ɃI�b�N�X�t�H�[�h�̃t���[���[��r���f�B���O���������Ă���B �����Č����A�r�[�g���Y�Ƃ����A�C�R���������Ă�����ʂ̋������A���z�̐��E�ł́A�W�F�[���Y�E�X�^�[�����O�ɂ͂������B �Ƃ���ŃX�^�[�����O�̓W�����E���m�����P�U�ΔN�������A ������A�����@�v�[���̃N�H���[�E�o���N���Z�Ƃ����������Z���o�Ă���B �D�ꂽ���z�͂��ꎩ�̂����̎���̌��z�ɑ����]�ɂȂ��Ă���Ƃ����B���X�^�[��w�H�w���́A �������A�����������z���L��Ȃ̂��Ǝv�킹��V����������A���������̂����z�Ƃ������̂Ȃ�A���z������Ă݂����ƁA ���z���u������҂Ɏv�킹��A�V�����������������B �X�^�[�����O�̑��݂��Ȃ���A ���������炭�������Ƃ��������ł��낤�A��ɑ������`���[�h�E���W���[�X��m�[�}���E�t�H�[�X�^�[�́A ����ɃR�[���n�[�X�̌��z����������̂ɂȂ��Ă����̂ł͂Ȃ����B |


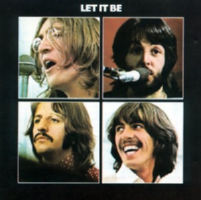
|
|
|---|---|
|
�R�D��w�V���[�Y3���� �\���X�^�[�A�P���u���b�W�A�I�b�N�X�t�H�[�h �R-�P�D���X�^�[��w�H�w�� �G�N�T���v���o���X�ŊJ���ꂽ�ACIAM(���ی��z�Ɖ�c)��MARS�O���[�v�̑�\�Ƃ��ĎQ�����������N1955�N�ɁA �X�^�[�����O�́A3�N�ԋ߂����C�I���Y�E�C�Y���G���E�A���h�E�G���X���z�����������߁A�����������W�F�[���Y�E�K�D������ �p�[�g�i�[�V�b�v��g�ݎ��������X�^�[�g������B�X�^�[�����O�̓n���E�R�����̏W���Z��A�K�D�����̓��C�g���̏Z��̎d���������āB ���Ȃ݂ɂ��̉�c�ɂ́A�ڂ��������Ă���HKPA�̃r���E�n�E�G���ƃW�����E�p�[�g���b�W���o�Ȃ��Ă���B �����ēƗ���3�N��A33�̎��ɁA�X�^�[�����O�E�A���h�E�K�D�����́A���X�^�[��w�̃}�X�^�[�v������S�����Ă��� ���X���[�E�}�[�e�B�����̐��E�ŁA�H�w�����̎d����B �X�^�[�����O�E�A���h�E�K�D�����ɂƂ��Ă̏��߂Ă̑傫�Ȏd���ŁA����܂� ������Ƃ�ςݏd�˂Ă�����l�̂R�N�Ԃ́A�R���y�����Ŕ|���Ă����A�C�f�B�A�̒~�ς��A�����ɖ��x�����O��I�ɓ�������邱�ƂɂȂ�B ���V�A�\����`�̃����j�R�t���v�킹��A�߂̏��ʂ�200�l�p��100�l�p�̍u�`���́A ���ꂼ���K�̃I�t�B�X�^���[�ƌ������^���[�ɂ���Ĉ�������Ԃ�Ȃ��悤�A���������Ă���B  |
���[�N�V���b�v�̃K���X�����̓t�@���N�V���i���E�g���f�B�V�����Ŏ�グ���A���@�i�L�����[�ȍH�ꌚ�z�̃K���X�̃m�R�M����������A ��w����̗v���Ŗk�Ɍ��������߂ƁA�[���ɉ������I���ȏ����ɂ���āA�v���Y����45�x�����ɘA�����ĕ��ׂ�ꂽ�悤�Ɍ����閣�͓I�Ȃ��̂ɕϖe������ꂽ�B ��w3����ɌJ��Ԃ����T�[�L�����[�V�����̎��o���Ƃ�������A�K�i�ƃG�����F�[�^�[�̃y�A�E�V���t�g�B ������������̃y���V���x�j�A��w���`���[�Y��w�������ł̂����郋�C�X�E�J�[���̃T�[���@���g�E�X�y�[�X �̃y�A�E�V���t�g�Ɏ��Ă��邪�A����ɐ旧���X�^�[�����O�E�A���h�E�K�D�����́A�V�F�t�B�[���h��w�R���y�ĂƃZ���E�B���E�J���b�W�̃R���y�ĂŊ��ɁA ���̃y�A�E�V���t�g�̃A�C�f�B�A���o���Ă���i�Z���E�B���̃V���t�g�͐ݔ��p�����j�B ��������[�h���邱�̓�l�̌��z�Ƃ��A�����A�C�f�B�A���o���Ă���͖̂ʔ����B �����ė��p����l������K�ɍs���ɏ]���Č���̂�\�������A����ׂ��Ȃ�K���X�̑�̂悤�ȃT�[�L�����[�V�����̕\���B �܂��I�t�B�X�^���[�ƌ������^���[�́A�@�\�̈Ⴂ�ɂ���āA�\�����O�ς̕\����ς��Ă���B 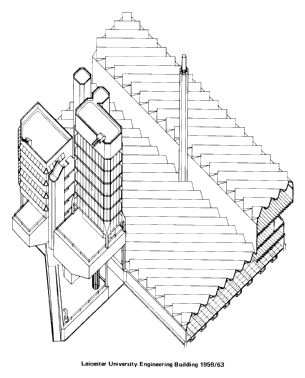 |
�@�\���Ƃɕʂ̌`�A�ʂ̃��H�����[����p�ӂ���Ƃ����A���߂��Ɍ����镪�߃A�[�e�B�L�����[�V�����B �x�������w���̂��߂́A�Ɛ��������A�|�f�B�E������u�`���ɗ����オ��A�����K�i���ރK���X�̃`���[�u�B �A�[�e�B�L�����[�V�����ƃT�[�L�����[�V�������ւ̂������́A�����I�ȏ�����ւ̋C�������炩�A�������Ď��X�ɌJ��Ԃ���Ă���B �O�����w�̑��̌����Ɉ͂܂ꂽ�����~�n�ɔz�u���ꂽ�����ƁA�K���X�ʂ�^�k�Ɍ��������߂ɏo�����v���Y��������45�x�̃��C���A �������̋��E���ɉ��킹���|�f�B�E���̎߂̃��C���A �U�O�t�B�[�g�̍����́A���ʂ����߂�ꂽ�������g�b�v�ɒu�����߂ɁA�����̌��܂����I�t�B�X�^���[�B�i���ۂ͂P�O�O�t�B�[�g�ɂ܂Ŏ����グ���A��w��������B�j �R���N���[�g���o���ɂ��Ȃ����ƂƂ�����w�̗v���ɏ]�����A�����ƃ^�C���ƃK���X�Ŏd�グ��ꂽ�O�ǂ̎d��B �u�`���̊O�Njy�ю߂̏グ���A�����ăI�t�B�X�^���[�ƃy�A�V���t�g�̃^�C���́A �������^���[�̊O�ǂƃ|�f�B�E���̃L�����B�e�B�E�E�H�[���i����ǁj�̗����ς݂ƁA�����ɋ�ʂ��ďc�\��ɂ���Ă���B |
��w�����玦���ꂽ�v���O�����ւ̕��]�ƁA����������Ƃ��ēO��I�Ƀf�U�C���ʼn����A���X�ȃR���e�N�X�`���A���Y���B ���������������́A��{�p���Ƃ��āA�X�^�[�����O�̍Ō�̍�i�܂ł��ĉ��B �S�̂��\�������{�P�ʂ̓K�D�����̐ݒ肵���A���ʁA���ʂƂ��A10�t�B�[�g��20�t�B�[�g�̃��f���[���ɂ�������ڂ��Ă���B ����ƃ��[�N�V���b�v�̃K���X�����̃f�B�e�[���́A�����炭�K�D�����̂��̂ŁA���X�^�[�ŃK�D�����̉ʂ����������͑傫���B �v����x�тɈ�ꂽ�A�A�C�f�B�A�Ɏ����A�C�f�B�A�A�X�^�[�����O�ƃK�D�����́A�܂�Ń��m��/�}�b�J�[�g�j�[�̋ȍ��݂����ȁA �v�v���Z�X��ł���B 1955�|64�̃p�[�g�i�[�V�b�v�������烌�X�^�[�̏v�H���̃p�[�g�i�[�V�b�v�����܂ł�10�N��A �X�^�[�����O�E�A���h�E�K�D�����͂����������ɖ��x�̍���������Ƃ��s���Ă���B �p�[�g�i�[�V�b�v�̊��Ԃ����x�r�[�g���Y��1960-70�̌���������U�܂ł̖�10�N�Ԃɕ�������B |
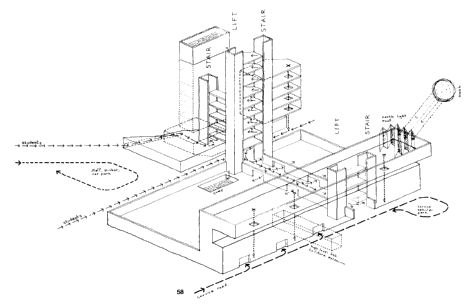

|
|
|---|---|
|
�R-�Q�D�P���u���b�W��w���j�w�� �W�F�[���Y�E�K�D�����Ƃ̃p�[�g�i�[�V�b�v���������Ă���A�ŏ��̎d�������̃P���u���b�W��w���j�w���ŁA ���X�^�[�̂��߂��ɂ�������A�[�e�B�L�����[�V�����͉������A�p���̓`���I�ȉ�����w�ɂɋ߂��A���ʑ̂̃K���X�̃s���~�b�h �Ƃ����P��̃A�C�f�B�A�ł܂Ƃ߂��Ă���B �G�����F�[�^�[�ƊK�i�̃y�A�̃V���t�g�A�p�e���g�E�O���[�W���O�ƌĂ������̃g�b�v���C�g�p�T�b�V�̎g�p�A ��w���̗����ς݂̃L�����B�e�B�E�E�H�[���̉��ς݂Əc�\��̗����^�C���̑Δ�ȂǁA��w�V���[�Y�Ƃ��ăA�C�f���e�B�t�@�C�ł���悤�ɁA �O�ς̍\���v�f�́A�ӎ��I�Ƀ��X�^�[�P���Ă���B �X�^�[�����O�̐����ɂ��� �g�c��ȗʂ̋ߑ㌚�z�����ł��闝�R�́A�ЂƂɂ͌����S�̂̒P���Ȍ`�ɕ����̔z�u����艟�����߂Ă��܂��Ă��邩��ł��B ���B�͒ʏ핔���ɋ��߂��闝�z�I�Ȍ`���o���邾���c�����ƍl���A�\���I�ȃ��f���[����O�����čl����ꂽ�����S�̂̌`�ɂ��킹�āA ������c�߂邱�Ƃ͂��Ȃ��悤�ɂ��Ă��܂��B ���j�w���ł́A�����̌`���ςݏd�˂��āA�����S�̂̌`�ɂȂ�悤�ɂ��Ă��܂��B �����͏����Ȃ��̂͏�̊K�ɁA�傫���Ȃ�ɂ��������ĉ��̊K�Ɏ����čs���悤�ɂ��Ă��܂��B �{�����̏�Ɏ߂ɉ˂���ꂽ�I�[�v���ȃX�e�B�[���E�g���X�̉��� |
�́A���̌����{�����ɐZ�������A �܂��T�[�L�����[�V�����̘L���ɂ��˂����ނ悤�ɂ��Ă��܂��B ���̉����͋Z�p�I�ȃG�������g�����A �q�[�^�[�A���C�p���[���@�[�A�r�C�t�@���A�Ɩ��Ȃǂ���������C�ߑ��u�ł�����A�O���̋C��̕ω��ɍ��킹�����I�ɒ��߂��A ���̋C������ɕۂ悤�ɂȂ��Ă��܂��B ���́g�����|�������h����̊O�����̉��͂͂k�^�� �u���b�N�̃o�b�g���X�̌��ʂɂ���Ĉ��肳���Ă��܂��B �����Č����̃}�X�ʉ�S�̂́A�l�X�ȍ\���̉��͂ɂ���Č���t�����Ă��܂��B �O���̓��X�^�[�Ɠ����f�ނ̃K���X��^�C���Ȃǂ��g���A�d���A�₽���A���˂���\��͊O�̋C��ɍ����Ă��܂��B �����̑f�ނ͒��ɂ͎������܂ꂸ�A�}�����Ȃǂ̓��ǂ͋z���ނŎd�グ���Ă��܂��B ���̓��ǂ͎��o�I�ɂ́A�e���r�̃X�^�W�I�̂悤�ł��B�L���͉{�����̏�̃X�y�[�X������M�������[�Ƃ��čl�����Ă��܂��B �h���̂��߂ɃK���X���Ƃ߂��A��v�ȃT�[�L�����[�V�����̃X�y�[�X�ɂȂ��Ă��܂��B �����̒����w���́A�w���̒��ōł��d�v�Ȏd����ł���}�����Ǝ��o�I�ɐڐG���܂��B ���̑��֊W�͊w������������T�v���ɂ������������甭�W�������l���ł��B�h ��w�V���[�Y��P��ڂ̃��X�^�[�ɔ�ׁA�莝���̃A�C�f�B�A�̑S�Ă荞�����Ƃ����݂͂������A�V���v���ȍ\���̌��z�ɂȂ��Ă���B |

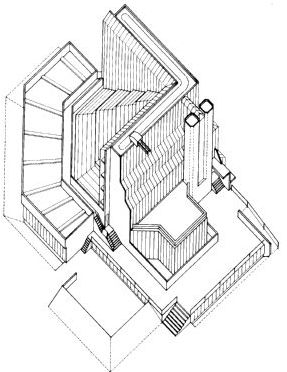
|
|
|---|---|
|
�R-�R�D�I�b�N�X�t�H�[�h��w�t���[���[��r���f�B���O ��w�V���[�Y��3�e�́A���̃I�b�N�X�t�H�[�h�̃N�C�[���Y�E�J���b�W�̊w�����ŁA�t���[���[�E�r���f�B���O�ƌĂ�Ă���B �Ăё�w�V���[�Y�Ƃ��ẴA�C�f���e�B�t�B�P�[�V�����̂��߂ɁA �O�ς̍\���v�f�́A�G�����F�[�^�[�ƊK�i�̃y�A�̃V���t�g�A�c�\��̗����^�C���ƃp�e���g�E�O���[�W���O�̑g�ݍ��킹�ŁA �Ăу��X�^�[�P���đ�w�V���[�Y�̍Ō�������Ă���B ��ɖʂ���������͂�ŁA�ʂ��Ƃ����R�̎��^�̕��ʂ����Ă���B ���̒���^���ʂ͂܂� ������͂I�b�N�X�t�H�[�h�A�P���u���b�W�̃J���b�W�̃v���b�g�^�C�v���ꉞ���P���ăA�����W���Ă���Ƃ������ƂɂȂ��Ă��āA ����̎���ɂ͈�i�����x���̉��������A�N���C�X�^�[�̉�L���߂��炳��Ă���B ��K�ɍs���ɏ]���āA �O���ɍL����Ƃ���ȂǁA�t�����ł͂��邪�A�Z���E�B���E�J���b�W�̃R���y�Ă��v���o������B �Ȗʂ̃u���b�N�̂�������y�A�E�V���t�g���Ă���Ƃ�������Ă���B �܂�����Ɣ��Α��̊O�ς́A�X���������I�o���Ă��āA�ǂ��ƂȂ��A�[�L�O�����̃E�H�[�L���O�E�V�e�B��A�z������t�@�j�[�ȕ\������Ă���B �O���ɃI�[�o�[�n���O���Ă���̂ŁA���K�i���A��ɍs���ɏ]���āA �O���֊O���ւƃY���Ă����ʔ����\�������Ă��āA���̕����̓K���X�ŁA�O���猩����悤�ɂ��Ă���B |
��ɖʂ����R�[�i�[�ɂ́A�p���e�B���O�ƌĂ��D�V�т̑D�����ꂪ����A����͂�������X���[�v�ŏオ�����ʒu�ŁA �v���b�g�t�H�[����ɂȂ��Ă���B �����������̃v���b�g�t�H�[�����A���̑�w�V���[�Y�� �O�ς̍\���v�f�̈�ŁA�X�^�[�����O�͕K���A����̃��x������l���v���b�g�t�H�[���Ɉ�U�グ�Ă���A�G���g�����X�ւƓ����B ����̒���̃v���b�g�t�H�[�b���̉��ɂ́A���H���Ɛ~�[���Z�b�g����Ă���B ���X�^�[�ł͑����p�C�v�̊��C���u���A �����̃g�C���̂��߂ɓ˂��o���Ă������A�����ł���͂�D���v�킹��~�[�̂��߂̊��C���u���˂��o���Ă���B ���X�^�[�����傫���|�b�v�ȕ����{�̂悤�ȃI�u�W�F�Ƃ��āB ���G�ȍ\���̃��X�^�[�A�����v�f�̏��Ȃ��P���u���b�W�Ɣ�ׁA�v���O�����̓V���v���ŁA���߂��Ă���̂͊w�����ƒ��H�������A �����ׂ����͏��Ȃ��A��w�V���[�Y�R��̒��ł́A��Ԍy�₩�Ń��[�����X�ȃf�U�C���ɂȂ��Ă���B �P���u���b�W��w���j�w�����t���[���[�E�r���f�B���O���A���X�^�[�ɑ������ۓI�ɂ͍����]�������A �p�����ł́A�I�b�N�X�u���b�W�̂P�U���I�̃J���b�W�̌��z���̒��ɂ����āA�`���I�Ȕ��ςƂ͑�����Ȃ��Ƃ����������ᔻ���������������B |

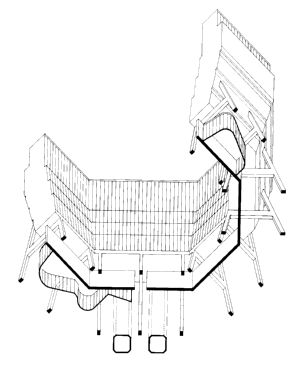
|
|
|---|---|
|
�S�D�����^�[�W���H�@(�g�����H�@) �S-�P�D�Z���g�E�A���h�����[�X��w�A���h�����[�e�������B���f�z�[�� �P���u���b�W��w���j�w��(1964�|67)�ƃt���[���[�E�r���f�B���O(1966�|71)�ŁA���X�^�[�ȗ��� �c�\��̗����^�C���ƃp�e���g�E�O���[�W���O�̊O���� �Ŏ����Ă����̂Ɠ��������ɁA�X�^�[�����O�́A�v���L���X�g�E�R���N���[�g�̃p�l���ƁAGRP(�K���X�@�ە⋭�|���G�X�e��-���{�ł���FRP)�� �p�l����g�ݗ��Ă�A �Ⴄ�f�ނ̐V���ȂQ�̍\�@�Ɏ��g�݁A1964�N�ɂ̓v���R���ɂ��Z���g�E�A���h�����[�X��w�A���h�����[�e�������B���f�z�[���A������ 1969�N�ɂ�GRP�ɂ��I�����F�b�e�B�E�g���[�j���O�E�Z���^�[�̐v���X�^�[�g���Ă���B �A���h�����[�e�������B���f�z�[���̕~�n�́A�X�R�b�g�����h�́A�n��ŗL�̍ޗ����A�E�l�����݂��Ȃ��ꏊ�Ȃ̂ŁA �v���L���X�g�E�R���N���[�g�\�@���I�����ꂽ�B�v���R���𑼂̏ꏊ�Ő��삵�A�~�n�ɉ^��őg���Ă���@�B �H��̓Z���g�E�A���h�����[�X����P�Q�O�L����̃G�f�B���o���ɂ���B �Q�{�̎w���J�����悤�Ȍ`�����Ă��錚���́A32��̃^�C�v�̃v���L���X�g�̕ǂƏ��̃��j�b�g���A�Z���u�����đ����A �����̂ЂȌ^�͌�̌����ōė��p�����B |
�ŏ��̌����͍��������A��Ɍ��݂��镪�̃R�X�g�͈����Ȃ�A�S�̂Ƃ��ẴR�X�g�͓`���I�ȍ\�@�Ɠ����ʂɉ���������A�ƃX�^�[�����O�͌����B ����������250�����e�̓����S������v�悾�������A��w�̎���ŁA�ŏ��̈�����ł��Ȃ������̂ŁA�ЂȌ^���̃R�X�g�͂��̂P�� �̕��S�ƂȂ�R�X�g�팸�̂�����݂͊O�ꂽ�B ���ꂼ��Q�{�̎w���J�����悤�Ȍ`�����Ă���S���̏h�ɂ́A�X�֒ʂ�������ɉ�����������A�v���[�`���A �}�Ζʂɂ���A���������͌���ł��R���N���[�g�̃_�C�j���O�z�[���Ȃǂ̋��p�{�݂����Ɍ��āA �K�i������A�v�����i�[�h�E�f�b�L�ɒB����B �K���X�̃v�����i�[�h�E�f�b�L�́A�����̓r���K�ɂ����āA��������㉺�̌��ւƎ���A�T�[�L�����[�V�����̓����ɂȂ��Ă���A �܂����̊w���ƐڐG�����ɂ��Ȃ��Ă���B ���ׂĂ̌��̑��́A�k�C�ƃX�R�b�g�����h�̎R�X�̒��߂̗ǂ������ɐU���Ă���B �V�����\�@�����݂��A���̌��z�̐v�{�H����(1964�|68)���A�P���u���b�W��w���j�w���̐v�{�H����(1964�|67)�� �قڏd�Ȃ�Ƃ��낪�ʔ����B |
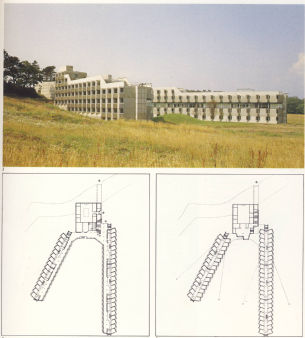
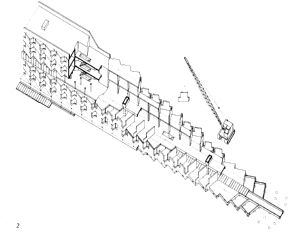
| |
|---|---|
|
�S-�Q�D�I�����F�b�e�B�E�g���[�j���O�E�X�N�[�� GRP�̃I�����F�b�e�B�E�g���[�j���O�E�Z���^�[���A�����Q�ɕ����A�Q�̃E�B���O�̊Ԃ���A�v���[�`����Ƃ���� �Z���g�E�A���h�����[�X��w�Ɏ��Ă��邪�A������͒����A��s�@���v�킹�镽�ʌ`�����Ă���B �I�����F�b�e�B�Ђ́A�P�T,�U���I�`���[�_�[�E�G���U�x�X���̃}�i�[�E�n�E�X���������āA�P�����̂��߂̋��Z�{�݂Ƃ��A ���[�i�[�E�n�E�X�ɗאڂ��ČP���{�݂�V�z�����B ���[�i�[�E�n�E�X�̉����́A�y�₩�ȃI�����F�b�e�B�E�j���[�E�u�����`�Ŏ��т̂���G�h�E�J���i�����S�����A�V�z�������X�^�[�����O���S�������B �����ł��X�^�[�����O�͂����̂悤�ɁA�^����ꂽ�v���O������N���C�A���g�̗v�]����ъ�Ƃ̃C���[�W�A �~�n�̃R���e�N�X�g���̗^�������痣��Ĕ�邱�Ƃ͂Ȃ��A ���X�ɂ����̈Ӗ���ǂ݂Ƃ�A���߂��A�����̒�N����ۑ�ɍł��ӂ��킵�����o�����Ƃ��Ă���B �Z�p�S���p�̋������Ɖc�ƒS���p�̋������ɕ����ꂽ��̃E�B���O�̊ԂɁA���ԃ��x���ɂ���}�i�[�E�n�E�X�̋��Z��������A��{�̃X���[�v���������܂�A �㉺�K�ɃA�v���[�`����B �X���[�v���~�肽�Ƃ���ɂ́A���ړI���������āA�����͗p�r�ɂ���āA�Q�����A�S�����ł���悤�ɂȂ��Ă���B �d���̊Ԏd��p�l���́A�����ɓ˂��o���\���`�̌ˑ܂Ɏ��[�����B�����J�ɂ����̌ˑ܂͓����K���X�ŁA �Ԏd��̎��[��������悤�ɂȂ��Ă���B 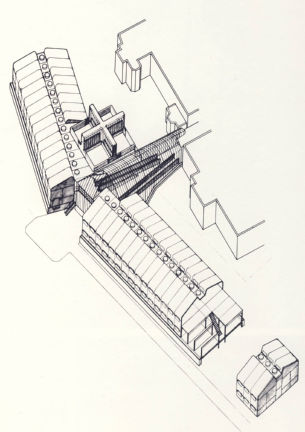 |
���̓d�����Ԏd��p�l�̌ˑ܂��A�����̏�ɓ˂��o���A�C�f�B�A���X�^�[�����O�͋C�ɓ������炵���A
�Z���g�E�A���h�����[�X��w�A�[�g�E�Z���^�[�̃v���W�F�N�g�ɂ��g���Ă���B ��ɂ���āA�v���O�����A�R���e�N�X�g��ǂݍ��X�^�[�����O�́A�^���Ԃȃ^�C�v���C�^�[�Ȃǂ́A �J���t���ł��ׂ��ׂ�������̂���A�I�����F�b�e�B���i�̊�ƃC���[�W����A GRP�̃p�l���Ƃ����O���̃C���[�W���A�Ƃ��ē����o���B�J���t���ȐF�͎��ۂɂ́A�����̎w���ł��ƂȂ����F�ɗ}����ꂽ���B �����ɊJ������̃E�B���O�̊p�x�́A�~�n�̃R���e�N�X�g���猾���ƁA�ЂƂɂ̓R���^�[�̃��C���ɍ��킹�Ă���̂ƁA �[���ɔ���X�̖X�̃��C��������āA���P�{�̑厖�Ȏ����A��Ȃ����߂Ƃ������R����r�߂��Ă���B �v���L���X�g�E�R���N���[�g�̂Q�K���A�������A�����Ă����炭���u�ɁA�����|����悤��GRP�̃p�l�������t�����Ă���B ����͂Ȃ������ƕǂ͈�ɂȂ��āA���z�Ƃ������̓I�����F�b�e�B�̂��鐻�i�̂悤�Ɍ�����B �X�^�[�����O�͂��̌�A�����R�[���E�j���[�^�E���̃��E�R�X�g�E�n�E�W���O�Ńv���R���E�p�l�����A���� �����R�[���E�j���[�^�E���̃T�E�X�Q�[�g�E�n�E�W���O�ł�GRP�p�l�����A�Ăю��݂Ă���B 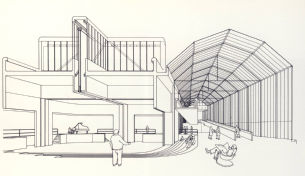

|
|
�T�D����Ɍb�܂�Ȃ����� �T-�P�D�_�[�r�[�E�^�E���E�Z���^�[ �����R�[���E�j���[�^�E���\����1976�N����A1983�N�̃V���g�D�b�g�K���g���p�ِV�ق̔��\ �܂ł�7,8�N�ԁA�X�^�[�����O�̐V������i���G����Ō��邱�Ƃ͂Ȃ������B�܂肻�̈ʂ̊��ԁA�X�^�[�����O�̎������ɂ͎���̎d�����Ȃ������Ƃ������ƁB �����P�X�V�S�N�����Ǝv�����A�X�^�[�����O�̎������œ����Ă����X�C�X�l�̗F�l�E�F���i�[�E�N���C�X�ƁA GLC�̃L�����e�B�[���Œ���H�ׂ����A�d�����Ȃ��Ď���ҋ@���Ă���Ƃ����b�������Ƃ��������B �܂��A���{�A������A�R�t�[���E�A���h�E�~���[�œ����Ă����b�N���X�^�[�����O�������ɓ������B ����͂����炭�V���g�D�b�g�K���g���p�ق̎d�������܂��āA �����o���P�X�V�V�N���������̂��낤�B �����瑽���A���E�I�ɂ����Ƃ������̍��܂����P�X�V�O�N��O���̎�����7,8�N�ԁA �X�^�[�����O�͎���̋@��Ɍb�܂�Ȃ��Ƃ�������Ȃ��ƂɂȂ��Ă����B ���̎d���̂Ȃ������ɁA���I���E�N���G���X�^�[�����O�̎������ɓ���A1968�N����1971�N�܂ōݐЂ��A����ȊO�̖ʂōv�����Ă���B ���I���E�N���G��1946�N���N�Z���u���O���܂�ŁA����͖w�ǂȂ��̂����A�h���[�C���O�𐔑������\���A 1970�N��O���ɉe���͂��������B |
���[���b�p�̊����̓s�s��ǂ݉����āA���̍\���v�f�œs�s���č\������A�l�I�N���V�J���ȃh���[�C���O�͖��͓I�Ől�C���������B �ނ��S�������̂��_�[�r�[�E�^�E���E�Z���^�[�̃R���y�ĂŁA�N���W�b�g������ƁA�X�^�[�����O�ƃN���G�݂̂��ւ�������ƂɂȂ��Ă���B �����ɃN���G�̃A�C�f�B�A�Ǝv����A�d�b�{�b�N�X�̏W���Ƃ��A�X�����t�@�T�[�h�Ƃ��A���[���X���C�X�̒����Ƃ��A �h���[�C���O�̊������A�N���G�F�������A���̂��Ƃ̃I�����F�b�e�B�{�Јȍ~�̃h���[�C���O�ɉe����^�����̂ł͂Ȃ����B �������A�N���G�̍ő�̌��т͉��ƌ����Ă��A�����X�^�[�����O�̍�i�W��Z�߂����Ƃł͂Ȃ����Ǝv���B �ڂ��͂��̖{���A�o������̍��ɁA�E�F���i�[�E�N���C�X�ɂ�������̂����A �ʐ^�A�h���[�C���O�A���ׂă��m�N���œZ�߂��A�\����James Stirling�̕����������Ԃ��A�N���V�J���ȕ\���������i�W�ŁA�ЂƖڂŖ�����ꂽ�B �ߋ��̍�i�̃h���[�C���O���N���G���V���ɋN�������肵�Ă���B ���m�N���œZ�߂����ƂŁA�X�^�[�����O�̂����ʂ��S�ʂɉ����o����Ă���C�������B ���̌�̃V���g�D�b�g�K���g���p�ِV�ق��A���̍�i�W�̒��Ɏ��߂��āA ���m�N���Œ��ꂽ�Ƃ�����A�啪�������ۂɂȂ����̂ł͂Ȃ����ƁA�ӂ��Ǝv���B |
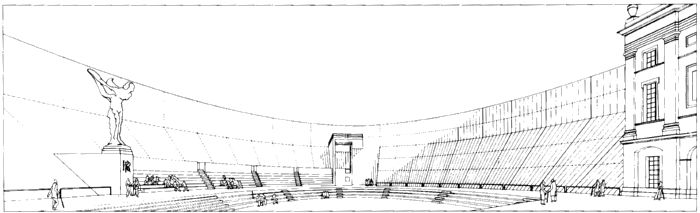
|
|
|---|---|
|
�T-�Q�D�I�����F�b�e�B�{�� �W�[�����X�E�~�����w���{�ЁA�����̎����̍�i�ŁA ���I���E�N���G���ւ���Ă��� �p�[�X�ɂ��̐F���o�Ă���B�I�����F�b�e�B�E�~���g���E�L�[���Y�{�Ђ̌v��Ă̓N���G����߂���̍�i�ŁA�����炭�E�F���i�[�E�N���C�X�� �p�[�X��`�����̂ł͂Ȃ����Ǝv���̂����A���̑s��ȕ��i�̕\���̓N���G�̉e����������Ȃ��B �I�����F�b�e�B�E�~���g���E�L�[���Y�{�Ђ́A����܂ł̃X�^�[�����O�̌��z�̍\���v�f�̑����̂悤�ȍ�i�ŁA �g�X�^�[�����O�̐ܒ���`�̖L����������ɂ��A�ɂ߂đn���I�ȗ��j��`�҂̌`�ԂɊւ��鋳�{�ɏo��h�ƁA�P�l�X�^�t�����v�g���͌����B 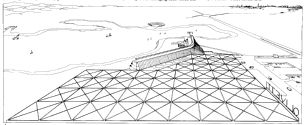 |
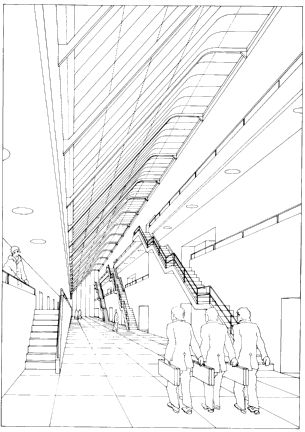 |
|
�U�D�h�C�c�̔��p�كV���[�Y�R���� �\�f���b�Z���h���t�A�P�����A�V���g�D�b�g�K���g �U-�P�D�f���b�Z���h���t���p�� 1975�N�A�X�^�[�����O�̓h�C�c�̓�̗��j�I���S�n�ɍ����p�ق̎w���R���y�ɏ��҂��ꂽ�B 1�Ԗڂ̃f���b�Z���h���t�ł́A�����̌����ƃt�@�T�[�h�́A�ۑ����邱�Ƃ��l������Ă����̂ŁA�V���������͒n���ɖ��߁A �����̃p���B���I��������n��Ɍ����āA���p�ّS�̂��V���{���C�Y����B ����͂܂��A�v�����ɂ���A �~�n����������̕����́A�o���_�̂��邵�ł�����B���̃V���[�g�J�b�g�̕����́A�h�C�c�̃R���y�ŁA "����I�ȁh�v�����Ƃ��Ă悭�o����A�V���g�D�b�g�K���g�ł��o�Ă���B�@ |
�U-�Q�D�P�����E���[�����b�t�E���`���[�Y���p�� �P�����i2�Ԗڂ̃R���y�j�ł́A�V�������z�Q�A �z�[�w���c�H���������̗����ɂ����āA���C��������f����S���̎��i�J�e�h�����̎���ł�����j���A ��������`�ɂȂ��Ă���B���p�ق̃}�b�V�u�ȕ����́A�J�e�h��������ł����ꂽ�ꏊ�ɒu���A�G���g�����X�z�[���⑼�̏ꏊ�ɂ��A ����̗v�f��t�����āA�J�e�h�����ւ̌h�ӂ�����킵�Ă���B ����2�̃R���y�ɃX�^�[�����O�͔s��邪�A����2�Ŏ��݂����Ƃ́A3�Ԗڂ̃V���g�D�b�g�K���g�Ő������ꂽ�`�ŁA �������B |
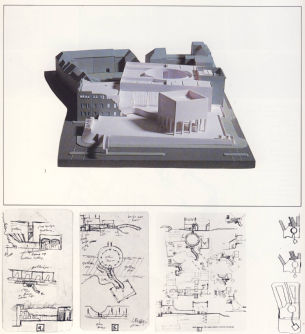
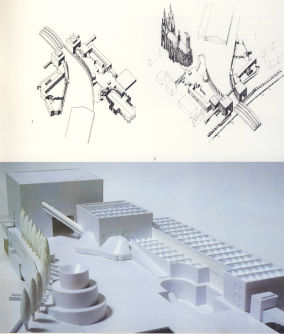
|
|
|---|---|
|
�U-�R�D�V���g�D�b�g�K���g���p�ِV�� 1977�N�A�h�C�c�̔��p�كV���[�Y�R�Ԗڂ̃R���y�A�V���g�D�b�g�K���g�ł悤�₭�������A �X�^�[�����O�͂��悢��v���U��̎���Ɏ��g�ނ��ƂɂȂ����B �~�n��12���̗����̂���A�������p�قɗאڂ���1.2ha�̓y�n�ŁA���߂�ꂽ�̂� �����̍������p�ق̑��z�ƁA����A���y�w�Z�A�}���ق̃R���v���b�N�X�ł���B �f���b�Z���h���t�ɑ����A�~�n�𓌐��ɉ���V���[�g�J�b�g�̕�����݂��邱�Ƃ��A�����Ɋ܂܂ꂽ�B �h�C�c�̃V���g�D�b�g�K���g�Ƃ����n�ŁA�p���l���ǂ��R���e�N�X�g��ǂݍ��ނ������ڂ��ꂽ�B �����ŁA�X�^�[�����O�̓h�C�c�̌��z�ƃt���[�h���b�q�E�V���P���̃A���e�X�E���[�E���̕��ʂ� �߂��`�ŁA�f���b�Z���h���t�̉~�`�̒�����A�Ăю����o���Ă����B �A���e�X�E���[�E���̒����̃p���e�I���̓f���b�Z���h���t�Ɠ��������̂Ȃ�����Ƃ��āA �v�����̃t�b�g�p�X���A���x�͉~�̓��@���߂���B �����āA�R�̎��`�̓W����������e���X�̒����L�����āA���H�C�h�̒���p���e�I�����͂ތ`�ɂ����B�B �W�����́A������ɗ����W�����łȂ��A�V���P���̃A���e�X�E���[�E���̓W�������Q�Ƃ��āA �c���Ɍq����A�e�W�����̏o���������������A�����̕����̑S�̂����ʂ���A�N���V�J���ȁg�G���t�B���C�h�z�u�h�� �̗p���A�V�ق̃G���g�����X����A�{�قւƈ�M�Ōq�����B ���̃V���^�[�c�K�����[�V�ق��]������Ďd�����A�N���[�E�M�������[�i�����h���̃e�[�g�E�M�������[�̑��z�j�ł��A �T�b�N���[���p�فi�n�[���@�[�h��w�t�H�O���p�ّ��z�j�ł��A�X�^�[�����O�́g�G���t�B���C�h�z�u�h������Ȍ�A�����Ǝg�������Ă���B 

| �W�����K�̉��A�G���g�����X�K�̕��ʂ�����ƁA�k�����ɒ����`�̓��ʓW�����A�~�`�L��A�O�p�`�̃��N�`���[�z�[�������ɕ���ł���B L���`�̌���A�s�A�m�`�̉��y�w�Z�A�R���̃T���H�A�@�ւ̃I�}�[�W���ł���}���ق͕ʂɂ��āA �G���g�����X�K�ƓW�����K�Ƃ͑S���Ⴄ���ʂ����Ă��āA���̊K�ŕK�v�Ȏ����㉺�ɊW�Ȃ��A���R�ɔz�u���Ă���B ���ʓI�Ƀ��E�R���r���W�G�̃h�~�m�݂����ɁA���R�ȃv�����邽�߂ɁA�����������āA�������Ŏx����t���b�g�E�X���u�̍\���`�����Ƃ��Ă���B ���̌��ʒ��̒��ɂ́A�ǂ�����ԓI�ɕK�v�Ɣ��f���Ēu����A�\���Ŏg���Ă��Ȃ����̂�����悤�ł���B �P�X�W�S�N�A���̃V���^�[�c�K�����[�����\���ꂽ���A �O�ρA�`�ԁA���ɑ��l�ȐF�ʂ�����܂ł̃X�^�[�����O�̃C���[�W�Ƒ傫���قȂ�A �X�^�[�����O�͕ς�����ƌ���ꂽ�B ����̂������������ɉ����āA�V���^�[�c�K�����[�̔��\�Ɠ����� �g���j�������^���ŃC���t�H�[�}���h�Ƃ������͂���{�̎G���iSD 1984/10,GA DOCUMENNT 11�j�ɔ��\�����B ���̒��ŃX�^�[�����O�̓��j�������^���ƃC���t�H�[�}���i�C�y�œ���݂₷���j�ƁA���ۓIabstract�Ƌ�ۓIrepresentational�Ƃ�����̑Η��T�O�������A �����B������Ă������͏�ɂ��̑Η��T�O�̗����̑��ʂ��ύt�����Ȃ��猚��������Ă��������Ƃ����A ����̓V���g�D�b�g�K���g�ł��ς��Ȃ��ƌ����Ă���B ���ۓI�Ƃ́A���_���E���[�������g�Ɋ֘A�����s�����̂��Ƃł���A ��ۓI�Ƃ͓`���A���@�i�L�����[�A���j�A���z��Y�Ɋւ����̂Ȃǂ́A���Ԃ������z�̎p�ւ̊S�̂��Ƃł���Ƃ����B 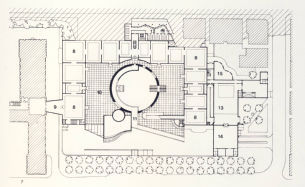
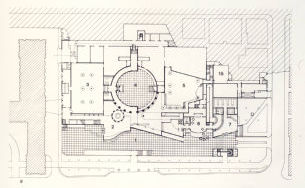
|
|
�V�D�R���e�N�X�g�� �V-�P�D�Z���g�E�A���h�����[�X��w�A�[�g�E�Z���^�[�ƃ��C�X��w ������O�A1971�N�ɁA�X�^�[�����O�͋����Z���g�E�A���h�����[�X�̒��S�ŗ��j�I�Ȍ����̕ۑ��̖����l����f�U�C���Ɏ��g��ł���B 18���I�̓@��̘e�ɁA������̖�q�̌����i���b�W�j�����͎c���A�אڂ��錚���͎��Ƃ��������ŁA �M�������[�ƃX�^�W�I��v�����B�O����g���āA�X�̂��߂̐V�����g�ˊO�̕����h�A �s���Ƒ�w�����ԁi�^�E���E�A���h�E�K�E���j�A���Ԃ̔}��X�y�[�X���Ă����B �R���e�N�X�g�͏�ɃX�^�[�����O�̏d�v�ۑ�ł͂��邪�A�����Ƃ̎�荇���̃v���W�F�N�g�͏��߂ĂŁA���ɃR���e�N�X�g�������ӎ�����A�؊|�ɂȂ����v���W�F�N�g�ł���B 1971�N����81�N�̃��C�X��w�̌��z�w�����z�́A��͂肱�̃R���e�N�X�g�ւ̔�d���傫���A���̈ӎ��͂������̌�́A�N���[�M�������[�ɂȂ����Ă���悤�Ɏv����B �P�X�Q�O�N��Ɍ��Ă�ꂽ�I���W�i���̃L�����p�X�́A����탔�F�l�`�A���A�t�B�����c�F���A�܂��A�[���f�R���̌��z�́A ����ꂽ�͈͂́A�����A�p���^�C�����A���z�������g���ăf�U�C�����邱�Ƃ����߂炽�B |
���z�w���̌��z�͂k���^�����Ă���A����ɁC�����ЂƂ̂k���^�̕��ʂ��t�����ꂽ�B �V�����W���X�y�[�X�̏�ƁA�u�]�̂��߂̕����̏オ�A�K�����A�ɂȂ��Ă���B �������́A�R���l�[�h�ɂ���āA�אڂ��錚�z�ɘA������A�k���^�̑��z���͎O�ʂ̒�����A �܂�I�[�v���ȃL�����p�X�ɐV�����͂܂ꂽ������o���Ă���B �X�^�[�����O�̃f�U�C�������V���������̃t�@�T�[�h�́A�����̌����̃t�@�T�[�h�ƌ�������̂�����قǂŁA�t�B���b�v�E�W�����\���́g���C�X�ɍs���Ă݂����A �����ɂ�����炵�����̂͂Ȃ������B�g�Ƌ���Ȕ�����q�ׂĂ���B �������������ɑ��ăX�^�[�����O�́g���̃f�U�C�������ƂȂ����A �܂��͕ێ�I���ƍl����l�ɁA�T�݂�}���́A���̃v���W�F�N�g�̌`�Ԏ�`�Ɠ����悤�ɁA���B�ɂƂ��Ă͕ϖe�ł͂Ȃ��i�����j �}���ƌ`�Ԏ�`�́A���҂Ƃ��Ɏ��B�̃��H�L���u�����[�̒��ɂ���܂��B�h�Ƃ����B |
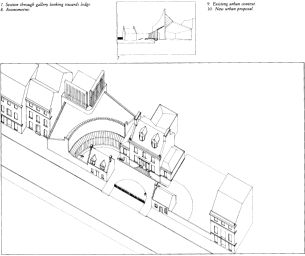

|
|
|---|---|
�V-�Q�D�N���[�M�������[ 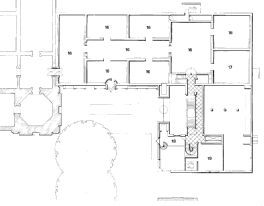
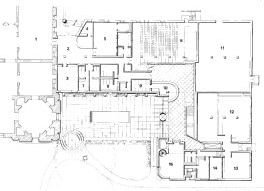 �V���g�D�b�g�K���g�̂Q�N��ɏv�H�����N���[�M�������[�i�e�[�g�E�M�������[�̉�ƃ^�[�i�[�̂��߂̑��z���j�ɂ��āA �C���^�����[�̒��Ń`���[���Y�E�W�F���N�X�́g�W�����E�T�}�[�\�����͂��̔��p�ق̓\�[�����p�ق̗l�ɏ����C�Ⴂ���݂Ă���ƌ����Ă��܂��B ���͂��̊�ȋ����͈��̔�_���I�_���ɂ���Ǝv���܂��B�܂�ꌩ�C�܂���Ɍ����镨���A �悭�ώ@���Ă݂�ƈӎ��I�ɂȂ��ꂽ�_���ƌĂׂ�f���Ȃ��̂ł���Ƃ킩��̂ł��B�h ���ʓI�ɊO���猩�āA���ӓI�Ƃ����v���Ȃ����̂ɂ��Ă��A�X�^�[�����O�͗^����ꂽ�v���O������O��I�ɓǂ݂���ŁA �v���O��������̓W�J�Ō`�ݏo���čs���Ă���B���̂��Ƃ��X�^�[�����O�͌J��Ԃ��A�����Ă���B �X�^�[�����O�̍�i����͏�ɃR���e�N�X�g�̐�������n�܂�B �����̃��b�W�i��ԏ����j���c���Čv�悵�Ȃ���Ȃ�Ȃ������Z���g�E�A���h�����[�X��w�A�[�g�Z���^�[�i�P�X�V�Q�N�j�Ȍ�A ���Ɏ��ӊ��̃R���e�N�X�g�ւ̍l�@�������\�ɏo�Ă���B ���̃e�[�g�E�M�������[�̑��z�ł���N���[�M�������[�ł͓��ɃR���e�N�X�g�̓ǂݍ��݂��O�ꂵ�Ă���B �O�ǂ́A�{�ق̃R�[�j�X�̌J�`���A���̂܂ܘA�������A ���{�ق̊O�ǂ̃|�[�g�����h�X�g�[������A�i�X�ƕۑ������������� �����ɋ߂Â��ɂ�āA�����̊O�ǂɕω����Ă䂭�B���̂��߂̓���Ƃ��āA�A�X�v�� | 
 ���h�̃Q�[�e�{���O�ٔ����̊O�ǂ� �i�q�p�^�[�������p���āA���ɍI���ȊO�ς����o���Ă���B �{�ق̑��ʂɑΛ����������ʃt�@�T�[�h�́A�|�[�g�����h�X�g�[���Ƃ��A�G�W�v�g�I�ȎO�p�̐荞�݂ŃG���g�����X�������A �{�ق̔��~���̌ÓT�v�f�����̏�ɉ�����B �G���g�����X�̊K�i���オ�����Ƃ���ɂ���A�e�[�g�E�M�������[�{�ق̂P�K�̓W�����̃��x���ɁA �Q�K�̃N���[�̓W�������x�������킹�邽�߂ɁA�G���g�����X�ƑO���GL���班�������ăC���e�B���C�g�ȕ��͋C�ɂ��Ă���B �����̓W�����͐F��f�U�C����}���āA�^�[�i�[�̌��Ɖe�̊G������������߂ɁA���R�����ǂ�����邩�����ɕ��S���Ă���B �ʏ�̕~�n�̓s�s�I�R���e�N�X�g�A ���������̃R���e�N�X�g�����łȂ��A�v���O�����̎��R���e�N�X�g�A�N���[�M�������[�ł���A �^�[�i�[�̃R���e�N�X�g�܂ł����܂܂��B �����̃R���e�N�X�g����g�ӎ��I�ɂȂ��ꂽ�_���ƌĂׂ�f���Ȃ��́h�ɂ���āA���Ӑ[���`�Ԃւƈڂ���Ă����B �X�^�[�����O�͌J��Ԃ����������������������Â��Ă���B ����Ӗ��ł͌��z�ƂɂƂ��ē�����O�̂��Ƃł���B ���z������Ƃɂ́A�X�^�[�����O�̂悤�ɋ��łȃR���e�N�X�`���A���Y����A �t�@���N�V���i���Y��������ɂ���Ƃ����V���v���Ȃ��Ƃ��A�V�N�ɁA�܂������Ō�����B |
|
�W�D�V���g�D�b�g�K���g���p�وȍ~ �X�^�[�����O�������́A�V���g�D�b�g�K���g���p�وȍ~�A�X�^�[�����O�̎��܂łɌv��āA�R���y�Ă��܂�20�]�̃v���W�F�N�g���c�����B ���̒��Ŏ��������̂́A���C�X��w�̌��z�w�����z79/81�A�n�[���@�[�h��w�T�b�N���[���p��79/84�A �x�������E�T�C�G���X�E�Z���^�[79/88�A�N���[�M�������[80/87�A �R�[�l����w����|�p�Z���^�[82/87�A�u���E���{�ЁE���Y�H��86/92�ANo.1�|�E���g���[86/97�B �ŔӔN�Ɏ��������v���W�F�N�g�́A�R�[�l����w����|�p�Z���^�[�i�����j�ƃu���E���{�ЁE���Y�H��(���E)�́A����܂Ō����ꂽ�X�^�[�����O�̍�i�� �v���O�����A�R���e�N�X�g����ςݏグ�Ă䂭�����̉�������ɂ����āA ���S�ł��邪�A�P�X�W�U�N�ɐv���n�܂��ăX�^�[�����O�̎���Ɋ�������No.1�|�E���g���[��A�������Ȃ����� �������̃v���W�F�N�g�ɂ́A���X�`�Ԃ̑���ɑS�̂̔�d���X�������Ă�����̂�����B |
���F���`���[���ɔs�ꂽ�����h���̃i�V���i���E�M�������[���z�̃R���y�Ăɂ��A���܂ł̃X�^�[�����O�̃R���e�N�X�`���A���� �C���[�W�Ƃǂ����Ⴄ�A�`�ԑ���ɌX���������A��a����������B �ł����x�̍������X�^�[��w�H�w������n�܂����A�v���O�����ƃR���e�N�X�g�J�ɓǂݍ��݁A �g�n���I�ȗ��j��`�҂̌`�ԂɊւ��鋳�{�h����g�����A�ܒ���`�҃X�^�[�����O�� �f�U�C����@�́A�P���u���b�W��w���j�w���A�I�b�N�X�t�H�[�h��w�t���[���E�r���f�B���O�Ƒ�����w3����A���̌�̋̊ԂɁA �R���e�N�X�g�̓ǂݍ��݂ɖ����̂��������h�C�c�̔��p��3����ւƋ삯���A���̍Ō�̎�����A �V���g�D�b�g�K���g���p�قւƎ��ʂ����B �����ăV���g�D�b�g�K���g�̗]�C�̎c�邤���ɁA���̗͂������A�]�T�������āA�ǂ��`�Ō��������̂������h���̃N���\�M�������[���Ǝv���B |


| |
|---|---|
|
�X�D�e���������z�� RIBA�̃S�[���h�E���_�������ł̍u���ŁA�X�^�[�����O�͎��g������܂ʼne���������z�ɂ��Č���Ă���B �g���z�w�Z�̒��Ԃ̊w�N�̍��A�}�b�L���g�b�V����z�t�}���Ƃ������A ���łȃA�[���k�[���H�[�̃f�U�C�i�[�B�ɂ̂߂肱�݂܂������A ���H�C�W�[��x�C���[�E�X�R�b�g�Ƃ������p���̓�����l�ɂ͋������킫�܂���ł����B�ŏI�w�N�ɂȂ�ɂ��������āA ���̋����̓��E�R���r���W�G��C�^���A�̍�����`�ҒB�Ɉڂ�܂������B �P�X�T�O�N�A���͑��Ƃ��ă����h���ɍs���Ƃ����ɁA�z�[�N�X���[�A�̔���������������Q�����ɍs���܂����B ���́A�A�[�`���[�A���@���u���A�z�[�N�X���[�A�Ƃ������C���O���b�V���E�o���b�N�̌��z�ƒB�Ɏ䂩��A �ނ�̃A�h�E�z�b�N�ȃe�N�j�b�N�Ɋ��Q���܂����B�ނ�͂���ɂ���āA���[�}���A�t�����`�A �S�V�b�N�Ȃǂ̂��܂��܂ȗv�f�������Γ��������̒��Ŏ��݂Ɏg���ăf�U�C�����܂��B �����h���Ɉڂ����ŏ��̍��A�����@�v�[���Ŋw��ł������ɂ͒m��Ȃ������A���V�A�\����`�ҒB�ɂ��Ă��w�т܂����B �����@�v�[���ɂ͂���ɂ��Ă̖{�͑S������܂���ł����B�������̂̓A�X�v�����h�̖{�ŁA���͂�����Â�ǂ݂܂����B �������A�ߑ㌚�z�ɂ��ẮA�R���r���W�G�̏����ƃ��V�A�\����`�܂łŁA����ȏ�V�������̂ɂ͋��������Ă܂���ł����B �����ĂT�O�N�㏉���ɂ́A���@�i�L�����[�Ȍ������ׂĂւ̋����������Ă����܂����B�_�ƁA�[���A�����̏W�Z�Ƃ������A ���ɏ����Ȃ��̂���A�q�ɁA�H��A�S����W����̂悤�ȓy�ؓI�ȍ\�����Ƃ������A���ɑ傫�Ȃ��̂܂ŁB |
�T�O�N�㒆���ɂ́i�^�̃u���[�^���Y���̔����Ɗ֘A������̂ł��傤���H�j���͎ȁX�̗�����^�C�����g���A
�o�^�[�t�B�[���h�A�X�g���[�g�A�X�R�b�g�Ȃǂ́A���B�N�g���A���̌��z�ƒB�ɊS�������܂����B (����) �@�T�O�N�㏉�߂���A�\�[���E�~���[�W�A���ɂ��Ă͒m���Ă��āA ���̌��\�[���A�K���f�B�A�O�b�h���b�W�A�v���C�t�F�A�Ƃ������A�l�I�N���V�V�Y���̌��z�Ƃɋ��������悤�ɂȂ�܂����B �h�C�c�̃l�I�N���V�V�Y���̌��z�ƒB�A�M���[��C���u���i�[�A�t�H���E�N�����c�F�����ăV���P���́A �قȂ�X�P�[����A�قȂ�ޗ����W���N�X�^�|�W�V�������u�����@���g�������̂��Ǝv���܂��B �������ɋ��������̂͂P�X���I�̑O���ŁA�l�I�N���V�V�Y���V�ÓT��`���烍�}���e�B�V�Y���Q����`�ւ̓]�����̌��z�ł��B ��̘A�z���ő�������A�ŏ��̒��ۂ���A���A���Y���ƃi�`�������Y���̌��ꂪ�����Ă��āA �N���V�V�Y��������Ƃ����v���Z�X�͍����̏ɒʂ���Ƃ��낪�����Ĕ��ɋ����[���Ƃ���ł��B" �X�^�[�����O�̌`�Ԃɂ��Ă̊S�́A�����鎞��ɓn��A�V���P���A�A�X�v�����h�A���V�A�\����`�A���E�R���r���W�G �ƂƂ��ɁA�p���̌��z�ƒB�A�z�[�N�X���[�A�A�\�[���A�}�b�L���g�b�V���A�����Ă����ɂ͏o�Ă��Ȃ��������炭���b�`�F���X�ɂ��Ă��A���ɋ����Έ�������Ă����B �����ă��[�}���A�t�����`�A�S�V�b�N�Ȃǂ̂��܂��܂ȗv�f�������Γ��������̒��Ŏ��݂Ɏg���ăf�U�C�������A ���z�`�Ԃ̏N�W�ƃz�[�N�X���[�A�� �g�A�h�E�z�b�N�ȃe�N�j�b�N�h�͂܂��ɋ��łȐܒ���`�҃X�^�[�����O�̂��̂ł��������B |
| �U�DSIR EDWIN LUTYENS(1869-1944) ���b�`�F���X�̃J���g���[�E�n�E�X�\�����ƉI��\ �P�D���@�i�L�����[�E�A�v���[�` �t�B���b�v�E�E�F�b�u�͐v���n�߂�ɂ�����A���̓y�n�ł̍ޗ��A�H�@�ׁA�Â����������A ���������ꂩ��s���v�̊�b�ɐ������Ƃ�����B����̓��@�i�L�����[�E�A�v���[�`�ƌĂ��B �Â��ƁX�ƈꏏ�ɂȂ��āA���̓y�n���琶���Ă����悤�Ȍ��z�A�E�B���A���E�����X�����A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̏Z��ڎw�������̂��B �����X���S���Ȃ�܂ł̂Q�O���N�ԁA�x�ɂ��߂����̂Ɏ�Ă����P�����X�R�b�g�E�}�i�[�́A �Ƃ炵���̏ے��ł���j���i�Q�[�u���j�̘A�Ȃ�f�p�ȕ\�������16���I�G���U�x�X���Ɍ��Ă�ꂽ�Α��̃}�i�[�E�n�E�X�ł���B �����X��E�F�b�u�̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̍l��������s����A���b�`�F���X�̐���������͂����������ゾ�B �O��������ƂƂ��Ċ������A �W�����E���X�L���̎v�z�I�e�����������Ƃ̃K�[�g���[�h�E�W�[�L���B�W�[�L���ɓ�����A�T���[�̃��@�i�L�����[�����邱�Ƃ���X�^�[�g�������b�`�F���X�B ���b�`�F���X�̐v���悤�Ƃ���~�n�̎��ӂɂ́A16,17���I�ɃC�^���A�̃��l�T���X���z���n���������̃S�V�b�N���z�ɍ������n�߂��A �`���[�_�[���A�����ăG���U�x�X���̃Q�[�u���ƃ`���j�[�ƃT���[�B���L�̃o�[�Q�[�g�E�X�g�[���̏Z��������B �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O���A�����̌��~�n�̃R���e�N�X�g��厖�ɂ����悤�ɁA �}�b�L���g�b�V�����X�R�e�B�b�V���E�o���j�A���l���Ƃ������̓y�n�ŗL�̗l����厖�ɂ����悤�ɁA���b�`�F���X���Z��̐v���X�^�[�g������ �T���[�B�̃��@�i�L�����[�̃R���e�N�X�g�ɌŎ������B �P�D�U�E�T���e�[�V���� �Q�D�O���[�g�E�f�B�N�X�^�[ �R�D�v�����v�g���v���[�X 


|
���̂悤�ɃR���e�N�X�`���A���Y����S�������A���b�`�F���X�����̎����ɋN�����A�[���E�k�[���H�[�̂悤�ɁA�V�����l����͍������_�j�Y���̃p�C�I�j�A�ɂȂ�Ȃ�Ă��Ƃ́A�N���肦�Ȃ����Ƃ������B �ߑ㌚�z�j�ł͑�G�c�Ɍ����ƁA�P�X���I�̗l�������@�C���@���A�ܒ���`�̎��ォ��A�������甲���������Ƃ��ċN�����A�[�c�E�A���h�E�N���t�c��A ���I���̃A�[���E�k�[���H�[�Ȃǂ̉^�����o�āA �P�X�Q�O�N��ɁA�̂��ɃC���^�[�i�V���i���E�X�^�C���Ƃ��Ă�� �ߑ㌚�z�����_�j�Y���Ɍ��������Ƃ����B�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�͉p�����哱�������A���̌�̃��_�j�Y���̗h�Պ��Ƃ���鎞�����哱�����̂̓��[���b�p ���邢�̓h�C�c����̖S����̃A�����J�ŁA �P�X�U�O�N��ɃW�F�[���Y�E�X�^�[�����O���o�ꂷ��܂ŁA�p���͊��S�Ƀ��_�j�Y���̗��j�̕\���䂩��O��Ă��܂��B �p���̂��̎����̌��z�ƂƂ��ẮA�}�b�L���g�b�V���ЂƂ肪�A�[���E�k�[���H�[�̖��[�Ɉ����������āA���낤���ă��_�j�Y���̃p�C�I�j�A�Ƃ��ċL�q����邪�A ���������̃��b�`�F���X�ɂ��Ă͈ʒu�t���̂��悤���Ȃ������B�}�b�L���g�b�V�������č��ƂȂ��ẮA���_�j�Y���̃p�C�I�j�A�̈�l�ɐ����邱�Ƃ� ���̈Ӗ����Ȃ��B �Q�O���I�㔼�Ƀ��_�j�Y���ɑ���^�₩�甭�����|�X�g�E���_�j�Y���Ƃ������ۂ̓o�ꂩ������łɌ��\�ȔN��������A���_�j�Y���� ���łɑ��Ή�����Ă��鍡�Ȃ�A���b�`�F���X�̏Z��Ŕނ���낤�Ƃ������Ƃ��A��ÂɌ��邱�Ƃ��ł���̂ł͂Ȃ����B ���_�j�Y���̃t�B���^�[��ʂ��Ȃ��ڂŃV���v���ɂ݂�ƁA���b�`�F���X�̏Z��͖��͈���ނ܂�Ȍ��z�Ƃ��Ėl��̑O�Ɍ���Ă���B �S�D�e�B�O�{�[���E�R�[�g �T�D�S�b�_�[�Y �U�D�z�[���E�b�h�@�@2014�N�ĖK�˂��U�̓@�� 

 |
|
�Q�D�ΏƓI�ȓ�l ���b�`�F���X�̖��O�����߂Ėڂɂ����̂́A1969�N�ɔ��p�o�ł���g���z�̕����ƑΗ��h�Ƃ��Ė|��o�ł��ꂽ���o�[�g�E���F���`���[���̖{�̒��������B ���@���u����z�[�N�X���[�A�A�����ă\�[���̖��O�����l�ɂ��̖{�̒��Œm�����B ���̖����͌��̔ᔻ���炻�̌サ�炭��łɂȂ��Ă������A�ɓ������̐V��ɂ���āA ����"Complexity and Contradiction in Architecture"�̓��C�A�r�C�d���u���z�̑��l���ƑΗ����v�Ɖ��߂��A�����o�ʼn��1982�N�ɏo�ł��ꂽ�B �G�h�E�B���E���b�`�F���X�́A1869�N3��29���ɂP�S�l�Z���̂P�P�ԖڂƂ��āA�����h���Ő��܂�A�T���[�B�̃T�[�Y���[�ň�����B ���`���[���Y�̃��b�`�F���X�Ƃ����c���̓f���}�[�N�N���ŁA�R���ő؍݂��Ă����J�i�_�ŃA�C���b�V���̃��A���[�ƌ������A�A����͊G��Ǝ�ɐl�������������B ���`���[���Y�̎t�ł���F�l�ł�����������ƂŒ����Ƃ́A�G�h�E�B���E�w�����[�E�����V�A���i�g���t�@���K�[�E�X�N�G�A�̃��C�I�����̍�҂Ƃ��ėL���j�Ɉ���ŁA �G�h�E�B���E�����V�A�E���b�`�F���X�Ɩ��t����ꂽ�B �q���̍��̃��b�`�F���X�͕a�ゾ�������ߊw�Z�ɍs�����A��ɉ�ƂɂȂ����U�Ώ�̌Z�t���b�h���狳������B �P�U�̎��A�T�E�X�E�P���W���g���E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�A���݂̃��C�����E�J���b�W�E�I�u�E�A�[�g�Ō��z���w�сA���̌�A�A�[�l�X�g�E�W���[�W �̎������łQ�N�C�s�����̂��A�Q�O�Ŏ��g�̎������𗧂��グ��B �t�����N�E���C�h�E���C�g��1867���܂�A�}�b�L���g�b�V����1868�N���܂�Ȃ̂ŁA����3�l�͓�������̋�C���z���Ă������ƂɂȂ�B ���łɃA�h���t�E���[�X��1870�N���܂ꂾ�����B |
���b�`�F���X�ƃ}�b�L���g�b�V���́A�O���X�S�[�ƃ����h���Ɨ���Ă͂��邪�A�����p���ŁA
��s����t�B���b�v�E�E�F�b�u�ƃ��`���[�h�E�m�[�}���E�V���[�̏�����̐���Ƃ��āA��������Ă������A��l�̐l���͑S���ΏƓI���B
�����ƃn�j�[�}���E�A���h�E�P�s�[�Ƃ����������̏����������}�b�L���g�b�V���́A�O���X�S�[���p�w�Z���I��������ƁA�������̎d���ɋ����������A
1913�N�A�S�T�őސE���A���N�O���X�S�[������A�����h���ֈڂ�B�����đ�ꎟ���Ȍ�͂قƂ�nj��z��i������Ă��炸�A�����f���炵���G���i�͎c���āA
1928�N�A�U�O�Ŏ��ӂ̂����ɖS���Ȃ��Ă���B ����̃��b�`�F���X�́A�N���C�A���g�Ɍb�܂�A��������̓@���v���A �}�b�L���g�b�V���̎�v�Ȍ��z�������قڏI���A1912�N�A�����S0�Δ��̍��ɁA�p���������ɂ������j���[�f���[�̃C���h���@ �̐v���Ϗ������B����͕v�l�̕��e�����ăC���h�̑��ł����������W���Ă���悤���B ����Ȍ�A�ނ̎������̎d���͏Z���A�~�b�h�����h��s�̂悤�ȑ傫�Ȏd���Ɉڂ�A���������g�債�Ă������B �}�b�L���g�b�V�������z�����葱����̂��s�\�ɂȂ������傤�Ǔ������A ���b�`�F���X�͐V���ȑ傫�ȃX�e�b�v�ݏo���Ă���B ���̌�A��ꎟ����ʂ�߂��A��Q����풼�O�܂� ��i����葱���A1944�N�ɂV�T�ŖS���Ȃ�B ���b�`�F���X�̑S���z��i���̓v���W�F�N�g���܂�300���z����B �p���ɂ����錚�z�̗��j�̒��ŁA���o������̍˔\���A����������Ȃ���A����Ȃɂ��Ⴄ�l���𑗂��Ă���B |

| |
|---|---|
|
���b�`�F���X�̏Z��̏����̃N���C�A���g�́A�Ƒ��̗F�l��W�[�L���E�T�[�N�����������A1�X�O�O�N�ȍ~�̓V���E�̃N���C�A���g�Ɠ����悤�ɁA
��s�ƁA�����ƁA���ƉƁA�����ƎҁA���������l�A�Ƃ������T���ȁA��������ɂ����鎩�����̗͂Ő���オ�������ƉƂ������Ȃ�B ���B�N�g���A��(1837-1901)�̌���A1960�N�ȍ~�́A�V���ɖu�����Ă�������璆�Y�K���̐l�X�̋��߂ɉ����� ���z�Ƃ����������̏Z����������A�Z����i�h���X�e�B�b�N�E�����@�C���@���j�ƌ����鎞���ł������B ���b�`�F���X�̏Z����A���������l�X�̂��߂́A�w�ǂ��l���Ă�ŁA�p�[�e�B�����邽�߂̃Z�J���h�E�n�E�X�ŁA��r�I�傫�Ȃ��̂������B �P�X�P�O�N����P�X�R�O�N�܂łQ�O�N�����������A�L���b�X���E�h���[�S�Ƃ����J���g���[�E�n�E�X�����邪�A ����Ȃǂ́A�R���r���W�G���T���H�A�@�������Ă����A���_�j�Y���̖u�����Ɠ�������Ƃ͍l�����Ȃ��悤�ȁA�Α��̂���̐V�z�ł���B ���b�`�F���X�͏Z�����擱�������`���[�h�E�m�[�}���E�V���E(1831-1912)�ƃt�B���b�v�E�E�F�b�u(1831-1915)�Ƃ�����l�̐�B�� ���h���Ă����B �V���E�ƃE�F�b�u�̓�l�͓����N�ŁA�C�Ǝ��������G.E.�X�g���[�g�̎������ʼn߂����A�Ɨ���A�E�F�b�u�͂��̓y�n�ŗL�� �X�^�C����厖�ɂ��郔�@�i�L�����[�Ȑܒ��̕����A�V���[�͒����ȗ��̔_�Ƃ�[���Ȃǂ̃��`�[�t�̃s�N�`�����X�N�Ȑܒ� �̕����Ƃ��������Ⴄ�s�����ŁA���̎����傫�����[�h�����B |
�}�b�L���g�b�V���ƃ��b�`�F���X�͓�l�Ƃ��A�V���E�ƃE�F�b�u�A���ɃV���[����`�ԓI�ȉe�����Ă��āA �O���X�S�[�E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�ɂ��V���E�̍�i�Ƃ̕����I�ȗގ��_���������w�E����Ă���B �V���E�͐��U�A���@�i�L�����[�̃N�C�[���E�A���l������A�����̃X�^�C���̃����@�C���@�����o�āA�o���b�N�ւƃX�^�C����ϗe�����Ă������� ���̕ϗe���Ȃ���悤�Ƀ��b�`�F���X���A���@�i�L�����[���烌�����i���b�`�F���X�͟����ă����l�T���XWrenaissance�ƌĂԁj�A �����ăo���b�N�ւƃX�^�C����ϗe�������B �E�B���A���E�����X�̃��b�h�n�E�X��v������A���������Ŏ�ɏZ���i���������E�F�b�u�ƑΏ� �I�ɁA�V���E�͑厖�����������āA�Z��ȊO�̑傫�Ȏd�����܂߂đ�ʂ̎d�������Ȃ����B���̃V���E�̐������ɁA���b�`�F���X�͑傫�ȉe�����A�G�~���[�E���b�g���Ƃ̌����ɍۂ��� �V���[�̎��������̂������u���[���Y�x���[�E�X�N�G�A29�Ԓn����ĐV���ɂ��Ă���B ���b�`�F���X�́A1898�N������1906�N���܂ł�10�N��̊ԂɁA��ʂ̂悤�ȃJ���g���[�E�n�E�X���c���Ă���B���Ƃ�����ȍ~�������Ȃ������Ƃ��Ă� �d�v�Ȍ��z�ƂƂ��Ė����c�������낤�ƌ����Ă���B �ꌩ����Ɖp���̓`���̃A�m�j�}�X�ȃJ���g���[�E�n�E�X�ƂقƂ�Lj��Ȃ������郉�b�`�F���X�̏Z��̒��g���A���͖L���Ȍ��z�I�V�с\�E�B�b�g���܂A ���s���̐[�����z�ł��邱�Ƃ��������茩�Ă����Ɣ����ł���B �g�E�B�b�g�̂Ȃ�����Building���A���zArchitecture�Ƃ͌���Ȃ��h�Ƃ̓��b�`�F���X�͌��t�ł���B |
|
�R�D�}���X�e�b�h�E�E�b�h Munstead�@Wood 1893-1897 ���b�`�F���X�̌��z�ƂƂ��Ă̐��U���l����Ƃ��A�K�[�g���[�h�E�W�[�L��(1843-1932)�Ƃ����������|�Ƃ� �J���g���[�E���C�t�̎В��ł���G�h���[�h�E�n�h�\���Ƃ�����l�̐l���̑��݂������čl���邱�Ƃ͏o���Ȃ��B 1889�N�Ɏ�������ݗ����钼�O�A20�̎��Ƀ��b�`�F���X�̓K�[�g���[�h�E�W�[�L���ɏo������B ���݂ɗL����"�W�L�����m�ƃn�C�h��"�� ��҃X�e�B�[�����\�����ޏ��̖���̗F�l���������Ƃ����l���̖��O�Ɏg��ꂽ�Ƃ������Ƃł���B�܂�Jekyll�̔����ɂ��āA�뉀�j�ƃW�F�[���E�u���E���͒��� "Gardens of a Golden Afternoon"�̒��ŁA�htreacle�i�����j�̂悤�ɁA"e"��������������h�ƌ����Ă���B����ɏ]���Γ��{��\�L�̓W�[�N���A�܂��̓W�[�L�����߂��B �W�[�L���́A ���b�`�F���X���26�ΔN��̃T���[�B�ɏZ�ޗT���ȏ����ŁA�P�V�̎��A�S�N�O�ɐݗ���������̃T�E�X�P���W���g���E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�ɒʂ����̂��A ��ƂƂ��ăX�^�[�g�������A�G�悾���łȂ��A�ؒ��A��H�A�^�y�X�g���[�A�h�J�A�ʐ^�ɂ��G�łĂ����B ���ƌ�A�W�����E���X�L����E�B���A���E�����X�ɉ�ɍs���A�ނ�Ƃ̌𗬂���A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̒��ړI�ȉe�����A ���p�ƍH�|�Ɛl���͔ޏ��ɂƂ��ĕ����s�\�Ȉ�̂��̂ɂȂ����B ����������Ɏ��͂������A�S�V�̎��Ɋ�Ȉォ��G��Ǝh�J��f�O����悤�w�����ꂽ���ƂŁA�c��������e���݁A ���̍��܂łɂ͂��łɖ��O��m����悤�ɂȂ��Ă��������Ɖ��|�̊����ɏd�_���ڂ����B ���B�N�g���A���̖џ��Ԓd���̑����ߑ��Ȓ뉀�l�����������A�p���`���̏��K�͂Ȓ뉀�A�g�R�e�[�W�E�K�[�f���h�́A���N�������R�ɔɖ����A�F�ʂ��d������뉀 �𐄏����A���H��������Ŗ����c���������Ƃ̃E�B���A���E���r���\����32�̎��ɏo������B �W�[�L���̓��r���\������傫�ȉe�����A�]���̕��i���뉀�����A��莩�R�ɋ߂������A������������ ��Â������A�G��̐F�ʗ��_�Ɋ�Â��K�[�f���f�U�C�����肪���A����Ɍq����C���O���b�V���E�K�[�f���̌������������B �P�T���̒���������A���ł��P�Q�Ԗڂ̒���ł���A��P�����̎n�܂�P�X�P�S�N�A�V�O�̎��ɒ������gColour Schemes for the Flower Garden"(�y�����q��g�W�[�L���̔�������h)�� �x�X�g�Z���[�ɂȂ�A�Q�O���I�ɂ���������Ƃ��e���͂̑傫�ȉ��|���̂P���ł���ƌ�����B �������߂��������@�}���X�e�b�h�E�E�b�h�̒�ł̃K�[�f�j���O�̎��H�̏��ł���B ���b�`�F���X�ɐv���˗����A���g���둢����s�������@�A���̃}���X�e�b�h�E�E�b�h�Ȍ�A���b�`�F���X�̌��z��⊮���邩�����ŁA���z�Ɛ藣���Ȃ��������̒뉀���c�����B ���b�`�F���X�̌��z�ƃW�[�L���̒뉀�̃R���{���[�V�����́A�ŏ��͋��ɕ~�n��K�ˁA���́B�c�_����Ƃ��납��n�܂������A�̂��ɂ̓W�[�L���͕~�n��K�˂�̂�����Ȃ�A ���b�`�F���X����~�n�̏̐������A��Ă����A�ӌ����������A���b�`�F���X���`�ɂ���Ƃ����ߒ��B �W�[�L���̒뉀�̓��b�`�F���X�̌��z�ɑ傫�ȉe����^�������A���b�`�F���X�Ƃ̃R���{���[�V�����͂܂��W�[�L���ɂƂ��Ă��A ���g�̃K�[�f�j���O�̐��E��傫���L���鎖�ɂȂ����B �A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̉e�����ɂ������W�[�L���́A�}���X�e�b�h�E�E�b�h�̐v�����b�`�F���X���X�^�[�g����ɓ�����A �Ⴂ���b�`�F���X�ƂƂ��ɁA�T���[�B�̓`���I�Ȍ��z�A17,8���I�̃t�@�[���n�E�X�́A�\�@�A�d��ޗ��A�����Ă���炪��錚���̌`�Ԃ����A ���@�i�L�����[�ȁi���̓y�n�ŗL�́j�`����厖�ɂ��邱�Ƃ����b�`�F���X�ɝȂ����B �W�[�L���́gOld West Surrey:Some Notes and Memories�h�Ƃ���1904�N�ɂ��̐��ʂ��o�ł��Ă���B ����͓����悤�ɃT���[�B�ň炿�A�q���̍�����E�l�̓����Ƃ��������̂��D�����������b�`�F���X�ɂƂ��Ă�����e�����z�A�H�@�A�`�Ԃł������B �܂����̍��̃T���[�B�ł́A1860�N�ォ��N���������Y�K���̂��߂̏Z��݃u�[���A�h���X�e�B�b�N�E�����@�C���@���� �E�F�b�u��V���E�A���̑��̌��z�Ƃ̌���𐔑������邱�Ƃ��ł����B ����A���b�`�F���X�̐l���ɂƂ��Č������Ȃ�������l�̐l���G�h���[�h�E�n�h�\���́A�u�J���g���[�E���C�t�E�C���X�g���C�e�b�h�v�Ƃ����G����1897�N�ɑn������B �ŏ��͎�̎G�����������A�����ɃJ���g���[�E�W�F���g���}���̂��߂̐����̂�����ʂ��܂G���ƂȂ�A ������̒��ɂ͏Z��ƒ뉀���܂܂��B �E�B���A���E���r���\���̎�ɂ���u�U�E�K�[�f���v�Ƃ����G���ɃW�[�L���͊�e���Ă������A 1900�N�Ɂu�J���g���[�E���C�t�v���ƍ����������߁A�n�h�\���ɐ����Ĕ��\�̏���J���g���[�E���C�t�Ɉڂ����B �₪�Ĕޏ��̓n�h�\���Ƀ��b�`�F���X�𐄏����A�}���X�e�b�h�E�E�b�h���u�J���g���[�E���C�t�v���Ɍf�ڂ���邱�ƂɂȂ�A ���b�`�F���X���G�h���[�h�E�n�h�\���ƌ��т������������������B | 
   |


| |
|---|---|
|
�K�[�g���[�h�E�W�[�L�������b�`�F���X�Ɉ˗������W�[�L���̎��@�}���X�e�b�h�E�E�b�h�́A1893�N�ɐv���X�^�[�g���Ă���B
���݂Ƀ}�b�L���g�b�V�����O���X�S�[�E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�̃R���y�ɎQ�������̂�1896�N�ł���B
��l�̍̋߂����z�Ƃ��A�قړ������A���̌�̐l���ɂƂ��ďd�v�ȈӖ������d���̃X�^�[�g���C���ɗ����Ă���B �n���Y�̌��z�ޗ����g���A�����̂悤�ȐE�l�Z���g�������z���߂������}���X�e�b�h�E�E�b�h�́A�W�[�L���̈Ӑ}�ʂ�A�`���[�_�[���A�G���U�x�X��������Ƃ���T���[�E���@�i�L�����[�̊O�ρA �d�グ�ޗ��A�H�@�ŏo�������z�ŁA�����ɂ͐̂Ȃ���̉����p�^�C���A�����̃`���j�[�A �O�ǂɂ͒n���Y�̃o�[�Q�[�g�E�X�g�[�����g���Ă���B�k���̒���̊O�ǂ����́A��͂�T���[�ł悭������`���[�_�[���̃n�[�t�e�B���o�[�̕ǂɂ��Ă���B �\���ނƂ��Ēn���Y�̃I�[�N�ނ��g�������̂��������ɃI�[�N�ނ̗��⒌��K�i�̎萠�������Ă���B �I�[�N�ނ͌ÂтČ�����V���o�[�O���C�F�ɂ��邽�߂ɁA�\�ʂɔM���ΊD��h�����ケ���藎�Ƃ��Ƃ����H���������Ă���B �R�̎��^�̕��ʂ̓쓌�R�[�i�[�ɍׂ��|�[�`���˂��o�Ă���B |
�k���̓��H����A�v���[�`����ƁA�����ʂ̃t���b�g�ȑ傫�ȕǖʂ̍����ɃA�[�`�̕t�����J��������A ����������ă|�[�`�ɓ���ƁA�E��Ɍ��փh�A�������B(�㍶�ʐ^) ���ւ����ƃ��F�X�e�B�r�����A�_�C�j���O�A�g�F�̂���z�[���ւƑ����B�z�[���̑�����́A���̎Ő��̍L����̌������ɐX�ւƓ��铹��������B �z�[���̓˂�����̒g�F�̉��ɂQ�K�ւ̊K�i�A���̌��ɊK�i�̓r���������}����������A�����瑤�̓ˏo���́A�W�[�L���̊G��H�|�̂��߂� ���[�N�V���b�v�A���|�p�̎�������A���̐�ɒ�ɏo��h�A������B �R�̎��̓����̓ˏo���̓L�b�`������ŁA����̎�����T�[�r�X�������͂�ł���B�V���v���ŋɂ߂ċ@�\�I�ȁA�����̂Ȃ��A�f���ȕ��ʍ\�������Ă���B �Q�K�̓�ʂɂ���V�����g���J���ȓ�̐Q���Ƃ��̗��[�̒g�F���A���ʂ̓�A�̃Q�[�u���Ƃ��̗��[�̃`���j�[�ɑΉ����Ă��邪�A �E���̓ˏo����|�[�`�Ƃ̃o�����X���炩�A���ǂ��Ȃ��� �����̃`���j�[��O�ʂɈړ����킴�킴�V�����g���[������Ă���B���b�`�F���X�̓��ӋZ�ƌ�����A�V�����g���A�E�V�����g���̔����ȗ��ʁE���ʂ̂��߂������₷���Ƃ��_�Ԍ����Ėʔ����B(��E�ʐ^) |
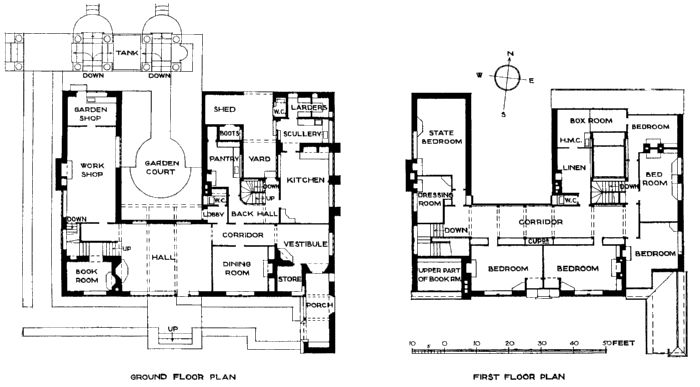
|
|
|---|---|
|
�S�D���E�{���E�f�E���`�G Le Bois des Moutiers 1898 �t�����X�̃m���}���f�B�n���A���@�����W�����B���E�V���[���E���[���Ƃ������Ƀ��b�`�F���X�̐v�����Z�����B 1898�N�A���b�`�F���X29�̎��̍�i�ł���B ���b�`�F���X�v�l�G�~���[�̏f�ꂪ�A���̏Z��̃N���C�A���g�ł���M���[���E�}���̕v�l�A���A���[�E�A�f���C�h��m���Ă����A�Ƃ����W�ň˗����ꂽ�d���ł���B 1900�N�̃p�������̉p���̉^�c�ψ��ł������W�[�L���̌Z�̐��E�ŁA���̍����b�`�F���X�́A�p�������̉p���p���B���I���̐v�҂Ɏw������A ���̏����Ńp���ɗ��Ă����B���̃��b�`�F���X�Ƀ}�������ډ���Đv���˗������Ƃ����o�܂ł���B �}�����w�������~�n�ɂ́A�������̋�`���ʂ̊�������������A�}���̈˗��́A���̋�̂��c���A���p���� �A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̃e�C�X�g�ő����z���{���ė~�����Ƃ������̂ł������B �؍ȉ����̓��[�Ɛ��[�ɗ����オ��傫�ȉ��˂ɋ��܂ꂽ�����������ŁA ���b�`�F���X�͂��̋�`���ʂ̐����ɁA�~���[�W�b�N�E���[���A�����ɃT�[���B�X����lj����A����ɋ�`�̓쐼���ɃG���g�����X/�K�i����t���������B �ʐ^�E�F�k�ʁA�ˏo�����~���[�W�b�N�E���[���̃A���R�[�u�B�����F�G���g�����X/�K�i���B�����F��ʃ~���[�W�b�N�E���[���ƃG���g�����X�̓ˏo���B ���E�F���ʃT�[�r�X�����̃E�B�b�g�ɕx�G�����F�[�V�����B �N���C�A���g�̉p���̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�ւ̕Έ�����A�Ƌ�̓A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̃e�C�X�g�ł܂Ƃ߂��A ���b�`�F���X�E�f�U�C���̉Ƌ�������X����ō��ꂽ�B ��X�̃N���C�A���g�͒둢�����������悤�ŁA�W�[�L���̒�͈�����A�ƂĂ�������ԂŌ��݂܂ňێ�����Ă���B �Ǝ�̈������A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̕��͋C���c�������b�`�F���X�̏Z��ƁA�W�[�L���̃f�U�C�������L��ȃC���O���b�V���E�K�[�f���́A ���|�D���̉Ǝ�ɂ���Ă悭����ꂳ��A100�N�ȏ�̎����o�������A�܂��܂��P���𑝂��Ă���B ���b�`�F���X�ƃW�[�L���̃R���{���[�V�����̑�ꋉ�̍�i���A������������p���ɂ���ǂ̍�i���� �����`�Ńt�����X�ɕۑ�����Ă���̂�������Ȃ��B | 
 |



| |
|---|---|
|
�~���[�W�b�N�E���[���́A�쑤�ɃM�������[�̂���Q�w���̓V��̍�����������ԂŁA�k���̃s�A�m�̒u���ꂽ�A���R�[�u�ɂ�
�����ɊC��]�ށA����7���̑傫�ȊJ��������B ���̊J���ׂ͍�����`�ɕ�������A�O�ώʐ^���킩��₷�����A�c�ɂP�P���`�̘A�Ȃ�́A ���S�̗�̗����A�R�I���G�����̌`��ɂ������Ă���B ���̃v���Y����̏c���̃I���G�����̃��`�[�t�͒P�ƂŁA�쑤�̃G���g�����X/�K�i���̓ˏo���ɂ��J��Ԃ����B �ׂ�����`�ɕ������ꂽ���̊J���̃f�U�C���́A��u�}�b�L���g�b�V�����v�킹�邪�A �}�b�L���g�b�V���Ƃ͏����Ⴄ�e�C�X�g�������A�ƂĂ��V�N�Ȉ�ۂ̑����B |
�}�b�L���g�b�V���̉e�����Ƃ�����]�����������A�q���n�E�X��1902�N�ɁA�E�B���f�B�E�q���ł���1899�N�ɐv���J�n���Ă���̂ŁA
�{���E�f�E���`�G��菭���x���A���ڂ̉e���͂��肻�����Ȃ��B �ނ��냉�b�`�F���X������A�}�b�L���g�b�V�����e������ ���`���[�h�E�m�[�}���E�V���[���炫�Ă���C������ �����A������O�O���X�S�[�ɂقNj߂����X�j�[�X�Ƃ������ŁA���b�`�F���X�̓t�F���[�E�C���i1896-97�j�Ƃ����Z�������Ă��āA ����֍s���r���A�W���[�W�E�E�H���g���v�Ń}�b�L���g�b�V����������������u�L���i���E�X�g���[�g�E�e�B�[���[���Ɋ���Ă���̂ŁA ���炩�̉e���͂������̂�������Ȃ��B |


| |
|---|---|
|
���̏Z��́A���̃��b�`�F���X�̏Z��Ǝ�قȂ�A������������E�F�b�u�⃔�H�C�W�[�����ă}�b�L���g�b�V��������ł����̂Ɠ�������́A�j���[�E�A�[�g�ƌĂꂽ
�V��������Ɋ��Y���A�S���Ⴄ���b�`�F���X������ꂽ��������Ȃ��A����Ӗ�����_�̗l����������Z��ł���B ���������̑O��ɂ����̃t�F���[�E�C����U�E�v���U�E���X�ȂǁA�����e�C�X�g�̏Z����������Ă͂��邪�A1913�N�ɃJ���g���[�n�E�X�Ђ��� ���s���ꂽ���b�`�F���X�̏Z���i�W�ɂ͂����̏Z��͌f�ڂ���Ă��Ȃ��B �傫�Ȍ�돂�ł������A�n�h�\���ƃW�[�L�����Ƃ��ɁA�{���E�f�E���`�G�̐V����������]�܂Ȃ������Ƃ������Ƃ����m��Ȃ��B �}���X�e�b�h�E�E�b�h�̑O�A���b�`�F���X�̓W�[�L���ƂƂ��ɁA�ߕӂ̃T���[�B�̃��@�i�L�����[�ȏZ���T�����Ă���B ���̓y�n�ŗL�̍ޗ��A�e�C�X�g���g�����Ƃ��A�W�[�L���͓O�ꂵ�ċ��߂��B |
�������T���[�B�ȊO�̓y�n�ŁA�Ⴆ�O���X�S�[�̍x�O�̃t�F���[�E�C���ł́A���t�L���X�g���ނ��냔�@�i�L�����[�� �O�ς������̂́A���̓y�n���L�̃X�R�e�B�b�V���E�o���j�A���E�X�^�C���P�����}�b�L���g�b�V���̏Z����ςĂ��킩��B ���b�`�F���X�́A���s��̃X�^�C���ɌX�����Ƃ������A�W�[�L���ɋ�����ꂽ�A���@�i�L�����[�ȃX�^�C����厖�ɂ��邱�Ƃ��A�t�����X�̂��̒n���ł����s���� �ɉ߂��Ȃ��Ƃ����������ł���̂ł͂Ȃ����낤���B �J���g���[�E���C�t�̃n�h�\����A���b�`�F���X�̍�i�W��҂E�B�[�o�[�́A���s��́g�j���[�E�A�[�g�h�� �h�C�c��I�[�X�g���A�������X�^�C���Ƃ��Č������Ă����B�t�F���[�E�C���̓��b�`�F���X�ɂƂ��Ă̓��@�i�L�����[�ȃX�^�C�����������A ���ɏc���̃I���G�������A�}�b�L���g�b�V���ɑ�\�����g�j���[�E�A�[�g�h�̏ے��̂悤�Ƀn�h�\����E�B�[�o�[�A�W�[�L���� �����A��������������̂�������Ȃ��B����Ȍド�b�`�F���X�̏Z��ɂ��ׂ̍�����`�ɕ������ꂽ�^�C�v�̃I���G�����͌���Ȃ��B |



|
|
|---|---|
|
�T�D�S�_�[�YGoddards 1898-1899�^1910 �S�_�[�Y�͓����A�Z��ł͂Ȃ��A�Ō�t�A�ƒ닳�t�Ƃ������A�o�ϓI�ɗ]�T�̂Ȃ��A�������������̂��߂ɁA�����h���̌����𗣂�ċx���̂ł���Ă� �ۗ{�{�݂Ƃ��Čv�悳�ꂽ�B�܂���A�t���J�푈(1899-1903)�̌�͏��a���̂��߂̎{�݂Ƃ��Ă��g��ꂽ�B �v���O�̃��V�A�̃��X�N����T���N�g=�y�e���u���O�ŁA�����̃f�p�[�g�o�c�ɐ��������A��������������̐e�̑D��Ђ��������p�����A �x�T�ȃX�R�b�g�����h�l�̃~���[���X�Ƃ����l�����̎��P���Ƃ��v�悵�A���b�`�F���X�ɐv���˗������B �T���[�ɂ̓W�[�L���̑��ɂ�����l�A���b�`�F���X�Ƒ����̃N���C�A���g�����т����o�[�o���E�E�F�b�u�Ƃ����l�����āA���̐l�̉ƂŃ��b�`�F���X�� �~���[���X�Ɛe�����Ȃ����B �~�n�ɂ͐́A�S�_�[�Y�ƌĂꂽ�}�i�[�n�E�X�������Ă����B���̂��Ƃ����E�Ώ̂�H�^�Ƃ�������v���������b�`�F���X���̗p�������R��������Ȃ��B ���̍����b�`�F���X�͏T���́A�W�[�L���̃}���X�e�b�h�E�E�b�h�́A���b�`�F���X�����R�Ɏg����悤�ɂȂ��Ă����X�^�W�I�ŁA�v���W�F�N�g�̃X�P�b�`������ �߂����A�܂��W�[�L���ƂƂ��ɃT���[�n���̃��@�i�L�����[��K�˕����Ă����B ���̒T���s�͂̂��Ɂg�I�[���h�E�E�F�X�g�E�T���[�h�Ƃ����W�[�L���̖{�ɂ܂Ƃ߂�ꂽ�B �������ăW�[�L���ɂ���ă��b�`�F���X�ɍ��荞�܂ꂽ�T���[�̃��@�i�L�����[�Z��̃��H�L���u�����[�̉e������A �����܂ł̃��b�`�F���X�̏Z��ɂ̓V�����g���[�̕��ʂ͌���ꂸ�A�S�_�[�Y�����߂Ăƌ�����B ���ۂɂ́AH�^�ƌ������A�Q�K���ẮA�V�����g���[�̃R�̎��^�̗��T�C�h�̓r������A�K���̂悤�ɂP�K��H�����܂��ē��H���ɐL�����A �ƌ������������������m��Ȃ��B �F���W�܂�A�j�ƂȂ�R�������[���������ɂ����āA�����ɂ͂P�K�ɂ͓엃�ɃX�^�W�I�A�k���Ƀp�[���[�A�Q�K�ɐQ���������āA �R�̎��^�ɃK�[�f���E�R�[�g���͂݁A�K�������H���̃t�����g�E�K�[�f�����͂ށB �������̃K�[�f���E�R�[�g�́A�ߌ�̌����ő���̂����邽�߂ɁA90�x�ł͂Ȃ�102�x�ɏ����J������`�����Ă���B �쑤�̐K���́A����]������9�{�̃s����|���ėV�ԁA�{�E�����O�̑O�g�̂悤�ȁA�X�L�g���Ƃ����Q�[���̂��߂̕����A�X�L�g���E�A���[�ŁA �k�̐K���ɂ́A�_�C�j���O�̔����ƃL�b�`���̕t�����������Ă���B ��̋��E�͎l�����A�Ⴂ�����Ɉ͂܂�A�T���[�n���ɐ̂��炠�邳�܂��܂ȐA�͂������̍ۂɂ܂ł��܂�A�F�����Ԃ̍�����ق̂��Ɏ����ɉ^�ԁB ����A�K�[�f���E�R�[�g�́A�~�`�̈�˂𒆐S�ɁA�����ɃA�b�v�E�_�E������ܐƐA�͂ŁA�L���Ɋw�I�ɍ\������Ă���B �����̓��ƊO�݂͌��Ɉ������č����悤�Ɍ����ɗZ�����Ă���A �P�O���܂�̃��b�`�F���X�̌��z�E�W�L���̑����̃R���{���[�V�����̒��ł��A�ł�����������ł͂Ȃ����Ǝv���B �����v�����͓����̂��̂����A�v�H��10�N�o����1910�N�A�N���C�A���g�̎q���v�w�̏Z���ɕύX���邽�߂̑��z���A�Ăу��b�`�F���X�Ɉ˗����ꂽ�B �둤�̗��E�B���O�������L����āA���ꂼ��엃�ɏ��ցE���C�u�����[�k���Ƀ_�C�j���O�Ƃ�����E���v�����̌��݂̌`�ɂȂ����B ���E�B���O�����ɐL�т��[���̗��ʂ̌��I�ȕω���A�L�����������Ƃ����͂���u�₷�鐶�_�̊w�I�`�ԁA �ڒz���ꂽ�[���ɂ��G���g�����X�̓����̕ϖe�ȂǁA���̑��z�ōs��ꂽ�������͂ƂĂ��d�v�ŁA�������Ȃ̂ɁA���Ⴆ��قǂɂ��̏Z��̖��͂��������B |  

|
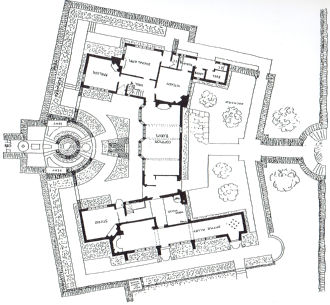
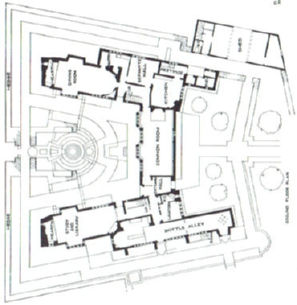
| |
|---|---|
|
1910�N�̑��z���ɁA�N���C�A���g�ɂ���čw�����ꂽ17���I�̔[���̌������A���b�`�F���X�͖k���̓��H�ۂ̃G���g�����X�ւ̖k����h���ʒu�ɔz�u�����B ���݂̕~�n�ւ̓����͂��̔[���̘e�̒��ԃX�y�[�X�ɂ���A�K���[�W�p�̏����̕ǂ̓��H���猩����ʒu��"GODDARDS"�̃T�C��������B �[���̊Ԃ̒ʘH���A�ǂɂ����Ĉړ�����ƁA �L�b�`���̏�����Ɏ���A�܂������A�[�`�^�̃g�s�A���[�����ƃG���g�����X�E�R�[�g�ւƎ���B ���S����ɂ���Y���^�̓�̖،˂͂��܂�g���Ă��Ȃ��悤���B���̉�荞�ރA�v���[�`�́A�l���������b�`�F���X���ӂ̓��������ɂ����Ă���B |
�G���g�����X�̂��铌���ʂ́A���E�Ώ̌`�ŁA
�����ɁA��s���郔�H�C�W�[���悭�g�p���A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̌��z�Ƃ����A
���ɃE�F�b�u���g�ƒ�炵���h���Î�����Ƃ��čD�A�ƌ`���Q�[�u��(�j��)���A�Ȃ�A
�}���X�e�b�h�E�E�b�h�̃t�@�T�[�h�ɂ��g��ꂽ�g��A�Q�[�u���h�𒆐S�ɁA
�}�b�V�u�ȉ��˂����T�C�h�ɛ�������B �g��A�Q�[�u���h�Ɨ��T�C�h�̃}�b�V�u�ȉ��˂̃��`�[�t�́A���̌�e�B�O�{�[���E�R�[�g�A�z�[���E�b�h�ŁA�O�A�Q�[�u���Ƃ��ă��b�`�F���X�Ǝ��̃f�U�C���ɐ�������Ă����B ����Ƀz�[���E�b�h�ł́A�O���؍ȉ����́A�����S�̂̒f�ʂ��t�@�T�[�h�ɕ\�����ꂽ�`�Ɍ�������B |


| |
|---|---|
|
2014�N�̉āA�����h���ɑ؍݂��A�̏Z�ƁA�v���o�̒n��40�N�Ԃ�Ɍ��ĉ�����̂��@�ɁA���b�`�F���X�̏Z����v�U���K�˂��B ���邱�Ƃ̏o�����Z��̒��ŁA�S�_�[�Y�ɂ��ǂ蒅���̂ɂ͈�Ԏ���Ă����B�����ׂ��s�\���ŁA�n���̃A�r���W���[�E�R�������A �A�r���W���[�E�n�}�[�Ǝv���Ⴂ�����Ă����̂��������B ����ɁA�r���ŋ����Ă��ꂽ�l�̕`�����n�}���A�s�\���ŁA�����Ă������Ă����Ȃ��B ���{�قǏ����͂Ȃ��������A�Ă̗z�˂��̉�������������B �A�����Ă���O�[�O���E�}�b�v�Ŋm�F������A�~�n�̂����߂��Ƀo�X�₪�������B | �Q���ԋ߂������������A�قƂ�� ���߂������Ƃ��ɒʂ肩�������Ԃ̑��������o���āA�����Ȃ�m���Ă���A�悹�čs���Ă�����ƌ����Ă����e�Ȑl�ɏo������B �Ⴂ�����̉ԉ�����ŁA�߂��ɉԑ���͂���̂ŁA�����Ɋ���Ă���ł悯��A�ƌ����B���������_�������̂ŁA�������A���Ȃ����肾�����B ����Ƃ̎v���ł��ǂ蒅�����S�_�[�Y�ɂ́A���b�`�F���X�E�g���X�g�̖{��������A�������ς邱�Ƃ��o�����B �h���V�[����Ƃ����g���X�g�̐l���A�����ē����Ă��ꂽ�B |

| |
|---|---|
|
�P�X�P�O�N�ɑ��z���ꂽ���փ��C�u�����[���A���݃��b�`�F���X�E�g���X�g�̖{���Ƃ��Ďg���A
���b�`�F���X�̃E�B�b�g�̂���y�����f�U�C�������֎q��������Ă���B�h���V�[�����b�`�F���X�̃f�U�C���ɂ��Ă��낢��������Ă����B |
��`�̏o���ɂ���ăW�L���̒뉀�����߂��Ɋ���������B�g�F����͗����ς݂��l�X�ȕ\��������A���ӂ̃V�[�g�̏�ƁA�g�F�̉E�T�C�h�ɔz�u���ꂽ�����ȑ���
���Â�����A�e���ȕ\��������Ă���B
|



|
|
|---|---|
|
�{�E�����O�Ɏ����Q�[�������邽�߂̃X�L�g���E�A���C�̕����̓����K�̃A�[�`�̘A���ɂ���Ďx�����Ă���B
���܂��ܓ������̃}�b�L���g�b�V���̃O���X�S�[���p�w�Z�̑��z���̍ŏ�K�̃��b�W�A�������h���Ă͂��邪�A�����\���ł���B ���ʐ}������ƁA���̎ʐ^�ł��킩��悤�ɁA�Q�K�̐Q���̕Ў����̏����ׂ荇�������K�ǂɓn���ꂽ���ɂ���Ďx�����A�X�L�g���E�A���C�̏�ɒ��o���Ă���B |
�O���ɂ̓����K�̃A�[�`�̈ʒu�ɁA���͂���߂̃o�b�g���X����яo���Ă���B �f�U�C���I�Ɍ���ƁA�߂̃o�b�g���X�͓�����̃��H�C�W�[�̍�i�ɂ悭�o�ė��郂�`�[�t�ŁA ���b�`�F���X�͍\���I���R���炾���łȂ����̃f�U�C�����D�悤�ŁA��� �t�H�[���[�E�t�@�[���ł������K�̎߂̃o�b�g���X���g���Ă���B |


|
|
|---|---|
|
�}���X�e�b�h�E�E�b�h�ɑ����A�����������o�����Ƃ��Ȃ�����A���b�`�F���X�͂��̍��T���[�E���@�i�L�����[�̃��H�L���u�����[�ŏZ��������Ă����B
�S�_�[�Y�ɂ��A�Q�[�u���Ɖ��˂̍��������A�E�g���C���A�B�����ɕ\�����ꂽ�؍\���A��������������ǂɁA�J��������̃����K�̉����Ȃǂ̃T���[�B�̃��@�i�L�����[��
���ꂪ���p����Ă���B |
�����̏㕔�̐Ԋ����A���߂��ɂȂ��āA�z�[�V�����̃X���[�g�ɐ�ւ��A���̂Ȃ̂��s�v�c�Ɏv�����f�U�C�����A
�T���[�B�ɓ`���I�Ȍ������痈�Ă���悤���B
�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̋�C�̒��ŁA�t�B���b�v�E�E�F�b�u��`���[�h�E�m�[�}���E�V���[�Ƃ�����l�̐�s����̑�Ȍ��z�Ƃ������g��A�Q�[�u���h
�g�o�^�t���C�E�v�����h�̂悤�ȃ��H�L���u�����[���A���b�`�F���X�͎���Ɏ����Ǝ��̂��̂ɏ����čs���B |


| |
|---|---|
|
�o�^�t���C�E�v�����ɂ��Č����A�O���C�E�E�H�[���Y����p�s�����E�z�[���ւƔ��W�����A�C�f�B�A�̖G�肪�A�S�_�[�Y�́A
��葽���̑��z���̂����悤��102�x�ɊJ�����v������
�݂���ƌ����Ȃ����Ȃ��B���`���[�h�E�m�[�}���E�V���[�̃o�^�t���C�E�v�����̖���g�`�F�X�^�[�Y�h�����b�`�F���X�͂P�X�O�P�N�ɖK�˂Ă���B �G�����ꂽ�Ƃ��Ă��A���b�`�F���X�̒����A�O���C�E�E�H�[���Y��p�s�����E�z�[���́A�����ƕʂ̓Ǝ��̍��݂ɒB���Ă���ƌ����Ă����̂ł͂Ȃ����B |
1910�N�̑��z�̎��ɁA�k���̃_�C�j���O�Ɠ엃�̏��ցE���C�u�����[�ɂ́A�ǂ���ɂ��A
�Q�K�̐Q���܂ŒB����Q�w���̑傫�ȋ�`�̏o�����A���̗��T�C�h�ɉ�������B
�����ē�[���̒g�F����L�т�}�b�V�u�Ȉ�̃����K�̉��ˁA�t�����g�K�[�f���̉��˂Ɠ����ɁA�S�T�x�U���Ă���B �z�[�V�����̃X���[�g�̃X�J�[�g�̂悤�ȉ����̎��t�����G�����F�[�V�����́A���E�{���E�f�E���`�G���ʂ̃E�B�b�g�ɕx�\����v���o������B |

| |
|---|---|
|
�U�D�e�B�O�{�[���E�R�[�gTigbourne Court 1899-1901 �E�B���A���E�����X��1871�N����1896�N��62�ŖS���Ȃ�܂ŋx�ɂ��߂����̂Ɏ�Ă����P�����X�R�b�g�E�}�i�[�́A 16���I�G���U�x�X���Ɍ��Ă�ꂽ�Α��̃}�i�[�E�n�E�X�ŁA�����X�͉Ƃ炵���̏ے��ł���j���i�Q�[�u���j�̘A�Ȃ�f�p�ȕ\�����ڂŋC�ɓ���A 1892�N���犧�s���ꂽ�g���[�g�s�A�����h�̔��G�Ɏg���Ă���B ��s����E�F�b�u�A�V���[�A�����ă��H�C�W�[���D�A���̘A�Ȃ�Q�[�u���̃��`�[�t���A���b�`�F���X�͑�������̗p���Ă��āA23����� �}���X�e�b�h�E�R�[�i�[�i1891�|92�j�Ƃ����Z��ŁA�n�[�t�E�e�B���o�[�ł͂��邪�A���łɎO�A�Q�[�u�����̗p���Ă���B ���̌�A1903�N���܂ł�10�N�]�́A���b�`�F���X�̏Z��ɂ́A���[�ɉ��˂��A��Ȃ�Q�[�u���̃��`�[�t���J��Ԃ������B Munstead Corner 1891-1892 �O�A�Q�[�u���@�n�[�t�e�B���o�[ Munstead Wood 1893-1897 ��A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ��� Goddards 1897�@�@�@��A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ��� Tigbourne Court 1899-1902 �O�A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ��� Homewood 1901 �O�A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ���(�������������ʒu�j Little Thakeham 1902 �l�A�Q�[�u���@���T�C�h�ɉ���(�Q�[�u�����ɑO�シ��j �}���X�e�b�h�E�E�b�h�A�S�b�_�[�Y�A�Ɠ�A�Q�[�u���������A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�ŁA�ϑ��I�ȃ��b�`�F���X�Ɠ��̃v���|�[�V�����̎O�A�Q�[�u��������A �t�@�T�[�h������v�ȃf�U�C���Ƃ��āA���͓I�ȕ\������B��A�Q�[�u�������ʂɉ���Đ����Ă���B ���̓Ɠ��Ŕ������A�t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u���̃��`�[�t�́A�قړ������̃z�[���E�b�h�ł���v�ȃ��`�[�t�Ƃ��Ďg����B �A�Ȃ�Q�[�u���̃��`�[�t�ł́A�K���J���ł���̂ʼnJ���̏����̎d�����Ȃ��Ȃ�����A�f�U�C���I�ɂ����ʂ̕\�������傫�ȗv�f�ɂȂ�B �}���X�e�b�h�E�E�b�h�A�S�_�[�Y�ł��A���ꂼ�������������������Ă��Ėʔ����̂����A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�ł͂P�K�̗̊Ԃɂǂ����Ă� �c����~�낵�����Ȃ������̂��Ǝv�����A���ꗬ���̃K�[�S�C����̔�ɂ��Ă���B������ނŎx�����▭�ȃf�U�C�����Ⴆ�Ă���B |

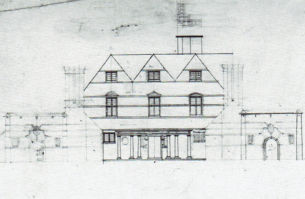
 |

 
| |
|---|---|
|
�}���X�e�b�h�E�b�h�̉J���̏����̎d�����ʔ����B��̃Q�[�u���̊Ԃ̒J�͌���Ŏďc��ō~�낵�Ă��邪�A
��ɏq�ׂ��V�����g���[�A�E�V�����g���[�̔����ȗ��ʑ�����s���Ă��鍶���́A
�O�ɏo�����˕����ł́A�c����~�낳���ɁA���˂̕ǂ����f�����A�R�[�i�[���A�ׂ̉����ɐ��ꗬ���Ă���B
���b�`�F���X�́A�o���邾���c����g�킸�ɁA�ǂ�������J����n��Ɏ����Ă����邩����ɒT�����߂�B |
�S�_�[�Y�̃G���g�����X���̓�A�Q�[�u���ł��A��̃Q�[�u���̊Ԃ̒J�́A����Ŏďc��ʼn����Ă��邪�A
���T�C�h�̉��˂ƂԂ��镔���ł́A�}���X�e�b�h�E�b�h�Ɠ����悤�ɉ��˂̕ǂ����f�����A�R�[�i�[���A
�ׂ̉����ɐ��ꗬ������ŎA���������ɂ�����x�A�ׂ̉����ɐ��ꗬ��
����ŎA�������ꂽ�Ƃ���ɏc���݂��āA�����ł���ƒn��ɗ����B
|


| |
|---|---|
|
2014�N�A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�̓S�_�[�Y�̑O�ɖK�˂��̂����A������͊ȒP�ɒH�蒅�����Ƃ��o�����B �E�B�b�g���[�Ƃ����w����P�O�����x�������܁A�y�b�g���[�X�E���[�h�ɓ���ƂقǂȂ��A�O�w�̎剮����A�}�b�V���ȉ��˂�����w�̗����� �G���g�����X�E�R�[�g���͂ށA�����V�����g���J���ȍ\���́A�������t�@�T�[�h���ڂɓ����Ă����B���T�C�h�̉��˂̉��ɂ́A���Ȗʂ̕ǂ������āA ���̒����ɂ��ꂼ���ւ̃h�A�A�T�[�r�X����ւ̃h�A������B���̃t�@�T�[�h�̌����ڂ̃V�����g���[�ƕ��ʂɌ���A�E�V�����g���[���ꗂ��A �܂��Ƀ��b�`�F���X�������Ă���g�E�B�b�g�̂Ȃ�����Building���A���zArchitecture�Ƃ͌���Ȃ��h�̌��t�ʂ�̃E�B�b�g�̗͋Z���B |
�O�[�O���}�b�v�̍q��ʐ^������ƁA���ʂœ�A�Q�[�u���A�O�A�Q�[�u�������邽�߂Ƀ��b�`�F���X���A�؍ȉ������ǂ��\����������������B ����̃t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u���͏����ȕ����I�ȉ����ł������A����̒둤�ɓ�A�Q�[�u����������؍ȉ����́AL���^�̎剮�S�̂�傫�������ĐL�тĂ���B �i���Ȃ݂ɂ��̎ʐ^��L���^�̎剮�̖k���Ɍ����鉮���́A���Ƃŕt�����ꂽ�r�����[�h���[���̓��ł���B�j �}���X�e�b�h�E�E�b�h�ƃS�_�[�Y�̓�A�Q�[�u���͂ǂ�����t�����ꂽ�����I�ȉ����̒f�ʂ��������A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�̓���̗��ʂŏ��߂āA �S�̂��؍ȉ����̒f�ʂ̉ƌ`�Ƃ��Ă̓�A�Q�[�u���������B |

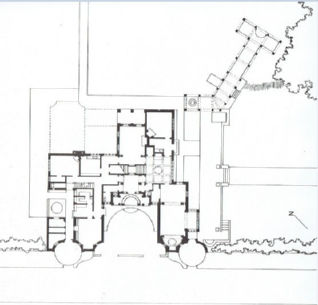
| |
|---|---|
|
1�K�Ƀz�[���Ə��ւ�����V�����g���J���ȓ�A�Q�[�u���̉��ɁA��������āA�ג����h���[�C���O�E���[�����L�т铌�엧�ʂ̍\���B ���ʂƗ��ʂ̘A�g���郉�b�`�F���X�̃f�U�C������͍I�݂ŁA���ʂ��ӎ����Ȃ��� ���ʂ��l���Ă��āA�Ȃ��������ɃE�B�b�g����܂���B �|�[�`���猺�փh�A���J�����F�X�e�B�r�����ɓ���ƁA���ʂɊK�i�̕ǂ������āA�l�̓����͕��ʂ̒��S�����O��A���ɉ�肱�݁A�K�i�̂���z�[���� �������B���b�`�F���X�̂��̌�̓@�قɓ����I�Ɍ����A���ʏ�̎�������킵�A�킵�A�����A�I���铮���������Ɏn�܂�B �܂��A�e���̕��ʂ�����ƁA�K����ǖʂɓ������h�A��A�g�F�A�����ĊK�i�Ȃǂ̗v�f�͑S�āA�K���e���̒��ŃV�����g���J���Ȉʒu�ɒu�����B |
2�K�̕��ʂ�L���^�����āA���̈�ʂ��O�A�Q�[�u�����\�����邱�ƁA���̉��̈�K�ɂ́A�|�[�`�̃N���V�J���ȗ����邱�ƁA
���̎O�A�A�[�`�E�̃t�@�T�[�h�ƃ}�b�V���ȉ��˂��ۂ������邽�߂ɁA�������͈�w�ɂ��邱�ƁB �����炭�����̂��Ƃ͓��̂Ȃ��ŏu���Ɍv�Z���āA���b�`�F���X�͂��炷����ƕ��ʁA���ʂ̃X�P�b�`���N�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����C������B �V�����g���J���ŁA�A�E�V�����g���J���ȗv�f������A���̏Z��́A�����̃��@�i�L�����[����N���V�J���Ɉڍs���悤�Ƃ���A���b�`�F���X�̍ł� �[�����������̃f�U�C�����B�y���X�i�[�Ƀ��b�`�F���X�̃x�X�g�̍�i���ƌ��킵�߂��B |
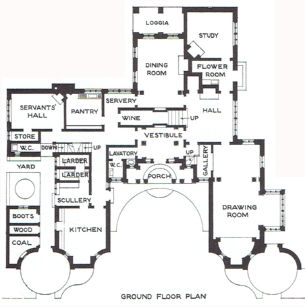

| |
|---|---|
|
�N���V�J���ȗv�f�͓��H���t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u���̉��A�P�K�̃h���X���I�[�_�[�̗Ɍ����B�P�U���I�G���U�x�X����
���o�[�g�E�X�~�b�\���̃n�[�h�E�B�b�N�E�z�[��Hardwick Hall,Derbyshire(1590-1597)��
��K�̕ǖʂƃ|�[�`�̃h���X����g�ݍ��킹���\��(���ʐ^��)�ɉe��������������Ȃ��Ƃ����B
����ɂ͂Q�K�̑��̏�ɂ́A�~�P�����W�F���̃t�@���l�[�[�{�ȗ����p���ꂽ�O�p�Ƌ��`�����݂Ɍ����y�f�B�����g�̕ω��B |
���@�i�L�����[�ȗv�f�́A�O�ǂ��\������ޗ��Ɍ����B�T���[�B�ɌŗL�̃o�[�Q�[�g�E�X�g�[���̊O�ǂ́A�����^���ɓS�z�̂�������������A
�K���b�e�B�b�h�E�W���C���g�ƌĂ��ڒn�̔[�܂�A�����ĉ����p�^�C���̏������߂ɑg�ݍ��킹�A���C����ɕǂɖ��ߍ��������̃A�N�Z���g�ł���B �W�[�L���̉e�����̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̎�@�ɁA���b�`�F���X�͏������N���V�J���Ȏ�@��▭�Ȍċz�ō������Ă����B |



| |
|---|---|
|
����̒둤���ʁB1�K�Ƀz�[���Ə��ւ��A�Q�K�ɐQ��������V�����g���J���ȓ�A�Q�[�u���B���̉��ɏ�������āA
�R�ʃK���X�̏o���A�I���G���E�E�B���h�E�̂���ג����h���[�C���O�E���[�����L�т�B |
�t�����ꂽ�����I�ȉ����̒f�ʂł͂Ȃ��A��A�Q�[�u���͑S�̂��؍ȉ����̒f�ʂɂȂ��Ă���B ���k���ʂ̂Q�K�̃R�[�i�[�߂��ɂ́A�Q������o����o���R�j�[�̔������\�������B |


|
|
|---|---|
|
�S�̓��H�����ʁB�w��̃A�E�V�����g���J���ȕ��ʂɔ����ȑ���������A�V�����g���J���ɂ܂Ƃ߂����j�[�N�ȃt�@�T�[�h�B �ǂɖ��ߍ��܂ꂽ�����p�^�C���̐����ȃX�g���C�v�̑т��A�N�Z���g�ɂȂ��āA�Ȗʕǂ���������B |
���S�̎O�w�̎O�A�Q�[�u�����ۗ�������悤�ɁA�O�ʂ͈�w�ɗ}�����A���Ȗʒ[���Ƀc�C���̉��˂��������Ă���B
���˂ƃQ�[�u���̑g������1898�N�ɖK�ꂽ���C�v���_�[�����E�n�E�XMapledurham House,Oxfordshire�ic1581-1612)�̗��ʂ���̉e��������Ǝv���A
�������`�[�t�̓S�_�[�Y�̑��z�����i1910�N�j�̒[���ɂ������B
|

|
|
|---|---|
|
�V�D�f�B�[�i���[�E�K�[�f��Deanery Garden 1899-1902 �f�B�[�i���[�E�K�[�f���́A�G�h���[�h�E�n�h�\�����A�}���X�e�b�h�E�E�b�h�����āA �ނɗ��ŏ��̎d���ł���B ���̌�n�h�\���͏�Ƀ��b�`�F���X�̃p�g�����ł��葱���A ���b�`�F���X�̍�i�͎��X�ƃJ���g���[�E���C�t���Ɍf�ڂ���A1913�N�ɍ�i�W�Ƃ��Ă܂Ƃ߂���B ��ŏq�ׂ�p�s�����E�z�[����}�[�V���R�[�g�́A�J���g���[�E���C�t����Ń��b�`�F���X�̍�i���� ���l���˗����ė������̂����A�L���b�X���E�h���[�S�̎{��̓n�h�\���Ɍ��z�Ƃ𐢘b���� �����悤�ɑ��k�ɗ������Ƃ���A���b�`�F���X�ƌ��т����B�Ƃ������ɑ����̃N���C�A���g���A �n�h�\����ʂ��Ĕނ̂��Ƃɂ���Ă��Ă���B |
���̂悤�ɃG�h���[�h�E�n�h�\���̓K�[�g���[�h�E�W�[�L���Ƌ��ɁA
���b�`�F���X�̌��z�ƂƂ��Ă̐��U�ɁA���ɏd�v�Ȗ������ʂ������B ���g���f�B�[�i���[�E�K�[�f���̌�A�����f�B�X�t�@�[���E�L���b�X��(1903)�A �N�C�[���E�A���Y�E�Q�[�g15�Ԓn(1906)��A�v�����v�g���v���C�X(1927)�̉����A �����ăJ���g���[�E���C�t�̎Љ��Ƃ����悤�Ɏ��X�ƃ��b�`�F���X�Ɏd�����˗����Ă���B ���݂̓��b�h�E�c�F�b�y�����̃W�~�[�E�y�[�W�����̃f�B�[�i���[�E�K�[�f�������L���Ă���B ����ȑO�ނ́A��͂�n�h�\���E���b�`�F���X�̃v�����v�g���E�v���[�X�ɏZ��ł����B�������p���A��̗ǂ����b�J�[������B |

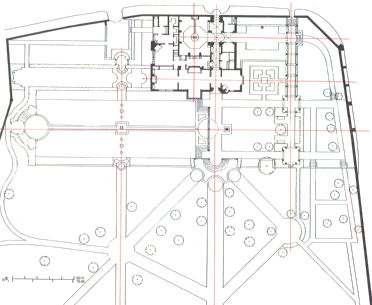
|
|
|---|---|
|
�~�n�͉ʎ����������Ƃ���ŁA�n�h�\�����y�n����ɓ��ꂽ�Ƃ��A���ӂ����������̕�����芪���Ă����B
���b�`�F���X�͖k���̗����̕������̂܂�荞��ŁA�R�̎��^�̕��ʂ�������ɂԂ��ăR�[�g���[�h���������B ����ɍ��킹���̂��A�O�ǂ�����܂ł̓@�قɎg��ꂽ�T���[�B���L�̃o�[�Q�[�g�E�X�g�[����烉�t�L���X�g�ł͂Ȃ��A���̒n���� �o�[�N�V���[��������v�\�������Ďd��Ɏg���Ă���B |
�R�[�g�̒��S�ɒ�����u���A���̉�������̌������ɒg�F��2�K���ɐ����������傫�ȏo���A�I���G���E�E�B���h�E�𑊑������B
���ꂪ�R�̎��^���ʂ̒��S��ʂ�V�����g���̓�k�����̎����Ƃ��ēǂ݂Ƃ��B ���̃V�����g���̑Ώ̎������A���H���̃G���g�����X����������H�[���g�̓V��̃A�v���[�`�ʘH��ʂ�A�E�V�����g���J���Ȏ����A ������˂������āA��̃u���b�W���炻�̐�̔��~�̊K�i�ւƐL�тāA�����ƒ뉀�����鋭���������`�����Ă���B |
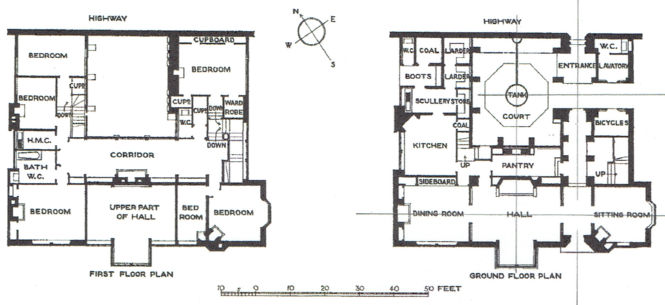
|
|
|---|---|
|
�둤�ɂ͓��H�̓�������p�[�S����ʂ铌���̎��ƁA��͂蓹�H�̓��������`�̒r��ʉ߂��Ē����L�т鎲��������B �����S�{�̓�k���ɒ��p�����̓�������3�{�ǂ݂Ƃ��B �R�[�g�̒�������p�[�S���Ɍ������Ă̎��A�_�C�j���O�E�z�[���A �V�b�e�B���O�E���[���̒��S���A�����āA�ׂ����H�̎������̉��̉~�`�̒r����A��`�̒r��ʉ߂��Đ��ɐL�сA ������̉~�`�̒r�ɒB�������1�{�̎��ł���(���̒r�̎��ӂɂ͊K�i�������ė������炻�ꂼ��Z�p�`�� �p�[�S���Ɏ���B�j |
���������łȂ��뉀���܂߂��~�n�S�̂��т��������������݂��A
����炪���݂��ɍ�p���S�̍\�������肠���Ă���B ������������˂������A�c���ɑ����Ă��邽�߂ɁA���b�`�F���X�̕��ʂ̂Ȃ��ł��A ��ƌ������ł����R�Ɉ�̉����Ă���B ���������z�ƒ뉀�����邱�̃f�B�[�i���[�E�K�[�f���́A 10��ʂƎv���郉�b�`�F���X�ƃW�L���̑�\�I�ȃR���{���[�V�����̒��ł��A�S�_�[�Y�Ƃ͈Ⴄ�Ӗ��ŁA�ł����܂���������ƌ�����B |


|
|
|---|---|
|
�O��𓌐��ɑ���A�ׂ��������H�̃A�C�f�B�A�́A�W�[�L�����X�y�C�����s���玝���A�������̂��Ƃ����B�����炭�̓A���n���u���{�a�̐��H�����ɂ������Ǝv����B �뉀���̗��ʂ̓V�����g����������A�▭�̃v���|�[�V�����������A�@�ׂȃu���b�N���[�N�̃A�[�`�≌�ˁA�I�[�N�g�� �ׂ������̎V�̃I���G�����̕\��A�����Đ��H�A�K�i�A�u���b�W�Ƃ������뉀���\������ו��������A���ɐ�捂ŁA�������\������o���Ă���B |
�I���G���͕��ʏ���엧�ʂƂ��Ă��A���S�ɂ����ċ������݊��������Ă��邽�߁A���̂܂܂��ƁA���ʂ̕\��̓I���G���𒆐S�Ƃ��镽�}�ȍ\���ɂȂ��Ă��܂��B
���̃V�����g��������A���ʏ�ł������A�v���[�`�̓�k�̎����Ɍĉ����āA���ʂ̏d�S���A�[�`�̊J���A
���̘e�̉��˂Ȃǂ̗v�f�œ����ɊāA�A�E�V�����g���ȍ\���������ĂƂ��āA���b�`�F���X�̓@�ق̒��ł��o�����X�̂Ƃꂽ�A���I�ŁA
�ł��s�N�`�����X�N�Ȕ��������ʂ�n��o�����B
|

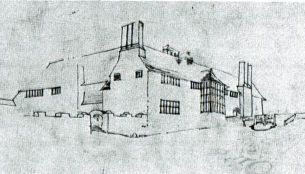 |
|
|---|---|
|
�n�h�\���͂����ŏT�������߂����A1�A2�N�g�����̂�1903�N�ɂ͔��p���Ă���B�����������烉�b�`�F���X�̂��߂̃��f���n�E�X�̂悤�ɍl���Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ƃ��v�킹��B
|
�n�h�\���̔��p��A1912�N�ɂ͖k�����ɐV���ȓ��̑��z�A�����1927�N�ɂ͎剮�̉��˂̓쐼�����������鑝�z�����b�`�F���X�ɂ���čs���A�엧�ʂ̎��I�ȕ\��������ꂽ�B
|

 |
|
|---|---|
|
�W�D�O���C�E�E�H�[���Y GREY WALLS 1901 ���b�`�F���X�����g�̐v�����Z��S�̒��ł��D���ȏZ��ƌ�����Ƃ����O���C�E�E�H�[���Y�B �Ίp���̃A�v���[�`��p�Ȃ����t�@�T�[�h�Ŏ�Ƃ����A���j�[�N�����͓I�Ȕz�u�v���������Ă���B ��ŏq�ׂ�悤�ɁA���I�̕ς��ڂ̂��̍�����A���b�`�F���X�͕��ʂɃG���U�x�X���ȗ��̃}�i�[�n�E�X�̊�{�p�^�[���ł���g�^���̗p���n�߂�B ��q���郊�g���E�Z�C�J����q�[�X�R�[�g�̂悤�ɖk����̏ꍇ�A ���S�̖k���Ɍ��ցA�쑤�Ƀz�[���A���̍��E�̗����ɓ쑤�ł̓_�C�j���O�E���[���ƃh���[�C���O�E���[���A �k���ł̓L�b�`���ƃ��C�u�����[��z�����p�^�[���ł���B �������O���C�E�E�H�[���Y�͕~�n�̏����Ō���p�s�����E�z�[���Ƌ��ɓ����(���ۂ͓쐼�A�v���[�`)�ɂ�������A ����ɕ~�n�̈ꕔ���S���t��̃N���u�E�n�E�X�̕~�n�ɂƂ��ē����ŋ����Ȃ��Ă���Ƃ������������d�Ȃ��Ă���B �]���ăp�s�����E�z�[���̂悤�ɐ��������荞��œ���A�v���[�`���Ƃ�Ȃ��B �����Ń��b�`�F���X�͈͂����܂ꂽ�쓌�̃v���C�x�[�g�Ȓ�Ƃ͕ʂɁA �L���G���g�����X�E�R�[�g���Ƃ��āA�_�C�A�S�i���Ȏ�(����͕��ʂ̓�k���ɂقڈ�v����)���A�v���[�`�̎��Ƃ����B ���̃A�v���[�`�̎��̐�ɁA�p�Ȃ����t�@�T�[�h���}����B������ ���̘p�Ȃ������ʂ̗��[�ɂ́A���F���`���[���̌����g�܂����������I�ȓ����̂��邵�h�ł���A���˂�z���Ă���B �p�ȕ����ɂ́A�L�b�`���A�g�p�l���Ȃǂ̃T�[�r�X���傪�����Ă��āA ��v���͂����܂Ŗk������H�^�����ɂ���B ����H�^��������́A�W�[�L���ɂ���ĐA�͂��ꂽ�쓌���̒뉀�ɏo����B �G���g�����X�̃t�@�U�[�h�̘p�Ȃ������ʂ́A�����ł͂����܂ł��O���̏������猈�肳�ꂽ�� �̂ŁA�����̕��ʂ́A���̉~�ʂ̂��߂ɘc�߂��Ă���B ���̘c�߂�ꂽ���ʂ́h���܍��킹�h���f���炵���B�Ⴆ�t�@�T�[�h���ɗ��ʂ̍\����A���̂Ƃ�Ȃ��ʒu�ɂ��� �L�b�`���́A���̐��������̕��������i��������ʍ\���㕽���ɂ��Ă���j�Ƀg�b�v���C�g���Ƃ�A�܂����C�g�R�[�g��z���č̌��̖����������Ă���B �~�ʂƂg�^���ʂ̞B���ȗZ���̎d���ɂ́A���ՂɒP���������A�܂��^����ꂽ������ ���������A���̂܂܂̌`�Œ��������A�v������L���Ȃ��̂ɂ��Ă���B ���̕ӂ̂Ƃ���́A�y���b�c�B�ɂ�郍�[�}�̃p���b�c�H�E�}�b�V�[�~��A�W�����E�\�[�����ɂ�� �C���O�����h��s�̕��ʂ�z�N������B | 
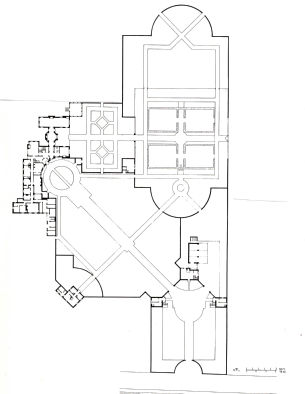
|


| |
|---|---|
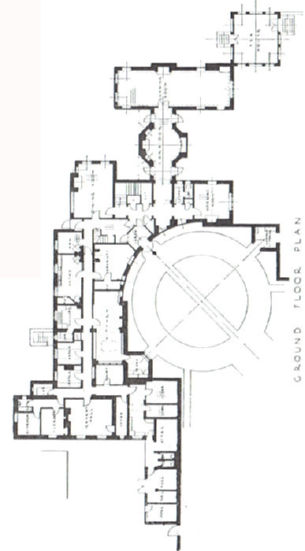

|
|---|
|
���̕ό`�̕~�n�ɔY��ł������b�`�F���X���A���`���[�h�E�m�[�}���E�V���E�̌���A�ÓT��`�l���Ɉڍs���Ă���̌���A�o�^�t���C�E�v�����̓@�فg�`�F�X�^�[�Y�h��1901�N�ɖK�ꂽ���Ƃ��A�g�^�̃v�����ɘp�Ȃ����G���g�����X���������A�C�f�B�A�̂��������ɂȂ����ƌ����Ă���B �`�F�X�^�[�Y�̑��ʂ̘p�Ȃ������ʁA�z�u���O���C�E�E�H�[���Y�̗��ʂ����ă��j�[�N�Ȕz�u�v��̃q���g�ɂȂ����A�ƍl������B | ���̌�A�`�F�X�^�[�Y�̉e���̂����Ɂg�o�^�t���C�E�v�����h�̓@�فA���̖����p�s�����E�z�[��������A ����ɂ́A���b�`�F���X�̌ÓT��`�l���̒��_�ł���q�[�X�R�[�g�ւƎ���B ���̂悤�Ɂg�`�F�X�^�[�Y�h�������������Ƃ̈Ӗ��͑傫���A�O���C�E�E�H�[���Y1901�A���g���E�Z�C�J��1902�A�p�s���E�z�[��1903�|4�A�q�[�X�R�[�g1905�|7 �Ƒ����l��́g�`�F�X�^�[�Y�h����̉e���Ȃ��ɂ͐��������Ȃ��������낤�B |

 |
|
|---|---|
|
�X�D�z�[���E�b�h Homewood 1901 ���b�`�F���X�̏Z��̖��͂ɂڂ����䂫����ꂽ��ԍŏ��̏Z��ŁA2014�N�̗��s�ł��A�K�₷��̂��ł��y���݂ɂ��Ă����B �P���u���b�W�ɍs���r���A�����h�������Ԃ�30���̃l�v���[�X�w�ō~�肽�B �w���o�Ă��Ăǂ�����čs�����ƁA�Ƃ肠�����w�O�̉ƂŎԂ̂��ɂ����l�ɓ���q�˂�B ���J�U�钆�����̂́A���z���Ǝv���Ă��ꂽ�̂��A�e�ɂ����̎ԂŃz�[���E�b�h�̑O�܂ő����Ă��ꂽ�B ���̗��Őu�˂����b�`�F���X�̏Z��́A�K�^�Ȃ��ƂɑS�Ă̏Z�l����܂ŏ�������Č����Ă��ꂽ���A �z�[���E�b�h�ł́A�����������Ƃɂ���ɉƂ̒��܂ňē����Ă��ꂽ�B �z�[���E�b�h�͐v�������d�Ȃ邽�߂��A�t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u���A���ʂ̓�A�Q�[�u���A �����ĊK�i�̈ʒu�E���ʂ̍\���ɁA�e�B�O�{�[���E�R�[�g�Ƌ��L�����������������B �K�͂͏��������߂ɁA�����̓������z�[���E�b�h�ɂ͂��V���v���ɁA���N���ɏo�Ă���B�q��ʐ^�Ŕ�ׂ�ƕ����邪�A �t�@�T�[�h�̎O�A�Q�[�u�����e�B�O�{�[���E�R�[�g�̂悤�ɕ����I�ȉ����ł͂Ȃ��A �剮�S�̂�傫�������ĐL�тĂ���B ���b�`�F���X�̓C���h�����������b�g�����݂̖��A���f�B�E�G�~���[�E���b�g���ƂP�W�X�V�N�Ɍ�������B���b�g�����݂͂��łɂP�W�X�P�N�ɖS���Ȃ��Ă���A ���S�l�������`��̃��f�B�E���b�g���̂��߂̏Z����̃z�[���E�b�h�ł���B ���b�`�F���X�̉Ƒ��́A�z�[���E�b�h�ɂ悭�؍݂��A�q���������x�ɂ������ʼn߂������Ƃ��ƂĂ��D�Ƃ����B �k�����ʂ̊O�ς̓e�B�O�{�[���E�R�[�g�Ɠ����A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�I�ȁA���@�i�L�����[�� �\��������Ǝ��̎O�A�Q�[�u��(�㔼��)�ƁA�N���V�J���ȃf�B�e�[�����������A�����X�^�b�R����(������)�� ���͓I�ȗ��ʂ������Ă���B ���ނɍ����X�e�C����h��ꂽ��������́A�O�A�Q�[�u���Ƃ��ꂼ��ɐ����ꂽ�O�̓c�̎��^�̑��A���E���[�ɉ��т������Ȉ�w�̉����A �����ăG���g�����X�̔����h��ꂽ�ؐ��̃A�[�`�A�����Ă��̉��̒��ɕ������ے��I�ȃ}�O�T�Ƃ������ɁA ����ɃN���V�J���ȕ����ɌX���Ă������̎����̃��b�`�F���X�́A���@�i�L�����[�ƃN���V�b�N�������荇�����A�w�I�Ȍ`�ԑ���A�}�j�G���X�e�B�b�N�ȁA���ʑ��삪�ڂ�D���B�G�킩�������B �q��ʐ^������ƁA������ �k�����ʂ̔j�����牄�т�R�̐؍ȉ������쓌���ʂ̐؍ȉ����ɒ��p�ɂԂ���\�������Ă���B �쐼���ʂ̔j�����牄�т�Q�̐؍ȉ����̂����쑤�͕���t�ɐL�сA�k���͒Z���B ����ɂ����̐؍ȉ����̊Ԃɂ͍̌��̂��߂ɏ����ȉ������i�h�[�}�[�j���Q�K�̊K�i����A�Q���ɕt������Ă���B | 
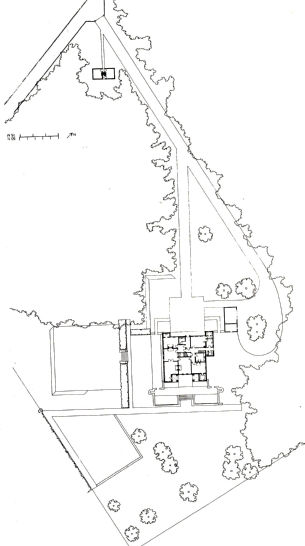
|
 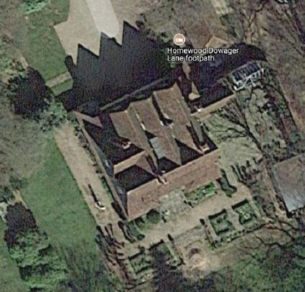
| |
|---|---|
�A���Q�[�u���̃��`�[�t�ɂ��ẮA���b�`�F���X�ɉe����^�����A�Ƃ��Ă悭���������ɏo�����A �t�B���b�v�E�E�F�b�u�̃W�����h�E�B���Y�i���}���j��X�^���f��1891�i���}�E�j�̂悤�ɁA�����̃Q�[�u��������ɓ����ɕ��Ԃ̂Ƃ́A���b�`�F���X�̎O�A�Q�[�u���͈قȂ�B 
|
�e�B�O�{�[���E�R�[�g�̃t�@�T�[�h�Ɠ����悤�ɁA�z�[���E�b�h�̃t�@�T�[�h�ł����b�`�F���X�̎O�A�Q�[�u���́A���ӂ��� �J����āA�S�̂Ƃ��ĂЂƂ܂Ƃ܂�̎O�A�Q�[�u���Ƃ����`�Ԃɂ��Ă��āA�E�F�b�u�̘A���Q�[�u���Ƃ͍l�������قȂ�A���b�`�F���X�Ǝ��̂��̂ɂȂ��Ă���悤�Ɏv���B �@ 
|
|
���b�`�F���X�̓@�ق̒��ł́A���Ə��������ł���A���ʂ�����ƁA�����`����A����̓ˋN���o���悤�Ȍ`�����Ă���B
���S�̐����`�͏c�O���O�ɕ�������A��G�c�Ɍ����ċ�̋�悩�琬���Ă���B �O�������������̏c��ɂ̓X�^�f�B�A�z�[���A�h���[�C���O�E���[���Ƃ����O�����c�ɕ��сA�^���̗�ɁA�G���g�����X�A�K�i�A�_�C�j���O�����ԂƂ���� �e�B�O�{�[���E�R�[�g�Ɠ����\���ł��邪�A�Ⴄ�̂̓T�[�r�X�E�u���b�N�ŁA���G�ȃe�B�O�{�[���E�R�[�g�ƈ���āA �z�[���E�b�h�ł̓L�b�`���A�p���g���[�A�T�[���@���g�E�z�[���ƁA�O�����V���v���ɓ�k�ɕ��ԁB �p�u���b�N-�v���C�x�[�g�̒i�K�I�q�G�����L�[�����ɖ��m�ŃV���v���ȕ��ʍ\���ł���B �A�v���[�`�̎ԓ��́A�_�C�A�S�i���ɐL�сA�r������G���g�����X�ɐ^�������Ԃ��铹�H�ɕ����B |
���̎����G���g�����X�̊J����ʂ鎲�ƈ�v����̂����A���̊J���͕��ʏ�͒��S���班���O��A���ʏ�̒��S���ƁA���ʂŌ��钆�S������Ă���B
�G���g�����X�e�Ƀg�C�����Ƃ������߂����A�����̏��̓O���X�S�[���p�w�Z�̃G���g�����X�Ń}�b�L���g�b�V������������ƂƏ������Ă���B �V�����g���[�ƃA�E�V�����g���[���ӎ��I�ɑ��삷��f�U�C���p���́A�}�b�L���g�b�V���ƃ��b�`�F���X�Ɍ��炸�A ���̎���̌��z�Ƃ������Ă������ʈӎ��Ȃ̂�������Ȃ��B �t�@�T�[�h�́A�������č����̃L�b�`���ɐH�i�ɂƐ��ˏo�����āA �G�����F�[�V�����̏�ł́A���S�ȃV�����g���[���\�����āA�O���Ɠ����́u���܍��킹�v���I���ɍs���Ă���B |
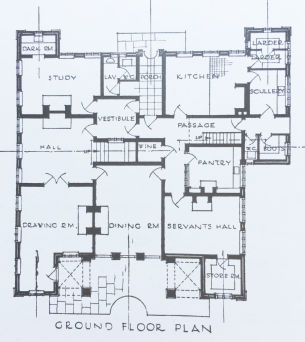
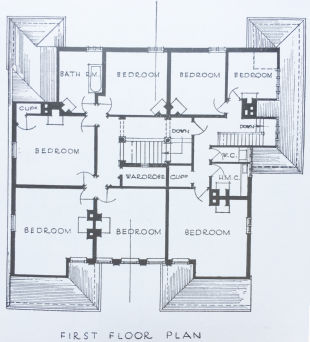
| |
|---|---|
�O�Ϗ�A�l�̗��ʂ͂��ꂼ��ɖ��͓I�ȁA�S��������\���悵�Ă���A���ꂼ��̗��ʂ��Ƃ� �A�Ɨ������`�ԑ��삪�A���ʁA�����ĉ����̌����ƘA�����Ȃ���s���Ă���B ���ʂS�ʂ��P�ʂ��Ȃ�������ɂ����A���ʁA�����̕����̋@�\�A�����ĉ����A���ꏏ�ɍl�������ĉ����Ă䂭�B �k���̃G���g�����X���͉�������̎O�A�Q�[�u���A�쐼���͓�A�Q�[�u���ō\������A �쓌�̗��ʂ͌��z�������P�K�̌��܂ʼn���Ă���Ƃ����A�S���Ⴄ�\������A �������V�����g���[�̒��S�����A���ʏ�ŁA����Ă���B 

|
�둤�̓쓌���ʂ́A�k���Q�ʂ̔j���̕\���Ƃ́A�قȂ����\������Ă���B ���������[�Ő^���Ɍ�������1�K�̌����܂ʼn���Ă��āA �����̃e���X�̏�ɔ��艺���āA�G���g�����X�Ɠ����A�ĂуN���V�J���ȃ��`�[�t������A�������Ɏx�����Ă���B ���S�����ł�1�K�̔����X�^�b�R�̕ǂ��A2�K�ɂ܂ŐL�сA2�K���̍����̕t���i�s���X�^�[�j��4�{�A2�K�̌��܂ŐL�тĂ���B ���̔��ǂ͗����ɔ����X�^�b�R�h��ŁA�t���͖ؐ��Ƀy���L��h�������̂ł���B 

|
|
�e���ʂ̓Ɨ������V�����g���\���ɉ����āA�z�[���E�b�h�ɂ́A�������
�̃��b�`�F���X�̓@�ق̑傫�ȓ��F���A�e�B�O�{�[���E�R�[�g��肳��ɋ����o�Ă���B ����͐l�̓������A���ʂ̎�������O���A���炵�āA���炵�Ē��������镽�ʑ���ŁA���b�`�F���X�̕��ʂ̓����ł��� ���������́A���̏���A���b�`�F���X�͑f���ɑO�ւ͐i�܂��Ă͂���Ȃ��B �G���g�����X�E�|�[�e�B�R�����Ɛ��ʂ͕ǂɓ˂�������A���̉E�ɂ���Ɠ����h�A������B�h�A���J���A���F�X�e�B�r�����ɂ͂���ƁA���E�Ώ̂ɓ�̃h�A��������B ���ʂł͂Ȃ��A�Ίp��̃h�A���J����ƃz�[���ցB�z�[���ł͐U��Ԃ�`�ŁA2�K�֍s���X�g���[�g�̊K�i�ƃ_�C�j���O�ւ̃h�A������B ���Ȃ݂ɁA���̊K�i�㕔�ɂ́A�g�b�v�E�T�C�h�E���C�g�������Č��𗎂��Ă���B |
���̌��́A�K�i�ƌ��֕����̊Ԏd��ɂ�����ꂽ��̔��p�`�̑���ʂ��āA���F�X�e�B�r�����ɂ��B����B �̂����ɂЂ˂��āA�K�i�̉E�ɂ���h�A����ƁA����ƃ_�C�j���O�E���[���Ɏ���B ���G�Ō��I�ȃT�[�L�����[�V�����́A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�ȍ~�̃��b�`�F���X�̕��ʂ̓����ł���B ���������F�X�e�B�r�����ł��z�[���ł��_�C�j���O�E���[���ł��A�e�����̃h�A��g�F�͕K���A���E�Ώ̃V�����g���J���Ȉʒu�ɒu�����B �S�̍\���ł̓V�����g���[������ɕ����A���������ʏ�̃V�����g���[���I���ɃL�[�v����Ƃ����E�B�b�g�������A �������\������e�����͓O�ꂵ�ăV�����g���J���Ȕz�u���Ƃ�B �����������͑Ίp�����A�Ίp�����ɐl����������B�Ȃ�Ƃ������ʂȂ����Ė��͓I�ȗV�т��낤�B |



|
|
|---|---|
���_�j�Y����傫���]�������������h���z�̑��l���ƑΗ����h�ŁA���o�[�g�E���F���`���[���́A���b�`�F���X�ɑ������y���Ă��邪�A
�P�X�U�Q�N�́g��̉Ɓh�ɂ����āA�O�ςɃz�[���E�b�h�̃Q�[�u�����A
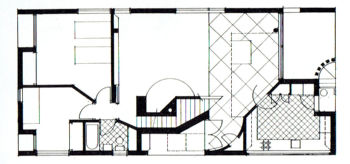
|
��������ŁA�ǂɂԂ���G���g�����X�A�����ƒ��p�̊K�i�̈ʒu�A�X�O�x�^�[���A�����Ĉ����I�铮���ȂǁA ���炩�Ƀz�[���E�b�h���Q�Ƃ��Ă���B 
|
|
�P�O�D���g���E�Z�C�J��Little Thakeham 1902 ���b�`�F���X�̂��̎����́A�ÓT��`���z�̃��H�L���u�����[�ւ̌X�Ƃ����Ӗ��ŁA���g���E�Z�C�J���ɂ��`�F�X�^�[�Y����̉e�������Ȃ��炸������B ���ړI�ɂ̓`�F�X�^�[�Y�̊O���̑�����Ɍ�����A��Ō��� "�M�b�u�Y�E�T���E���hGibbs surround�i�M�b�u�Y���͂��g�j"���A������Ԃ̑傫�ȍ\���v�f�Ƃ��č̂荞�܂�Ă��邱�Ƃł���B ���b�`�F���X��30���߂��邠����A���I�̕ς��ڂ�1900�N�O�ォ��A�T���[�E���@�i�L�����[�ɁA �������ÓT��`���z�̃��H�L���u�����[�ꍞ�܂��n�߂�B �e�B�O�{�[���E�R�[�g1899-1901(�E�ʐ^��)�A�z�[���E�b�h1901�i�����j�A�����ăO���C�E�E�H�[���Y1901�i�����j�ƁA �G���U�x�X���̓@�قɎg����ÓT��`�̗v�f�Ƃ��̎g���������ł�悤�ɁB �z�[���E�b�h�ł̓G���g�����X�̃s���X�^�[�̃��X�e�B�P�[�V���������T�C�h�̓ˏo���A����ɂ͓�ʂ̃e���X�ɂ��g����B �`���[�_�[���̎���A1534�N�w�����[8���ɂ���ĉp��������������A�C���O�����h�̎O���̈�̍��Y�����ƌ���ꂽ �����̏C���@�̓y�n���ĕ��z����A�J���g���[�n�E�X�̌��z���b�V�����n�܂�B �܂����̎���́A�܂��ɃC�^���A���烋�l�T���X�̌��z�������Ă��āA�ו��ɏ��������̉e�����������Ă��������ŁA �����S�V�b�N�̐H�̋Z�p�ƃ��l�T���X�̌ÓT��`�̃��H�L���u�����[���Z�������������ゾ�B ���݂̃��b�V���Ƃ����A���b�`�F���X�ɐ�s����A19���I�㔼�A�u�����Ă������Y�K���̂̋��߂ɉ������`�́A �E�F�b�u��V���E�̃h���X�e�B�b�N�E�����@�C���@���̌��݃u�[���Ə������Ă��Ȃ����Ȃ��B �����ăG���U�x�X����16���I�㔼�Ƃ��������́A���������S�V�b�N���烋�l�T���X�ւ̓]���������A�C�^���A�ł͐������l�T���X����}�j�G���X���Ɉڍs���鎞���ŁA �C�^���A�l���z�Ƃ������p���ɓn���Ă��Ă���̂ŁA�}�j�G���X���̉e����������B ���b�`�F���X�ɂ̓`���[�_�[������G���U�x�X���A�W�F�[���Y���ɂ����Ă̏Z��ɊS������A��ɐG�ꂽ�悤��1898�N�ɁA ���C�v���_�[�����E�n�E�XMapledurham House,Oxfordshire�ic1581-1612)��K��Ă���B �j���[���[�N�Ń}�f�C�����C���̗A���ō��𐬂������e�̈�Y���p���ŁA�J���g���[�E�W�F���g���}�������đ����ƂɂȂ����{��̃g���E�u���b�N�o�[���́A �ŏ��̌��z�ƃn�b�`���[�h�E�X�~�X����Ă��������ƃn�[�t�e�B���o�[�̌��z���C�ɓ��炸�A���b�`�F���X�ɑ��k�����B �~�n��K�˂��Ƃ��͂��ł� �Q�K�܂ōH�����i��ł������A���b�`�F���X�͒n���Y�̃p���o����Pulborough rock�ł��邱�Ƃ��āA�L�b�`���������c���āA ���Ƃ͉�̂���悤�ɂƂ������������A�v��������B �~�n��K�˂��A��̋D�Ԃ̒��ŁA�قڍŏI�Ăɋ߂����ʁA���ʁA�f�ʂ̃X�P�b�`��`���グ���A�Ɠ����̏�������Ɍ���Ă���B | 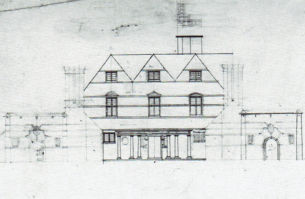
 
|


| |
|---|---|
|
�Ƃ������Ƃ́A���̎��̃��b�`�F���X�ɂ͎��̎d���ł���Ă݂��������e�[�}������A���ꂪ�S�_�[�Y��O���C�E�E�H�[���Y�ŁA���������o���Ɏ��݂Ă����A
�G���U�x�X���̃}�i�[�n�E�X��H�^�v�����ŁA���̎d�����܂���������ɑł��Ă����ƍl�����̂ł͂Ȃ��낤���B �������āA ���g���E�Z�C�J��(����)�́A���ʂɃG���U�x�X���R���̂g�^��S�ʓI�ɍ̗p�����A���b�`�F���X�̍ŏ��̏Z��ɂȂ����B �}�i�[�n�E�X�̊�{�p�^�[����16���I�G���U�x�X���ɁA�R�̎��̐^�Ƀ|�[�`�̕t����E�^����n�܂�A�������L�тĂg�^�ɕω������B ���g���E�Z�C�J���ł̓G���U�x�X����H�^�ƈ���āA�z�˂����d��k����ɂȂ�A�g�^�̎�v�u���b�N�̖k���ɁA ��̂����Ɏc�����������̃L�b�`���E�u���b�N�������Ă���B 
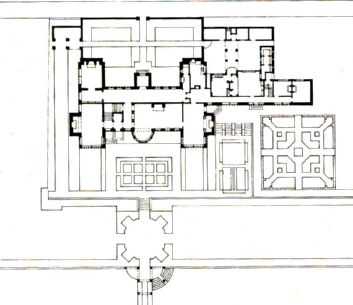
|
�قړ������ɂ���ꂽ�}�[�V���R�[�g(���E)�͓쓌���ɗ������o���d�^�Ƃg�^�̒��Ԃ̂悤�ȕ��ʂ����A��͂�k���ɃT�[�r�X�E�u���b�N�������Ă���B ���g���E�Z�C�J����}�[�V���R�[�g�́A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�e�����ŁA�`���[�_�[�l���̗v�f���������g�T���[�E���@�i�L�����[�h���� �g�ÓT��`�h�G�h���[�f�B�A���E�o���b�N�̃q�[�X�R�[�g�֓���ϑJ�ߒ��́A�ߓn���̍�i�ƌ�����B ���g���E�Z�C�J�����}�[�V���R�[�g���A�O�ςɁA�`���[�_�[�l���̃��@�i�L�����[�A���ςɁA�ÓT��`�}�j�G���X���̃��H�L���u�����[�Ƃ����A ���O�̗l���̕s���ꂪ�݂��邪�A�l�����f�U�C���v�f�Ƃ��đ��ΓI�Ɉ������b�`�F���X�̎p�����ǂݎ��A��a���͂Ȃ��B 
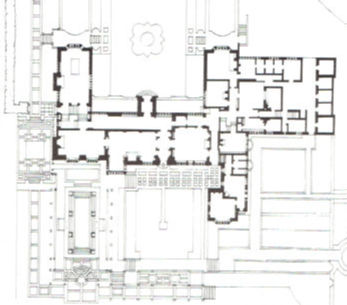
|
|
�p���̓c���Ɏc���ꂽ���@�i�L�����[�Ȍ��z�̕�����ڎw�����E�B���A���E�����X�����̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̋����ɒ����ɁA
�T���[�B�̃t�@�[���n�E�X�̃��@�i�L�����[���Ƃ��ɏ��邱�ƂŁA���b�`�F���X�ɒ@������26�ΔN���̃K�[�g���[�h�E�W�L������ۂ���ꂽ�f�U�C���I�}������A
������������u�����ƁA�ÓT��`�Ɉڍs���n�߂��A�Ƃ����������݂���B
�������A�ނ���P�ɃT���[�B�̃t�@�[���n�E�X�̃��@�i�L�����[����A�G���U�x�X���̓@�ق̗v�f���̗p������Ƀ��b�`�F���X�̋������ڂ����A
�ƌ������ق������m�ȋC������B ���C�v���_�[�����E�n�E�X����^�L���[�g�E�n�E�XMontacute House,Somerset(c.1590-1601���})�Ȃǂ̃G���U�x�X���̓@�قɂ́A ���l�T���X�A���邢�̓}�j�G���X���̉e���������Ă��āA �ÓT��`�̃��H�L���u�����[���g���Ă���̂�����B ���b�`�F���X�ɂƂ��ẮA�t�@�[���n�E�X�̃��@�i�L�����[�ɂ��A�G���U�x�X���̓@�ق̌ÓT��`�ɂ��A �f�U�C���̌���Ƃ��Ă̓����x���̋���������Ă��āA���̌�A�ÓT��`�̕��ɋ����̓x�����������Ă����������A�Ƃ������Ƃ��낤�A �����炱���V���E�̃`�F�X�^�[�Y�����ɍs�����̂��A�Ƃ������Ƃ�����̂��낤�B �܂�ÓT��`�̕��Ƀ��b�`�F���X�̋����̓x�����������Ă��������Ƃɂ͂����ЂƂA�V���E����̉e���Ƃ������Ƃ�����̂����m��Ȃ��B 
|
35�ΔN���̃��`���[�h�E�m�[�}���E�V���E�i1834-1912�j�́A�����̃`���[�_�[�E���@�i�L�����[����A
�N�C�[���E�A���l���A�����̃I�[���h�E�C���O���b�V���l�����o�āA����́A�̂���
�G�h���[�f�B�A���E�o���b�N�ƌĂ�邱�ƂɂȂ�ÓT��`�I�ȍ앗�ւƎ��g�̃X�^�C����ϖe�����Ă������B
1870�N������1890�N���Ɏ����20�N�Ԃ̃V���E�̃X�^�C���̕ϑJ��ڂ̓�����ɂ��āA����ɌÓT��`�ɖڊo�߂����b�`�F���X��1896�N������1906�N���܂ł�
�ق�10�N�ԂƂ��������̊��ԂŃV���E�̕ϑJ���g���[�X����B �]�k�����A�V���E���哱�����N�C�[���E�A���l���Ƃ́A�ԃ����K�A���h��グ�������A�R�[�i�[�E�^���[�A�Q�[�u���Ȃǂ�����Ƃ���h���X�e�B�b�N�E�����@�C���@���̗l���ŁA 1702�N-1714�N�̃A�������̎���̌��z�Ƃ͂���قǂ̊W�͂Ȃ��B �N�C�[���E�A���l���͎�ɁA�ǂ��ƂȂ��Ö��ȏZ��̗l�������A�V���E�̃N�C�[���E�A���l���Ƃ��ẮA �����h���x�����A�X�R�b�g�����h�E���[�h�Ȃǂ̎ȁX�̌������z�̕������ɕ����ԁB �����w���͂��߂Ƃ��ē��{�e�n�ɓ_�݂���C�����̎ȁX�̃����K���z�́A�����炭�͒C��̉p�����w���Ƀ����h���ł���������ꂽ�A �V���E�̂������̕��̃N�C�[���E�A���l���̌����̉e�����������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B 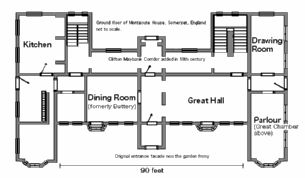
|
|
���g���E�Z�C�J���́A���ň͂܂ꂽ�G���g�����X�E�R�[�g��������|�[�`�����ƍL���L���ŁA
���S������E�ɂ��ꂽ�Ƃ���Ƀz�[���ւ̓���������B 14,5���I�̃}�i�[�E�n�E�X�Ɏn�܂�A�G���U�x�X���̃����^�L���[�g�E�n�E�X�ɂ��݂���A�������̖�ڂ�����X�N���[���E�p�b�Z�[�W�ɂ��̓������ʒu���A �X�N���[���E�p�b�Z�[�W�̔w��ɊK�i����̂ɂȂ��đg�ݍ��܂ꂽ�B ���ʂ̒��S����̓쑤�ɁA�f�B�[�i���[�E�K�[�f���̂悤��2�K���̏o��(�I�[���G��)������(�o���̕��ʌ`�͔��~�ňقȂ邪)�A�K�i�������������H���E���̒��S�ɂ� �g�F���ʒu����B�K�i���̑}���ɂ�镽�ʑS�̂̒��S�̃Y�����A�g�F����������B�����ł̃V�����g���[�ƁA�ƑS�̂̃V�����g���[���A�e�����Ŕ����ɑΗ����� ���݂ɋْ��W�����܂��B �܂��A�z�[���̗��[�ɂ���A�_�C�j���O�E���[���ƃh���[�C���O�E���[���̒��S�ɂ���g�F���A���������Ɍ��Ԏ����́A�X�N���[���̈���̒[�A �둤�̊J���̃Z���^�[�ɐݒ肳���B |
���̂悤�ɁA���ʂ��\������v�f�Ƃ��Ă̎����������ӎ�����Ă���A�����������̃V�����g���[���ǂ̋�Ԃ̒��ł̃V�����g���[�Ȃ̂�����ɍl������A
�g���b�L�[�Ȏ����ݒ肪�s����B �z�[����2�K���̍����̓V�䍂�������A�K�i�̗x��ꕔ������z�[�����]�߂�悤�ɂȂ��Ă��� ��������2�K�̘L���ɂȂ���B�������i������Ƃ���ɁA��Q���̃h�A������B �����ł��l�̓����͒��S��������A���ʂ̏�ł̎������A����������Ȃ���A�I�Ȃ���A���ʂ��\������Ă����B �O�����ʂł́A�I�[���G���̗����ɃQ�[�u���������A�X�ɂ��̏����O�̗��[�Ƀ_�C�j���O�E���[���ƃh���[�C���O�E���[���̃Q�[�u�� �������オ��B�O�����ʂ̓z�[�������ʼn����N���Ă��邩�ɊS���Ȃ��A�����̊����ɂ͂��ւ����Ƃ����悤�ȁA �����̃A�E�V�����g���[�ƒf�₵�����ʂ̃V�����g���[���`�������B |
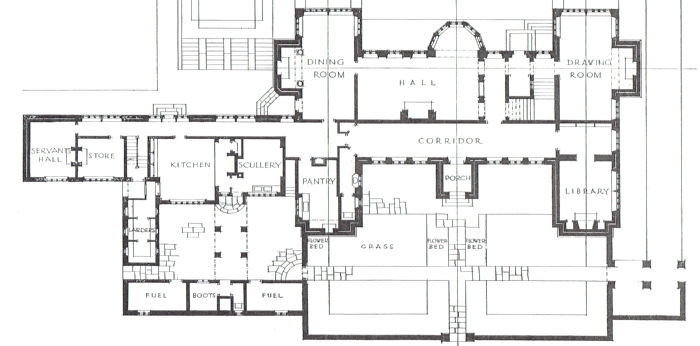

 |
|
|---|---|
|
�z�[���ƊK�i���܂ރX�N���[���E�p�b�Z�[�W���d��X�N���[���ɂ́A���̏Z��̊�Ƃ�������A������ۂ�^����}�j�G���X���I�A
���邢�̓o���b�N�I�ȕ\��^�����Ă���B �C���O���b�V���E�o���b�N�̃��@���u����z�[�N�X���[�A�Ɠ������ ���z�ƁA�W�F�[���Y�E�M�b�u�Y���g�������Ƃ���A�M�b�u�Y�E�T���E���h�ƌĂ��ÓT��`�̃��e�B�[�t ���g���Ă���B�ʏ�͊O���́A�J�����Ɏg���郂�e�B�[�t�Ƃ������Ƃ�����A�h�Ƃ̒��̉Ɓh�I�Ȋ��o��������A�܂����䑕�u�̏��� �̂悤�ȕ��͋C������B ���䑕�u�I�Ȍ��ʂ́A�g�F�̒��x�^��ɓ˂��o���Ă���A2�K�̘L������̂�������̂悤�ȃo���R�j�[�ɂ� ����B�X�N���[���̏�̓S���̎萠�̃��`�[�t�������ɂ��g����B |
�M�b�u�Y�E�T���E���h�́A�p�b���[�f�B�I�̃��B�`�F���c�@�ɂ���p���b�c�H�E�e�B�G�[�l�i���E�ʐ^�j�ɂ��݂�����̂ŁA�M�b�u�Y�̃I���W�i���ł͂Ȃ��B
�g���t�@���K�[�L��̈��ɂ���M�b�u�Y�̑�\��Z���g�E�}�[�e�B���E�C���E�U�E�t�B�[���Y���ō̗p���A�܂�
�p�Ăʼne���͂̂������M�b�u�Y���z���gBook of Architecture"�Œ������ƂŁA�p�Ăł͂����Ă��B �M�b�u�Y���z����l�T���X�̌��z�����̑��A�\�[�X�u�b�N�Ƃ��Ă̌��z�֘A�����Q�Ƃ��A�M�b�u�Y�E�T���E���h���̑��� �ÓT�̃��H�L���u�����[�����b�`�F���X�͏n�m���Ă����B �V���E�̃`�F�X�^�[�Y�̊O���̊J�����ɂ��M�b�u�Y�E�T���E���h�̃��e�B�[�t�͎g���Ă���̂ŁA����ɂ��Ă��`�F�X�^�[�Y��K�ꂽ���Ƃ������|���ɂȂ����\��������B |

 |
|
|---|---|
|
�P�P�D�����f�B�X�t�@�[���E�L���b�X��Lindisfarne Castle 1903 �����h����HKPA�Ƃ����������œ����n�߂čŏ��̋x�ɁA�P�X�V�R�N�̃C�[�X�^�[�E�z���f�[�ɁA�}�b�L���g�b�V���̌��������ɁA�O���X�S�[�����߂ĖK�ꂽ�B ���̗��s�̓r���A�F�l�ɑE�߂��A�����f�B�X�t�@�[���Ƃ������ňꔑ�����B �L���X�g�����A�C�������h�A�C���O�����h�ɂ����炳�ꂽ�̂͂T���I�A�U���I���ŁA�y���̃P���g�l�Љ�̐M�ƗZ�����A�e�n�ɃP���g�E�L���X�g���̏C���@������ꂽ�B �X�R�b�g�����h�̓��A�C�I�i���P���g�C���@�̈��Z���^�[�ƂȂ�A�������琹�G�C�_���Ƃ����m��������āA���̃X�R�b�g�����h�ɋ߂��Ӌ��̒n�A�����f�B�X�t�@�[���ɃP���g�C���@���J���ꂽ�B �C���@�͔p�ЂɂȂ��Ă��邪�A���n�Ƃ��č����l�X�̐M���W�߁A�z�[���[�E�A�C�����h�ƌĂ�Ă���B | ����ȗ\���m�����Ȃ��A��������̃C�M���X�A�ǂ���Ƃ����܂��̉���r������H�ލr���Ƃ������i�̒��ɁA �ۂ�ƛ��������̎p���A�����Ĉ���ɓ��A�����̎��ɂ����A�{�y�ƒn�����ɂȂ�Ƃ����b���������������v���o���B 1903�N���A���b�`�F���X�̍ő�̃p�g�����A�G�h���[�h�E�n�h�\�������̏����ɓ���A���z�����b�`�F���X�ɈϏ�����B �����菭���O1893�N��1901�N�ɁA�}�b�L���g�b�V���͂��̓���K��A��̃X�P�b�`���������c���Ă���̂�� �z�[���[�E�A�C�����h�ƌĂ�邱�̓��́A����������Ȃ���A�قƂ�ǐړ_�̂Ȃ��������̓�l�̌��z�Ƃ��A�������������u ����������������Ȃ��B��̏ꏊ�ł������B |


| |
|---|---|
| �P�Q�D�p�s�����E�z�[��Papilon Hall 1903-1904 �����̊j�́A1620�N��Ɍ��Ă�ꂽ�A���������ɕ��ׂ������L�т����p�`�̎剮�ɕ����������k�Ɏ��t�������ʂ�������ȏZ��ł���B ����̓`���[���Y�ꐢ�̕�Ώ��l�ł������A�f�B���B�b�h�E�p�s�����Ƃ����l�ŁA ���̍��ɂ͗H�쉮�~�̂悤�ɂȂ��Ă����B �u���b�N��t�������`�̑��z�ł͂Ȃ��A�l�̗��̌`�ɒ���o���o�^�t���C�E�v������ ���{�����̂́A���̃p�s�����Ƃ������O����̘A�z����̂��������ɂȂ��Ă���Ǝv����B �����Ă�����̂��������͖ܘ_�A���̌v��̑O�Ƀm�[�}���E�V���E�v�̃`�F�X�^�[�Y��K��Ă��邱�Ƃł���B | �����̎�v�u���b�N���A�l�̕ӂ��痃��L���Ղ����p�`�Ƃ�������������̕��ʂ����Ă������Ƃ��A�ނ��o�^�t���C�E�v�����Ɍ����� �����傫�ȗ��R�ł��낤�B�i���ʐ}�̎ΐ��̃n�b�`���{�����ǂ������������B�j �����̎剮�ɒ��̉H���̂悤�ȗ����z�����m�[�}���E�V���E�̃`�F�X�^�[�Y�ƁA���b�`�F���X�͂قƂ�Ǔ���������{�����B �o�^�t���C�E�v�����͂��̍��A������x�̗��s���݂Ă��āA�V���E�̑��ɂ�E.S.�v���C�A�[�A M.H.�x�C���[�X�R�b�g�������݂Ă���B |
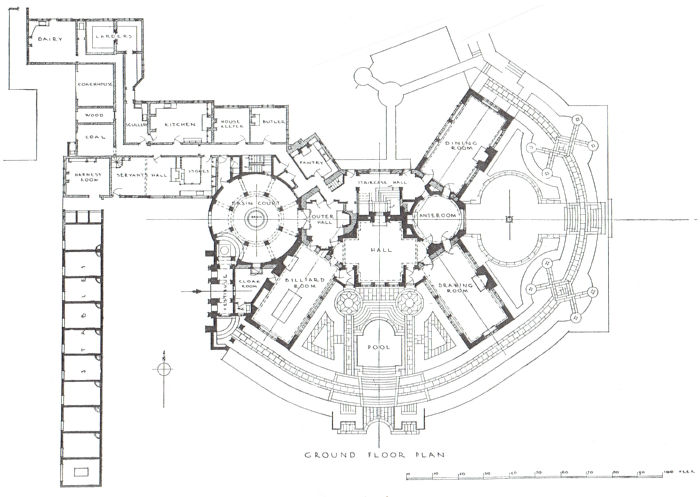
|
|
|---|---|
���̓@�ق͕~�n������������ł���B��Ɍ����ʂ胉�b�`�F���X�̓@�ق̊�{�^�� H�^�v�����Ŗk���肪���ʂł���B ���̎��ɐ�����̃��@���G�[�V����������A��v��i�̒��œ����̓@�ق� �O���C�E�E�H�[���Y�Ƃ��̃p�s�����E�z�[���ʂł���B ���̓����ł���Ƃ����v���C���@�V�[�����ɂ�������ȕ~�n��������A �����ɃA�v���[�`�ɉ����Ē����L�т��X�ɂ���������A�܂��~�`�̃R�[�g������ȂǁA ���܂��܂ȑ�������Đl�������ς��Ă���B | �����Ă���ɃG���g�����X�E�R�[�g����A�z�[������܂ł̌o�H�� �́A���l�ȋ�ԑ̌������킦��悤�ȍH�v���Ȃ���Ă��āA���b�`�F���X�̃E�B�b�g�̐^ ������������B �܂��G���g�����X�����ɂ́A���̕����ɂ͌����Ȃ����@���u�����v�킹��A ���X�e�B�P�C�V�����̎{���ꂽ4�{�̒��Ŏx�����ꂽ�y�f�B�����g���A����Ă����悤�Ƀ`���[ �_�[�l���̓@�ق�1�K�ɒ���o���Ă���B |
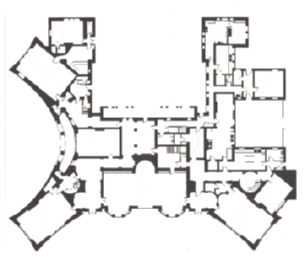

 |
|
|---|---|
���̃M�b�u�Y�E�T���E���h�̕ό`�̂悤�ȃo���b�N�I�͋����́A�z�[�N�X���[�A�A���@���u����t�����X�̃��h�D�[�A ����ɂ̓W�����I�E���}�[�m���z���N������f�U�C�����`�F�X�^�[�Y�̉e�����낤�B ���̃y�f�B�����g�̉���������ƌ��ւȂ̂����A���ʂ͍s���~�܂�ŁA�����ɍ��ɋȂ���� �x�C�X���E�R�[�g�ƌĂ��~�`�̒���ɏo��B �����͎��͂��g�X�J�i���̗��߂��点���A�[�P�[�h�ɂȂ��Ă��āA���Α��ɂ���� �G���g�����X�E�h�A�������邱�Ƃ��o����B �h�A���J���ăA�E�^�[�E�z�[���ƌĂ��G���g�����X�E�z�[���ɓ����Ă��A�^�������� �����C���̃z�[���Ƃ����킯�ɂ͂����Ȃ��B �ߍ��O���̊J���������ƃM���V���\���`�̃��C���E�z�[���ɒB���邱�Ƃ��ł���B | �����̗��ʂ̍\���́A�O���C�E�E�H�[���Y�̘p�Ȃ����G���g�����X�t�@�T�[�h�Ɨǂ��� �ė����ɉ��˂��������ǂ��p�x�ŗ��[������o���Ă���B ���̗��ʂ̒��S�ɂ���Q�[�u���́A���z�O�̊����������ێ�����Ă���B �������A�n�[�t�E�e�B���o�[�ɂ����̂̓��b�`�F���X�̃f�U�C�����Ƃ�����B �l���̍����A���Ԃ̗v�f�A�T�[�L�����[�V�����̈Ӑ}���ꂽ���G�����A���b�`�F���X�� �v�����j���O�̓����̑������A���̃p�s�����E�z�[���ɂ�������Ă���B �o�^�t���C�E�v�����̒��ł͍ō��ɐ������ꂽ�A���̃p�s�����E�z�[�������A �c�O�Ȃ���1948�N�ɉ�̂���A�������Ă��Ȃ��B |

 |
|
|---|---|
|
�P�R�D�q�[�X�R�[�gHeathcote 1905-1907 �p�s�����E�z�[���̃o���b�N�I�t�@�T�[�h�̂�����ɁA����܂ŕ����I�Ɏg���Ă����A �ÓT�I�ȗl���̃��H�L���u�����[�𗧖ʑS�̂ɋy�ڂ����q�[�X�R�[�g������ė���B �m�[�}���E�V���E�̃`�F�X�^�[�Y�̕~�n�͌Ñネ�[�}�̗̓y���ő�ɂȂ������̖k�[�A�C���O�����h�k���̃j���[�J�b�X���ɋ߂��A �n�h���A�k�X��̒���̈�Ղ̋߂��ɂ���B�`�F�X�^�[�Ƃ����P����Ñネ�[�}�̌R�c�̏h�c�n���Ӗ�����B ���̈�Ղ̑��݂��A�m�[�}���E�V���E�̑z���͂��h�����āA�Ñネ�[�}��A�z������A��Ȗʂ̃f�U�C�����Ƃ��e�Ղɍl������B ���b�`�F���X�̃q�[�X�R�[�g�̕~�n���A��͂�C���O�����h�k���A���[�Y�ɋ߂��C���N���[�Ƃ����ꏊ�ł���B�`�F�X�^�[�Y���͏����삾���A �~�n�����b�`�F���X�̈�����T���[�B�������������̒n��ł�������A�����炭�̓��b�`�F���X�͂����܂ŌÓT��`�������o�����Ƃɂ� �S�O�����̂ł͂Ȃ����낤���B�����̓��@���u���A�z�[�N�X���[�A�̃L���b�X���E�n���[�h�̂��郈�[�N�ɂ��߂��B ���������ꏊ����̘A�z���A���b�`�F���X���ÓT��`�Ɍ����킹���v���ɂȂ��Ă���C������B �ꏊ�̃R���e�N�X�g���d�����郉�b�`�F���X���A�����������Ƃ�厖�ɂ��Ȃ���A�����Ȃ�ÓT��`�A�}�j�G���X���A�o���b�N�� �����ė��Ă������̂ł͂Ȃ����ƁA������������l�����̂ł͂Ȃ����낤���B | ���ʑS�̂��O�ꂵ�ČÓT��`���z�̃��H�L���u�����[�ł܂Ƃ߂��Ă���B���F���ۂ����̂ƃO���C�̒n���Y�̐̊O���̑���́A �ÓT��`�ł��}�j�G���X�����A�{�����[���̂��鉌�˂̌`�ԂȂǂ̓o���b�N���v�킹��B �F�l�n�[�o�[�g�E�x�[�J�[���̎莆�̒��ŁA���b�`�F���X�̓I�[�_�[�ւ̌X�|�������L���Ă���B �g�����o���h���X���I�[�_�[�|�Ȃ�ƈ��炵���|�����͐}�X�������̗p����B�����ł��邽�߂ɂ͂����P�ɃR�s�[���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��A ��U�̗p����ƌ��߂���A���g�Ńf�U�C�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�D�D�D�����3�����̑S�Ă̐�����ш��̐ڍ����ɂ��čl�������n�[�h�ȍ�Ƃ��Ӗ�����B �ǂ̂ЂƂ̐����Ղɂ��炷���Ƃ͂ł��Ȃ��B�������������Ď��g��ł����A�I�[�_�[�͎����̂��̂ƂȂ�A�����������_�I�ȑ�����J��Ԃ����ƂŁA�_����������� ���I�Ō|�p�I�Ȕ\�͂��g�ɂ��Ă����̂��B�h �q�[�X�R�[�g�ŌÓT��`�A���邢�̓m�[�}���E�V���E�Ȃ݂̃G�h���[�f�B�A���E�o���b�N��O�ꂵ�Ă�����������A���̌ド�b�`�F���X�͂���قǂ� �ÓT��`��S�ʂɉ����o�����Z��͂����Ă��Ȃ��B�ނ��냔�@�i�L�����[�ȃN�C�[���E�A���l���A�����l�T���X�̏Z������Ȃ�B �G�h���[�f�B�A���E�o���b�N�Ƃ��Ă��A�q�[�X�R�[�g���p�s�����E�z�[���̃G���g�����X��x�C�X���E�R�[�g�A���邢�͂܂����g���Z�C�J���̓������ �̕����f�U�C���I�ɂ͖ʔ����v����B |

 |
|
|---|---|
�엧�ʂ̍��E�ˏo�����̈ӏ��͉E�̃T���~�P�[���̃|���^�E�p���I�̈ӏ������p���Ă���B ���̓q�[�X�R�[�g�엧�ʂ̃��b�`�F���X�̃h���[�C���O�B �E�̓C�^���A�A���F���[�i�̃|���^�E�p���I(1530�N��)�Őv�̓}�j�G���X���̌��z�ƃ~�P�[���E�T���~�P�[���B �}�j�G���X���͏����ɂ���ĉp���̌��z�Ƃɑ傫�ȉe����^�����B�T���~�P�[���̖{��1735�N�ɏo�ł���A ���o�[�g�E�A�_����R�b�J�����A�u�����t�B�[���h�ȂǑ����̌��z�ƂɎQ�Ƃ��ꂽ�B |
���b�`�F���X�̓��F���[�i�ɍs�������Ƃ͂Ȃ��A�T���~�P�[���̖{�̃h���[�C���O����̈��p�̂悤���B �嗤�ł̓��_�j�Y�����萶���n�߂�20���I���߁A���b�`�F���X�͌ÓT��`���z�̃I�[�_�[���ǂ��Z��ɉ��p���邩���A 19���I�̉p���̐�B����S�����悤�ɐ^���Ɍ������Ă����B ����ɊO���̕t���̒����̉��́A���X�e�B�P�[�V�����̕ǂ̒��ɏ��ł��Ă���B �C�^���A�̃}�j�G���X�g�A�W�����I�E���}�[�m���v�킹�郉�b�`�F���X�ŏ�̃E�B�b�g�A�W���[�N�����A ���́g������s���X�^�[�h���A�y���X�i�[�́g�V���[�E�W���[�N�h�Ƃ��Ĕے�I�Ɍ��Ă���B |
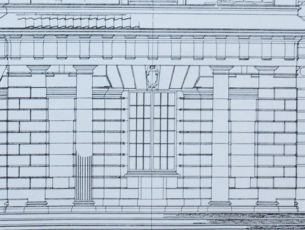

| |
|---|---|
�����ɂ��A�ÓT��`���z�̌��ꂪ�䂫�킽���Ă���B���̃N���V�J���ȗl���Ɋւ�炸�A���ʍ\���͓T�^�I��H�^ �Ŗk����̃v�����ł���B ��ɂ���āA���E�Ώ̂̎����ƁA�����̃Y���Ƀ��b�`�F���X�炵�����o�Ă���B �z�u�������S�̂̌`���A���Ȃ�O��I�ȍ��E�Ώ̂ł���B�G���g�����X �E�h�A�ƃz�[���A�����Ē뉀�̎��́A���S�Ɏ�����ɂ̂��Ă���B���ꂾ���ɗ]�v�A�G�� �g�����X����z�[���Ɏ��铮���́A�����ȂƂ��낪�ڗ��B �G���g�����X�����Ɛ��ʂ̓z�[���̒g�F�̗����ɂ�����ǂł���A �E�[�Ƀ��r�[�ւ̓���������B ���̌��ւ̊Ԏ��̂́A����Ƃ͕ʂɒg�F�𒆐S�ɍ��E�Ώ̂� �Ȃ��Ă���B�E�ɊK�i�����_�Ԍ��Ȃ���z�[���ɓ���ƁA�����́A�z�[���̒��S����� 4�{�̒��ƃA�[�`�ŕ��f���ꂽ��Ԃɏo��B |
���̂܂ܑO�^�����s���Β�ɏo��h�A������B �z�[���̗��[�Ƀ_�C�j���O�ƃV�b�e�B���O�E���[���������āA���S���ƒ������鎲���Ō� ��Ă��āA�[���ɂ��ꂼ��̕����̒g�F������Ƃ���́A���g���E�Z�C�J���Ƃ悭���Ă���B �O�Ϗ㒍�ڂ��ׂ����b�`�F���X�̃E�B�b�g�́A���X�e�B�P�C�g���ꂽ��̃o���b�N�I�ȃ}�b�V���ȉ��˂��B �����̏㕔���}�O�T��ɂȂ����Ă��āA���������h�A�J�����A�ɕ������ ���݂���悤�ɂ�������B �܂����g���E�Z�C�J���̃z�[�������ɂ������o���R�j�[���� �̃A�C�A���E���[�N�̎萠��Ɠ������̂��A�O���e���X�Ɍ����A�S�̂̃}�b�X�� �͋����ɝh�R���āA�\���a�炰�Ă��邱�Ƃł���B |
  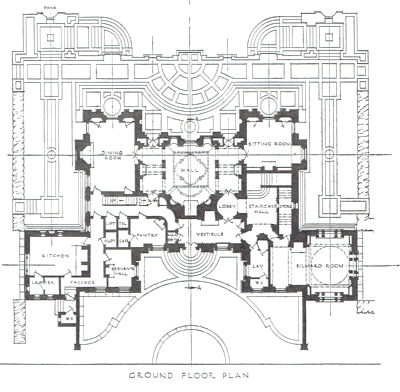 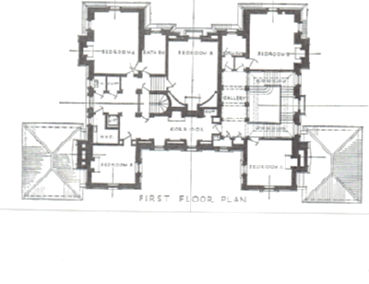 |
|
|---|---|
|
�P�S.�U�E�T���e�[�V����THE Salutation 1911 �~�n�̃R���e�N�X�g��ǂݐ�A��������g�������b�`�F���X�̃U�E�T���e�[�V�����̃T�C�g�v�����́A�ۂ����čI���Ŕ������A �K�[�g���[�h�E�W�[�L���̑����Ƒ��܂��āA�@�m�ɕx�A�C�f�B�A�ɖ����Ă���B �~�n�̌`��A�A�v���[�`���H�A���ʂ��猚���̈ʒu�͓K�ȏꏊ�Ɍ��肳��āA��������~�n�S�̂ɁA ������2�{�A��k��1�{�̋����������ݒ肳��A��������뉀�܂ł�����B �A�v���[�`���H�̂Ԃ���ʒu�ɃG���g�����X�Q�[�g���Ƃ�A���̉�������ɓ�������ݒ肷��B�����̒��S�̓������͂������班���k�ɂ��炵���ʒu�� �u���A�G���g�����X�Q�[�g�����ƑO�����̑Ίp�����Ɍ����̌��ւ��Ƃ��Đl���B���̂悤�ɊO���ł��A�����̂悤�ɐl�̓����������Ƃ��炷�B �~�n�̌`��ɍ��킹�āA���C���̒뉀�̓������Ɠ�k���̉��s�������قڍő�ɂƂ��悤�ɍl����ꂽ�ʒu�Ɍ������z�u����Ă���B ��̑O�납��O�ꂽ3�p�̋��̃z���C�g�K�[�f���ƌĂ��A�����炭�̓W�[�L�����́A�~�`�̒납��A �~�n���E�ɉ����āA���͓I�ȃ|�v�����̕������L�т�B �~�n�̌`��ǂݍ���ʼn����ꂽ�A����ȊO�ɂ͍l�����Ȃ��悤�ȁA�����ƒ뉀����̂ɂȂ����A�s�^�b�ƌ��܂������̂���▭�ȃT�C�g�v�����ł���B �뉀�����猩�������́A�������̓��̎��̌�������7�̑����̕��̓����ʁi�E�ʐ^��j�ƁA�Z����̎��̌�������5�̑����̕��̓엧�ʁi�E�ʐ^���j�A���w�Ǔ����\��Ō����Ă���B �����̕ǂɐ̋��A�����i�q�̃T�b�V�E�E�B���h�E�ƌĂ��グ�������A�}���z�̉����Ƀh�[�}�[���A�X�p���������قȂ�A �����\��̗��ʂ��A���S�ȃV�����g���[�ŁA���s���̂����ɑΛ����Ă���B��̉��s�������̒Z�����ɂ͕��̋������ʁA�������ɂ͍L�����ʂ��ĉ����Ă���B �N�C�[���E�A���l���̉����ȉp���I�ȏZ��ɁA���ꂾ���͉����ł͂Ȃ����b�`�F���X���L�́A����ƌ����Ă������A��̃`���j�[��2�{�˂��o���Ă���B 1,2,3�K�̊e���ɂ���10�ӏ��̒g�F����́A�v10�{�̉��ǂU���Ȃ��ŁA����2�{�̉��˂ɐU�蕪���A�Ӑ}�I�ɕ��L�ɂ��Ă���B ���A��A���A�V�����g���J����3�̗��ʂ����剮�̖k���ɁA�����̃T�[�r�X�u���b�N�����t���āA�����ȃV�����g���J���Ȏ剮�̂P�������āA �����łȂ���Αދ��ɂȂ��������m��Ȃ��O�ς̃o�����X���Ƃ��Ă���B |

 
|
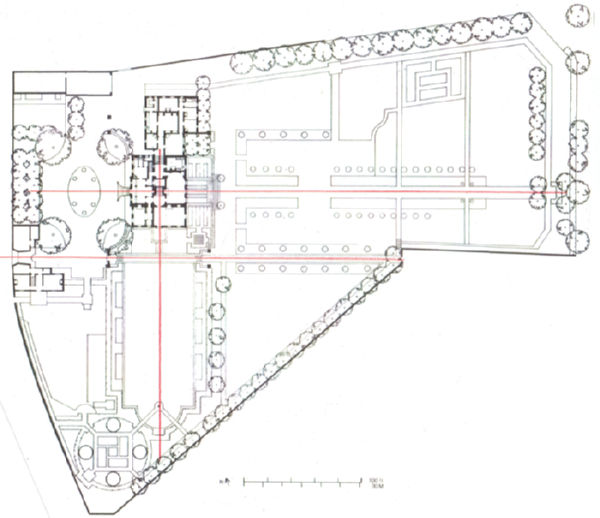
| |
|---|---|
2014�N�ĂɖK�˂��U�̏Z��̓��A����܂łɐG�ꂽ�S�_�[�Y�A�e�B�O�{�[���E�R�[�g�A�z�[���E�b�h�Ƃ͈قȂ�A �U�E�T���e�[�V�����A�O���[�g�E�f�B�N�X�^�[�A�v�����v�g���E�v���[�X�̂R�̏Z��́A�q�[�X�R�[�g�̌�ɂł����Z��ł���B ���葽���A�܂����l�ł������������s���Ԃ̓��B�_�ł���A�ÓT��`���z��S�ʓI�ɍ̗p�����q�[�X�R�[�g�ȍ~�A ���b�`�F���X�͌ÓT��`���z�̌���͕����I�Ɏg���ɗ��߁A �S�̂Ƃ��Ă͈�ʂ̉p���l���D�A�p���I�ȏZ��Ɉڍs����B |
�p���I�ȏZ��Ƃ́A�����l�T���X�ƃ��b�`�F���X���ĂA���l�T���X�̗v�f���������N���X�g�t�@�[�E�������̗������̗l���A ���邢�̓����l�T���X�Ɠ����̏d�Ȃ�A�P�W���I�����̃A����������̃����@�C���@���A19���I�㔼�ɑh�����A ��͂�����̊O�ς́A�����O�̎���̃V���E��E�F�b�u���D�A�N�C�[���E�A���l���ł���B �������������ȉp���Ɠ��̏Z��̊O�σf�U�C���ɁA�q�[�X�R�[�g������Ă���r�������烉�b�`�F���X�͌X���Ă����B |
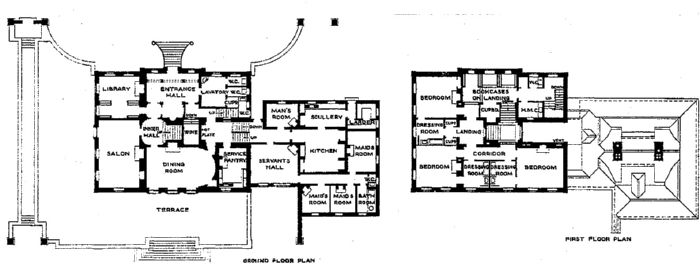
| |
|---|---|
����̓N���C�A���g�̚n�D�ɍ��킹�邱�Ƃł��������낤���A�O�ςɂ��Ă̓q�[�X�R�[�g�܂łɂ���������������A �ނ���~�n�̓�����ǂݎ��T�C�g�v�����A�܂����ʍ\���̕��Ƀ��b�`�F���X�̍�Ƃ̔�d���ڂ����̂�������Ȃ��B �U�E�T���e�[�V�����ɂ����Ă��A�O�ς͑f���ɂ������Ă����āA���ʂ̓��b�`�F���X��̎����ƁA�����Ƃ����l�̓����A �S�̂Ƃ��ẴV�����g���[�ƕ������Ƃ̃V�����g���[�Ŋe�����\������Ƃ��������ʑ���͂����ł������邪�A ���̏Z����͔�r�I���ƂȂ����[�߂Ă���B |
�K�i�̈ʒu�����������ɒ��p�����ɒu����Ă���̂́A�z�[���E�b�h��e�B�O�{�[���E�R�[�g�Ǝ��Ă��邪�A �Ƃ̐^�ɂ���K�i���֎��R�����̂����邽�߂ɁA�z�[���E�b�h�̃g�b�v�T�C�h���C�g�ƈ���āA�����ł͕����̃T�[�r�X���Ƃ̃W���C���g���́A �Q�K�����̕����ɁA�؍��݂����āA�O�ǂ�x���܂ň����āA��������悤�ɂ��Ă���B ���̐؍��݂͊O�ς��猩�邱�Ƃ��ł���B�Ƃ̒��ւ͓���Ȃ������̂ŁA�c�O�Ȃ���K�i�̗x��� �̌��̗l�q�͎����͂ł��Ȃ������̂����B |


| |
|---|---|
�ӂ��̃u���b�N�̊Ԃɉ����������āA���̗����Ƀh�[�}�[�E�E�B���h�E�̂��閣�͓I�ȃQ�[�g�n�E�X�B(��}) ���̃Q�[�g�̉�������Ƀz�E���E�I�[�N�E�E�H�[�N�i�E�o���K�V�̏��H�j�ƌĂԋ���������ʂ��Ă���B(���}) |
�剮�̖k���ʂ�2�K�����ɊJ����ꂽ�K�i���ւ̍̌��̂��߂̐؍��݂�������B(��}) �Q�[�g�n�E�X�̖k���u���b�N�ƁA��O�e���X�́A���S�n�̂����e�B�[���[���ɂȂ��Ă���B(���}) |


| |
|---|---|
|
�P�T.�O���[�g�E�f�B�N�X�^�[Great Dixter 1912 �i�T�j�G���E���C�h���P�X�O�X�N�ɍw�������m�[�V�A���̕~�n�ɂ́A15���I���Ɍ��Ă�ꂽ�f�B�N�X�^�[�ƌĂꂽ �n�[�t�E�e�B���o�[�̌������������B(�E��ʐ^�A���}���F�̕���) �剮�̃f�B�N�X�^�[�͉p���ōł��傫�Ȏc������ؑ��ƌ����Ă���B���̑��ɁA�~�n���ɂ̓O���[�g�o�[���Ƃ����[���A �I�E�X�g�n�E�X�ƌĂ��z�b�v�̊����F�̂��߂̌����A�z���C�g�o�[���Ƃ����X�ɓ��A ��r�I�V�����P�X���I�̌������������B �����������������������z�v��̗��Ă����C�h�͍ŏ��A�A�[�l�X�g�E�W���[�W�ƃ��b�`�F���X�̓�l�Ɉ˗����A���ʓI�ɂ̓��b�`�F���X���������A�d���� ���b�`�F���X�͓Ɨ��O�ɂU�����ԁA�A�[�l�X�g�E�W���[�W�̎������œ����Ă���B�ނ̓N�C�[���E�A���l���̃J���g���[�n�E�X�̃f�U�C���� ��]�����������z�ƂŁA���b�`�F���X�̂���Ύt�ɓ�����l�A�X�^�[�g���C���ʼn��炩�̉e�������͂��ł���B �i�T�j�G���E���C�h�����@�i�L�����[�ȃA�v���[�`��厖�ɂ���l���̐l�ŁA�W�[�L���������̂Ɠ����悤�Ƀ��b�`�F���X�Ǝ��ӂ̌��z�ׂĉ�����B ���̎��A�m�[�V�A�������14km���ꂽ�P���g�B�x�l���f���ŁA�قƂ�ǔp���ƌ����Ă����A�n�[�t�e�B���o�[�̌����������w�����A ��̂��āA�f�B�N�X�^�[�̑Ίp�ʒu�̓�̃R�[�i�[�Ɉڒz�����B(�E���ʐ^�������A���}���F�̕���) �~�n�ɂ͒i���������āA���̈ʒu�œ쑤����i�Ⴍ�Ȃ��Ă��āA���̒i���̍ۂɂ��̃x�l���f���E�n�E�X�͈ڒz���ꂽ�B �f�B�N�X�^�[�Ɠ������x���ɂ��邽�߁A �P�w���̗������̊�b����������ɐ�����ꂽ�B����ɊK�i�����������A��K�̂P,�Q�K�͐Q���ɉ������ꂽ�B �P�K���x���̊O���ɂ̓e���X�A���̒[�Ƀ��b�W�A������A�����K�̊�b�����͒n���P�K�̃r���A�[�h���Ƃ��Ďg��ꂽ�B �I���Ȉʒu�Ɉڒz���ꂽ�x�l���f���E�n�E�X�ƁA���Ƃ��Ƃ������f�B�N�X�^�[�����z���A���̓�̃n�[�t�e�B���o�[�̌����ɋ��܂ꂽ�����ɁA 1�K�ɃT�[�r�X����A�Q�K�ɂ͐Q���Ǝq������������A�O�ς̓A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�I�ȕ\��������������̌������}�����ꂽ�B �q�������i�i�[�T���[�j�ɂ́ACrawling Window�ƌĂ��A�͂��͂�����c���ɂ��O�̌i�F��������悤�ɁA�����x���̑����ݒu����Ă��āA �E�B�b�g�̂��邫�ߍׂ₩�ȃ��b�`�F���X�̔z��������������B 3�̕����S�͓̂����^�C�������ŕ����A����͂܂��15���I�ȗ��i�X�Ƒ����z���d�˂Ă�����̂̌��z�̂悤�Ɍ�����B ������������z�́A���E�{���E�f�E���`�G�ȗ��A�p�s�����E�z�[���A�O���C�g�E���C�T���A�A�C�������h�̃����x�C�E�L���b�X���A ���̑啪��̃v�����v�g���E�v���[�X�ƁA���b�`�F���X�͐������c���Ă��邪�A��������������Ƒ��z�������A �I���ɗZ�������̂ƂȂ�A��a�������������Ȃ��B ���Ƃ��Ƃ����������f�B�N�X�^�[�̓��͑�X�p���̖؍\���̃O���[�g�E�z�[�������A�����̂Q�w�����ɊK�i��ݒu���A�P�K���p�[���[�i�Ƒ����j�A �Q�K���\�[���[�i�T�����[���j�ɉ������Ă���B �i�T�j�G���E���C�h�̓O���[�g�E�f�B�N�X�^�[�̑����z�̌��݉ߒ��ŁA���z���邱�Ƃ̖ʔ����ɖ�������A���猚�z���w�сA�����Ȏ��������J���A ���̎��ӂɊ���̍�i���c�����B����ɂ͌��z�̗��j�ɂ��������g���A�̂���"�p�����������̗��j�h�i1925�N���s�j�h�p���Z��̗��j�h�i1931�N���s�j �Ƃ���2���̖{���㈲�����B |




|
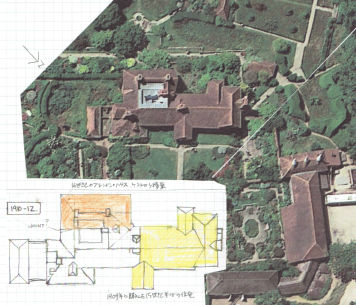
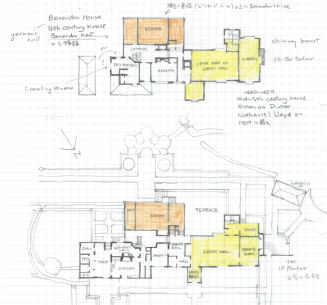
| |
|---|---|
|
�U�E�T���e�[�V�����E�e�B�[���[���̃e���X�ŋx��ł���ƁA�J���~�肻���ȋC�z�Ȃ̂ŋ}���ŗ�������߂�A
�T���h�C�b�`�w�ɒ������r�[�̋ǒn�I�ȏW�����J�A�낤���Z�[�t�������B
�T���h�E�B�b�`���烉�C�ւ͗�Ԃňړ��B ���C�ɒ����Ƃ����ĕς���ĉ����B���C����̓o�X��20���̃m�[�V�A���Ƃ����Ƃ���ɃO���[�g�E�f�B�N�X�^�[�͂���B 3�����ɓ����B�l�b�g�Œ��ׂ����ł́A�O���[�g�E�f�B�N�X�^�[�͌��J����Ă��āA�����͌��J���̂͂��ł������̂ɁA�x�݂��Ƃ����f�����o�Ă����B �K�b�J�����āA�Ƃɂ������肾���ł����悤�ƕ����Ă���ƃI�[�i�[�炵���w�l����d�������Ă���B ������Ǝv���Đq�˂Ă݂�ƒ낾���Ȃ炢���ł���A�ƌ����B |
��l8�|���h�̓������͂���������ꂽ���A���ɗ��K�҂����Ȃ��̂ł������ƒ뉀�ƌ����̊O�ς����邱�Ƃ��o����
���ǂƖ̕ǂ̃n�[�t�E�e�B���o�[�ƁA�����A�傫�Ȍ��z�����̃A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̍I�݂ȗZ���A�s�N�`���A���X�N�B
�����ĉ��������b�`�F���X�̃I���W�i���i�K�[�g���[�h�E�W�[�L���̓O���[�g�E�f�B�N�X�^�[�̒뉀�v��ɂ͊ւ���Ă��Ȃ��悤�ŁA
�뉀�����b�`�F���X��l�ɂ��Ƃ���Ă���j�ɉ�����ꂽ�A�q���̑����ƁA���{�ł��m���Ă���N���X�g�t�@�[�E���C�h�̉p�����뉀�B �炫�����ԁX�̎�ނƗʁB���|�I�ȉߏ�A���ׂ̒��̒����Ƃ�������A�͂ɐ��킳���B����Ȓ뉀�͍��܂Ŋς����Ƃ��Ȃ������B |


| |
|---|---|
|
�P�U.�v�����v�g���E�v���[�XPlumpton Place 1928 �p�����s�̒��O�A�e���r���ςĂ�����A�ǂ����Ō����悤�ȉƂ��o�Ă��āA�͂��Ƃ��āA �������A���b�`�F���X�̃v�����v�g���E�v���[�X�Ɏ��Ă���Ǝv���������B �X�^�W�I�E�W�u���́g�v���o�̃}�[�j�[�h�̗\���������B �ł��������ė\���҂̉摜�A����A�����Ăڂ����v���o�����v�����v�g���E�v���[�X����ׂĔ�ׂĂ݂�ƁA����Ă����B ���Ă���̂̓��P�[�V�����������B ���Ă����̂́A�f���炵�����������ӂ̃��P�[�V�����Ɍ��A���b�`�F���X�̏Z��A�v�����v�g���E�v���[�X�B �p�����z�̃s�N�`�����X�N�A�G�̂悤�ȁA�Ƃ͂��������Z��̂��Ƃ��낤���B ���̂悤�ɉ��̗\���m���Ȃ��ɁA��ʂ̐l���������Ɗ�����A���b�`�F���X�������������͂���ȏZ������̂ł͂Ȃ����낤���B �R���r���W�G��~�[�X���A�ߑ㌚�z�A���_�j�Y���̌��z���������n�߂鏭���O�A���邢�͓�������A ���b�`�F���X�̓��_�j�Y���ɂ͖ڂ����ꂸ�A�Ђ������ʂ̉p���l���������Ɗ�����̂��炻���ɂ������悤�ȏZ������葱�����B ����A���ۂɂ̓��b�`�F���X�̓}�b�L���g�b�V�������Ă������A�t�����X�̃h�[�o�[�C���ɖʂ����{�A�E�f�E���`�G�ŁA �������������V���������Ɍ��������Ƃ����`�Ղ��A�_�Ԍ����Ă��邪�A�����ɋO���C�����āA �����Ђ�����A��ʂ̉p���l�ɂƂ��Ă̔������Ƃ̕����ɖ߂����B �ʔ������ƂɁA���̃v�����v�g���E�v���[�X�̓��b�h�E�c�F�b�y�����̃W�~�[�E�y�C�W���A���ďZ��ł����Ƃł����邱�Ƃ��B ���b�N�X�^�[�̍D�މƁA���邢�͉p���l�̍D�މƁB �l�b�g�����낢�뒭�߂Ă���ƁA�ȑO�v�����v�g���E�v���[�X�͔��Ƃ̍L����8,000,000�|���h�Ŕ���ɏo�Ă������A ���ꂪ�����A�����Ă����B ���b�h�E�c�F�b�y�����̃W�~�[�E�y�C�W�͍���A�����ЂƂ̃��b�`�F���X�̏Z��f�B�[�i���[�E�K�[�f�������L���Ă���悤���B ����Ȃ킯�ŁA���w�\��̃��b�`�F���X�̏Z��Ƀv�����v�g���E�v���[�X���������B �D�ԂŃv�����v�g���܂ōs���ăO�[�O���E�}�b�v�𗊂�ɁA�Q�O���ʕ����Ă��ǂ蒅�����B ����̗��ł̓t���L�V�E�p�X��WiFi���劈��ŁA�����ɍs���ɂ����{�ɂ��鎞�Ɠ����悤�ɕ\�������O�[�O���E�}�b�v����B �r���œ���q�˂����ɁA�������̓v���C�x�[�g�E�n�E�X������A �s���Ă�����܂����A�ƌ���ꂽ���Ƃ������āA��������֎~�̃T�C���̂����̑O�ł��炭�S�O���Ă���A �v�����Ē��܂œ����čs���āA����@���B ���݂̎�����̃A�����J�l�͕s�݂̂悤�ŁA�^�̗ǂ����ƂɁA�Ǘ������Ă���K�[�f�i�[�̐l���ē����Ă���邱�ƂɂȂ����B���b�`�F���X�̘b�Ő���オ���āA���������� �������Ȃ���A�L��ȊO�����ςĉ�邱�Ƃ��o�����B �L���ɕ����ԓ��Ɋ����̃}�i�[�n�E�X������A���̃R�[�i�[�̐��ӂɖʂ����ʒu�ɁA���b�`�F���X�̓~���[�W�b�N���[���z�����B �L���~�n������Ă���ԁA���̌������ɂ͏�ɂ��̃~���[�W�b�N���[���̈�p���������B �V�����g���[�̃}�i�[�n�E�X�̂��̃R�[�i�[�̈ʒu���A�뉀�S�̂���݂Ď��o�I�ɏd�v�ȏꏊ���Ƃ������Ƃ́A ���������ł͂����炭�ӎ�����Ă��Ȃ������ł��낤���A�~���[�W�b�N���[�����ł��邱�Ƃɂ���āA�}�i�[�n�E�X�ɑS���V�������͂��t����������B |
    |
 | ||
|---|---|---|
���b�`�F���X�ɂƂ��Ĉ̑�ȃp�g�����ł���G�h���[�h�E�n�h�\������˗����ꂽ�f�B�[�i���[�E�K�[�f���A�����f�B�X�t�@�[���E�L���b�X���� ����3�Ԗڂ̂����čŌ�̏Z��ł���B �����̃}�i�[�n�E�X�̑����z�ƒ뉀�v����܂ޑS�̌v��ŁA�����߂��̃Q�[�g�n�E�X�̐V�z�A�A�v���[�`�̋���ւ̊K�i��e���X�̐V�z�A �����Ċ������ւ̃~���[�W�b�N���[�����z����Ȃ�B �ʐ^�����쐼�G���g�����X�Q�[�g�������A���b�`�F���X���V�z�����Q�[�g�n�E�X�̃Z���^�[�����A�r�����b�`�F���X�̋���n��A �����}�i�[�n�E�X�֎��鎲�����L�т�B�}�i�[�n�E�X�k���̃R�[�i�[�Ɍɖʂ��ă~���[�W�b�N���[��������B �f�B�[�i���[�E�K�[�f���ƃ����f�B�X�t�@�[���E�L���b�X���ł͋��������K�[�g���[�h�E�W�[�L���͂��łɍ���ŁA�뉀�̐v�ɒ��ړI�ɂ͎Q�����Ă��Ȃ��B 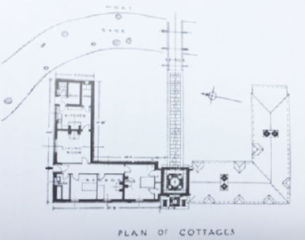

|
�������n�h�\������̃X�i�b�v�ʐ^�𑗂�ȂǏ��������ł���A�n�h�\���Ƃ̎莆�̂���肩��A�W�[�L���̃A�C�f�B�A�����f���ꂽ�悤���B �W�[�L���͂��̐��N��A1932�N��89�ŖS���Ȃ����B �n�h�\���͖S���Ȃ�܂ŁA�v�����v�g���E�v���[�X�{�̂ɂ͉��̂��Z�ނ��Ƃ͂Ȃ��A�ނ̂��߂Ƀ��b�`�F���X�����������A �̈�ԉ��ɂ��鐅�ԏ����ɑ؍݂��������ł���B�n�h�\�����W�[�L����4�N��A1936�N�ɖS���Ȃ����B ���E�{���E�f�E���`�G����O���[�g�E�f�B�N�X�^�[�܂ŁA���b�`�F���X�͐������̑����z�̍�i���c���Ă��邪�A �������������ăR���v���b�N�X�����グ�郉�b�`�F���X�̂����͎��ɍI�݂ŁA���������̓I���W�i��������������� ��݂�����B �����z�����͂��������̂��炻���ɂ��������̂悤�ɁA�����o�Ă������������ɂقƂ�Nj�ʂ����Ȃ��悤�ȍI���Ȃ����ŁA�V���Ȗ��͂�t��������B 

|
|
�P�V�D���b�`�F���X�̐v��@ �W�����E���X�L���̎v�z�I�e�����������Ƃ̃K�[�g���[�h�E�W�[�L���Ƌ��ɁA�T���[�̃��@�i�L�����[�ȃt�@�[���n�E�X�_�Ƃ� �������邱�Ƃ��烉�b�`�F���X�̓X�^�[�g�����B ���b�`�F���X�̏����̏Z��̕~�n�̎��ӁA�E�F�X�g�E�T���[�ɂ́A16,17���I�ɃC�^���A�̃��l�T���X���z���n���������̃S�V�b�N���z�ɍ������n�߂��A �`���[�_�[���A�����ăG���U�x�X���ȗ��̏Z��ɁA�E�l�����̎肪��������Z�����A ���邢�͂܂�1860�N��ȍ~�̃h���X�e�B�b�N�E�����@�C���@���̌��z�ƒB�ɂ��Z��������B �O�ς̓Q�[�u���ƃ`���j�[�������ŁA�O�ǂɂ́A���̂��邢�̓X�^�b�R���h��ꂽ�����A�o�[�Q�[�g�E�X�g�[���A�܂��`���[�_�[���ȗ��̃n�[�t�E�e�B���o�[�̏Z�������B �����ɂ��Ԃ����[�t�^�C���A�܂��̓z�[�V�����E�X���[�g�̂悤�ɃT���[�B���L�̍ޗ����g���Ă���B �W�F�[���Y�E�X�^�[�����O���A�����̌��~�n�̃R���e�N�X�g��厖�ɂ����悤�ɁA �}�b�L���g�b�V�����X�R�e�B�b�V���E�o���j�A���l���Ƃ������̓y�n�ŗL�̗l����厖�ɂ����悤�ɁA���b�`�F���X�� �T���[�B�̃��@�i�L�����[�̃R���e�N�X�g����Z��̐v���X�^�[�g�����A���̌���v���˗����ꂽ�e�n�́A�ꏊ�̃R���e�N�X�g�ɏ�ɌŎ������B | �K�����̓y�n�̍ޗ����g���A�����̌��~�n�̗�����ǂݍ��ނȂǂ́A�R���e�N�X�g��厖�ɂ��邱�Ƃ����b�`�F���X�́A���U���������A ���z�̌`�Ԃ��l�����ő��ΓI�ɑ����Ă����l���ɂ��ẮA 1900�N�O�ォ�烉�b�`�F���X�̋����̓��@�i�L�����[����ÓT��`�ւƌ������A�q�[�X�R�[�g1905-1907�ŋɓ_�ɒB����B �q�[�X�R�[�g�ł�肫�����Ƃ������Ƃ��낤���A���̌�́A���̎���̉p���l�Ɏ������₷���A�����ȁA�`���[�_�[��A �N�C�[���E�A���A�l�I�E�W���[�W�A���i�����l�T���X�j�ɃV�t�g�E�_�E������B 1898�N�̃��C�v���_�[�����E�n�E�X�K��A1901�N�̃`�F�X�^�[�Y�K�₪�A���b�`�F���X�̂��̎����̊S�̕����������ƂƂ��ɁA �����̖K�₪�g�^���ʁA�ÓT��`���H�L���u�����[�A�ȖʕǂȂǂւ̂��̎����̃��b�`�F���X�̃f�U�C�����s������Â����B 1900�N���ׂ��A1898�N������1906�N���܂ł�10�N��̒Z���ԂɁA���b�`�F���X���s�����f�U�C�����s�ɂ�萶�ݏo���ꂽ�A���l�ŁA�Ǝ��� ���ʕ��ɂ́A�ڂ��ӂ点�����B ���}��1900�N�O��̏Z���i�̂����悻�̐����N���B |
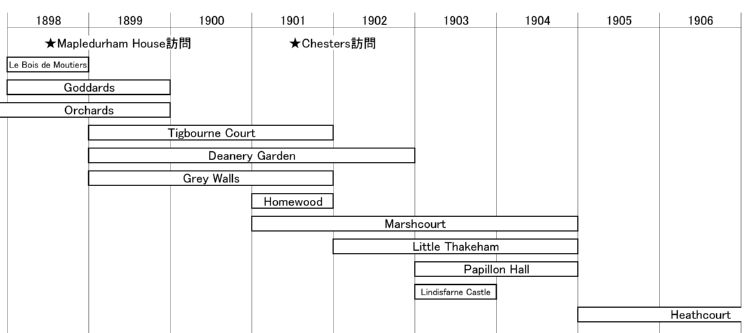
|
|
|---|---|
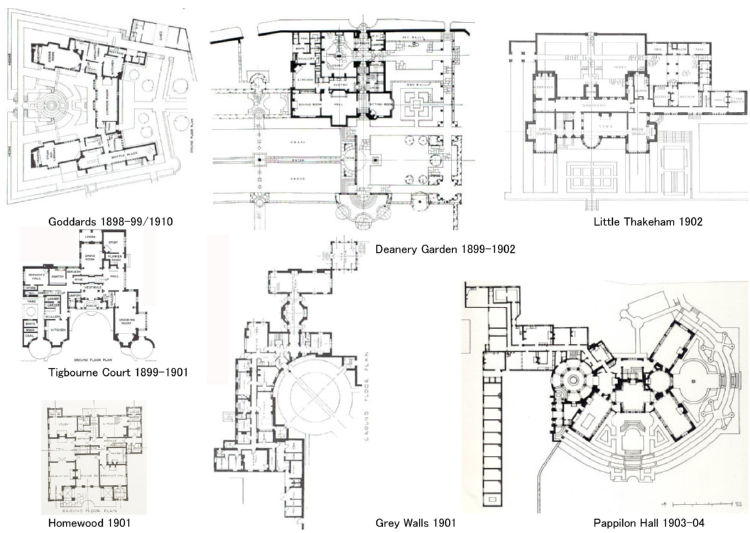
|
|---|
�@)�V�����g���[�ƃA�E�V�����g���[ �A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̉e�����̏������@�i�L�����[�Z��ł́A�V�����g���[������A �A�E�V�����g���[�ȕ��ʍ\������{�Ƃ��Ă������A��L1900�N�O�ォ��n�܂� �G���U�x�X���̃}�i�[�n�E�X�̂g�^���ʂƃN���V�V�Y���ւ̌X�|����A�V�����g���J���ȕ��ʍ\�����̂�n�߂�B �����炭�S�_�[�Y�����肩��A���̎��s���n�܂�B �e�B�O�{�[���E�R�[�g�A�z�[���E�b�h�ł̓t�@�T�[�h�̗��ʂ��V�����g���J���ɍ\�����邽�߂ɕ��ʂ�����A���G�ɂȂ��� �������Ƃ𖾂炩�Ɋy���݁A���ł���A�悤�ɂ݂���B�V���v���ɃV�����g���[���A�E�V�����g���[���A�ł͂Ȃ��A �����ւ̐U�ꕝ������Ƀo�����X���Ƃ�Ȃ��畽�ʂ��\�����Ă䂭�B �A)�����ɂ��S�̍\�� �S�̂̕��ʔz�u�ɂ̓V�����g���[�Ώ̎����ݒ肳���B���̑Ώ̎��ȊO�ɁA�������̃T�u�̎� ������������A����XY�������̎���(��O�I�ɃO���C�E�E�H�[���Y�̂� ���ȃ_�C�A�S�i���Ȏ����������)�ɉ��������ʂ̍\�����Ȃ����B ���ɂ�镽�ʂ̑g���Ă̓f�B�[�i���[�E�K�[�f���̕��ʂ����肩�狭���ӎ������悤�ɂȂ����B �f�B�[�i���[�E�K�[�f���ł͑����̎������ݒ肳��A �G���g�����X����뉀�̋����o�ĉʎ����Ɏ��鎲�ƁA �R�[�g���[�h�ƌ����̒��S���A�����ăp�[�S���̎����� ����3�{�̓�k���ƁA����ɒ��s�����͂�3�{�̓����������m�Ɍ��ĂƂ��B �����ŁA ���S���ł͂Ȃ��ΐS�����ʒu�ɓ����H�̎���ݒ肵�����Ƃ��A���ʁA���ʂ̃V�����g���[�A�A�E�V�����g���[�̔����ȑ���ւƓ����A �둤���ʂɎ��I�Ƃ�������A�������o�����X�A�\��ݏo���Ă���B �B)�I���铮�� ���F���`���[���́u���z�̑��l���ƑΗ����v�̒��ŁA�g�M�������[�̓����́A���������� ����������Ԃł���Ȃ���A�ɂ��ւ�炸�A�˂�����̕ǂ͖ӂƂȂ��Ă���h�ƁA���b�` �F���X�̃~�h���g���E�p�[�N�i���}�j��Η���(�R���g���f�B�N�V����)�̗�Ƃ��Ă����Ă���B �V�����g���[�̑Ώ̎��ɃG���g�����X���Ƃ�A�l���Ă����Ȃ���A�r���ɖӕ�(������ �ꍇ�A���Α��̓z�[���̒g�F�ɂȂ��Ă���)�������Ă��āA�������I���镽�ʍ\���� ���b�`�F���X�́A�����̓@�قō̗p���Ă���B �q�[�X�R�[�g���A���̑�\�I�ȗ�ŁA�l�͎����Ɨ���ĉI�铮�������������B �C���X�L�b�v�́A���̗��R�Ƃ��āA������傫�������邽�߂��Ƃ��āA ���̏؋��ɂ��̑��삪�s����̂́A��r�I�������@�قŁA�傫�ȓ@�قł͑Ώ̎� �Ɠ����̃Y���̂Ȃ��v������������������Ƃ����B�������A�����͂ނ���A �V�����g���J���ȑS�̂̍\�����A��Ԃ�̌�����l�̎��_�̑�����A��������Č������A ��Ԃ��ْ����̂���L���Ȃ��̂ɂ���Ӑ}���痈�Ă���̂ł͂Ȃ����B�����̓��b�`�F���X�̃E�B�b�g�A�m�I�V�т� �\�����Ƃ��v����B �C)���S�������ޗ��T�C�h�̓����� �e�B�O�{�[���E�R�[�g�ƃz�[���E�b�h�̃��F�X�e�B�r�����ł́A��������̒��S���̗��T�C�h�� �h�A������A���̈�������̕����ւ̓����̎��ƂȂ�B���̃z�[���ł��K�i�̏�����̗��T�C�h�Ƀh�A�������āA ���ꂼ�ꃔ�F�X�e�B�r�����A�_�C�j���O�ւƂȂ���B | ���g���E�Z�C�J���ł́A�X�N���[���E�p�b�Z�[�W��3��������A���T�C�h�̊J������������ɂ���B �O�Ǒ��̓������͐L�тāA�����̗��h���[�C���O�E���[���ƃ_�C�j���O�E���[���̒��S���ɂȂ�A�g�F�ƂԂ���B �D)�����ƑS�̂��� �e�ʂ̃G�����F�[�V�����A�e�����̓����ɂ�����l�̎��_���畽�ʂ͍Č�������A���� �ɂ������Ԃ̍\�������͑S�̂̍\�������Ƃ͕ʓr�ɍl�@����A�S�̍\���Ƃ̊ԂɋN���ꗂ́A���̂܂ܕ\�������B �Ⴆ�q�[�X�R�[�g�ɂ����錺�ւ̊ԁA�z�[�����ꂼ��̕����̒��ł̑Ώ̎��ƑS�̂̑Ώ̎��Ƃ̃Y���A ���g���E�Z�C�J���̃z�[���̑Ώ̎��ƑS�̂̑Ώ̎��̃Y���B �E)�����ƊO������ �����̋@�\�I�v���A�����͍\���������痈������ƁA�O���̏I�v���A�����͍\���� �����痈������Ƃ́A���ꂼ��ʁX�ɍl������A�\������A�����ƊO���̕\���̘�����Y ���́A���̂܂ܕ\�������B �Ⴆ�O���C�E�E�H�[���Y�ɂ�����p�Ȃ������ʂ̃t�@�T�[�h�Ɠ����̐ݔ�����̕��ʂƂ̃Y���A ���g���E�Z�C�J���̃z�[�������̓�����ԂƊO�ςƂ̕\���̘����B �F)�����ƒ뉀�̗Z�� �@)�̎����ɂ��S�̍\���Ō���ʂ�A�����͌������������łȂ��A�뉀�� �\���ɂ��K�p����A�����ƒ뉀�Ƃ͈�̂ɕ\�������B �C���X�L�b�v�́A�� ���̓@�قł́A�z�[������ԍ\���̃q�G�����L�[�̊j�ł��邪�A����̓@�فA�O���C�g�E ���C�T����O���h�X�g�[���ł́A�뉀���ނ���j�ƂȂ��āA�������뉀�̑O���I�Ȗ����� �ʂ��Ă���Ǝw�E����B �G)���Ԃ̕\�� �p�s�����E�z�[���̂悤�ȑ��z�̏ꍇ�ɁA���b�`�F���X�́A���̌����̗R��������̌` �Ԃd���A�厖�ɂ��Ă���B�O���[�g�E�f�B�N�X�^�[�ł͎���̈قȂ錚�����č\�����āA�������������o�� ���z���d�˂Ă������̂悤�Ɍ�����B�v�����v�g���E�v���[�X�̃T�C�g�E�v�������č\�����A �~���[�W�b�N�E���[����t�������āA���}�ȃJ���g���[�E�n�E�X��L���ȋ�Ԃɍ��ւ��A���̌o�߂����̂܂ܕ\�����Ƃ���B ���邢�́A�V�z�ł���Ȃ���A�킴�ƈ�����l���̕������������āA �����������̕���������ŕt�������ꂽ�悤�ȕ\���������������B �Ƌ�ɂ��Ă��A���e�B�[�N�̉� ���Y�����Ďg�����肵�āA�S�̂ɐV�i�������A���Ԃ̌o�߂��D�B ���̎���̌�����������ɂ����A���܂��܂Ȏ���̗l�����������Ďg�p���A������������������A���z �����肵�ĉ�������Ԃ��o�߂��������ł��邩�̂悤�ȕ\��������B �����������Ԃ̕\���́A��ɂ͎{��̑����������鐬��オ��҂ł��������Ƃ��������B ����ȏ�Ƀ��b�`�F���X���g�̃��}���e�B�b�N�Ȃ��̂��D�ސ����ɗR�����Ă���B �ނ͂���Ȃ��Ƃ������Ă���B�u���͂ނ����邵���Ƃ�A�݂��ڂ炵����͌������B�� �͓w�͂̐Ղ��������ɁA�D�����▾������\���������v�B |
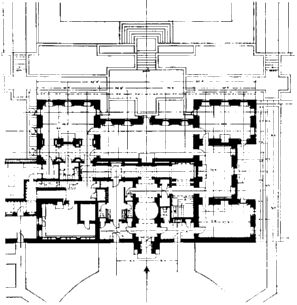
 |
|
|---|---|
back to top
| �V.CHARLES RENNIE MACKINTOSH(1868�`1928) �}�b�L���g�b�V���[���㐸�_�̎�@���[ �P�D�����̂ւ̎��� �C�M���X�ɓn���āA�͂��߂ĖK�ꂽ�~�̃O���X�S�[�̈�ۂ́A�����čD���������̂ł͂Ȃ������B ���ꂪ�A���̃}�b�L���g�b�V���`���p�[�X�̋ƁA�[��������O���[�~�[�ȓ~��̉��ŁA �O���X�S�[�E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�͂������A�X�̉��Ƃ������Ȃ��Â��Ɨ����ɁA�ƂĂ�����₩�� ��ۂ������炵�Ă��ꂽ�B ���̂���₩���͂����炭�A���̌��z�Ƃ́A�����̂ɑ��鎷���́A���̂��܂�̋����炭����̂ł͂Ȃ����Ƃ����C�������B �O�ʂɏo����Ԃ̃R���Z�v�g�̂���炵���A���邢�́A��������܂킳�ꂽ��Ԃ̕s���Ă��A���G���́A ���̌����Ƃ͖����̂��̂ł���B �O�ς́A�O���X�S�[�ŗL�̃A�m�j�}�X�Ȍ��z�ɋ߂��B�����đS�̂̍\���̓V���v���Ŗ����ł���B �������Ȃ��A���̋�Ԃ��A�L���ȁA�������A�����Ă܂��l�� ���炬��^�����捂Ȃ��̂ɂȂ��Ă���̂́A�����̂ւ́A�f�B�e�[���ւ̌��z�Ƃ́A�̂߂肱�ݕ��� �����ł���B������́u�[��������Ԃ́A�����ȃf�B�e�[���̏W�ρv�Ƃ������t��z���o�����B ���̂���₩���̂����ЂƂ̗��R�́A�ނ������Č��z�Ƃ������̂̈�ʉ������߂��̂ł͂Ȃ��A �O���X�S�[�E�X�N�[���E�I�u�E�A�[�g�Ƃ����ۑ�ɑ�����������ɒNj����Ă������炾�Ǝv���B �o�ϓI�ȁA�����ĕ~�n�����́A�܂��A�w�Z���̑��ʂȗv�����̑��́A�����̐ؔ�����������f�U�C���ߒ��̃v���X�̖ʂ� �����Ă����p�����A��Ɍ��z�Ƃɂ͂������B |
�}�b�L���g�b�V���͖��炩�ɁA���̌����̐ؔ�����������A�����̌��z����������̂Ƃ��Ċ��}���Ă����悤�ł���B ���̍l�����́A���z���邱�Ƃ��P�Ȃ�n���s�ׂł͂Ȃ��A�Љ�I�ȃv���Z�X�ƌ���A���X�L���A�����X�� �v�z���炫�Ă���B ���ہA����������ɂȂ�Ȃ�قǁA�}�b�L���g�b�V���̃f�U�C���͍Ⴆ�Ă���悤�ł���B 1896�N�̃R���y���܂���A1909�N�̑�2���H���i���̌����̍H�����A�o�ϓI���R����2���ɕ����ꂽ�̂� �K���Ȃ��Ƃł������j�̊����܂ł�10�N�ԗ]��́A�}�b�L���g�b�V�����Љ�Ɩ��ڂɊւ���� �S���Ԃł���A���̊ԂɁA�ނ̑�\��͂قƂ�ǑS�Ăł��������Ă���B�ЂƂ�̍�Ƃ̎�����̊������ԂƂ��Ă� �Z�����A���̖��x�̍����ɂ����ẮA���ɂ��܂������Ȃ��Ǝv���B�قƂ�ǑS�ẮA�}�b�L���g�b�V���̌��z����́A ���̌����̒��Ɍ��邱�Ƃ��ł���B�������ł��������ꂽ�������ŁB 3�N�������̃C�M���X�؍ݒ��A��������1�N�̊Ԋu��u���ĎO�x���̊w�Z��K�ꂽ���A���̂��т��ƂɑO�ɂ� �C�̂��Ȃ������A�ו��̃f�U�C���̑f���炵����V���ɔ��������B �����Ă܂��A�ʐ^�����Ċ����邱�̌����� �ו��̑@�ׂ����A���ۂ̕��ނׂ̍����炭����̂ł͂Ȃ����Ƃ��Ĕ�������B�}�b�L���g�b�V���̎g�����ނ͂ނ��� �K�b�V���Ƃ��ė͋����A�ʐ^�ɗ�����1�N�ԂŔ��ꂽ�C���[�W�𗠐��āA���ނ̐�ΓI�쑾�����A���߂Č��������ƂɂȂ����B �iSD�@7603�j | |
 
  | ||
|---|---|---|
|
�Q�D�����ʂ��琼���ʂ� �E�B���E�E�e�B�[���[���̂���\�[�L�[�z�[���E�X�g���[�g�𐼂ɍs���ƁA��ڂ̏\���H�̓_���n�E�W�[�E�X�g���[�g�A ���̏\���H�̓X�R�b�g�E�X�g���[�g�ƌ�������B ���̓�̒ʂ�ɂ͂��܂�A�\�[�L�[�z�[���E�X�g���[�g�ƕ��s���Ĉ�{�k���𓌐��ɑ���A�����t���[�E�X�g���[�g�ɖʂ��āA �O���X�S�[���p�w�Z������B �_���n�E�W�[�E�X�g���[�g�ƁA �X�R�b�g�E�X�g���[�g�͋��ɔ��ȋ}��ŁA�\�[�L�[�z�[���E�X�g���[�g���猩�グ��ƁA���p�w�Z�̓��ʂ܂��͐��ʂƓ�ʂ̈ꕔ��������B �_���n�E�W�[�E�X�g���[�g�̍��o���čs���ƁA���ʂ̃G�����F�[�V�������A�����S�̂̃R���e�N�X�g�𗣂�āA�Ɨ�������̃G�����F�[�V�����Ƃ��ė͋����܂����o����B(��}��) ���߂ĖK�ꂽ�Ƃ��A�����̌��z�Ƃ��āA������������݊����������G�����F�[�V�������A���܂łɌ������Ƃ͂Ȃ��悤�Ɋ������B ���̓����̖ʂ́A�����̐}���ق̂��鐼���̃G�����F�[�V�����Ƃ́A���ɑΏƓI�Ȑ��i�������Ă���B �܂����n���Ă��Ȃ����z�Ƃ̊��������̌`�ŕ\��Ă���̂����m��Ȃ��B ���ꂾ���]�v�ɁA�}�b�L���g�b�V���Ǝ��́A���܂�Ȃ���̔�ኴ�o���\��Ă���ƌ�����B �����ʐ}1907 | ���n�̈�ɒB�������ʂ̔��ɓ��ꊴ�̂���G�����F�[�V�����ɔ�ׂ�ƁA���̖@�����Ȃ��Ɋe�X�قȂ�`�ԗv�f���ނ̊��������𗊂�Ɋ��W�܂��āA �s�v�c�ȃo�����X��ۂ��Ă���B ���ʂ̓��ꊴ�Ɠ����ʂɁA���邢�͂���ȏ�ɁA���̓��ʂ̕s�v�c�ȃo�����X���o�͐S�n�悢�B �����ʂ��f�U�C�����ꂽ�̂́A�R���y���s�Ȃ�ꂽ1896�N�ŁA�k���̉����ɂ��Ƃ��瑋���������ꂽ�ȊO�́A �قƂ�ǃR���y�̎��̌v��ʂ�Ɏ{�H����Ă���B ����ɑ��Đ����ʂ́A�R���y�̎��̃f�U�C����������H���̐v�ύX�̎��_1906�N�`7�N�̊ԂɁA �}�����̑啝�ȕύX�ɔ����A�S���ŏ��Ƃ͈قȂ���̂ɂȂ����B(��}�E) 1896�N�̃R���y����A�v�ύX���s�Ȃ��A1909�N�ɐ�������������܂łɁA10�N������Ƃ̔N�����o���Ă��āA���̊��Ԃ��}�b�L���g�b�V���� ���z�ƂƂ��Ă̎����I�Ȋ������Ԃ̂قڑS�Ăł���B �N��Ō����A�}�b�L���g�b�V��20��㔼����A30��㔼�܂ł̂��Ƃł���B�܂�A���̃O���X�S�[���p�w�Z�̓����̊炩�琼���̊�ւ̕ω����A �}�b�L���g�b�V���̌��z�̑S�Ă���Ă���ƌ�����B �����ʐ}1907 |
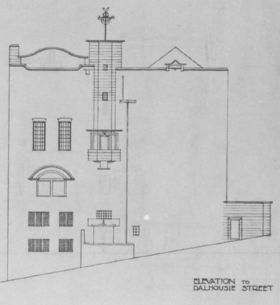
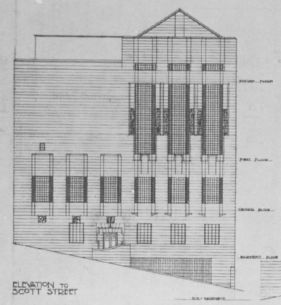 |
|
|---|---|
|
�R�D�O���X�S�[���p�w�Z�R���y ���p�w�Z���s�̏����q�ɂ��O���X�S�[���p�w�Z��1840�N�A�����̃f�U�C���w�Z�Ƃ��đn�݂��ꂽ�B ���̖ړI�ɂ́A���̑�H�Ɠs�s�̍H�Ɛ��i�̃f�U�C�����A���悢���̂ɂ��悤�Ƃ����[�֓I�ȈӖ��������������B 1852�N�ɂ́A�����h���̃T�E�X�E�P���W���g���ɂ������Ȋw�|�p���̃R���g���[�����ɒu���ꂽ�B �O���X�S�[���p�w�Z�͂����T�E�X�E�P���W���g���Ɋw���̍�i�𑗂�A 1882�N�ɂ́A�X�R�b�g�����h���ŁA�ł������̏܂��l�������B�p���S�̂ł��ł��������{����̕⏕�����l�����A 1897�N�ɂ́A�p���S�̂ōł���������̃��_�������B �C���O�����h�̐l�A�t�����V�X �E H �E �j���[�x���[���A1885�N�ɍZ���ɔC������ĕ��C���Ă����B �j���[�x���[�͂��̎��܂�31�A�����h���̂��܂��܂Ȍ|�p�����ɐ��ʂ��Ă���A �O���X�S�[�̐V���������ɑ傫�ȊS���A�ӗ~�[���ɏ�荞��ł����B�s���\�͂�����A 1890�N�㏉�߂���܂łɂ́A�}���Ɋw�����𑝂₵�A�p���S�̂���݂Ă��A �����炭�ł����͓I�Ȋw�Z�ɂȂ����B �����Ԏs�̃M�������[������̍Z�ɂɂ��Ă������A�w�����̑����ŊԂɍ���Ȃ��Ȃ�A �t���E�j���[�x���[���Z���ɂȂ��Ă���10�N�ڂ�1895�N9��6���A��������W����A�V�Z�Ɍ��z�̕��������ꂽ�B ���̌�A��t�ȂǂŁA2��1��|���h�̎������W�܂������Ƃ��A1896�N2��26���́u�O���X�S�[�E�w�����h�v�Ɍf�ڂ���Ă���B | �~�n�͂�����O�ɁA��2,500�u�̓y�n���m�ۂ���Ă����B �������Ɍ��݈ψ���g�D����A�v���Z�̏����ݒ肪�s�Ȃ�ꂽ�B���݃R�X�g�ɂ��ẮA 1��4��|���h�Ƃ�����������߂�ꂽ�B����ɂ͌��z�A�ݔ��A�d�C�A�O�\�ȂǑS���݃R�X�g���܂܂ꂽ�B ���̃R�X�g���ꊄ�ȏ�I�[�o�[�����҂͎��i�Ƃ��ꂽ�B �j���[�x���[���ʐϕ\�Ȃǂ̐v�v���̍쐬���s�Ȃ����B���̒��ɂ́A�����̐��@�A���̂Ƃ����傫���ɂ��Ă��G����Ă����B ���̎��ɃR���y�ɎQ�����錚�z�Ƃ́A8�l�ȓ��ƌ��߂�ꂽ�B �ŏI�I�ɂ�12�l�ɑ��������A���ۂɒ�o�����̂�11�l�ł������B �ݕ����l�����Ƃ͈Ⴄ�̂ŁA1��4��|���h���ǂ̈ʂ̉��l�Ȃ̂��͕���Ȃ����A�@�O�Ɍ������������Ƃ͊m���炵���B �����A�����̒��ɂ͉��ɂ������̂Ȃ��v���[���Ȍ����ł悢�Ƌ������ꂽ�B �Q�����z�ƒB�͐������̃X�^�f�B�̂̂��A���̗\�Z�ł́A�v�����ꂽ�K�͂̌��������݂��邱�Ƃ͕s�\�ł���ƌ��_�������A ���̂��Ƃ������ŕ\�������B ���̂��߁A���݈ψ���͐v�v������蒼���A���̂悤�ȏ�����v���ɕ��������B ���Ȃ킿�R���y�Q���҂́A�����S�̂̓��A1��4��|���h�Ō��݉\�Ȕ͈͂�}�ʂŎ����A�܂��S�̂ł����炩����̂��A �R�X�g�̌��ς���o����悤�ɗv�����ꂽ�̂ł���B����Ɠ����ɁA�Y��1896�N��9��15������10��1���ɉ������ꂽ�B |

 |
|
|---|---|
�R���y�̌��ʂ�1897�N1��13���ɔ��\����A���҂̓n�j�[�}���E�A���h�E�P�s�[�������ł������B �����Ċ����Ƀ}�b�L���g�b�V����l�̑S�ʓI�ȃf�U�C���ł������B �j���[�x���[�́A���łɂ���ȑO���琶�k�ł���}�b�L���g�b�V���̒��ɁA�f���炵���˔\�̖G���F�߂Ă����B �͂�����ƃ}�b�L���g�b�V���̎�ɂ����̂ł��邱�Ƃ�m������ŋ������̈Ă𐄂����̂ł���B ������r���A�܂��j���[�x���[�̃v���O�����ɓK�m�ɑΉ������}�b�L���g�b�V���̈ẮA�������\�Z�̒��ŁA �����łȂ��Ă��ŏ�̂��̂ł��������ł���B �������Č������}�b�L���g�b�V���̈ẮA�S�̂�����ɂ킩��čH���o����悤�ɔ����ɕ������ꂽ���̂ŁA �����̔����������Ƃ��Ă܂��{�H����邱�ƂɂȂ�A�������ɂ��Ă͊�b�݂̂��{�H����邱�ƂƂȂ�B�i��}�j ���̈Ă̌��ς�ɂ��ƁA�S�̂̃R�X�g��22,753�|���h�ł������B����͏Ɩ����K�X�ōl�����ꍇ�ŁA �d�C�Ȃ�110�|���h�]�v�ɂ�����ƒf���Ă���B �������́A�G���g�����X�E�z�[���ƊK�i���܂��܂ł̓������ŁA ���̃R�X�g��13,922�|���h�]�ł������B���ۂɂ͑������̌��ݔ�́A�v�H���ɂ͑啝�ɂ��̌��ς���I�[�o�[���邱�ƂɂȂ�̂����B �}�b�L���g�b�V���́A���̔N�܂łɊ��ɎO�̌������n�j�[�}���E�A���h�E�P�s�[�Ƃ�����l�̃p�[�g�i�[�̎w�����Őv���A����ɐӔC�͈̔͂��L���Ă��Ă����B 1896�N�ƌ����A�}�b�L���g�b�V��28�̎��ł���B ���̎��ɂ������������I�ɂ����܂�|�݂̂Ȃ��A �������K�͂��債�����Ƃ��Ȃ��A�܂��v�������̌������d�����������Ƃ������Ƃ́A�}�b�L���g�b�V���ɂƂ��āA ���ɍD�s���ł������B | ���̍��n�j�[�}���E�A���h�E�P�s�[�������́A���Ȃ�̗ʂ̎d���������Ă���A ���̔��p�w�Z�̃R���y�̎d���͔�r�I�}�C�i�[�ȕ��ނɓ����Ă����B ����r���グ�Ă���A�V�X�^���g�ɔC����ɂ́A���傤�ǓK�Ȃ��̂ł������̂��낤�B 1896�N�̃R���y�̎��_�̐}�ʂ́A���ł͂ǂ��ɂ�������Ȃ��B����1897�N�̎��_�̕��ʂ��c����Ă���A �ŏ��̒i�K���ǂ������v��ł����������킩��B �v�����̍\���́A�~�n�Ȃ�ɓ����ɒ����A�L�������ɂ��Ċe������t���Ă���`�ŁA���傤�� �A���t�@�x�b�g��E�̎������ɐQ�������P���Ȍ`�����Ă���B �~�n�����A����ꂽ�\�Z�Ƃ�����������A�j���[�x���[�̎w�肵���A�X�^�W�I�ɂ͖k�����̑傫�ȑ����Ƃ�ׂ����ƂȂǂ̗l�X�Ȑ��A ���̒P���Ȍ`���Ƃ点�����ړI�ȗ��R�ł���B�i��}�E�A���}�|�A���Q���v�H��j �}�b�L���g�b�V���̋��Z�v�ɗՂޑԓx�����̒P���ȃv�����ݏo�����傫�ȗv�f�ł������낤�B �ނ́A�����̃R���Z�v�`���A���Ȏv�l�ߒ��̒��ŁA ��ʉ��Ƃ��Ă̌��z��[�肵�A���̌����̐v���A���̓����ƍl����^�C�v�̌��z�Ƃł͂Ȃ��B �X�̗^�����ɒ����Ƀf�U�C����i�߂�^�C�v�̌��z�ƂŁA �����������Q���ƍl��������A�ނ��낻��𗘗p���Ă��܂��āA������������Ƃɂ���āA�t�ɐV������@�����Ă����A�Ƃ������x�Ȑv���@���̂�B |
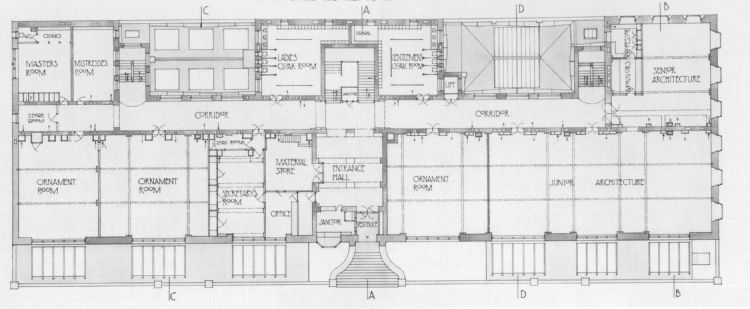
| |
|---|---|
|
�S�D���p�w�Z�����H�� �S-�P�D�G���g�����X �S�̍\���̒P�����̒��ɂ́A�L�����ƌ���ˋC��������B�Ⴆ�G���g�����X�̃h�A�͐��@�I�ɂ͂��傤�ǖk���ʂ̒��S�Ɉʒu���Ă���̂����A ���ʓI�ɂ����ʓI�ɂ��A�ӎ��I�ɃV�����g���[�ɂȂ�̂�����Ă���_�ł���B�i��}�j �k���ʐ}�Œn����K�̃g�b�v���C�g��ی삷��ړI�̃t�F���X������A���̃h�A�����S�Ɉʒu���邱�Ƃ��킩��B �]���Ē��S�ɂȂ�悤�Ɍ������K�̃~���[�W�A���֒ʂ���K�i���͔����ɓ����ɃY���Ă���B ���̊K�i�̈�K����x���܂ŏオ�鑤�̔������A�G���g�����X�O�̊K�i�A�|�[�`�A �܂��G���g�����X�E�z�[���̕ǂƒ��ɂ͂��܂ꂽ���H�[���g�V��̎��ƈ�v���A���̎��������̃Z���^�[���C���ɂȂ�B �G���g�����X�E�z�[���͍ŏ����̕������Ă���A���H�[���g�V������̎�̃G���g�����X�E�z�[���Ƃ��Ă͋ɒ[�ɒႭ�A�Â��X�y�[�X�������Ă���B �G���g�����X�E�z�[���ɂ���O�{�̓Ɨ����́A�K�v�ȏ�ɑ����A�ݏd�Ȓ��ŁA���̃z�[�������S�ɓ�ɕ��f���Ă���B ���S���́A���܂��܂ȕ��@�ŋ�������A���Ɉ�����ݓ����ƁA�����̓~���[�W�A���̓V��̃g�b�v���C�g������̍~�肻�����K�i�ւƁA���R�ɓ������B �i���}���j ���Â������G���g�����X�E�z�[������A���邢�~���[�W�A���Ƃ����֒ʂ���K�i�ւƂ����A���ƉA�ȂƂ̑Δ�A���̍I�݂ȉ��o�͂��̌����ł́A���������Ɍ�����B�i���}���j ������Âւ̋N���̗��ꂪ�A��Ԃ̂Ȃ���̒��ŁA�G���g�����X��z�[���̋�ԓI�L�����������������Ă���B ���̗ʂ̖��ƁA�X�y�[�X�̑傫���̖��A���̓�̖ʂŁA�G���g�����X��z�[���́A�����A �Â��Ƃ����l�K�e�B�u�ȕ����Ŕ��Ȑ��������߂Ă���B �������ł����邯��悢�Ƃ����킯�ł͂Ȃ����A�������ł��L����Ԃ��悢�Ƃ����킯�ł��Ȃ��B �����S�̂̒��̈�̋�Ԃ͂����܂ł��A ���̋�ԂƂ̊W�Ō��܂��Ă���B�g���l���̂悤�ȍׂ��A���Â���Ԃ́A���Ɉ�ꂽ�~���[�W�A���ւƓ������B | �S-�Q�D��K�i �K�i���̎萠�q�̈������܂����Q�ɂ悢�B�萠�q�̐��Ƃ��Ăł͂Ȃ��A���i�q�̃X�N���[���̖ʂƂ��Ĉ����Ă���B ����ʂ��Ȃ���e������A��Ԃf���Ȃ�����A���݂Ɍ��э��킹��A ���̊i�q�̃X�N���[���̐��i���}�b�L���g�b�V���́A�I���Ɉ����B �ނ́A���i�q�̃X�N���[���̂����i�ɖ������A�q����n�E�X��e�B�[���[���Ȃlj��x�����x���J�Ԃ����p���Ă���B �P�K����x���܂ł̌��i�q�́A�x��ꃌ���F���ł̒ʏ�̎萠�̕K�v�̍����ɑ����Ă���A �����悤�ɗx��ꂩ��Q�K�܂ł̌��i�q�́A�Q�K�����F���ł̒ʏ�̎萠�̕K�v���ɍ��킹�Ă���B�i���}���j ���̕ӂ̎萠���̏����@�͎��ɍI���ł���B�K�i�̎ΐ��͎萠�X�N���[���ɂ͔��f����Ă��Ȃ��B �萠�X�N���[���͂����܂ł����ł͂Ȃ��ʂł���B���̓�̊i�q�ʂ��x����e���́A �����Ƃ���K�̎萠�̍����ɑ����Ă���A��������x���̕ǂ���˂��o�����A�ɂȂ������ɂ���Ďx������Ă���B ���̓�{�̐����ނɂ���āA��{�̐����ނ��͂��ޖ̈������A�i�q�X�N���[���Ƌ��ɁA �}�b�L���g�b�V���̌��z�ɉ��x�������郔�H�L���u�����[�ł���B ���i�q�X�N���[���̊K�i�ւ̎g�p�́A�������H�C�W�[�̏Z��̕����悩���m��Ȃ��B���������̈������̓}�b�L���g�b�V���̕����f�R���܂��B �K�i���������猩�グ��ƁA���{�̒ޏ��̃~�j�`���A���A�s�v�c�Ȍ`�������A�S�̐��ނŏo�����I�u�W�F�̉��ɒނ艺�����Ă���B �i���}�E�j ���̃I�u�W�F�͎��́A�O���X�S�[�s�̖�͂��A�����W�������̂ł���B �ޏ��̕��́A�j���[�x���[���A���̊w�Z�̂��߂ɈȑO�w�����Ă������̂ł���B �}�b�L���g�b�V���̋�ԍ\���́A�����܂ł����������A�����ȃ��m�B���܂߂ďo������Ă���B ���̃O���X�S�[�s�̖�͂����`�[�t�ɂ����A�C�A������[�N�ƒޏ����A�K�i�����ے��I�ɁA�L���b�ƈ����߂Ă���B |

 
| |
|---|---|
|
�S-�R�D�~���[�W�A�� �~���[�W�A���́A�K�i�Ɠ��������̘L����Z�����̑O���Ƃ����Ԍ����S�̂̒��̃s���H�b�g�̂悤�ȋ�Ԃł���B ��i��W������X�y�[�X�Ƃ��āA�@�\�I�Ȗʂɂ����Ă����p�w�Z�̒��ł��ł��d�v�ȋ�Ԃł��낤���A ���ʍ\���̏�ł��A�S�̂̒��̊j�ɂȂ�ꏊ�ł���B �S�Ă���l�߂�ꂽ�S�̂̒��ŁA�������ɍL�X�Ƃ����X�y�[�X�ɂȂ��Ă���B �@�\�I�ɂ͓W���X�y�[�X�Ƃ��ĕK�v�Ƃ͂����Ă��A���i�͊m����ړI���������ꏊ�ł͂Ȃ��B ����Ζ��ʂȋ�Ԃł���B�T�[�L�����[�V�����̓b�݂����ȋ�Ԃł���B �������A���̌��ɖ�����(�ƌ����Ă��k���̌��͎ア)��Ԃ́A�����H���̒��ōł��d�v�ȋ�Ԃł���B �~���[�W�A���̒��S�Ɉʒu����K�i���̌�(�E�G��)�͐����`�ɋ߂���`�ŁA���̎l�̃R�[�i�[����́A�X�����_�[�Ȗؐ��̒��������Ă���B �i���}���j ���̒��̈������ŁA�g�b�v���C�g�̃g���X�̉����ނ��n����Ă���B �g�b�v���C�g�́A�K�i���̃E�G���̕��ŁA���̂܂ܓ��������ɁA�G���h�̕ǂ̈ʒu�܂ŐL�тĂ���B | �~���[�W�A���ɂ����āA�K�i���̒ޏ��ɑ������郂�m�́A�g�b�v���C�g�̉��̌y�₩�ȏƖ����ł���B ���̏Ɩ����͌Â��ʐ^�ɂ͏o�Ă��Ȃ����A���݂��Ȃ��̂ŁA������������}�b�L���g�b�V�����f�U�C���������̂ł͂Ȃ������m��Ȃ����A���ɂ����B �i���}�E�j �I�b�g�[����O�i�[�́A�E�B�[���ɂ���X�֒����ǂ̌����́A�K���X�����̋�Ԃ̒��Ɏ�t����ꂽ�Ɩ������A�A�z���Ă��܂��B �ǂ�����g�b�v���C�g����̎��R�̌��̉��ɁA�݂艺�����Ă���A�@�ׂȉԂ��v�킹��B �}�����̈Â��i�V�䂩�獽�Œ݂艺����ꂽ�A�d�����ȏƖ����ƁA�ΏƓI�ł���B �S�{�̐����̖_�Ƃ���ɒ��p�ȂQ�{�̖_���A �g�b�v���C�g�̗��[����݂艺�����Ă���B���̎l�{�̖_�̂��ꂼ��̐�[����ގ��ɂ��������̂悤�ɁA �����̃V�F�C�h���݂��Ă���B���̌y�₩���A�@�ׂ����A�~�肻�������R���Ƃ悭���a���Ă���B |

 |
|
|---|---|
|
�S-�S�D�k���� �����t���[�ʂ�ɖʂ����k���ʂ́A�j���[�x���[�̗v���ɉ������A�傫�Ȗʐς��������A�����̕�������ɍ��킹�ăA�V�����g���ɂ������Ă���B �����I�ɒ��S�Ɉʒu����G���g�����X�E�h�A�ɂ���āA���ʂɂ��ƃV�����g���[�ɂȂ闧�ʂ��ӎ��I�ɕ������Ƃ��Ă��邩�̂悤�ɂ݂���B �p���̌��z�Ƃ͂悭 "Let function dictate"(�@�\�D��)�Ƃ������Ƃ����ɂ���B�����̋@�\���l���Ȃ��ŁA ���ʂ�Ɨ��������̂Ƃ��ăs�N�`�����X�N�ɍ\�����Ă͂����Ȃ��Ƃ������Ȃȑԓx�ł���B �i���}�|�A���Q���H����k���ʐ}�j ���݂ł��p���l�̌��z�Ƃ̑����ɂ݂��邱�̑ԓx�́A���X�L���A�����X����k���āA�I�[�K�X�^�X�E�E�F���r�[�E�m�[�X���A�E�s���[�W���ɂ��̌�������B �J�\���b�N�ł���s���[�W���̋���Ȓ����ւ̓��ۂ́A���z�ɗϗ����������B �H���g���z�̎��́A����ݏo�����Љ�̎��Ƀ_�C���N�g�Ɉˑ�����h�H���g�^���̕\���h�A�g���^�ȍ\���h�A �g�����̊e���́A���̖ړI��\�킳(�X�s�[�N��)�Ȃ���Ȃ�Ȃ��h�B�H���g�����̓�����Ԃ̔z�u�́A���̊O���ɕ\�������ׂ��ł���h�B ���������s���[�W���̍l�����́g����z�w����(�G�N���W�I���W�J���E�\�T�G�e�B)�h�̔��s����@�֎��u�G�N���W�I���W�X�g�v��ʂ��āA�L�Ăȉe���͂��������B �g����z�w����h�́A�����̃L���X�g�����ᔻ���A��q���̉��v�A�܂��������܂߂���q���Ɏg���邠����함�̉��v��ڂ������B �ނ�͊�{�I�Ƀs���[�W���̍l�����ɁA���l���f�̊�b�������Ă����B | �g����z�w����h�̂Q�l�̎�v�Ȍ��z�Ƃ̃����o�[�ł���A�E�B���A���E�o�^�[�t�B�[���h�ƃW���[�W�E�G�h�����h�E�X�g���[�g�́A �s���[�W������̉e���ƁA�����̎Љ�I�v����Z���������A�V�����f�U�C���̕��@�_���������B �܂�13���I�S�V�b�N���z�ɑ��̗l���A�O������̃f�B�e�[���A�ߑ�Z�p��ڂ��������̂ł���B �Ⴆ�A�o�^�[�t�B�[���h�̐v�����A�����h���E�I�b�N�X�t�H�[�h�E�T�[�J�X�̂����߂��A�}�[�K���b�g�E�X�g���[�g�ɂ���g�I�[���E�Z�C���c����h�ɂ��̋�̗Ⴊ�݂���B ����̓h�C�c�E�S�V�b�N�̐듃�������A�����h���̏㎿�������g���A���S�̗�������ɘI�o���A�W���[�W�A���̃T�b�V�����������S�V�b�N���z�ł������B �������A����͜��ӓI�ɑI�ꂽ�l�����������킹�����ӔC�Ȑܒ���`�ł͂Ȃ��B ���B�N�g���A�����L�̂���Ɠ��̎����������A���B�N�g���A���̈�̒��_�������z�ł���B �����ɂ̓s���[�W������̉e���ł���A���̌̈ӂ̕s��p���A�������Ȃ����݂���B�g�^���h�g�����h�g�������h�Ƃ������������̎���������B ���������s���[�W���̎v�z�́A�E�F�b�u����X�ւƎp����A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�^���ւƁA���������̌`��ς��āA�A�Ȃ��Ă����B �����������㐸�_���A�}�b�L���g�b�V���́A�i�C�[���Ȃ܂łɐ��^�ʖڂɋz�����Ă���B |
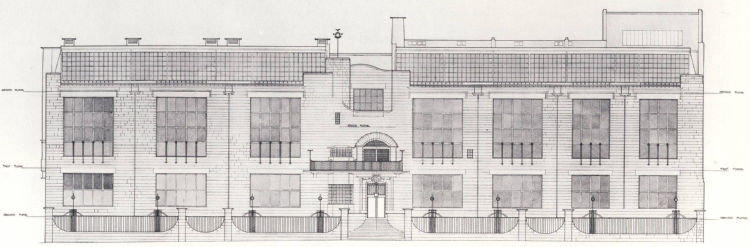
| |
|---|---|
|
�ނ́A��̑Η�����v�z�I���h�A�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�ƃ��B�N�g���A�R���^���Ƃ̗��҂���A���܂��܂Ȍ`�ʼne�����Ă���B
�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�́A�|�p�́A���̌`�ԁA���e�A���ʂɂ���ĎЉ������A���߁A�������߂Ȃ���Ȃ�Ȃ��A
�Ƃ������悤�ɎЉ�I�Ń������X�e�B�b�N�Ȋ�b�ɗ����Ă����B����ɑ��A���B�N�g���A�R���^���́A�|�p�Ƃ݂̂ɋ`�����A�Ƃ����|�p�̂��߂̌|�p�Ƃ�������ɂ����B
�]���ĎЉ�I�ϓ_����݂�A�|�p�͔��I�ŁA�Љ�ɑ��Ă͖��S�A�܂��R�����̂ł��蓾���B ���̓�̉^���̌����́A�Ίp���̗��[�őΗ����Ă����̂����A�����ɉe���������H�ҒB���A���m�ɋ�ʂ����Ă����Ƃ��������͂Ȃ��B ���������Ȏ��H�҂���}�b�L���g�b�V���͂��̎���̎v�z�̌n�A�`�Ԛn�D���A�����ʂ��×~�ɁA�m���Ȕ�]��������āA �z�����A�������A�������g�̓Ǝ��̎�@�A�`�Ԃ̗p�@�ւƑ�������B ���H�C�W�[�̍ޗ��ƍH�@�ɑ��钉���ƃr�A�Y���[�̐��̝��ꂪ�A�����Ă܂��o�[���E�W���[���Y�̓����I���A���Y���ƃ����E�g�[���b�v�̐_��I���ۂ��A �ӑR��̂ƂȂ��ĎQ�Ƃ���A�S���ʂ̊m�ł���Ǝ��̐��E�ɕό`�����B ���̃����t���[�ʂ�ɖʂ����G�����F�[�V�����ɂ́g�����̔z�u�́A���̊O�`�ɕ\�������ׂ��ł���h�Ƃ� �g���̔z�u�̓A�N�Z�X����ʂ�A�̌��A�����Ċ��C���l���Č��肷�ׂ��ŁA�s�N�g���A���ɍ\�����ׂ��ł͂Ȃ��h�Ƃ������s���[�W���ȗ��̌������A ���O�Ƃ��ẮA���ɐ��m�Ɏ��H����Ă���B |
������Ԃ̊e�����ɑ��K�Ȉʒu�ɑ����������Ă���B ���������z�Ƃ̓v���������ōl���Ă����킯�ł͂Ȃ��B ��������O���ւƃf�U�C�����邱�ƂƁA�O����������ւƃf�U�C�����邱�Ƃ��A�ӂ��̗͂̓]���_�]��-�ŏo��B �����͊O���ɕ\������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ƃ����A�ߑ㌚�z�̋��`�ɂ��Ȃ����A �P���Ō��S�ȍl�����B�������A���ۂɌ��z������Ƃ�����Ƃ͂���ȂɊȒP�ł͂Ȃ��B �]���_�]��-�ŋN���閵�����炱���D�ꂽ���z�����܂��B�@�\�Ƌ�Ԃ́A�����ƊO���́A�͂Ɨ͂̏o��ɂ����Č��z�͎n�܂�B ���ɂ͓�����ƊO����̖�������A�X�y�[�X�E�C���E�X�y�[�X�Ƃ��|�[�V�F poche �Ƃ��̃��H�L���u�����[���Ђ˂�o�����B �����͊O���ɕ\�������ׂ��ł���A�Ƃ�������́A�\�㐢�I�̈ꕔ�̍ˋC�݂̂��Ȃ��ܒ���`�I�ȁA �܂��s�N�`�����X�N�Ȍ��z�ւ̃A���`�e�[�[�Ƃ͂Ȃ蓾�Ă��A���z�̕��@�_�Ƃ͂Ȃ蓾�Ȃ��B ���̖���ʂ�ɐv���s�Ȃ��A�^���̌������ł���قǁA���͒P���ł͂Ȃ��͂����B���̖���̎��̒i�K�̍�Ƃ��d�v�Ȃ̂ł����āA �������A���z�ƌl�ň���Ă���Ƃ���ł���B �����ƊO���̂Ԃ��荇�������z�ɂȂ�B�����������z�Ƃ̗͗ʂ̖����Ƃ���ł���B �}�b�L���g�b�V���̂����ł̕��@�́A�S�̂̍\���́A�����܂ł��w�Z���̋@�\�I�v���𒉎��ɂ܂��邱�ƁA �����čו��ɂ����ẮA���@�i�L�����[�Ȑ��A������̌��z�Ƃ̌`�Ԃ̗p�@�A����̊J�������O���t�B�J���Ȍ`�ԁA �ȂǁA�ނ�����܂łɋz���������ւ̃��t�@�����X�������āA�����ƊO���̏o��ꏊ���闧�ʂ̍\�����s�Ȃ����Ƃł���B |
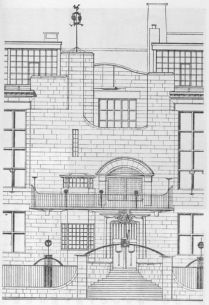

|
|
|---|---|
���ɍZ�����̓����ƊO���̗͂Ɨ͂̏o��ɂ��O�ǂ̍\���ɂ́A���̂��Ƃ��݂���B �A�v���[�`�K�i�y�уG���g�����X�E�h�A�̐^��ɂ́A�����ʂ̈�K�X�^�b�t�E���[���̃A�[�`�̂������Ɠ������`�[�t�̑傫�ȑ�������A ���̑��̃A�[�`�ɑΉ����āA�����ɂ̓A�[�`�ɍ��킹���V��̂����A���R�[�����o���Ă���B �i��}�E�j �q���E�n�E�X�̐Q���̃A���R�[���Ɠ����n���̃X�y�[�X�̂�����ł���B ���̃A���R�[���������Ă���̂͗אڂ���Z�����p�̐��ʏ��ł���B ���ʏ��̏o���́A�O���ł͂P�K�̎�q���̏o���ɑΉ����āA ��̂̃��H�����[���������Ă���B �i���}�|�A���Q���H����2�K���ʐ}�j �o���̃��H�����[���́A�Q�K�ň�U�I��A�Z��������Z���̃X�^�W�I�ɏ��K�i���̓��ɂȂ��Ă�����x������B �R�K�̍Z�����̃X�^�W�I�͕ǖʂ������������ăv���C���@�V�[�����Ƌ��ɁA����ɂ���� �K�i�����ۗ������Ă���B�܂��Z�����̃A�[�`�̑��ւ̃v���C���@�V�[�̊m�ۂ́A�����̃o���R�j�[���݂��o�����Ƃōs�Ȃ���B ���̃o���R�j�[�̓X�^�W�I�̑��Ƒ��̊Ԃ́A�G���g�����X���\������ǖʈ�t�ɍL�����Ă���B |
���̂悤�ɃG���g�����X���̃G�����F�[�V���������́A�����ƑΉ������Ȃ���A���ɔ����Ȏ��o�I������s�Ȃ��Ă���B �V�����g���[�łȂ������Ɍ����Ȃ���A���͂Q�K�̎萠���V�����g���[�ɂ�����A�G���g�����X�E�h�A�͒��S����Y���Ă������ŁA ���͒��S�ɂ�������A�o���̃��H���E���́A�ォ�牺�܂Œʂ肻���ł��Ȃ�����͈�U���f�����B�����̎������܂������Ă���悤�ŁA ���ۂ͂���Ă���B �i��}���j �����̍ו��̌���ɂ͖@�����������Ȃ��B �S�Ă̌���s�ׂ͂Ђǂ������ŁA�������Ȃ����̌���s�ׂɂ͌��������Ȃ��B �K�����ɑ�����̂������āA�O�̌���s�ׂŊm�����ꂻ���ɂȂ����K�����́A ���̌���s�ׂł́A�̈ӂɕ������Ƃ���B ����s�ׂ̈˂菊�́A��Ɉ�����̂��̂ł���B���������ԓx���A�}�b�L���g�b�V���̐v�s�ׂɂ͏�ɂ���B ��ςȃG�l���M�[��v����d���ł���B ���̐��ʂ̃G�����F�[�V�����ɂ��ӂ��ْ����̈˂��ė����鏊�́A���������v�s�ׂɂ���B |
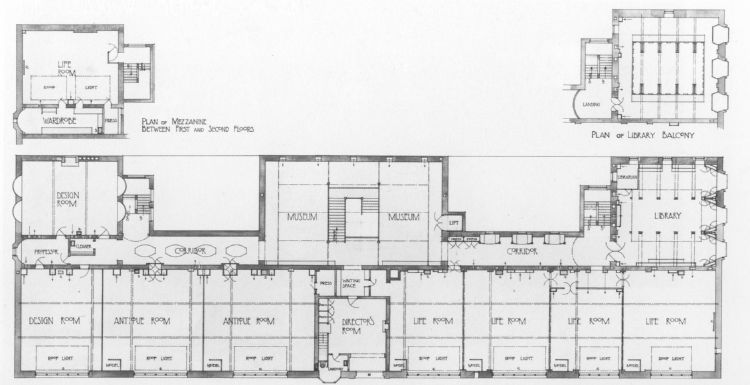
|
|
|---|---|
|
�S-�T�D�\���b�h�ȐƃA�C�A���E���[�N�̕\�w �@���p�w�Z�̍\���́A��{�I�ɂ͐Α��Ɨ������ł���B �k�ʁA���ʁA���ʂ͂��̒n���̎Y�̊D�F�̐ɂ��Α��A��ʂ����͗������̏�Ƀ����^����h��A���̏�ɍ����A �Ӑ⏬�𐁕t����A��ʂɃ��t�L���X�g�ƌĂ��d������Ă���B�����̑ϗ͕ǂ͗����ς݂ł���B ���ɂ̓X�`�[���̃��e�B�X�E�K�[�_�[���A���S�̗����g���Ă���B��X�p���̕����ł͂����̗����A ���^���E���X�Ƀ����^���ł����ł���B �X�^�W�I��11���[�g���߂��̑�X�p���̗���30�~60�Z���`���[�g���̃��e�B�X�E�K�[�_�[�ŁA �X�p�����R���������ʒu�ɏ���������A���̏�ɖؑ��̏����A�ڂ������Ă���B�X�^�W�I�̊Ԏd��͖ؐ��̃p�[�e�B�V�����ł���B �]���ĉ��s��ꃁ�[�g���߂��̃X�p���́A�G���g�����X�����̗�����ʂɂ��āA�ϗ͕ǂ��S���Ȃ��̂ŁA �����͖]�݂̑傫���Ɏ��R�ɕ����ł���悤�ɂȂ��Ă���B �����͊�{�I�ɂ̓t���b�g�E���[�t�ŁA�ؐ��̍��g�̏�ɃA�X�t�@���g�h�����{����Ă���B�X�^�W�I�̏�̔ݕ����́A ���̔ނŕ�����Ă���(�p���ł́A���݂����∟���̔ނ��A���̉��H���₷������悭�����ނɎg���Ă���)�B �߂̃g�b�v���C�g�����ɂ́A�}�b�L���g�b�V�����L�́A�쑾���g���X���g�܂�A���̏�ɃK���X���˂����Ă���B ��b�ƒn����K�A�n����K�́A�S�R���N���[�g�ŁA�X���u��15�`17�Z���`���[�g���B��K�̃X���u�͑S�Ėؑ��ł���B �k�ʃt�@�U�[�h�ɂ���A�X�^�W�I�̑��͐Α��̌����Ƃ��ẮA�����傫�����ŁA���ނ���X�p���̑傫�����̊J�����́A�U���[�g���߂����ł���B ���̂��߂Q�K�̑��̂܂����ɂ́A���S���̃{�b�N�X�r�[�����g���(��K�̑��̂܂����͓S�R���N���[�g�ł���j�i���}�E�j�A ���̃T�C�Y��60�~75�Z���`���[�g��������B�܂��T�b�V���͖ؐ��ł���B �����āA���̑傫�ȑ��ɂ́A�ڂ𖣂����ɂ͂����Ȃ��A�S���̃u���P�b�g�����Ă���B | �t�F���V���O�̌����t���ɂ����悤�Ȍ`�̂��̃u���P�b�g�́A��ɂ́A���̑傫�ȑ��̃u���[�V���O�̖�ڂ����������Ă���A �Ȃ������̃K���X�@���̂Ƃ�����ɂȂ��n�����߂̂��̂ł���ƁA�@�\�I�ɂ͐�������Ă���B�i���}���j �������A���̃u���P�b�g�̈Ӗ��́A �P�ɂ��������@�\�I�ȈӖ������ɗ��܂���̂ł͂Ȃ��B����ɂ��ăy���X�i�[�͎��̂悤�Ɍ����Ă���B �g���̋����̐��̗�́A�}�b�L���g�b�V���̍ł��d�v�Ȑ����̈�A���Ȃ킿�ނ̋�ԉ��l�ɑ��鋭��Ȋ����\���̂ł���A �����̖ڂ��A�����̃\���b�h�Ȑ̕ǖʂɓ��B����O�ɂ́A �܂�����������ɂ���Ď�������Ԃ̑��w��ʉ߂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B ���l�ȏ�����Ԃ̓��ߐ��́A���ׂẴ}�b�L���g�b�V���̏d�v��ɔ��������͂��ł���B�h �\���b�h�Ȑ̕ǖʂɓ��B����O�́A�S���̋����ɂ��w(���C���[)�B�y���X�i�[�͓��ɖʂ����A �n����K�̃X�J�C�E���C�g��ی삷��ׂ́A�t�F���X�Ƃ��̏�̐A���I�ȑ������܂߂āA ���̑��w�Ƃ������t���g���Ă���B�������G���g�����X�̏�ɂ���o���R�j�[�̎萠�ɂ��Ă�������B�i���}�E�j �����A�C�A���E���[�N�́A�P�Ȃ鑕���Ƃ��ĕЕt�����Ȃ��Ӗ��������Ă���ɈႢ�Ȃ��B �t�B���^�[�Ƃ��ẴA�C�A���E���[�N�B�\�ʂ̃��C���[�Ƃ��ẴA�C�A���E���[�N�B�d�w��(���C���[�����O)�A�\�w���B�\�ʂ̖ѐ[���B �ʁA���邢�͗ʉ�Ƃ��Ă̐̕ǖʂƁA���ނƂ��ẴA�C�A���E���[�N�̕\�w�̕t���B �@ ���������w���d�˂��@�͓�����Ԃɂ�������B���R�ȕǖʂɁA���ނɂ��\�w�Ƃ��Ẵt�B���^�[��t�����悤�Ƃ���X���́A ���܂��܂ȂƂ���Ō�����B�Ⴆ�A�����̐}�����ł͂��ꂪ�����ɂ������B ���ɃM�������[�����̈������Ɍ����邪�A����ɂ��Ă͑����H���̏��ŐG��悤�Ǝv���B |


 |
|
|---|---|
|
�S-�U�D����ł̕ύX �}�b�L���g�b�V���́A����ɓ����Ă���̕ύX�A�C���𑊓����x�s�Ȃ����Ƃ������Ƃ������Ă���B 1896�N�Ƀf�U�C�����ꂽ���̂ɋ߂��ƌ����Ă���k���ʐ}�ƁA���ۂ̌������r���Ă݂�ƁA �ύX��C�������Ȃ��Ȃ��������Ƃ������ɕ���B���̒��œ������̑����H���v�H�܂ł̊Ԃɍs�Ȃ�ꂽ�ύX�ɂ��Ă݂Ă��������B 10�N�߂��N�����o�������ɂ�����ύX�قǑ傫�Ȃ��̂͂Ȃ����A �H�����Ԃɂ��A�}�b�L���g�b�V�������X�ɍו��ɂ�������Ă���̂������Ėʔ����B �Z��������A�Z���p�̃X�^�W�I�ɓo�鎄�p�K�i�̎�荞�܂�Ă��铃�́A �����ŏ�K�̃p���y�b�g�̏�ŏ��߂ēƗ��������Ƃ��ē˂��o���Ă��āA�p���y�b�g��艺�͊O�ǖʂƈ�v���Ă����B �ύX��͂��̓��̌`�������ƃA�[�e�B�L�����[�g�����邽�߂ɁA�p���y�b�g�̉��A�X�^�W�I�̑��̂܂����̉��[�܂ł̕ǂ��A ���̓��̕ǖʂ��c���Ĕ����Ɉ�i��ނ����Ă���B�܂��Z���p�X�^�W�I�̃o���R�j�[�̎萠�ǂ́A �����̐}�ʂł́A���[�ŋȐ���`���ė����オ���Ă����̂��A���������ɂ��Ă���B �����Ă��̎��p�K�i�̂��߂ɁA�����ȏc���̑��������������Ă���B �Z�����̕��̃o���R�j�[�̃A�C�A���E���[�N�̎萠���A�ŏ��̐}�ʂł͉��̕ϓN���Ȃ����A�o���オ�������̂ɂ́A �X�^�W�I�̑��̃u���P�b�g�Ɍĉ������u���P�b�g���t���A�[���ł͎萠�̃��C���������ȋȐ��ɏC������Ă���B �i���}���j �G���g�����X�E�h�A�㕔�̂܂����́A�ŏ��P���ȃL�[�X�g�������Ă����̂����A�O���t�B�J���ȋȐ��ō\�����ꂽ�Ɠ��̂܂����ɕύX���ꂽ�B ����ɂ��ẮA�}�b�L���g�b�V�����������Őp���g���āA���̃L�[�X�g���̌����͌^�������Č������Ă������Ƃ��A �E�B���A���E���C�G�X�Ƃ��������A�}�b�L���g�b�V���̃h���t�g�}���Ƃ��ē����Ă����l���A�n���[�X�Ɍ���Ă���B | �X�^�W�I�㕔�̃t���b�g�E���[�t�̑O�ʂɂ͍ŏ��p���y�b�g�����݂��A�R�[�j�X��̂��̂��}�ʏ�Ŋm�F�ł���̂����A �{�H���Ɏ�苎���A�p���y�b�g�Ȃ��Ŕ݂��ؐ��̃u���P�b�g�̏�ɂ̂�Ƃ����A �������@�ɕύX����Ă���B �n���̃X�J�C���C�g��ی삷�邽�߂̃A�C�A���E���[�N�̂�͂�ϓN�̂Ȃ��t�F���X���A�啝�ɕύX����A �k�ʂ��\������d�v�Ȍ`�ԗv�f�ɂȂ����B ����ɔ����ȕύX������B���ꂼ��̃X�^�W�I�̑呋�̗��e�̒��p�̃R�[�i�[���C�ɓ��炸�A ���łɑ����H��������������ł���ɂ�������炸�A�}�b�L���g�b�V���͐H���Ăі߂��āA�V���[�v�ȃR�[�i�[�ɑS�Ċۖʂ��Ƃ点���B �i���}�E�j �ǂ�Ȃɏ����Ȃ��Ƃł��Ō�܂Ō����Ē���߂Ȃ��B���m�ւ̓O�ꂵ�������������ɂ͌�����B �}�b�L���g�b�V���͂˂ÂˁA���z�Ƃ̐}�ʂ́A��̃A�C�f�B�A�̃��t�Ȏw���ɉ߂��Ȃ����Ƃ�\�����Ă����B �ނ̈ӌ��ł́A�H���̐i�s�ɔ����A���ӂɏC�����鎩�R���f�U�C�i�[�͂��ׂ��Ȃ̂ł���Ƃ����B ���̍l�����́A���X�L������X�̒����Љ�̑n���ߒ��𗝑z�����錩���ɁA�ǂ������̌�������炵���B �����̎Љ�ł́A�}�X�^�[�E�r���_�[���A��̂̃A�C�f�B�A�̘g�g�������A���̎w�����ŏn�������E�l�������A ���̂��̑n���̗]�n���܂͂��A�^����ꂽ�͈͂̒��Ŕ������Ă����B ���������̃��B�N�g���A���̎���ɂ́A���Ƃ��n�������E�l�������Ƃ��Ă��A�R�X�g�I�ɂ��A�n���I�s�ׂ��s�Ȃ��ꏊ�̗]�T���A �ނ玩�g�ɂ͗��z�I�Ȓ����Љ�قǂɂ͋��߂��Ȃ������B�]���Č��z�Ǝ��g���A����ɂ����ĐE�l�B�Ƌ��Ɍ������Ȃ���A �ו����C���A�ύX���Ă����ׂ��ł���Ƃ����l�����Ɏ������̂ł���B �������āA�}�b�L���g�b�V���́A���݂̉ߒ��ŁA�����ȍו��Ɏ���܂ŁA�ύX�A�C�����邱�Ƃ��S�O���Ȃ������B ���������}�b�L���g�b�V���̐v�ԓx�́A����H���Ɏ����Ă�苭�������邱�ƂɂȂ�B |

 |
|
|---|---|
|
�S-�V�D�ݔ��v�� �y���X�i�[�́A����قlj��x���}�b�L���g�b�V���̂��Ƃ������Ă���̂����A���p�w�Z�̊��ݔ��ɂ��Ă͐G��Ă��Ȃ��A�ƃ��C�i�[�E�o���n���͌����B �l�������Ă���HKPA��������AGLC�ɂ����Ă��A�_�N�g�����̒g�[�͍s�Ȃ��Ă��Ȃ������B �ʏ�̕����͑������������C�̃��f�B�G�^�[���u���Ă��邾���ŁA���C�͑��������邱�Ƃɂ�鎩�R���C�ł���B �����h���̌Â������ł͑�̂ɂ����āA�l�̒m�����ł͂��ꂪ���ʂł������B �C�M���X�l�́A�����Ƃ����Ƃ����A��C���X�^�b�t�B������A�����J���悤�ƌ����Ȃ���A���ɂ܂߂ɑ���������B GLC��HKPA�̌����������Ƃ��A���Ȃ�Â����������m��Ȃ��B ���������AGLC�̃A�C�����h�E�u���b�N�Ƃ����V�������Ă�ꂽ���z�����ł́A������Ă����悤�ȋC������B �O���X�S�[���p�w�Z�Ƀ_�N�g�����̒g�[�Ɗ��C�̃V�X�e�����A�v�̍ŏ��̒i�K�����������Ă����Ƃ������Ƃ́A ���̓������ɗႪ�Ȃ������킯�ł͂Ȃ�����A�K�������v���I�Ƃ͌����Ȃ����A�V�������Ƃ������ɂ͈Ⴂ�Ȃ��B �܂����Ȃ��\�Z�Ƃ��܂��܂Ȑ�����l����ƁA�}�b�L���g�b�V���̌��z�ɑ��錒�S�ȍl�����̈�[�����邱�Ƃ��o����Ǝv���B | �k�ʂ̃X�^�W�I�ɂ́A�傫�ȑ����������Ă���A�k���O���X�S�[�ł́A�����Ȋ������\�z����A���������̕����ł́A���f���ɂ��f�b�T�����s�Ȃ���B ������l���ă}�b�L���g�b�V���͐v�̍ŏ��̒i�K����g�[�Ɗ��C�V�X�e�����l�����A�����ǂ̒��ɏc�����̃_�N�g�ߍ���Ōv�悵�Ă���B �����Ēn���Q�K�̒����L���ɂ́A�{�C���[���Ƃ��ׂ̗̃t�@���E���[������̉��������̏c�_�N�g�ɑ��荞�ނ��߁A �L����t�̕��ŁA1.8���[�g���̍����̃_�N�g�������Ă���B���̃_�N�e�B���O�́A�قƂ�ǂ̕������T�[�����Ă���A �܂��k���̃X�^�W�I�̑��ۂɂ́A�⏕�I�Ƀ��f�B�G�^�[���ݒu����Ă���B �i���}�n�K���ʐ}�j ��������N�A�����̃��f�B�G�^�[�ɂ��V�X�e���ɕϊ�����āA���݂ł͂����̃_�N�g�͎g���Ă��Ȃ��B �o���n���͂���ɂ���āA�}�b�L���g�b�V���̂��̌���̋�Ԃ̍I���Ȏ�@�̈ꕔ���A���o�I�ɉĂ���ƁA���Ă���B �ނ͂���ɂ��̃_�N�g���s�\���ɂ��������Ȃ��Ȃ����̂́A�ŏ��̐v�������̂ł͂Ȃ��A�ێ��Ǘ����[���ł͂Ȃ��������炾�Ǝw�E���Ă���B ������ɂ��Ă��A�}�b�L���g�b�V�����A��낤�Ƃ��Ă������Ƃ́A�P�Ɏ��o�I�Ȋ�т邽�߂����̍�Ƃł͂Ȃ��A ���z�ƂƂ��Ă̌��S�Ȋ��ɑ���l�������܂߂��A���Ɏ����I�ȁA�����đ����I�Ȑv��Ƃł��������Ƃ̗Ꭶ���A���̃_�N�g�E�V�X�e���͕�����Ă���B |
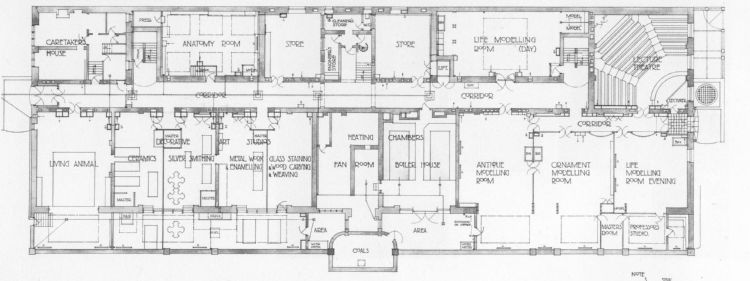
|
|
|---|---|
|
�T�D���p�w�Z����H���� �T-�P�D�ł��[���������� �@ �������đ����H���́A1899�N�̖��ɏI�������B ���p�w�Z�Ɏc���Ă���L�^�ɂ��ƁA�����̐����̐v�ύX�̈ϑ����}�b�L���g�b�V���ɏo���ꂽ�̂�1906�N9���̂��Ƃł���B �܂������L�^�ɂ��A ���z�Ƃ��A���̑��z�v����I�������Ƃ������A�X�R�b�g�����h����ǂɒ�o�����̂́A1907�N9��25���Ƃ������t�ł������B �܂��n���ꂳ�ꂽ�����̕ύX�}�ʂ���������Ă���̂����A���̐}�ʂɂ͌��݂̏�ԂƓ����G�����F�[�V�������`����Ă��āA 1907�N5���Ƃ������t�������Ă����B �������Đ��������H���̍Čv�悪�s�Ȃ�ꂽ�̂�1906�N9������1907�N5�����܂ňʂ̊��Ԃł��������Ƃ����肳��Ă���B ���̑����H���܂łɂ́A�]���đ����H���I������6�N�߂��A�܂��R���y�̎��_���琔�����10�N�̔N�����o�߂��Ă���B ���̊��Ԃ̓}�b�L���g�b�V���ɂƂ��āA���z�ƂƂ��čł��[�����������ł������B �܂��}�[�K���b�g�E�}�N�h�i���h�Ƃ̌����������Ď������ɂ����Ă��A�K���Ȋ��Ԃł������B ���̊ԂɂقƂ�ǂ̏d�v�삪�v����Ă���B �����̂ق��ɂ��~�X�E�N�����X�g���̂��߂̃e�B�[���[���Q�����߂Ƃ���A�������̓����̃f�U�C�����s�Ȃ��Ă���B �����̒��ł́A �O���X�S�[���p�w�Z�̑����H���ւƌq�����čs���A�}�b�L���g�b�V���̐��n�̉ߒ��Ƃ��āA ���p�w�Z�Ō�������A�������̃��H�L���u�����[�����s����Ă���Ƃ����Ӗ��ł́A �N�C�[���Y�E�N���X�E�`���[�`�ƃX�R�b�g�����h�E�X�g���[�g�E�X�N�[�������ɏd�v���B �N�C�[���Y�E�N���X�E�`���[�`�́A���p�w�Z�����̒���A�X�R�b�g�����h�E�X�g���[�g�E�X�N�[���͔��p�w�Z�����̒��O�Ƃ�����ɁA �����I�ɂ������Ƒ����̃}�b�L���g�b�V���̍l������A��@�̔����ȑ��Ⴊ���ĂƂ�Ėʔ����B | �s���{���ꂽ���z�t ���N�C�[���Y�E�N���X�E�`���[�` Queen's Cross Church �@�v1897�N�A�v�H1899�N �����b�N�q���E�X�g���[�g�E�`���[�`�E�z�[�� Ruchill Street Church Halls �@�v1898�N�A�v�H1899�N ���E�B���f�B�q�� Windyhill,Kilmacolm �@�v1899�N�A�v�H1901�N ���Q�C�g�E���b�W�@Gate Lodge,Auchenbothie �@�v�H1901�N ���f�C���[�E���R�[�h�E�r���f�B���O�@Daily Record Building �@�v�H1901�N ���q���E�n�E�X�@Hill House,Helensburgh �@�v1902�N�A�v�H1904�N ���X�R�b�g�����h�E�X�g���[�g�E�X�N�[���@Scotland Street School �@�v1904�N�A�v�H1906�N �����T�C�h�@Mosside �@�v�H1906�N ���I�[�L�j�o�[�g�@Auchenibert �@�v�H1906�N �s�v���W�F�N�g�t ��1901�N�̃O���X�S�[������v���Z �@International Exhibition Buildings Competition 1898 ���|�p�Ƃ̃J���g���[�E�R�e�[�W �@An Artist's Country Cottage 1900 ���|�p�Ƃ̃^�E���E�n�E�X �@An Artist's Town House 1900 ���|�p���D�Ƃ̂��߂̏Z��v���Z �@Haus eines kunstfreundes 1901 �������@�v�[���E�J�V�[�h�����v���Z �@Liverpool Cathedral Competition 1903 |
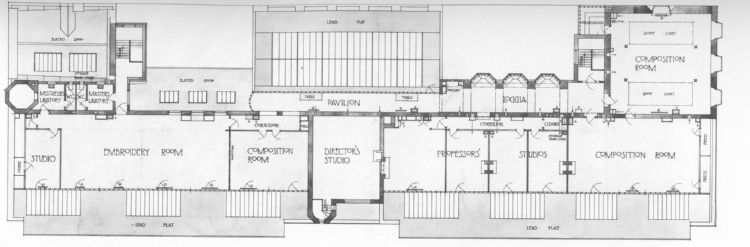
|
|
|---|---|
|
�T-�Q�D�����̐v�ύX �����̌v��ł́A�Q�K����P�K�ɒʂ�����K�i�́A�O�q�̃G���g�����X�̉�������ɂ����K�i�B������Ȃ������B ����Ɉ������ƂɁA���̊K�i�͑O�q�̒ʂ�ؐ��ł���B �s���ǂ́A�ŏ���������߂��Ă����̂����A�����H���ɂ����ẮA�����̗������ꂼ��ɁA �ω\���̊K�i����݂��邱�Ƃ�]�V�Ȃ����ꂽ�B ���E�Ώ̂̈ʒu�A�����ł͐}�����ׂ̗�A�����ł́A�����̌v��ɂ�����f�U�C���E���[��(���݂̓}�b�L���g�b�V���E���[��)�ׂ̗肪�A �ł��K�����ʒu�ł��邱�Ƃ͖����������B �i���}���j ��P���Ŋ������Ă����Q�K�̉�c���ɂ́A�����̗��ǖʂɈ���̘p�Ȃ����������łɂ������B �܂蓌���ʂ̂Q�K�����̓���Ɍ������̑��Ɠ������̂��A���Α��̊O�ǂɂ����Ă��鎖�ɂȂ�B �����Ń}�b�L���g�b�V���́A���̈�̑�����菜�����ɁA�K�i���̕��̒i�����̑��̘p�Ȗʂɍ��킹�āA������ĕ������Ƃ����������s�Ȃ����B ���̕��͂��̂܂c����A���̊K�i���ɕs�v�c�Ȍ��ʂ������炵���B �i���}�E�j | �Ȃɂ��듥�ʂ�˂������āA�c���̘p�Ȃ��������K�i�����ɂ�荞��ł��Ă���̂�����B ���o�[�g�E�}�N���E�h�ɂ��ƁA�A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�́A���z�̐v����̎Љ�I�ȃh�L�������g�Ƃ��Ă݂錴���A ���Ȃ킿�g�v���悤�Ƃ��錚�����������邽�߂́A���܂��܂ȕK�v�����ɂ��Ă����łȂ��A ���̐�������ߒ���A�ύX�̉ߒ��ɂ�����̕ω��ɂ��Ă��A���̐v���ꂽ�����̒��ŁA�Љ�I�ȃh�L�������g�Ƃ��Č�点�Ȃ���Ȃ�Ȃ��h �Ƃ��������ɏ]���āA�}�b�L���g�b�V���͂��̃E�B�b�g�ɕx�ޏ������s�Ȃ����Ƃ����̂ł���B �}�b�L���g�b�V���̐v���@�ɂ́A�������ĉ��Ƃ��������肠�邢�͌Ӗ������ĒP�������悤�Ƃ���̂Ƃ͔��̑ԓx��������B �v�ߒ��Ŗ�肪�o�Ă������ɂ́A�������瓦�ꂸ�A�Ӗ��������A���ʂł���}�C�i�X�̗v�����A�ނ��낻�̂܂ܘI�悳���A �c�����Ƃŋt�Ƀv���X�̗v�f�ɓ]�����Ă����B�}�C�i�X�̗v�������g�̃f�U�C���̋N���܂ɂ��Ă��܂��B |

 |
|
|---|---|
�v�ύX�ɂ��V���ȉ�����̒́A���z�ƂɂƂ��ď�ɗv���������̂����A���̏ꍇ�A�}�C�i�X�̗v���ƂȂ�A �Ë��̌��ʕύX�O�����R���Z�v�g�̞B���Ȃ��̂ɂȂ��Ă��܂��̂���ł���B �}�b�L���g�b�V���͋t�ɂ���𗘗p���āA�V���ȃR���Z�v�g�Ɍ��т��čs���A�������y�����ɁB���̍P��I�ȋ��x���͋��Q�ɒl����B ��̔��K�i�̐V�݂͖@�K��̗v����������N�����傫�ȕύX�ł��������A������������ւ̎��Ԃ̌o�߂́A �w�Z���ǂ���̐V���ȋ@�\��̗v�����������A�����������N�������B���̈�́A���ʓI�Ɂu�w���E�����v the hen run �ƁA �̂��Ɋw���B�ɌĂ��ʘH�����ݏo����邱�ƂɂȂ�ύX�ł���B �i��}�R�K���ʐ}�j ���̗v���́A�w�Z���̗v���ɂ��A���K(�A�e�B�b�N)�A�܂�R�K�̃X�^�W�I�����̒lj��ł���B ���̃A�e�B�b�N�̃X�^�W�I�����́A ���S���̍Z���p�̃X�^�W�I(����͂��Ƃ��Ɖ��K���̂��Ă���̂�)�������A �����O�ʑS�̂ɂ킽���Ă���B |
�o�ϓI���R�ƁA���R�Ȃ�ׂ��y���Ƃ����\���I���R�ɂ���āA���̕����͖ؑ��ł���B
�k�ǖʂ����i�������Ă���̂ŁA���ʓI�ɂ̓����t���[�E�X�g���[�g�̓��H�����F���ɗ����Č��グ�Ă��A���邱�Ƃ��o���Ȃ��B
���̈�i�����邱�Ƃɂ���ďo������K�̃X�^�W�I�̉����̃X�y�[�X�ɂ́A�k���ʂ̑呋�ɍ��킹���ʒu�ɃX�J�C���C�g���A���̐��Ɠ��������������Ă���B �}�b�L���g�b�V���́A���̃A�e�B�b�N�̃X�^�W�I�ɂ́A��i�����邱�Ƃɂ���Ă����łȂ��A �P�A�Q�K�̑傫�ȑ�����Ƃ͈قȂ�ׂ����������S�ʂɎ{�����Ƃɂ���āA�P�A�Q�K�Ƃ͑S���Ⴄ�\���^���āA ���ł�1896�N�̗��ʂŊ������Ă����k���ʂ̃v���|�[�V����������Ȃ��悤�ɂ��Ă���B �Ƃ��������A���̑�����̕\��̕ω��ɂ���Ėk���ʂ����L���Ȃ��̂ɂ��Ă���B �R�K���ʐ}�A�k���ʐ}�A�f�ʐ}�Q�� | |

 |
||
|---|---|---|
|
�T-�R�D�엧�ʂ̎��Ӗ� ���̃A�e�B�b�N�̃X�^�W�I�̕����ɂ���Đ��������������́A�����̃A�e�B�b�N�Ɛ����̃A�e�B�b�N���A ���ɍ݂�Z���p�̃X�^�W�I�ɂ���ĕ��f����čs�������o���Ȃ����Ƃł������B �S�̂ɘL����ʂ����Ƃ́A�����̂Q�K�̘L���̉����ɁA�X�J�C���C�g������̂ł������Ȃ��B �}�b�L���g�b�V���͐����}�����̏�̃R���|�W�V�����E���[���ׂ̗�̊K�i����܂��Q�K�̘L���̏�� �g���b�W�A�h�ƌĂ������̃A�[�`�ō\�����ꂽ����L�����B �g���b�W�A�h�ɂ͎O�̕Ў����̏o������������(���̏o���̈ʒu�͂Q�K�̎O�̃A���R�[���ƈ�v���Ă���)�A �������̃A�[�`�Ƒ��ւ��đ��̕����Ƃ͕��͋C�̈�����Ɠ��̋�Ԃ��`�����Ă���B���݁A���̗����ǂɂ͔��y���L���h���Ă��邪�A ���Ƃ��Ƃ́A�e�������ǂ��I�o����Ă���A���e�X�����d�ʊ��̂����Ԃł������B �i��}���j �Ƃɂ������̃��b�W�A�ɂ��ẮA�Q�K�̘L���̗����̕ǂɂ���Ďx�����邱�Ƃ��ł���̂Ŗ��Ȃ��B ���́A�Z���p�X�^�W�I�̔w��̕����œ��������ǂ��q�����ł���B�Ƃ����̂����̕����ɂ́A �f�ʂ�����ƕ��邪��K�̃~���[�W�A���̃X�J�C���C�g�̃g���X�������˂��o�Ă��āA�܂��L���̊O���̕ǂ���ǂ́A��K�����ɂ͂Ȃ��B | �����Ń}�b�L���g�b�V���́A���������������������łȂ��A�ڊo������� ��n�o�����̂ł���A�܂����Ă��y�����ɁB���ꂪ�u�w���E�����v�ł���B ��������͂�y���ؐ��ŁA����90�Z���`���[�g���̍�����V��܂ōׂ��������`�̑�����̃K���X�̔��ŁA �d�Ԃ�A�z������悤�Ȋi�D�����Ă���B �i��}�E�j�i���}���j ���[�̓~���[�W�A���̃p���y�b�g�ɂ���Ďx������A ���ԕ����͍Z���p�X�^�W�I�̎�������ǂ���o�Ă���S���̃u���P�b�g�Ŏx�����Ă���A �f�ʂŕ���ʂ�A�K���X�̔������ɕ����ăX�^�W�I�̃��t�E�L���X�g�̎�������ǂɎ�蕍�����`�ɂȂ��Ă���B ����ɒ[���ł̓K���X�ʂ͔����ɘp�Ȃ������������܂ŃK���X�̕ǂɂȂ��Ă���B �܂��~���[�W�A���̗��[�̃p���y�b�g�̂������b�W�A���́A�k���̃X�^�W�I�̃p���y�b�g�̍����܂ŗ����オ���āA ���b�W�A�̉����̃����F�����甼�~�̃A�[�`�̊J���������Ă���B �{�̂̕��̕ǂ̃��F���e�B���[�V�����ׂ̈̊J���ɍ��킹�āA�����Ȑ����`�̎l�̍E���A�A�[�`�̏�ɕ���Ő�����Ă���B �������ă}�b�L���g�b�V���́A�ǂ��܂ł��ו����Ȃ�������ɂ����A�S�Ă��f�U�C���������O��I�Ȕ����̍�Ƃ��y�����ɑ�����B |

 |
|
|---|---|
|
������}�C�i�X�̗v�f���v���X�ɓ]�������Ƃƌ`�e�����̂ł͏[���ł͂Ȃ����낤�B
�V���Ȗ@�I�ȗv���A�@�\�I�ȗv�����A�}�b�L���g�b�V���́A�V�������H�L���u�����[�����A
���������L���Ȃ��̂ɂ��邽�߂̓���Ƃ��đ劽�}���Ă���悤�Ɏv����B �ǂ��ɂ�����������������Ȃ��B������ו��ɂ́A�ނ̎�̐Ղ��O��I�ɍ��ݍ��܂�Ă���B ���̖��x�̍����͕����̂��̂ł͂Ȃ��B �A�[���E�k�[���H�[�̓��F�ł���A �S�̂��l�I�ȒP��̃X�^�C���ŕ����s�������Ƃ���ԓx�Ƃ͖����ł���B�܂�}�b�L���g�b�V���̓A�[���E�k�[���H�[�̈�h���ł͂Ȃ��B �����͕��������œƗ����Ă���A���ꂼ��̕����̋�Ԃ́A�قȂ郔�H�L���u�����[�ŁA���ꂼ��אS�̒��ӂ��Đv����Ă���B �����Č����S�̂��т��`�ԓI�@���ɏ]���Đv�����Ă��Ȃ��B�S�Ă̕����ňꂩ��X�^�[�g���Đv���Ă���B 1896�N�̎��_�ŁA�قڃV�����g���J���Ƀf�U�C������Ă����쑤�̃G�����F�[�V�����́A�������đ����̐v�ύX�̒i�K�ŁA �g�w���E�����h�����߂Ƃ��邳�܂��܂ȗv�f�̕����ɂ���āA�傫���ς���Ă������B |
�W�����E�\�[�����́A���̍u�`�^�̒��Ŏ��̂悤�Ɍ`�e���Ă����B �g���̌|�p�A�G��⒤���ɂ�����(���R��)�͕�Ƃ͔��ɁA���z�͏����ɔ���(�C�����F���V����)�̌|�p�ł���A ���̔����́A�l�Ԃ̐��_�ɂƂ��Ă����Ƃ��ꂵ���A�����Ƃ�����ȍ�Ƃł���B�h �엧�ʂɂ͂��Ƃ�������̃C�����F���V�����̗�Ƃ��āA�L�����e�B�����@�[�̉���������B �}�����̏�̃R���|�W�V������(�t�����[�E�y�C���e�B���O�E���[��)�ƁA�K�i���̕ǂɋ��܂ꂽ�������ɁA �}�b�L���g�b�V���͂S�A�T������o���Ă���Ў����̉����������B �n��24���[�g���̈ʒu�ɂ��邱�̉����́A���b�W�A���猩�n���L��ȃO���X�S�[�̊X�̉����̘A�Ȃ�ƁA �O���[�~�[�ȋ�̕��i�̒��ɁA���яo������ł���B �i��}�E�j �x�݂̂Ȃ��C�����F���V�����̎�X�G���ȏW���Ƃ�������쑤�̃G�����F�[�V�����ɂ́A����ł��Ȃ����s�v�c�ȓ��ꊴ������B ����͑S�̓I�ȃR���Z�v�g�ł���ꂽ�̈ӂ̓���ł͂Ȃ��A�����ւ̓O��I�Ȏ������琶�܂ꂽ�s�v�c�ȓ��ꊴ�Ƃ�����B �쑤�̗��ʂ́A���̈Ӗ��ŁA���̔��p�w�Z�ɂ�����}�b�L���g�b�V���̐v�p���������Ƃ��N���A�[�Ȍ`�ŘI�悵�Ă���B |
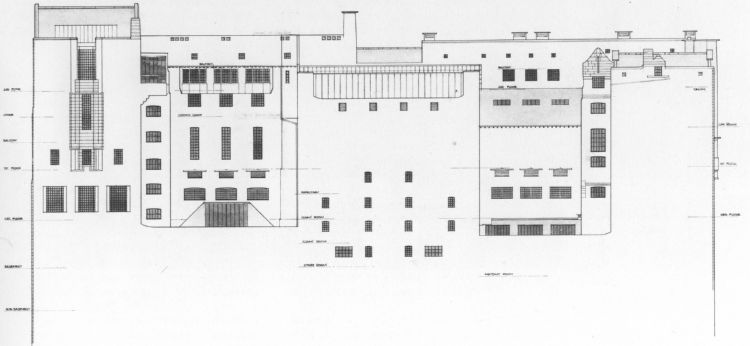 |
|
|---|---|
|
�T-�S�D�}�����Ɛ����� ���p�w�Z�̓����́A�Z������A���Ƃ̃{�[�h�E���[��(���݃}�b�L���g�b�V���E���[��)�̔�����ۂ̕����������ƁA ���̕����͖w�ǎd������Ȃ��f�ނ̂܂܂̕ǂɈ͂܂�Ă���A ���Ƀ_�[�N�E�u���E���̃X�e�C����h��ꂽ���A���A�H�ڔŕ���ꂽ�����͍����ۂ���ۂ������B �@�\��̗v������A�����̑S�̍\������ɔw�������k���ɑ傫�ȑ����Ƃ������߂������āA�X�^�W�I��w���E�������̗�O�������� �S�̓I�ɔ��Â���Ԃ������̂����A�����̍����ۂ��X�e�C�����]�v�ɂ�����������Ă���B �X�J�C���C�g����̌����A�k���̌��͎キ�A�J�b�Ɩ��邢���z�����͓����Ă��Ȃ��B �ߑ㌚�z�̋Z�p��`�I�ȌX���́A����ŋ�Ԃ���ł����A�e�̂Ȃ������I�ȋψ��Ԃ�����o�����B ���p�w�Z�ɂ݂���A���̈��̔��Â��́A�ߑ㌚�z�̖��邢��Ԃ������ꂽ�l������������̗v���ɂȂ��Ă���̂����m��Ȃ��B | �J�菁��Y�u�A�ȗ�^�v�̒��Ō��y���Ă���A���{�Ɖ��ɂ��đ��݂����u��Ɍ�����Łv�̊��o�̈Ӗ���l��͖Y��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B ���������u�A�ȁv�̂����Ԉӎ����l���邤���ŁA�K�E�f�B�ɂ��o���Z���i�̃R���j�A�E�O�G������̒n�������̈łƁA ���̃}�b�L���g�b�V���̔��p�w�Z�A���ɑ����̐}�����͖l��ɏ��Ȃ���ʃq���g��^���Ă����悤�ȋC������B �O�x�ڂɃO���X�S�[��K�ꂽ�̂́A���܂��܃o���Z���i�̃K�E�f�B�������A���Ƃ����ゾ�����̂ŁA �K�E�f�B�̌��z�̒��ōł����������n�������Ɛ}�������r���Ă��܂����B �R���j�A�E�O�G���̒n�������̈ꌩ���ӓI�Ɍ����邪�A ���͋K�����̂��邠�̌X�������̌Q�ƁA�����̕ύX�ŏ�����V��܂Ő^�����ɐL�т邱�ƂɂȂ����A�X�e�C���h��̂��̐}�����̒���ƂɁA �͂�����͕���Ȃ����A�����悤�Ȗ���������悤�ȋC�����ĂȂ�Ȃ��B ���͎��̃A�i���W�[�Ƃ��ăC���[�W���₷�����炩�A�ǂ���̋�Ԃɂ����Ă��A���Â��X�̖X�̊Ԃɋ���悤�ȉ��[���Â��ʼn��₩�Ȋ��������B |

 |
|
|---|---|
|
�}�����̕��ʂ́A1896�N�̎��_�ł́A�N�C�[���E�}�[�K���b�g��ȑ�w�̃~���[�W�A����A
�}�[�^�X�E�X�N�[���̃h�����E�z�[���ȂǂŔނ��D��Ŏg�����ȉ~�`�������������̂����L���(�M�������[)�̊�{�I�ȍ\�z����������Ă��Ȃ��B
�]���Đ����ʂ�����Ƃ͑S���قȂ����l����悵�A�����ʂ̃��`�[�t���A�����Ǝ�߂����̂ŁA�ْ����̂Ȃ����̂ɂȂ��Ă���B
�����̐v�ύX�̒��ŁA���̐}�����Ƃ��̃G�����F�[�V�����ł��鐼���ʂ́A�ł��ڊo�܂����ω��𐋂��Ă���A
�܂����̊Ԃ̃}�b�L���g�b�V���̚n�D�̔����ȕω����ł��I��Ɏ����Ă���B �����̌v��ł́A���̐}�����̂���u���b�N�́A��w�ō��������̕����Ɠ����ł��������A�v�ύX�ɂ��A�����ɂ��������N�`���A�E�z�[�����n����K�ɁA ���z�ȋ�������K�ɁA�����Đ}�������K���̍�����K�������߁A�O�K�ɂ̓R���|�W�V�����E���[�����݂����āA �ŏI�I�ɁA�����������S�̂ōł��w�̍��������ɂȂ�A�G�����F�[�V�����ɂ����Ă��A����ނ���`�ɂȂ����B ���ʓI�ɂ́A�ق�35�t�B�[�g�A�܂��10.5m�p�ŁA�f�ʂ�����Ε���ʂ蓌�������ɓS���̗����A �k�ʂ̃X�^�W�I���l�X�p�����O�ɕ������Ă���B�i���}�f�ʐ}�E�j |
���̃X�p���͐^��������������3.3m�A���e��3.6m�Ƃ�����ɔ����Ɉ���Ă���B
���̓��������̓S���̗��̏�ɁA�}�����̖ؑ��̒����e�l�{�����ɂ̂������Ă���B
�f�ʓI�ɂ́A�k�ʂ̃X�^�W�I�̊K�����O�������āA�����炻�ꂼ��}���������A�M�������[�����A�q�ɂɂȂ��Ă�����A
�]���ăM�������[���܂߂��}���������̓X�^�W�I�̎O���̓�̖�T.�P���̓V�䍂�ɂȂ��Ă���B
�܂��A�M�������[�̕���2.4m�Ȃ̂ŁA���̈ʒu�Ƃ̊Ԃ�1.2m�̃A�L���o����B
�������Ē����M�������[�̐�[���畂�������Ƃɂ��A���̋�Ԃ͂͂邩�ɖL���Ȃ��̂ƂȂ����B 1896�N�̐}�ʂł́A ���̒��͕��L�̃M�������[�̃X���u�̐�[��肤����ɂ������̂ŕ��f����A�������͂ނ���X���u�ɊJ�����ȉ~�̍E�Ƃ��������ł��������A �v�ύX�Œ����M�������[����Ɨ����ēV��܂Œʂ������Ƃɂ��A�V���ɂ��܂��܂Ȍ`�ԓI�ȑ��삪�K�v�ƂȂ�A����ɐV�����C�����F���V���������܂ꂽ�B �M�������[���x����ؑ��̗��́\���̕����Ń}�b�L���g�b�V�����D��Ŏg����@�ł��邪�\�������ƂȂ蒌�����݁A ���̕������̗����x�����邽�߂ɗ��e�ɓY������������ĕ��L�ɂȂ��Ă���B |
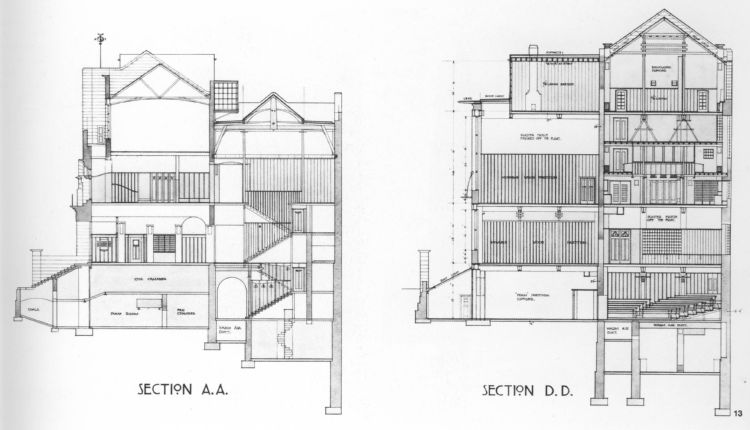
|
|
|---|---|
|
�M�������[�萠�ǂƒ��̊Ԃɂ̓��S���E�`�����t�@�[�̎{���ꂽ�萠�q�ƁA�܂��萠�ǂ̕����ɂ́A
�N�C�[���Y�E�N���X�E�`���[�`�Ɏg��ꂽ���蕨�̎{���ꂽ�y���_���g�Ƃ�����̑������`�[�t��������B
���̊p�ނ̊p���킬�Ƃ��ĐԁA�A�A���ōʐF�������S���E�`�����t�@�[(Wagon Chamfre)�Ƃ����������`�[�t�́A
�C���O�����h�ɂ͐̂��炠��ӏ��ł���炵���B���Ƃ��Ƃ͉w�n��(�R�[�`)��הn��(���S��)�̂��߂̌����Ɏg��ꂽ���̂ŁA
�}�N���E�h�ɂ��ƃ��T�r�[��u�����t�B�[���h�Ƃ������A�[�c�E�A���h�E�N���t�c�̐l�������͂ƂȂ����A
�P���g���E�A���h�E�J���p�j�[�Ƃ�����Ђ̉Ƌ�⌚�z�̑������`�[�t�Ƃ��ē������ꂽ���ł���B
�i���}���j �������̕����Ɏ萠�ǂ���ؐ��̃^�s�X�g���[�̂悤�ȃy���_���g���������Ă���B�萠�ǂ̉��[����˂��o�������ɂ́A �Z�Ղ̋ʂ̂悤�Ȗ͗l�̓������肪�{���Ă���B���̃p�^�[���͏����������ɈႦ���Ă��āA�ǂ������p�^�[�����Ȃ��B �i���}���j �ǂ������p�^�[�����Ȃ��ƌ����A���p�w�Z�Ɏg��ꂽ�����p�^�[���ɂ͂����������̂������B �k�ʂ̃����t���[�ʂ�ɖʂ����t�F���X�̎x��(�X�^���V�I��)�̏�Ɏ��t����ꂽ���̒�(��)�̂悤�Ȍ`������ �A�C�A���E���[�N�̉ؒ�(�t�B�j�A��)�́A�S���Ŕ����邤���A�O�������J��Ԃ���Ă���B �]���đS���Ō܂̈قȂ�p�^�[���ŏo���Ă���B �i���}�E�j |
�܂��O�q�������̕⋭�����˂�
�Č`�̓��̕�(�o�X�P�b�g�E�q���g)�݂����ȃu���P�b�g���A�������̃��@���G�[�V�����ō\������Ă���B �n���̃X�^�W�I�̖ؑ������̐������ނ���b�S��T�����́A��1.8�����ɕǂ���˂��o�Ă���̂����A ���̐�[�ɂ͌��іڂ̂悤�ȍH���{���Ă���B���ꂪ�܂�����ނ̈Ⴄ�p�^�[���ōH����Ă���B �}�b�L���g�b�V���́A���������E�l�̎�Z���������ɂ́A�O��I�Ɏ�̐Ղ����悤�Ƃ���B ���̗\�Z�̌���ꂽ�����ł��ꂾ���������Ȃ����ɁA���ʂ��ɂ͑����̒�R���������ƍl������B���ہA�E�l�̑��������R���������B ��L��T�����̐�[�̕��G�ȍH�̂��߁A�b��E�l�̓X�g���C�L���N�����Ă��܂��B ���������X�g���C�L�́A �����̓�K�̘L�������̃X�J�C���C�g�̂��߂̓V���S���Ȑ�(�I�W�[�E�J�[�u)��`���E�̃v���X�^�[�h���Ƃɂ����Ă��N�������B �ǂ���̏ꍇ���X�g���C�L�͂����炭�j���[�x���[�̏��͂Ŏ��E����A�}�b�L���g�b�V���͎v���ʂ�Ɏ����^��ł���B �E�l�ɑ��Ă���łȂ��A�{��ł���w�Z���Ƃ̊Ԃɂ��A�����I�Ȗ�����łȂ��������a瀂����������Ƃ��\�z�����B �����������̂��}�b�L���g�b�V���������ʂ����e�ɂ́A�Z���j���[�x���[�̐��Ȏx���Ɖ��삪����A �ނ����Ȃ�������s�\�Ȃ��Ƃł������B�܂������ɂ��������Ë��������Ȃ��}�b�L���g�b�V���̎p����������������ނ̍��܂̌����Ȃ̂����m��Ȃ��B �@ |
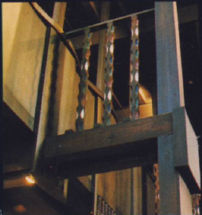

 |
|
|---|---|
�}�����̒���S���E�`�����t�@�[�Ȃǂɂ���Ċ������鐂�����́A�Ɩ����ɂ����f���Ă���B���ɂ���āA �����i�V�䂩��݂艺����ꂽ�A���̃����v�E�V�F�C�h�̏d�����Ȉ�ۂ́A�}������Ԃɐ������Ɛ[���A�Ȃ�^����B �~���[�W�A���̃X�J�C���C�g�̉��ɂ��锒���y�₩�ȏƖ����ƑΏƓI�ɁA�����d�����ȏƖ����́A�V��߂��ɕY�������ł�˂������āA �g�U���Ȃ��������̌�����������A���̋�Ԃ̍\���ɑ傫�Ȗ����������Ă���B �i���}���j ���̃����v�E�V�F�C�h�́A�^�J���̏�ɍ��F�̓h���ŁA�召���ނ̔����ȃ��@���G�[�V�����ɂ���č\������Ă���B ���S�ɑ傫�����̃V�F�C�h���܂���A���̊O���ɔ��̏����߂̃V�F�C�h�����܂��Ă���B�V��ɂ͓����`�̃V�F�C�h�����Ȃ���12�A ���v13�̃y���_���g�̍��̌Œ�ʒu�̎��͂Ɏ��t���Ă���B�i���}���j ���̊��̓M�������[�̑��ۂ̏��ɂ��P�̂Œ݂��Ă���A�}�������̏Ɩ����͂��ꂾ���œ��ꂳ��Ă���B ���������������������̗v�f�́A���ʂ̑��̈����ł���B���̑��͑����ɂ����ē����ʂɍŏ��Ɍ���A �k���ʂ̃G���g�����X�̉��ɂ����ꂽ�A����o����(�I�[���G��)�̃��`�[�t���A�}�b�L���g�b�V���Ǝ��̂��̂ɔ��W�A���������̂ł���B |
������������o�����́A�C���O�����h�̃��@�i�L�����[�ȏZ��ɂ悭�����郂�`�[�t�ł���A�}�b�L���g�b�V���̓C���O�����h�ւ̗��s���A
�������̃��`�[�t���X�P�b�`�E�u�b�N�ɔ[�߂Ă���B ���Ƃ��A1895�N�ɕ`���ꂽ�h�[�Z�b�g�B���C���E���W�X�̉Ƃ̃X�P�b�`�ɂ́A ���p�w�Z�̃G���g�����X�̍��̈�K�������ƍZ�������Ȃ�����o�����ɔ��ɗǂ�������w���̃I�[���G����������B 1894�N�̃��[�Z�X�^�[�B�`�b�y���E�J���f���̏Z��̃X�P�b�`�ɂ������悤�ȃI�[���G�������邱�Ƃ��ł���B ���̑��ɂ��}�b�L���g�b�V���̃X�P�b�`�E�u�b�N�ɂ́A�����悤�ȃI�[���G�������������B�ނ͑O�ɂ������悤�ɁA ���g�̃X�P�b�`�E�u�b�N���牽�x���`�ԃ��`�[�t�������o���Ă��āA�v���錚���ɓ]�ʂ���B �ނ̃X�P�b�`�E�u�b�N�́A���ꂾ���ŁA�G�Ƃ��Ă��f���炵���������Ă���̂����A �ނ͈�ʂł��������ړI�������ăX�P�b�`�����Ă���B �������ʂł́A���̌`�œ]�ʂ��ꂽ�I�[���G���̃��`�[�t���A�����̐}�����ɂ����āA �}�b�L���g�b�V���͑傫���ϊ����A���S�Ɏ��Ȃ̂��̂Ƃ��āA�����Ƃ͈قȂ�V�����Ӗ����������B |

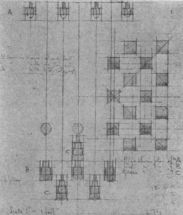
 |
|
|---|---|
|
�g(�|�p�Ƃ�)���g�̂��߂ɓK�ȕ\���ߒ���n�����邽�߂ɁA�Z�p�I �� ���i�C�����F���V�����j �̍˔\�����L���Ă��Ȃ���Ȃ�Ȃ��\
�Ƃ�킯�A���R���ނɒ��邳�܂��܂ȗv�f��ϊ����邽�߂ɁA
���̔����̍˔\�̏�����K�v�Ƃ���\�����āA�����̂��̂���V�����C���[�W��g�ݗ��ĂȂ���Ȃ�Ȃ��B�h �}�b�L���g�b�V���́g�K��Seemliness�h�Ƒ肵�āA���R���瓾���`�Ԃ̒P�Ȃ�]�ʂ���A�ϊ���ڎw���l�����������L�����B ���̕��̂��Ƃɔނ͎��̂悤�ɑ������B �g�|�p�Ƃ́A���ɖL���Ȑ��_�̋@�\�\�{�����y�ɑ�����́A�����߂��́\����ɘj��˔\�\������Ă���B �������ނ𑼂̐l����ۗ������\�����Ĕނ̑f���̗L�������肷��\���̂́A �ُ�ɔ��B������ꂽ�z����(�C�}�W�l�[�V����)�ł���\����͕`�ʂ���C�}�W�l�[�V��������łȂ��\ ���ɑn������C�}�W�l�[�V�����ł���B �|�p�Ƃ������Ă���A�ގ��g�ɂ��܂��܂ȑΏۂ�`�ʂ��Ď����\�͂́A �ނ̍�i�̌��z�I�Ȑ��i�\�����̑Ώۂɏ[�����鎍�\�����Ă����̑Ώۂ��V���{���Y���Ɍ����������\ ���ǂ����痈�Ă��邩���������B�������A�n���I�ȑz����(�N���G�C�e�B���E�C�}�W�l�[�V����)�͂����肸���Ƒ厖�Ȃ��̂ł���B �����̍˔\���ō��x�ɔ����Ă��Ȃ���A�|�p�Ƃ͔ނ̌|�p�𐪕����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��B�h | ���p�w�Z�����Ƒ����̒��Ԃ̎����ɏ����ꂽ�Ǝv����A���̈Ӑ}�A���R���瓾��v�f�̕ϊ��A �n������z����(�C�}�W�l�[�V����)���A�ނ͂��̑����̐}�����Ƃ��̗��ʂɂ����ĒB�����������B �}���������̎O�w�ɂ킽��c���̑��́A���⎩�R�A�܂胔�@�i�L�����[�Ȗ��Ƃ̃I�[���G���̎ʂ��ł͂Ȃ��A �}�b�L���g�b�V���̓��B�_�������n���I�z���͂̋�̉��ł���B �O���Ɠ����̝h�R���琶�܂ꂽ�A �\�w�̊T�O�A�|�[�V�F�ɋ߂���Ԃ��A�����ɂ͂���B ���̃I�[���G���͈�K����M�������[��˂������A����ɂ͂��̏�̑q�ɊK�ɂ܂ŐL�т�B �M�������[�̓I�[���G���̃l�K�̌`�ɍ�����A���S���E�`�����t�@�[�̎萠���t���������A �q�ɕ����������悤�ɊO���̑��̗��Ԃ��̑���t����������B�i��}�E�A���}���j �O���Ɠ����̗��Ԃ��A�����������Ɍ����A�h�R���ْ��݁A��̒m�I�Ȍ`�ԑ��삪�A��Ԃ̉A�Ȃɂ܂ō��߂��Ă���B �X�R�b�g�����h�E�X�g���[�g�E�X�N�[���̊K�i���̃C���[�W�́A���̑��̏����i�K�ɂ͂Ȃ��������m��Ȃ��B �������A���̏����i�K�̒P�Ȃ�c���̑�����A���̐}�����̃I�[���G�������܂��Ԃɂ́A��̒���A�Ӗ��̓]��������B ���̐������ʂƐ}������Ԃ̉A�ȁA���邢�͕ʂ̈Ӗ��łْ͋����́A�}�b�L���g�b�V�����A 10�N�������ČJ�Ԃ��J�Ԃ������Ă����`�ԃ��`�[�t�A��ԊT�O�A�`�Ԃ̗p�@���A���̌J�Ԃ��̒��ŁA�������莩���̎�ɓ�����̂ɂ��A ��U�S�Ă�Y�ꋎ��A���S�̂����ɒ��ē������B�_�ł���B |


 |
|
|---|---|
| �W�DSIR JOHN SOANE(1753�`1837) �W�����E�\�[���������ف[����܂ʈ�E �P�D�����h���̊X�� �l�ɂƂ��ĐS�Ɏc��܂��Ȃ݂Ƃ����A�Q�T����Q�X�܂ł̂R�N���� ��炵�������h���̂܂��Ȃ݂ł���B ���̐��ݕt�����A�Ԓ���C���F�A�D�F�A���܂��܂ȏĂ��F�́A�\���̂ł� ��������̊O�ǁA���邢�͗�����h�荞�߂������ǁA�V�R�X���[�g�����̉����A �h�[�}�[�E�E�B���h�E�i�������j�A���̉Ƃ̒g�F�̐��������� �オ���Ă��� �`���j�[�|�b�g�i�y�ǂ̉��ˁj�A�T�b�V�E�E�B���h�E�ƌĂ��c���̖ؐ� �グ�������A�����g���肳�ꂽ�\���v�f�h�́g�J��Ԃ��h������Ɠ��� �X���݂̕��i�ɁA���̌㉽��K��Ă��A�K��邽�тɁA�����������o���Ă����B �����e���X�n�E�X�̑����́A�����h����i1666�N�j�Ȍ�̂P�W�C�P�X���I�� �W���[�W�A���A���B�N�g���A���̎���ɁA���@�̑ΏۂƂ��Ă���ꂽ���̂��B �܂��͎��Y�Ƃ�99�N�i�����͂����ƒZ�������j�̎ؒn�����Œn�傩��y�n����A �����ɕ������A�����Ō��݂�����C�E�l�B�ɑ݂��ĉƂ����Ă�����B ���̏�Œn������ď��n����B���Y�Ƃ́A���݂ɂ���Ēn�オ�オ�邱�Ƃ� ���v�A�E�l�͉Ƃ����ĂĔ��邱�Ƃŗ��v��B�������đ�̌�A���� �u�[�����n�܂�19���I�܂ő������B �e���X�n�E�X�̌��݂͂܂��y�n�̑�������͂��܂�B�n�K�̕����̓y�H�� ����y���邱�ƂŁA���H�ƃo�b�N���[�h�ɔ��w���̃��x������l�H�I�ɂ��肾���B | ���̒i�X�ɂȂ����y�n�̂��Ƃ��e���X�ƌĂԂ��Ƃ���A�e���X�n�E�X�A���邢�� �e���X�ƌ����ď̂����܂ꂽ�Ƃ������̂悤���B ���@�̑ΏۂƂ��Ă݂��ꍇ�A���R�ЂƂ̓��H�ɖʂ��ďo���邾�������̏Z�˂� ���݂��邱�Ƃ��o�ϖʂ���v�������B���������ĊԌ��̋������s���̒����Z�� ���蒅�����̂ł���B �Q�Sft(��7.32m)����̊Ԍ��̕W���I�����ł���B���̊Ԍ��̋�������A��̂��A �O��ɓ��A�Б��ɒʘH�ƊK�i�Ƃ����V���v���ȕ��ʍ\���ŏ㉺�ɏd�Ȃ��Ă���B ���������ċ@�\�ɂ��e�����̋��������Â����\���ɂ܂ŋy���A�e�K�̊e���� �͂ǂ�ȋ@�\�ɂ��Ή��ł���B ���̂��Ƃ��A�e���X�n�E�X�����Չ����A������ �����ЂƂ̗��R�ł���B���X�Ӑ}���ꂽ�킯�ł͂Ȃ����A������g�X�P���g���E �A���h�E�C���t�B���h�ɂȂ��Ă���B�s�S���̃e���X�ł́A�������I�t�B�X�ɓ]�p ����A���˂��Ԃ������Ċw�Z��z�e���ɂȂ��Ă���Ƃ��������B ���ł���Ԉ�ۓI�Ȃ̂��A���������J�[���Y�E�C���E�t�B�[���Y�Ƃ����n���̈�p �ɂ����u�W�����E�\�[���������فv�ł���B�R�O��㔼����ӔN�܂łS�O�N�����āA �R���̃e���X�n�E�X�����X�ɔ��������A�������������Ă��������\�[���̎��@�ł���B �W�����E�\�[��(1753�`1837)�́A���z�ƂƂ��Ă̎v�����A�V���v���ȃX�P���g���� ���ɋÏk����A���l�ȃC���t�B���Ŗ�������A�f���炵�����F�����`�����Ă���B�i���̎ʐ^�͒��H���j �i�ƂƂ܂��Ȃ�54�@0609�j | |

 | ||
|---|---|---|
| �Q�D�W�����E�\�[���������� ���H�̃T���h�C�b�`�������̃x���`�ŗF�l�ƐH�ׁA�߂��ɖʔ������z�����邩�� �ƁA�A��čs���ꂽ�̂��ŏ��̏o��ł������B ���̌����͗F�l�̎d����ɋ߂��A�����J�[���Y�E�C���E�t�B�[���Y�ł���A���̌��z�́A �����J�[���Y�E�C���E�t�B�[���YNo.�P�R�A�W������\�[���������قł������B �Ƃɂ�����Ȍ��z�ł������B �������x�݂��߂����āA���̍������Ă����A�E�F�X�g�~���X�^�[���@�̋߂��̃I�t�B�X�֖߂� �����Ă������z�ɂ��āA��i�������`�[�t�̃A�C�������h�l���z�Ƃɋ������Đ��������̂������Ă���B �ނ͊��ɁA�������f���炵����Ԃł��邱�Ƃ��悭�m���Ă����B �����h���̒��S���ɂ��褍s���₷���Ƃ������Ƃ������Ĥ���̌㉽�x�������^��� ���x�s���Ă��V��������������A�ŏ��̋�������߂邱�Ƃ͂Ȃ���s���x�ɂ��̖������ꂽ�B �������Ă���\�[���̑��̌��z�����悤�ƁA�����h���؍ݒ��ɃC���O�����h��s�A �s�b�c�n���K�[�E���C�i�[(���̍��̓C�[�����O�����}����)�A�_���b�`�E�A�[�g�E�M�������[ ���ςɍs�����̂�����W�����E�\�[���������ق̂悤�Ȋ����͉���������Ȃ������B ���̗��R�́A�ŏ��̓�͓����������Ȃ��������ƂƁA�����ĂR�Ƃ� ���Ȃ范�������ς���Ă��邱�ƁA�ɂ���B �W�����E�\�[���������ق͂����ɂ����قȌ����ł���B �����ق��������A���Ă͌��z�Ǝ��g�̏Z�܂��ł���A�܂� ���z�Ƃ��J���������z����̏W�听����Ȃ��i�ł����褂����������ɏW�߂�� | �Ă���c��Ȑ��̓W�����́A �ނ����N�ɂ킽���āA���z�Ƃ̖ڂőI�Ѥ�W�߂��ÓT���z�̈�Ղ̂�����A���z�ɊW�̂��钤���A �G��(�s���l�[�W������)�ł���B ����Ƀ\�[�����g�̍�i�̖͌^�A�h���[�C���O(���̑������A�s���l�[�W�̃C�M���X�łƂ�������A ���z�̌��z��J.M.�K���f�B�ɂ���ĕ`���ꂽ����)�A�܂�\�[���Ƃ������z�Ƃ̂��ׂĂ������� �W�߂��Ă���B �����āA�\�[���̎����猻��ɂ�����P���I�ȏ�̊ԁA�����قƂ��Ĉ�ʂɌ��J����Ă���Ƃ������� ���ꂾ���ł��A���|����Ă��܂��B �\�[���͂P�W�O�U�N(�T�R��)�A�W���[�W�E�_���X�Q���̌���āA���C������A�J�f�~�[�̋����ɂȂ����B ���̎��̍u�`�^���c����Ă��邪����̒��Ń\�[���́A�u���z�́A�G��⒤���̂悤�ɖ͕�̌|�p�ł͂Ȃ��A�����ɔ����̌|�p�ł���B �����Ă��̔����Ƃ����̂́A�l�Ԃ̐��_�ɂƂ��Ă����Ƃ�����ō��̐܂���Ƃł���B(�u�`�V)�v�ƌ����Ă���B �\�[���͓�����̃W���[�W�E�_���X�Q����A�O�̎���̌��z�Ƃ����A���o�[�g�E�A�_���A�W��������@���u�����̉e�����Ȃ���A ����ɓƎ��̃��H�L���u�����[�����A������J��Ԃ����g�̌��z�̒��Ŏg���A���W������B ���̃G�b�Z���X�Ƃ�������̂��A���̔����ق̋�Ԃɂ͋Ïk����A���x�̍����\�[�����z�̏��F�����`�����Ă���B |
 |
|
|---|---|
|
�R�D���z�ƃ\�[���̌`���ߒ� �����Ȍ��z�j�Ƃł���A�W�����E�\�|�������قْ̊��ł��������W�����E�T�}�\�\�����ɂ��A�\�[���̌o���́A ���̂悤�ɑ傫��5�̎���ɕ�������B �u��1���v�C���̎���P�V�V�U�`�W�O�i�Q�R�`�Q�V�j ��Ƀt�����X�̃l�I�E�N���V�V�Y������̉e������B �s���l�[�W�̃h���[�C���O���璼�ړI�C���[�W�����Ă���A �M�����i�g���C�A���t�@���E�u���b�W�j�̃f�U�C���ŁA���C�����E�A�J�f�~�[�̃S�[���h�E���_�����l�����A 1778�N����2�N�]��C�^���A�ɑ؍݂���B���̃C�^���A�؍݂́A�Ì��z���w�ԋ@����łȂ��A�\�[���ɂƂ��Ă��̌� �d�v�ȃp�g�����ɂȂ�l�X�Ƃ̏o��̋@��ɂȂ�B �܂����̒��O�̃s���l�|�W�i�P�V�Q�O�`�V�W�j�ɖʉ�Ă���B �u��2���v������������P�V�W�O�`�X�P�i�Q�V�`�R�W�j 1781�N�ɁA���̎��������p��������̃W���[�W�E�_���X�Q������̈˗��ŁA�j���[�Q�C�g�č��̍Č��̎d������`���B �i�\�[�����P�T�̎����߂ďC�s�̂��߂ɓ��������������W���[�W�E�_���X�������ł������B�j �\�[���̓_���X�Q�����瑽���̉e�������B�ӂ���͔N����߂��A �i�ӔN�ɂ͒��Ⴂ�����Ă��邪�j���̂悢�F�l�ł��������B �C�^���A�Œm�����g�[�}�X�E�s�b�g����̂����Ƃ���n�߂ɁA�\�[�����g�����������X�^�[�g�����A �����̏��K�͂ȃJ���g���[�n�E�X�̐v���s���Ă���B �����ĂP�T�l�̋����҂�}���ăC���O�����h��s�̌��z�Ƃ̃|�X�g���l������B�����҂̒��ɂ̓W�F�C���X�E���C���b�g�A �w�����[�E�z�����h�i�\�[���͂P�V�̂Ƃ��A�����ʂ̕s���������āA�z�����h�������Ɉڂ��Ă���j�AS�DP�D�R�b�J������ �����������������錚�z�Ƃ����сA���̏������ٗ�ł��������Ƃ�������B�C�^���A�Œm���� �g�[�}�X�E�s�b�g�ɏЉ�ꂽ�A���̎E�B���A���E�s�b�g�̗͂ɂ��Ƃ����ł������悤���B �u��R���v������������P�V�X�P�`�P�W�O�U�i�R�W�`�T�R�j �ł�����̑��������ŁA�\�[���Ɠ��̃��H�L���u�����[�̂قƂ�ǂ͂��̎����Ɋm������Ă���B �t�ł���F�ł��������_���X�ƁA�ł��𗬂�[�߂��̂����̎����ł���B �����ă\�[���ɂƂ��čő�̍K�^�́A�P�V�X�O�N�ɗT���Ȍ��Ǝ҂ł������A�Ȃ̔����W���[�W�E���C���b�g���S���Ȃ�A ����Ȉ�Y���p�������Ƃł���B �o�ϓI�ȐS�z���Ȃ��Ȃ�A���ςݎd�������Ȃ��čς݁A�܂��C���O�����h��s���n�߂Ƃ����悢�d���ɂ��b�܂�A ���z�ƂɂƂ��āA����ȏ�]�߂Ȃ��悤�ȁA���z�I�ȗ���ɂ����ꂽ�B �P�V�X�Q�N�Ƀ\�[���͏��߂Ď����̉Ƃ����Ƃ��ƁA�����J�[���Y�E�C���E�t�B�[���YNo�D�P�Q���w������B �ŏ��͉��z���l�������A���ǂ͌��Ē����ꂽ�B�����Ĕ����ق̎����i�ɂȂ��Ă���i�X�̎��W���X�^�[�g������B | �u��S���v�s�N�`�����X�N�̎���P�W�O�U�`�Q�P�i�T�R�`�U�W�j ���܂��܂Ȑh���������d�Ȃ��������ł���B �P�W�O�U�N�Ƀ��C�����E�A�J�f�~�[�̋����ɂȂ邪�A �����炭����Ɋ֘A���āA�_���X�Ƃ̒��Ⴂ���n�܂�B�����đ��q�����Ƃ̕s�a�B �P�W�P�T�N���q�̃W���[�W���G����ŕ��e�̌��z��ᔻ����L���\�����B�\�[���v�l�͂���܂ł��a�C�����ł��������A ���̋L�����������ɂȂ������̂悤�ɁA���T�Ԍ�ɕa�v����B ���̎����A�V�������H�L���u�����[�̔����͂Ȃ��A�����ɊJ�������A�C�f�B�A���A���s�N�`�����X�N�ɊJ�Ԃ����Ă���B ���p�I�ȖړI�ŁA��s�Ɏg��ꂽ�g�b�v���C�g���A���s�N�`�����X�N�Ȍ`�ő��p�����悤�ɂȂ�B �\�[���̍ō�����̂ЂƂł���A�_���b�`�E�A�[�g�E�M�������[�A �����ă����J�[���Y�E�C���E�t�B�[���YNo�D�P�R�i���݂̔����ٕ����j�́A���̎����̎d���ł���B �u��T���v�ӔN�@�P�W�Q�P�`�R�R�i�U�W�`�W�O�j �ǓƂȎ����B �ō��ٔ����i�P�W�Q�O�`�j�A�����@�i�P�W�Q�S�`�Q�V�j�A�t���[���C�\���Y�E�z�[���i�P�W�Q�U�j�A �Ȃǂ̑�K�͂Ȍ������z��v���Ă���A�����������͔��Ȕᔻ���邱�ƂɂȂ�B ���̎����ɂ͍ĂсA �i�\�[���I�ȐV�����f�B�e�[�����������Ăł͂��邪�j�l�I�E�N���V�V�Y���I�X���ɖ߂��Ă���B ���̎����͂܂��A�A���e�B�[�N���W�̍ŏI�i�K�ł���A�W�����E�\�[�������ق����̌`�Ɍ�������B �\�[���̊�{�I�ȃ��H�L���u�����[���J�ꂽ�̂͑�R���A���ɂR�W����S�T���̐��N�Ԃ̂��ƂŁA ���̌�̃s�N�`�����X�N�̎����ɂ́A������������W�������������Ƃ����A�\�[���� �u���g�̃X�^�C���̎��l�ł������B�v�ƃT�}�[�\���͌����B �����Ă��̎����\�[���́A �t�ł���F�ł������W���[�W�E�_���X�Q���Ƌٖ��ȊW�ɂ���A�_���X�Ƃ̓��c�A�����������̃��H�L���u�����[�� ���グ���Ƃ�����B�\�[���̃X�^�C���́A��l�̐l�Ԃ̎d���ł͂Ȃ��A��l�̂��̂ł���ƁB �������\�[���̓Ɠ��̐���������������������̂ł͂��邪�A�_���X�Ƃ̊W���Ȃ���A���̃X�^�C���͐��܂�Ȃ������B �\�[���������قɂ���\�[���̃f�U�C�����������o���ɂ́A�_���X�̃h���[�C���O�E�R���N�V�������[�߂��A �܂�Ő���̂悤�Ɉ����Ă����Ƃ����B ���ɁA��ŐG���\�[���̏d�v�ȃ��H�L���u�����[�ł���A�h�[���E�A���h�E�����^���̃��`�[�t���A�W���[�W�E�_���X�Q���� �e�����œW�J����A�������ꂽ���̂ł���B | |

 | ||
|---|---|---|
|
�S�D���H��-the poetry of architecture �u���̕������猩���郂�j�������g�E�R�[�g��~���[�W�A��(�h�[��)�̌i�F�A���܂��܂ȗ֊s���f���A�V��ɂ͂ߍ��܂ꂽ����p���A ���̌���ꂽ�X�y�[�X�Ɏ{���ꂽ�A���������f�U�C������̑��̂́A�z���͂��������āA ���z�̎�the poetry of architecture�����B�v�\�[���͎��@�̒��H���ɂ��Ă�������Ă���B �����ɂ́A�܂��\�[���̑�\�I�ȃ��H�L���u�����[�ł���h�[����A���h������^���̌`�ԃ��`�[�t���g���Ă���B ���̃��`�[�t���ŏ��Ɋ����x�̍������̂Ƃ��Ď��������̂ͤ�C���O�����h��s�̃X�g�b�N��I�t�B�X�ł���B ���^�ɂȂ����̂̓_���X�̃M���h�z�[���̎s�c��c��(1777�`78)�ŁA�l�p�̕����Ƀy���f���e�B���ɂ���āA �h�[�����ڂ蒸�����J��(�I�L�����X)�ɂȂ��Ă���B ������̃q���g�́A�C���O�����h��s�̃\�[���̑O�̌��z�ƁA ���o�[�g��e�C���[���ɂ��A��s���̃��f���[�X�g��A�j���C�e�B�[�Y��I�t�B�X�����A�����ł͓V��̓t���b�g�ɂȂ��Ă���B �\�[���̃X�g�b�N��I�t�B�X�ł́A������y���f���e�B�����L�сA���̏�ɉ~����̃N���A�X�g�[���[�������āA �h�[�����ڂ��Ă���B �_���X��e�C���[�̋�ԂƈႤ�Ƃ���́A�y���f���e�B�����x������4�{�̒����A�ǂ��畂���Ă��āA�X�y�[�X�E�C���E�X�y�[�X �̍\���ɂȂ��Ă���Ƃ���ł���B �V��ɂ���Č��肳���X�y�[�X���A�����̎l���̕ǂ��痣����@�́A�\�[���̌����ɑ�������������ŁA ���̒��H���ł��A����ɂ���ďo����X���b�g�ɁA�g�b�v���C�g����̌��𗎂Ƃ��A�ǂɃo�E���h�����Ă���B | �N���v�g(�n���[����)��������у~���[�W�A��(�h�[��)���A�ǂ��畂�����S�{�̒��Ŏx�����ꂽ�A �X�y�[�X�E�C���E�X�y�[�X���`�����Ă���B �C���O�����h��s�̃X�g�b�N�I�t�B�X�ɖ߂�ƁA�����炭�X�P�[���_�E�������@�Ƃ��āA�y���f���e�B���ɂ͎ȏ�̍��݂��A ���ɂ������̍��݂������Ă���B �܂��y���f���e�B�`���̒��S�ɂ̓p�e��(�~�`�̕������葕��)���A �����ăO���[�N�E�t���b�g�ƌĂ��A�i���[�����̊�̉��ɂ���͗l�Ɏ����j���l��������B ���̕��l�̓\�[���̌����ɌJ��Ԃ������B �����͌����ȌÓT����̕��@����́A��������E���Ȃ���A�\�[���̌l�I�e�C�X�g�ɏ]���Č���Ă���B ���̂Ƃ��������ꂽ���`�[�t���T�}�[�\�������A�h�[���E�A���h�E�����^���ƌĂԃ��`�[�t�ł���B �T�}�[�\�����̐����ɂ��A���̃��`�[�t�ɂ̓|�W�ƃl�K�������āA���҂Ƃ��ɁA �\�[���̐��U�ɂ킽���i�ɌJ��Ԃ��g����̂ł���B �|�W�̂ق��Ō����A���܂łɌ����悤�ɔ����ق̒��H���A �C���O�����h��s�̃X�g�b�N�I�t�B�X�̑��ɁA�C���O�����h��s�̃R���\�����������A�I�[���h�E�f���B�f���g�E�I�t�B�X�A �s�b�c�n���K�[�E���C�i�[�̃p�[���[�A�R�[�g�E�I�u�E�G�N�X�`�F�b�J�[�A�t���[���C�\���Y�E�z�[���ȂǁA��������̗Ⴊ����B �l�K�̗�́A�_���b�`�E�M�������[�̗�_�̉����̒����A�v�l�̐������Ƀf�U�C�����ꂽ�\�[���̕�A �s�b�c�n���K�[�E���C�i�[�̃Q�[�g�̒����Ȃǂł���B�����l�K�̒����ɂ͂���ɂ��̏�ɁA ���ُ�̃��`�[�t���K���ڂ��Ă���B | |
| �T�D�_���b�`�E�A�[�g�E�M�������[-lumiere mysterieuse �P�V�V�U�N�Q�V�̂Ƃ��A���C�����E�A�J�f�~�[�̃S�[���h�E���_����_���āA�M�����̃f�U�C����i�߂Ă������ɁA ���Ԃ̒a���j�Ƀe�[���Y��̏M�Ńp�[�e�B�[���Â��Ƃ����A�U�������������A�\�[���͋Ζ����ԊO�����j�����A ���̏����ŖZ�����A���̗U����f�����B�s�K�Ȃ��ƂɁA���̃p�[�e�B�Œ��Ԃ̈�l���M�����Ă��܂��B ���̂��ƃ\�[���̓S�[���h����_���������l������̂����A���̎����ɂЂǂ��S��������A ���̗F�l�W�F�C���Y�E�L���O�̂��߂� �揊�̃f�U�C��������Ă���B ���̌�A�\�[���͎��ʂ܂ŁA���Ɋւ���f�U�C���𐔑����c���Ă���B �s�b�c�n���K�[�E���C�i�[�̃��C�u�����[�́A�A���e�B�[�N�̍��ق��A�����̎l���̕ǂ̃j�b�`�ɁA�������Ɣ[�߂��A �p�[���[�ɂ́A�g�F�̌������ɃA���e�B�[�N�̍��ق������Ă���B �����J�[���Y�E�C���E�t�B�[���Y�̎��@�̒n�K�ɂ��A�n���[����(�N���v�g)��n����n(�J�^�R�E��)�Ƃ���������������B �_���b�`�E�M�������[�̃R���N�V�����̓p������p���ɓn���Ă����m�G���E�f�U���t�@���Ƃ��� �A�[�g��R���N�^�[�̎c�����R���N�V������ ��Y�ɂ���Đ��藧���Ă���B �f�U���t�@���̎���A�ނɔ삳��Ă����X�C�X�o�g�̉�ƃt�����V�X��u���W���A�����A�f�U���t�@���̈⌾�ɏ]���A �����h���̃V���[���b�g�E�X�g���[�g�ɁA�\�[���Ɉ˗����ė�_�����Ă��B �\�[���Ƃ̓��C������A�J�f�~�[�ł��݂��Ɍ��m���Ă����̂ł���B ���̗�_����͂�h�[���E�A���h�E�����^���̃��`�[�t�ŁA��̃_���b�`��M�������[�̗�_�̌��^�ɂȂ��Ă���B �_���b�`��M�������[��K�ꂽ���ɁA���ۂɃK���X�z���Ɍ�����_�����́A��2�����ŋ�P�ɂ����āA�C���͂���Ă������A �啪�v�A�[�Ȉ�ۂł������肵���B ����ɑ��ăK���f�B�[�̕`�����V���[���b�g�E�X�g���[�g�̗�_�h���[�C���O�͑f���炵���A ���̓�����̕\���ŋ�Ԃɗ}�g��^���Ă���B | �v�����Ō���ƁA�ǂ�����قǂ̃����^���́A�U�{�̉~���ƂQ�{�̕t���Ɏx�����ꂽ�h�[���ɂ͂Ȃ��A ��������O�ꂽ�����ɐΊ���������A�ォ��̌��������Ă���B �F�K���X���g�������F�̌��ŁA������̃h�[�����͂ނ��딖�Â��A �A�[�`���Č���������ɗ���Ă���悤�ȍ\���ɂȂ��Ă��āA�����ق̒��H���̕Ǎۂ̌��̗��Ƃ����Ɏ��Ă���B �����ڌ������A�ǂɔ��˂����Ȃ���A�������A��ԂɉA�e��^����h���}�`�b�N�Ȍ��̈����́A �\�[���̂��̌�̌����ɂ����т��ь����B�K���f�B�[�̕`���h���[�C���O�ɂ́A���̌��ʂ���������ĕ\�������B �����lumiere mysterieuse�Ƃ������t�ŕ\������Ă���B �_���b�`�E�A�[�g�E�M�������[�̓\�[���̌����̒��ŁA�ł��I���W�i���e�B�̓x���������������������z�ŁA �v����������ƁA���F���`���[������т����ȁA�ǂ̑w�\���������A��_�̓A�[�e�B�L�����[�g����āA ���E�̗����L�сA�}�g�̌������\�������Ă���B ����͗��ʂɂ����f����āA�ǖʂ̉��ʁA�ǂ̍����̈Ⴂ�ŁA�A�[�e�B�L�����[�g���ꂽ�\��L���ȍ\���ɂȂ��Ă���B ���ɃX�J�C���C���́A���܂��܂ȓˋN�ŁA�L���ȕ\��������āA �W�����E���@���u��(1664�|1726)�ƃj�R���X�E�z�[�N�X���[�A(1661�|1736)���v�����u���j���{(1724)���霂Ƃ�����B �\�[���̓W�����E���@���u�����h���Ă���A �u�`�^�̒��ŁA���z�̐��E�̃V�F�[�N�X�s�A�ł���Ə^���Ă���B ���傤�ǃ_���b�`�E�M�������[��v���Ă��鍠�̍u�`�ł��A �u�����Ɋւ��ẮA���̍��Ŕށi���@���u���j�ɕ��Ԑl�͂��Ȃ��B��_�Ŏ��R�ȋ�z�́A �ނ̍�i�̂��ׂĂ͌���Ȃ����l���ɕx�݁A���ꂼ�ꂪ��������i�������Ă���B�v�ƌ����Ă���B �T�}�[�\�����̓��@���u���̃V�[�g���E�f�����@������̉e�����w�E���A���܂��܂ȍ����́A ���܂��܂ȓˋN�̑g�ݍ��킹���A���̃_���b�`�E�M�������[�ŁA�������Ă���A ���������������������z�̓\�[���̎���ɂ́A�\�[���̌��z�ȊO�ɗႪ�Ȃ��ƌ����B | |
|
�U�D�h�[���|�\�[�����Ǝ��̑��� �\�[���́A�P�V�X�Q�N�ɍŏ���No�D�P�Q���w�����A ������ނ̌����ɌJ��Ԃ������q�g�f�̌`���������`�[�t�̓V��̒��H����������B ���̌�P�W�O�O�N�ɂ̓C�[�����O�̃s�b�c�n���K�[�E���C�i�[��ʑ��Ƃ��čw�����A��������Ē������B ����ɂ͓�l�̑��q�ւ̌|�p����̈Ӗ����������Ƃ����B ���������ă����J�[���Y�E�C���E�t�B�[���Y�ł̓����́A�啪�Ԃ��āA�P�W�O�W�N�ɂ���B ���̔N�\�[����No�D�P�Q�̌��̕�����No�D�P�R�ɐL���A�����Ƀh�[���i�~���[�W�A���j�ƌĂ�镔����������B ��ɐG�ꂽ�悤�Ƀm�G���E�f�U���t�@���̎���A���̈�u�������āA�u���W���A�́A �V���[���b�g�E�X�g���[�g�̉X�̐ՂɃ\�[���Ɉ˗����A�揊���������B ����ɖ�������Ƃ����A�f�U���t�@���̂��� �A�C�f�B�A�ɉe�����āA�����ق̃h�[���ƌĂ�镔���̒n���ɂ́A�ŏ��A�g��_�h�Ƃ����������}�ʂɂ͏�����Ă����Ƃ����B ��ɂ��̎����͏��������A�h�[���ւ̂��̐��i�t���͍Ō�܂Ŏc�����B �\�[���̌����̂��߂ɁA�L���ȃC���[�W�̃h���[�C���O�𐔑����c����J�EM�K���f�B�́A�\�[���Ƃ͑ΏƓI�� �ߎS�Ȑl���𑗂����B�i���̂��Ƃ̓W�����E�T�}�[�\�����̖����u�V��̊فvSD�I����ؔ��V��́J�i�EM�K���f�B�̌��z���̏͂ɏڂ����B�j ���̑���Ȑl���f���Ă���̂��ǂ����͕s�������A�ނ͓��A��n������i�J�^�R���u�j�ɔ��ȋ���������Ă����B �ނ̓W�F�C���Y�E���C���b�g�̒�q�ł��������̂P�V�X�O�N�ɁA�u�P�̕���v�Ƃ����h���[�C���O�� ���C�����E�A�J�f�~�[�ɒ�o���Ă���A�P�W�O�O�N�ɂ́u����̎��v�A�P�W�O�Q�N�ɂ́u�n���̎��@�v�A �P�W�O�S�N�ɂ́u����̓���v�A�����ĂP�W�R�W�N�Ɂu���S���̌Ñ��n�v�����ꂼ��o�i���Ă���B ���̒��_�Ƃ����ׂ��h���[�C���O�́A���݂q�h�a�`�ɕۑ�����Ă���u�}�[�����̕���v�i�P�W�P�T�N�j�ł���B �\�[���͎��Ȃ��������A���̍�i�̓\�[���ɑ���ꂽ�����̂������B �u�嗝�͐��炩�ɋP���A�����ɂ͑��z�͎˂����܂��A���悻�̂��̂����A�S�̂��Ƃ炷�B�v | ���̃C���[�W�̓\�[���ɑ���ȉe����^�����B �P�W�P�V�N�G�W�v�g���̎��w�����[�E�\���g�̕ی�̉��ɁA�x���]�[�j�Ƃ����l���Z�e�B�ꐢ�� ��Ԑp�i�A���o�X�^�[�j���̐Ί��������B �\���g�͂P�W�Q�P�N�ɃC�M���X�ɉ^�сA��p�����قɐݒu�������A ���{���������x�������Ƃ��Ȃ������̂ŁA�Q�N��ɂ̓\�[���̏��L����Ƃ���ƂȂ�A�\�[���͂�����A ����̃h�[���̉��A�N���v�g�ɐݒu�����B �K���f�B�̃C���[�W�ɐG�����ꂽ�\�[���́A���̌����A���o�X�^�[�̐Ί��̒��Ƀ����v��u���āA �u�}�[�����̕���v�̃C���[�W�����o�������B �T�}�[�\�����́u�W�����E�\�[���Ǝ��̑���v�i�`�q�P�X�V�W�N�R�����j�̂Ȃ��ŁA���������\�[���� ���z�Ǝ��̑���Ƃ̌��т��A���邢�͎������A�����������Ă���B �\�[���ɂ͑��ɂ��u�s�b�g�L�O��v�Ƃ������Ɋ֘A�����d�v�ȍ�i������B�E�C���A���E�s�b�g�̋L�O��ŁA �Q�K�����̏��ɉ~�`�̊J��������A���̏�̃g�b�v���C�g����ʼn��K�ɂ܂ŁA�����~�蒍���A �u�g���r���[���v�ƌĂ��c���̋�ԍ\���ɂȂ��Ă���B ���̍\���́A�e�B�����K���̃J���g���[�n�E�X�i�P�V�X�R�|�P�W�O�O�j�̃G���g�����X�z�[���ɂ��g���� �i�����ł͊J���͑ȉ~�`�ł���j�B �W�����E�\�[���������ق̃h�[���́A���̊J�����~�`��ȉ~�`�ł͂Ȃ��A�傫����t�ɊJ����Ă���̂ŁA ���m�ɂ͑��̂��̂Ƃ͏����قȂ邪�A�c���̋�ԍ\���͈�A�́u�g���r���[���v�̂ЂƂ̔��W�`�ƌ�����B ���̃h�[���̋�Ԃ̃K���f�B�ɂ��h���[�C���O�́A�l�I�N���V�V�Y���̃L�[���[�h �u�T�u���C���i�s��ȁA�����ȁj�v�Ƃ������t��z���o������A�\�[���̈Ӑ}�������Ɖe�A �s��ȃX�P�[�������g�債�Ă݂����A�f���炵���h���[�C���O�ł���B �g�b�v���C�g����̌��ƁA �A���e�B�[�N�̃R�[�j�X�̒f�Ђ́A�w��ɉB���ꂽ��������̊Ԑڌ��ɂ���āA �h���}�e�B�b�N�ȕ\���^�����Ă���B �����ꖇ�ʂ̊p�x����̃h���[�C���O�ł́A ���́A�n���̃N���v�g�ɂ����������A�ǂɂ�����ꂽ�����̃A���e�B�[�N�̔j�Ђ� �������āA���G�ȉA�e����肾���Ă���B�����������Ɖe�̗V�т����A�\�[���̏d�v�Ȏ��ł������B |
|
�V�D�\�[������w�Ԃ��Ɓ|���I�v���|�[�V���� ���@�������ق̒��H���ƃh�[���𒆐S�ɁA�h�[���E�A���h�E�����^���ƃg���r���[���Ƃ����A �\�[������R���ɑn�삵�A���̌�J��Ԃ��g�����A�Q�̋�ԍ\���̃��`�[�t�ɂ��Č��Ă����B �\�[���̌��z�͂قƂ�ǑS�āA���̂Q�̃��`�|�t�̃��@���G�[�V�����ŏo���Ă���ƁA �������قǁA�ނ͂����ɌŎ����������B ���̂Q�̃��`�[�t�ɁA���ɂ����邢�����̃\�[�����L�̃e�C�X�g��������āA�\�[���̌��z�͏o���Ă���B �P�D�X�y�[�X�E�C���E�X�y�[�X ���H���A�h�[���A�X�g�b�N�E�I�t�B�X�Ō����悤�ɁA���ł����܂�A�h�[���̂��������X�y�|�X���A ���̒��œƗ����āA�������X�y�[�X�ɂȂ��Ă���B���邢�͔����ق̃t�@�T�[�h�̂悤�ɁA ��v�ȍ\�����̕\�ʂɂ����ꖇ�̕ǂ����āA�������w�\��������B ����̓_���b�`�E�A�[�g�E�M�������[�̗ɂ��݂���B ���C�X�E�J�[����A���F���`���[���⃀�[�A�ɂ������悤�Țn�D��������̂͂����炭 �\�[���̉e��������Ǝv����B �Q�D�B���ꂽ��������̌� ����ɂ���āA��ɐG�ꂽ�悤�Ƀ\�[���̍���ԂɌ��I�Ȍ��ʂ������炵�A lumiere mysteriseuse�ƌĂ��B �B���ꂽ��������A��ԂɌ����A���܂����Ȃ��瓱����������́A��͂胋�C�X�E�J�[�����ӎ��I�Ɏg���Ă���B �܂��g�b�v���C�g�A�����ĐF�K���X�B����ʖʋ����g�����A���ƉA�e�̗V�сB �R�D���̑���ւ̂������ ���̎���ɑ�ʂɔ�������A�����A��ꂽ�A���e�B�[�N�̕i�X����̉e���ƁA �l�I�E�N���V�V�Y���́g�T�u���C���h�g�s�N�`�����X�N�h�̊T�O�ƌ��т����e�C�X�g�ŁA �\�[���̐��U��ʒꂵ���e�[�}�ɂȂ��Ă���B | �S�D�ÓT���@����̈�E�A���ʐ� �����炭�͑��̌��z�Ƃ���̔ᔻ�̑Ώ̂ɂȂ����v�f�ŁA������W���[�W�E�_���X����̉e�����傫���B ���ʐ��̓��_�j�Y���ɒʂ���B���ʐ��ɂ͐荞�܂ꂽ���I�ȑ����ɂ��A�Ǝ��̃X�P�[���_�E���̎�@���t�������B �T�D�X���v���|�[�V���� �ӎ��I�Ƀv���|�[�V�������O�����Ƃ́A�\�[���̌��z������t����傫�ȓ����ł���B �u�`�^�̒��Ń\�[���́A�v���|�[�V�����̃Z�I���[�Ƃ������̂́A�K�ł��A�L�p�ł��Ȃ��ƁA�������Ă���B �����ČÓT���z�̕��@�̃v���|�[�V���������E���A�\�[���Ǝ��̃v���|�[�V�������̗p����B ����܂��_���X����̉e�����ŁA�\�[�����m�M���Ă��������̂ł���B �T�̌ÓT�I�v���|�[�V���������E�A�Ǝ��̃v���|�[�V�����ւ̌Ŏ��́A ������̌��z�̌ÓT���@�ւ̂�����肪�w�i�ɂ��������炱���A���ꂩ��̈�E���Ӗ����������킯�����A ���ꂾ���ł͂Ȃ��A�����ꂽ�`�Ԃ��O���A���������́A���ꂢ�ȃv���|�[�V�����A���ʂ�����ӎ��A ��ʓI�Ȕ��̊��o���O���āA�ӎ��I�Ɉ�E�����A�X���Ƃ�����悤�ȕ������u�����A �l�I�ȃe�C�X�g�ɒu��������\�[���̎p���́A���ł��A�ƂĂ����͓I�Ŏ����I���Ǝv����B ���ʍ��ōl������悤�ȃv���|�[�V�����ŏo���Ă��Ȃ��Ƃ��낪�A ���邢�͂����ǂ߂Ă��܂��悤�ȒP��̃X�g�[���[�ŏo���Ă��Ȃ��Ƃ��낪�A ���x�K��Ă��V��������������A�l��O�������Ȃ��A�\�[�������ق̖��͂ɂȂ��Ă���̂��Ǝv���B �����ł͂��܂��܂ȓǂݕ����\�ɂ���悤�ȁA���l�ȑ��삪�s���A �\�[���Ƃ������z�Ƃ̓�������������B �W�����E�\�[���������ق�K���ƁA��Ɍ��z�������A�����錚�z�̘g�����E���A ��Ɏ����̃e�C�X�g�ɒ����ł������\�[���A���̌��z�ς��A�����邱�Ƃ��o����B�i�J����No98�@8510�j |
|
|
|
|---|---|
| �X.NICHOLAS HAWKSMOOR(1661�`1736) �j�R���X�E�z�[�N�X���[�A�|���[�}�ւ̓��ہ\ �P�D�L���b�X���E�n���[�h �p���̌��z������HKPA�A������GLC�œ�����3�N�����o���āA���낻����{�ɋA�낤�Ǝv���Ă������A�F�l�Ƒ��ƈꏏ�ɃX�R�b�g�����h���s�ɏo�|�����B ���̓r�����[�N�ߍx�̃L���b�X���E�n���[�h�ɗ�������B1975�N�̂��Ƃł���B �j�R���X�E�z�[�N�X���[�A�̃L���b�X���E�n���[�h�ɂ͑O�X����@�����A����s���Ă݂����Ǝv���Ă����B �L���b�X���E�n���[�h�́A�s��ȃJ���g���[�E�n�E�X�ŁA�܂��A���̕~�n�̑s�傳�ɋ��������(�~�n��1000�G�[�J�[�A��405���u�Ƃ���)�B ������s��ȕ~�n�Ɍ��z�����ꂽ��ǂ�ȂɋC�������������낤�Ƃ܂��ŏ��Ɏv�����B �������q����A��Ă̗��s�ŁA���̖ړI�n�ւ̃X�P�W���[�������莞 |
�Ԃ������Ă����̂ŁA�뉀�Ɍ���̓_�i�A ���@���u���̃e���v���ƃz�[�N�X���[�A�̃��[�\���E�������邽�߂ɁA�F�l��2�l�ŎŐ��̒뉀�𑖂����B �Ƃ��낪�A�����Ă������Ă��Ȃ��Ȃ��ړI�̏��ɂ����A�뉀�̑s�傳�����������B���[�\���E���͌��Ǎ����ċ߂��ɂ͊�ꂸ�A �������璭�߂�݂̂ł��������A�N���̂���L��ȎŐ��A�����ē_�݂��鏬���ȐX�̉��ƂȂ������̏W���A �ג����ɂ�����Α��̋��A�����Ĕw�i�ƂȂ��̐��A���炦��ꂽ�s�N�`�����X�N�ȕ��i�̒��ɂ����āA �Î�ȃ��[�\���E���̎p�ɂ́A�����̂�Ō��Ƃ�Ă��܂����B���̃��[�\���E���́A�L���b�X���E�n���[�h�̌��z�Q�̒��ł��A ����̂��̂ŁA���@���u���S����A�z�[�N�X���[�A1�l�̐v�Ɉ˂�B �@�َ��̂̓W�����E���@���u����(1664-1726)���z�[�N�X���[�A���A�V�X�g����`�Őv���ꂽ�B |

|
|
|---|---|
|
���@���u���̓z�[�N�X���[�A���3�ΔN���ŁA1664�N�A�x�T�Ȑ����Ǝ҂̑��q�Ƃ��ă����h���Ő��܂ꂽ�B ���e�̓t�����_�[�X����̖S���ҁA��e�̓_�b�h���[�E�J�[���g�����̖��A���̗��e�̌��A �a�m�Ƃ��Ĉ�Ă��A22�̎��Ƀn���e�B���g�����݂̘A���ɎQ�������B �A������߂���A�t�����X�ŃX�p�C�e�^�őߕ߂���A3�N����������A�o�������Ƃ��͂Q�X�ɂȂ��Ă����B �o�X�e�B�[���̘S���ɂ��鍠����Y�Ȃ������͂��߁A�ߕ���A�E�B�b�g�ɕx�쌀�u���v��1696�N�A 32�̎��ɁA�u���𗧂Ă����[�v�Ƃ����������̔N�ɏ㉉���ă����h���q�������Ƃ����B ���̌�1700�N�A1704�N�A1705�N�ɂ�����ɋY�Ȃ��㉉���A���̐���10�{�ɂ��y�B���̃E�B�b�g���D�܂�A �z�B�b�O�}���̃N���u�A�L�b�g�E�L���b�g�E�N���u�ɉ���Ƃ��Č}�����A�����ŃL���b�X���E�n���[�h�̈˗��҂ł���J�[���C�����݂ƒm�荇�����B �J�[���C�����݂́A���łɃ`���b�c���[�X�ȂǃJ���g���[�E�n�E�X�̐v�ɒ�]�̂��錚�z�ƃE�B���A���E�g�[���}��(1650-1719)�ɁA �L���b�X���E�n���[�h�̐v���˗����Ă������A��V�̌��Ȃǂœr�����܂������Ȃ��Ȃ�A���܂��ܒm�荇��������܂łɌ��z�o���̂Ȃ��A �Ⴂ���@���u���ɔ��H�̖���Ă�ꂽ�B���@���u����35�̎��ł���B |
���z�̌o���̂Ȃ����@���u�����A�V�X�g�����̂��A�j�R���X�E�z�[�N�X���[�A�ł���B �z�[�N�X���[�A�̌o���́A���@���u���Ƃ͑ΏƓI�ł���B�m�b�e�B���K���V���[�̔_�Ƃɐ��܂�A�ŏ����[�N�V���[�̔����̏��L�����Ă������A �����ȍ����E�l�̏Љ��18�̎������h���ɏo�āA���z�ƃN���X�g�t�@�[�E������(1632-1723)�̏��L�ƂȂ�B 21�̎��ɂ͂��łɃ����̃`�F���V�[�a�@�̐v����`���悤�ɂȂ�B1680�N��ɂ̓����h���̋���̎d���ɏ]������B 1689�N�ɂ̓n���v�g���E�R�[�g�̐v�̐ӔC���闧��ɂ���A1691�N�ȍ~�Z���g�E�|�[���吹���������̏���Ƃ��Ď�`���B �L���b�X���E�n���[�h�ɂ����āA���@���u���̃A�C�f�B�A�͌o���L���ȃz�[�N�X���[�A�ɂ���Č`�ɂ���f�B�e�[���̓��t�����{���ꂽ�B ���@���u���ƃz�[�N�X���[�A�͊K����������o�����S������Ă����B ���@���u�����@�q�ɕx�݁A�ϋɓI�Ȑ��i�ł������̂ɑ��A �z�[�N�X���[�A�͋C�ނ��������A�C�܂���ŏ��ɓI�Ȑ��i�ł������B2�l�̊K�����́A ���@���u���̎��܂�2�l�̃p�[�g�i�[�V�b�v�𑶑�����������̑傫�ȗ��R�̂悤�ł���B |


|
|
|---|---|
|
�o������������̂ǂ̕��������@���u���ŁA�ǂ����z�[�N�X���[�A�ł��邩�����ʂ���̂́A�s�\���낤���A
�܂����܂�Ӗ��̂��邱�Ƃł��Ȃ��B���@���u����Ƃ�����L���b�X���E�n���[�h�̃e���v���E�I�u�E�U�E�t�H�[�E�E�B���Y(�l����)��A
�V�[�g���E�f�����@����A�z�[�N�X���[�A�̃��[�\���E���i��}���j��A�X�s�g���t�B�[���Y�̃N���C�X�g�E�`���[�`�i��}�E�j
�Ȃǂ̃����h���̘Z�̋���̑��A
�e�X�̓Ǝ��̎d��������ƁA��̂̑z���͂ł���B����ɂ��Ă��A2�l�����ɑ�z�������z�Ƃł��������Ƃɂ͊ԈႢ���Ȃ��B ���z�j�ƃW�����E�T�}�[�\�����ɂ��A���@���u���ƃz�[�N�X���[�A�͂��݂��ɂ��ꂼ��̒m���ƓƑn�����n�m���Ă��āA ����������c�_���d�˂Ȃ���n���Ă��������̂ŁA�X�̕����ɂ��Ă̍v���x�����邱�Ƃ͂ł��Ȃ��ƌ����B |
�W�����E���m���ƃ|�[���E�}�b�J�[�g�j�[�̋�����Ƃɂ������v�ߒ����������Ƒz������̂��y�����B �ނ̐���ł́A�L���b�X���E�n���[�h��u���j���E�p���X�̍\���̐V�����́A�����炭���@���u���̂��̂ŁA ���̃��@���u���̖`���ɓK�ȕ\����^�����̂��z�[�N�X���[�A���ƌ����B ���Ƀz�[�N�X���[�A�͊w���I�ŁA���z�̂�����\�[�X�E�u�b�N�ɖ��邭�A �p�����z�ɂ��Ă̒m�����L�x�ŁA�����̌��z�I�ȈӖ����Ĕ������Ă����B �Ƃɂ������@���u���ƃz�[�N�X���[�A�Ƃ����A�����̈Ⴄ2�l�̓V�˂��������āA�L���b�X���E�n���[�h��v���j���E�p���X �Ƃ����f���炵�����z���������̂ł���A�ǂ��炩1�l�������Ă͂�����̌���͑��݂��Ȃ��������͊m���ł���B |
 
|
|
|---|---|
�R�����E�L�����x����1715�N�ɉp���̌ÓT��`���W�߂ďo�ł����g�p���̃E�B�g���E�B�E�X Vitruvius Britannics�h �ɔ[�߂�ꂽ�}�łł́A�L���b�X���E�n���[�h�́A�����Ƀz�[���ƃT�������c�ɏd�Ȃ�A �T�����̗����ɓ����ɃA�p�[�g�����g�ƌĂ�镔�������ԁB �����Ėk���ɂ͓��������L�тāA ���ꂼ��L�b�`���E�R�[�g(�~�[�̒���j�ƃX�e�C�u���E�R�[�g(�X�ɂ̒���)�ƌĂ�钆����͂T�[�r�X�����̌����Q�������Ă���B �R�[�g���͂ޓ�̃u���b�N�̐^���ɍX�ɃO���[�g�E�R�[�g������A�S�̂��w�ǃV�����g���J���ɍL�����Ă���B �엧�ʂ��݂�ƒ��S�̃z�[���ƃT�����̕�����2�w���̍����ɂȂ��Ă��āA�A�p�[�g�����g�̕�����1�w���̍����ɂȂ��Ă���B ���̒����ɂ̓h�[�����̂��Ă���B ���̍������v�Ńz�[�N�X���[�A���ւ��̂���O���j�b�`�E�z�X�s�^����Z���g�E�|�[���吹���̃h�[���̃f�U�C�������܂������ŁA �p���ɂ������K�͂Ȃ�����h�[���E�A���h�E�����^���i�����^���Ƃ͎��͂ɊJ���̂���~�`�܂��͑��p�`�̏����ŁA�h�[���≮���̏�ɍڂ��Ă���j �̍ŏ��̗�ŁA���̃��`�[�t�͉p���̎��I�ȓ@�قł̓L���b�X���E�n���[�h�ɍŏ��Ɍ��ꂽ�B �L���b�X���E�n���[�h�̌��݂́A�P�V�O�P�N�ɃX�^�[�g�����B�P�V�P�S�N���ɒ������Ɠ����̗����y�уL�b�`���E�R�[�g�͊��������i�K�ŁA�J�[���C�����݂̋����� �뉀��A�v���[�`�Ƃ������O���Ɉڂ��Ă��܂��A�����ɂ͎肪�t�����Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B ���݂̐������ł����̂́A���@���u����z�[�N�X���[�A�̎���A�J�[���C�����݂̋`���̑��q�g�[�}�X�E���r���\�����ɂ���Ăł���A �g�p���̃E�B�g���E�B�E�X�h�̐}�łƂ͑����Ⴄ���̂ɂȂ����B �����̐������́A�g�[�}�X�E���r���\�����ɂ���āA�P�V�T�R�N����P�V�T�X�N�̊ԂɊ������Ă���B |
�ނ̓z�[�N�X���[�A�����[�\���E�������ĂĂ��鍠�ɂ��A�J�[���C�����̑��k���ƂȂ�A���@���u���A�z�[�N�X���[�A�̐v��
���܂��܂ȉ��ς������Ă���B ���݈�ʌ��J����Ă��镔���̃G���g�����X�́A���̃��r���\�����ɂ�鐼���̖k���ʂɂ����āA�G���g�����X�����Ƃ����ɑ�K�i�������� �����ɓ�����Ă����B���̂�����̋�ԍ\���́A���@���u���A�z�[�N�X���[�A�ƈႢ�͂��邪�A�Ȃ��Ȃ��s��ł����\���ł������̂��o���Ă���B �Ȃ�Ƃ����Ă������Ȃ̂͒������̃z�[���ł���B���ʂ͂T�Q�����i��P�T�D�W���j�����̐����`�Ȃ̂ɑ��āA�V�䍂���V�O�����i��Q�P�D�R���j������B ����Ȓg�F�A�A�[�`�̏d�Ȃ�A���|�I�ȁA�����̃W���C�A���g�E�I�[�_�[���x������y���f���e�B�u�A�����ăh�[���ɂ͍�������̌����������āA �h�[���ɕ`���ꂽ�A�S���̔n�A�n�ԁA�����Ԑl�A����炪�_�̏�ɕ��V���Ă���A���邢�F�ʂ̊G���A�h�[�����̂��y���ɕ��V�����Ă���悤�� ��ۂ�^����B�W���C�A���g�E�I�[�_�[��g�F�Ȃǂ̏d�ʊ��ɂ���āA�]�v�Ƀh�[���̌y�₩������������Ă���B ���łȂ���A�嗝�̂悤�Ɍ�����g�F�́A���̓X�J���I���ƌĂ��A�p�ɑ嗝�ΕЂ܂��͒��F�܂��������͑��嗝�ŏo���Ă���A�p���ł͊��Ə����̗�ŁA ���̌㕁�y���đ����p����ꂽ�Ƃ����B ���̃z�[���̓u���j���E�p���X�̃z�[���ɔ�ׂĂ��A�s��Ől����������֑�ϑz���I�ȋ�ԑ��삪����A���̕����͂̓u���j�����ʔ����Ǝv�����L��������B �u���j���̊O�ςɌ����͓������A�L���b�X���E�n���[�h�ł͓����ɁA�u���j����苭���\������Ă���C������B �\���}�g�p���̃E�B�g���E�B�E�X Vitruvius Britannics�h ���L���b�X���E�n���[�h�A�E�u���j���\ |
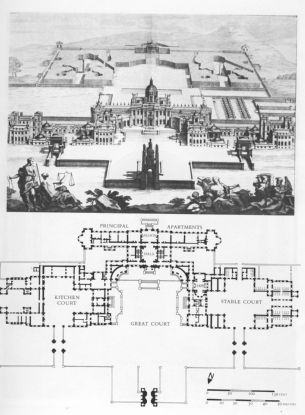 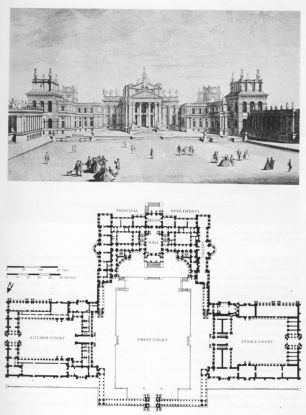
|
|
|---|---|
|
�Q�D�u���j���E�p���X �@���@���u���́A�L���b�X���E�n���[�h�̐v���˗����ꂽ���N�A�J�[���C�����ɂ���āA ���z�ǂ̊č����ɔC�����ꂽ(�O�C�҂̃g�[���}���͉��ق���Ă���)�B���i���Ȃ��܂܂Ƀ����̓����ɂȂ����̂ł���B ���̌�g�[���[�}���ނ���ꎞ�č������D�������A�A�������̎���A�E�ɕ������B 1705�N�A�u���j���̐킢�Ń��C14�����̃t�����X�R��ł����������}�[���{�����݂ɃA�������̓I�b�N�X�t�H�[�h�̐��k15�L���̏��ɂ���A �E�b�h�X�g�b�N�̍L��ȓy�n��^�����B�����ɐV�z����J���g���[�E�n�E�X�̐v�̎d�����A���Ƀ��@���u���͈˗����ꂽ�B �����ł����@���u���́A�z�[�N�X���[�A�Ƃ̋����ł��̐v���s�����B���̃u���j���̎d���̓��@���u���ɂƂ��đf���炵�������k�ł���������ŁA �l�X�ȃg���u���̔����d���ł������B �}�[���{�����̕v�l�T���̍U���I�Ȑ��i�ɂ����āA���܂��s���Ȃ��Ȃ�����A �܂�1711�N�̃g�[���[�}�̏����ɂ��}�[���{�������̂̉�E���������肵�āA�ŏI�I�ɂ́A���@���u���͂��̎d������O����A ���@���u���̎��̒��O�ɁA�z�[�N�X���[�A1�l�̎�Ŋ������ꂽ�B |
�u���j���E�p���X�́A�E�C���X�g���E�`���[�`��(�}�[���{�����A�W�����E�`���[�`���́A�`���[�`���̑c��ɂ�����)�̏o���̒n�Ƃ��Č��݂ł͗L���ŁA �`���[�`���̗c�����̔��̖т������Ă�������A�ό������ƂȂ��Ă��āA�l���K�ꂽ�������x�x�����������Ƃ�����A����ɒ��ւ̗ł��Ă����B �u���j���E�p���X�̕��ʂ́A�L���b�X���E�n���[�h�Ɏ��āA���i�ȃV�����g���J���ȍ\���ŁA��͂�O���[�g�E�R�[�g��^���ɂ��āA �����̓L�b�`���E�R�[�g�A�����̓X�e�[�u���E�R�[�g���T���A�������ɃT�����ƃz�[��������B �L���b�X���E�n���[�h�ł́A �L�b�`���E�R�[�g�ƃX�e�[�u���E�R�[�g(�O�ɂ݂��悤�Ɏ��ۂɂ͌��݂���Ȃ�������)�A�����ăO���[�g�E�R�[�g���F�A�k���A�뉀���Ɍ����ĊJ���Ă���̂ɑ��A �u���j���ł́A�L�b�`���E�R�[�g�ƁA�X�e�[�u���E�R�[�g�́A���S�̃O���[�g�E�R�[�g�Ɍ������āA�͂����ތ`�ɊJ���Ă��āA�O���[�g�E�R�[�g���S�̂̒��S�Ƃ��āA ���ʑS�̂ɋ��S�����������Ă���B �L���b�X���E�n���[�h�Ɣ�r����ƁA��薧�x�̍����Ïk���ꂽ�����̕��ʍ\���ɂȂ��Ă���B |
 
|
|
|---|---|
|
�z�[���ƃT�����̊W�́A�L���b�X���E�n���[�h�Ɠ��������A�L���b�X���E�n���[�h�ł͈꒼���ɓ����ɐL�т��A�p�[�g�����g���A
L���^�ɉ�荞��ŁA����ɏ����Ȓ�����͂����ތ`�ɂȂ��Ă���B �L���b�X���E�n���[�h�Ƃ͈���āA�����̃z�[���̕���������ł��A�ό��q�p�̃G���g�����X�ɂȂ��Ă��āA�l�͂܂������̃z�[���ɓ���B �z�[���͓V��̍����s��ȋ�ԂŁA��������͌����������ށB �˂�����̃A�[�`���ăT�����ɓ���B�A�[�`�̉��̃M�������[�Ŋy�������t���邱�Ƃ��������Ƃ����B �T�����͌����̐H�����Ƃ鎺�Ƃ��Ďg����B�T�����̃h�A�g�̏�̃A�[�`�̃L�[�X�g���̕����́A�L�k�̌`�����Ă���B ���̃h�A��ʂ蔲����Ɠ����̃A�p�[�g�����g�����ɓ����Ă����B ��k�ɐL�т��������͌��݂ƌ��ݕv�l�̎��I�ȃA�p�[�g�����g�ŁA ���̒��S�̔��~�`�ˏo���������������������I�ȃ_�C�j���O�ł���B ���Α��̐������̓�k�ɐL�т��M�������[�ƌĂꂽ�����́A ���@���u���������Č�(1722-25)�A�z�[�N�X���[�A�����ݕv�l�̗v���Ő}�����Ƃ��Đv���Ȃ����������ŁA�����O�E���C�u�����[�ƌĂ�Ă���B |
���ݕv�l�̑��q�T���_�[�����h����1722�N�ɖS���Ȃ��āA���̐}�������}篂����Ɉڂ����ƂɂȂ������߂ŁA�ǖʂɏ��I�����ߍ��܂ꂽ�B ���̐}���ق͍ג���120ft(��36.5m)������̂����A���[�͐����`�œV�䂪�����A�����̂��镔���A�����ɂ͑嗝�̃A�[�`�̓����̌������ɁA ���~�ɓˏo��������������B�܂蕽�ʓI�ɂ͌܂̕����ɕ��߂���Ă���A�L���ȋ�ԍ\���ƂȂ��Ă���B �z�[�N�X���[�A�͂��̒��O(1715�N)�ɃI�b�N�X�t�H�[�h�̃I�[���E�\�E���Y�̃R�h���g���}���قł�͂胊�j�A�[�ȃ��C�u�����[��v���Ă���B �܂��P���u���b�W�̃��j�[�N�ȉ~�`�̐}���فA���h�N���t�E�L�������i���}���j���z�[�N�X���[�A�����Ă����������C�u�����[�ł���B �u���j���̕��ʂ̓L���b�X���E�n���[�h�̔��W�`�ƌ����邪�A�O�ς͑S����������̂ɂȂ��Ă���B�L���b�X���E�n���[�h���D�����A �ÓI�Ȉ�ۂ�^����̂ɔ�ׁA�u���j���͗͋����͓������ӂ��O�ς����Ă���B���@���u�����g���u�j���I�v�Łu��s�I�ȕ��͋C�v�������z���D�ނƌ���Ă���B ���̃��@���u���̍D�݂́A���ɂ̂��̃V�[�g���E�f�����@���i���}�E�j�̒����̗v�ǂ̂悤�ȗʊ��̕\���ɂ�������B �������������܂߂�ƁA�����傫�Ȍ����Q�ɂȂ�킯�����A�e�[���Ń^���[��ɗ������A�S�̂̍\���ɒP���Ȋ�����^���Ȃ��B |
 
|
|
|---|---|
|
���o�[�g�E���F���`���[���́A�u���z�̑��l���ƑΗ����v(�ɓ�������)�̒��ŁA�����̗��ʍ\���ɂ��ĐG��Ă���B �܂�"���ҋ���(�{�[�X�A���h)"�̍��ł́A �g�u���j���E�p���X�̓������t�@�U�[�h�̒����p���B���I���̒[���̒���(�x�C)�́A�����ЂƂ̒��`�ɕ�������Ă��ĕ����I�ɂ͌�������̂ƌ�����(�����̎O�p�j���̉��̂Ƃ���́A �O�̒���(�x�C)���琬���Ă��邪�A���[�̒��Ԃ͊p���ɂ���Ă���ɓ���Ă���)�B���������ו����́A��d���������A�܂Ƃ܂�˂Ă���B �������S�̂Ƃ��Ă݂��ꍇ�ɂ́A���������s���S�����̂��̂��A�ނ��뒆���̒���(�x�C)���������A���G�ȍ\���ɂ܂Ƃ܂�������炵�Ă���B�h �܂�"���G�ȑS��(�f�B�t�B�J���g�E�z�[��)���l������Ӗ�"�̍��ł́A�g�u���j�����ƃz�[�J���E�z�[���̐��ʂ��r����ƁA�O�Ϗ�̋���(�C���t���N�V����)�̂��肳�܂��킩��B �z�[�J���E�z�[���̏ꍇ�A�����̓��Ƃ悭���������ȓ��������ɕ��сA���傫�ȑS�̂��`������Ă���B �e���Ƃ��j���̂����p���B���I���ŁA���ꎩ�̓Ɨ����Ă���B �]���āA�z�[�N�n���E�z�[���́A���ɕ��O�̌����ł���Ƃ�������B ����A�u���j���{�̕��́A�������Ȃ�������Ȃ����f�Ђ�ʂ��āA���l�ȑS�̂������Ă���B �����̃u���b�N�̗��[�̓��́A���ꎩ�͕̂s���S�ł���A��d���������Ă��邪�A�S�̂̒��̈ꕔ�Ƃ��Č������́A�����̃p���B���I���Ɍ������ċ��Ȃ����[���ƂȂ��Ă���A �S�̍\���̒��ŁA�j���̂������������m�łƂ������̂Ƃ���̂Ɋ�^���Ă���B�������������̋����̒��ƁA���̏�̃u���[�N���E�y�f�B�����g���A �Ƃ��ɒ[���̋��ȂƂ��ē����Ă���A�������������邱�ƂɂȂ��Ă���B�����āA���[�ɂ���p���B���I���́A������Ȃ��Ă��Ȃ��B ���̗��R�́A ����炪�䏊�ƉX�ɂł��邩�炾�낤�B ���@���u���̂��̂悤�ȁA�Ώ̌`�ł���Ȃ���g�U�����傫�Ȑ��ʂ����ۂ̕��@�́A �ꐢ�I�O�̃W�F�[���Y�����̕��@�̌p���ł���B�h �f�B�t�B�J���g�E�z�[���Ƃ��Ă̑S�̂ɑ��镔���̊�^�A���ʁA��ނƓˏo�A�ω��ɕx�֊s�A���I�ȃX�J�C���C���B �����̍v���ɂ��Ă�"��d�̋@�\�����v�f"�̍��ŁA���̂悤�Ɏ�肠�����Ă���B �g�����̑����͏C���I�ł���B���Ƃ��A���Y�������������o���o���b�N���z�̕t���Ƃ��A ���@���u���̃u���j���̐~�[����֎�����������̓Ɨ��������蒌���������B |
�����́A���z�I�ɂ͋������͂������̂ƍl����B���㌚�z�ɂ����ẮA�C���I�ł���Ɠ����ɍ\���I�ł�����v�f�͂܂�ł���B�����ƃx���j�[�j���A�ɈႢ�Ȃ��A
�~�[�X�̗p�����C���I��I�^�|�́A��O�ɑ�����̂ł���B�h ���̏��蒌�͓Ɨ����Ă���̂ł���B���̂悤�Ƀu���j���́A�L���b�X���E�n���[�h�ɔ�r���āA�����̃f�U�C���̖��x�������B �`�Ԃ̖ʔ�����V�����g���J���Ȕz�u�ƃe�N�X�`���A�̑��l���B���@���u���ƃz�[�N�X���[�A�́A������u�s�N�`���A���X�N�v�ƌĂ��A ���z���g����"���i"������o�����@�̖���ł������B �z�[�N�X���[�A�́A����Ӗ��Ŋw���I�ŁA�Í��̂������@�ɒʂ��Ă����B�C�^���A�Ɉ�x���s�������Ƃ��Ȃ��̂ɁA�o�ŕ��ɂ���ăC�^���A�̌��z�ɂ��Ă͐��ʂ��Ă����B ��s�̂悤�ȃC���[�W�A�͓����̓��@���u���̂��̂ł������Ƃ��āA�z�[�N�X���[�A�́A�����L�x�ȌÓT�ɂ��Ă̒m���A�f�B�e�[���ɑ���[���o���ɂ���āA ���@���u���̃C���[�W�����ȏ�Ɏ��������Ă������̂ł͂Ȃ����낤���B ���̔����I�O�ɂ���ꂽ�x���j�[�j�i1598-1680�j�ɂ��A�T���E�s�G�g���吹���̗L�i1667�j�A�����āA����ɂP���I�O�� �~�P�����W�F���i1475-1564�j�ɂ��T���E�s�G�g���吹���㕔�̋���t��(�s���X�^�[)�B����炪�A�u���j����50ft(��15m)�̍����������ʂ̃R�����g���̋���I�[�_�[�A �����ė����ɂ݂��锼���̍����̃h���X���I�[�_�[�̘A������R���l�[�h�Ɍĉ�����B �z�[�N�X���[�A�́A�T���E�s�G�g���吹���ōs���Ă��邱���������Ƃ��A ���ʼn�ɂ���Ēm���Ă����B ���[�}���z�ƁA����Ɋ֘A���邷�ׂĂɑ���M��Ȉ�����A�z�[�N�X���[�A�������A�����̏�s�A�Ƃ�킯�G���U�x�X����W�F�[���Y�ꐢ���́A ����������@����͂��߂Ƃ���p���̖��͓I�Ȍ����ւ̋����������A���@���u�����������ƌ�����B������̗v�f����������A ����Ƀ��@���u���{�z�[�N�X���[�A�Ƃ���2�l�̓V�˂̑�z�������z����͂ɂ���āA"�p���R���̖��G�̉h��"�Ƃ����A�u���j���ɗ^����ꂽ�e�[�}�Ƀs�b�^���ƍ������A �����Ă܂�����ȏ�̌��z�����肠�����̂ł���B |
 
|
|
|---|---|
|
�R�D�����h���̂U�̋��� 1666�N�̃����h����̌�A�N���X�g�t�@�[�E��������ɂ���āA�����̋���������ꂽ���A1711�N����Ɂu�T�O�̐V����������������邽�߂̖@�߁v�����肳��A �z�[�N�X���[�A������̐v�ė��̎d��������2�l�̊ē��̂�����1�l�ɔC�����ꂽ�B ����1�l�̊ē��͂��̌㉽����ς����̂����A�z�[�N�X���[�A�̕��́A���ʂ܂ł�25�N�Ԃ��̖�ڂ��ʂ������B �z�[�N�X���[�A�́A���̊ԘZ�̋�������Ă��B���@���u���{�z�[�N�X���[�A�̋�����Ƃ̒��Ńz�[�N�X���[�A���ǂꂾ���d�v�Ȗ������ʂ��������A ������x�A�z�[�N�X���[�A1�l�ɂ�邱�̘Z�̋��������ΐ��ʂ��邱�Ƃ��ł���B ���͖S���b�C��N�Ɠ�l�ŁA����N�̉Ă̈���������āA�O���j�b�W�̃Z���g�E�I���t�B�[�W����ȊO�̌܂̋�������ĉ�����B �A�[�L�e�N�`�������E�f�U�C�����̕t�^�̌��z�}�b�v�̃����h���҂�Ў�ɁA���Ɍ��ĉ�����B ����ɁA��l�Ŋ������Ȃ��玟�X�ƖK�˂čs�����B �r���������p�u�ł́A�������Ă����Ƃ��ƂƖ����Ă��܂��A�X���ɒ��ӂ��ꂽ��������B �قƂ�ǂ̋���Ƃ������͍r��͂ĂĂ��āA���邱�Ƃ��ł��Ȃ������B���������邱�Ƃ��ł����̂́A�u���[���Y�x���[�̃Z���g�E�W���[�W����݂̂ł���B �ĂуW�����E�T�}�[�\�����Ɉ˂�ƁA�z�[�N�X���[�A�̂����Z�̋���ɂ͎��̎O�̗v�f������ƌ����B �P.�����̉e�� ---�C�s�̎�����߂����A���R�������̋����S�����Ă���B �Q.�z�[�N�X���[�A�̕a�I�Ȃ܂ł̌ÓT�ւ̔M�� ---�L�͈͂ɂ킽��ނ̃��[�}���z�̌����B �����Ďq�����݂����e����ւ̋����B�p��Ō�����\��������������悤�ȃ��e����ŕ\�������肵���B �R.�S�V�b�N���z�ւ̉�ڎ ---�S�V�b�N�̍\�����ÓT��`�I�ɕ\�����悤�Ƃ�����A �����I�ɏo���邾���S�V�b�N�I�ȗv�f�������Ă��Ē����I�Ȍ��ʂ��o�����Ƃ���B ���̌X�����ł��\��Ă���̂�����듃�����ł���B ��L�̂T�O�̋���̖@�߂́A�����ƒ��������Ɓu�Α����邢�͂��̑��̓K�ȑf�ނłł��Ă��āA���ꂼ�꓃�܂��͐듃�������A �T�O�̐V����������������邽�߂̖@�߁v�ƂȂ�A �����邢�͐듃�����邱�Ƃ��ŏ�����`���Â����Ă����B | �T�O�̐V��������A�Ƃ��邪���ۂɂ��̖@�߂ɂ���Č������ꂽ�̂͂P�O������Ƃ̋���ł������B ���̓��z�[�N�X���[�A�̂������Z�̋���Ƃ́A���̘Z�ł���B �@�@�O���j�b�W�̃Z���g�E�I���t�B�[�W����(1712-14) �@�A�Z���g�E�W���[�W�E�C���E�W�E�C�[�X�g����(1714-34) �@�B���C���n�E�X�̃Z���g�E�A������(1714-24) �@�C�X�s�g���t�B�[���Y�̃N���C�X�g�E�`���[�`(1714-29) �@�D�Z���g�E�����[�E�E�[���m�X����(1716-27) �@�E�u���[���Y�x���[�̃Z���g�E�W���[�W����(1716-27) �܂��ŏ��Ɍ������̂��@�O���j�b�W�̃Z���g�E�I���t�B�[�W����ł���B����͎��ۂɂ͌��Ă��Ȃ��̂��c�O���B ���ɌÓT��`�I�Ń��[�}�I�ȗ��ʂ����Ă���B �����t�@�T�[�h�̃|�[�e�B�R�͗��[��{���̕t��(�A���^)�������āA �����ɂQ�{�̃h���X���̉~�����Ɨ����ė����A���̏㕔�̃A�[�`���y�f�B�����g�̈ʒu�܂ŗ�������Ă���B ���ɗ͋������[�}�I�ł���B���ʂ̑��ɂ̓z�[�N�X���[�A�̑��̋���ɂ�������s�ލ��ɑ傫�ȃL�[�X�g����������B ���̓z�[�N�X���[�A�̈Ă͏��F���ꂸ�A��ɃW�����E�W�F�C���Y(1716�N���������l�̊ē��ɂȂ���)�ɂ���Č��Ă�ꂽ���̂ł���B ������ƈ������ۂ���̂͂��̂��߂ł���B �A�Z���g�E�W���[�W�E�C���E�W�E�C�[�X�g����́A�B���C���n�E�X�̃Z���g�E�A������ �����ćC�X�s�g���t�B�[���Y�̃N���C�X�g�E�`���[�`�̎O�͂قړ������ɐv���s���Ă���B �N���C�X�g�E�`���[�`�͂��̎O�̒��ł͕ʌn��ɓ��邪�A�A�ƇB�́A���ʓI�ɂ����Ă���B �v����������ƁA�����Ƃ��l�{�̒��Ɏx�����ꂽ�����`�̕����������Ă���B ���̐����`�ɑΉ����ăZ���g�E�A������ł͓V��ɉ~�`���`����Ă���A�Z���g�E�W���[�W�E�C���E�W�E�C�[�X�g����ł́A ���̕����͌������H�[���g�ɂȂ��Ă��āA����ɂ��̊O���Ɏl�̗����K�i�̓�������B �O�ςɂ�����4�{�̊K�i�����A�ˏo���Ă���㕔�Ŕ��p�`�̃����^���ɂȂ��Ă���B �Z���g�E�A������ł́A�|�[�`�����Ƀh�[���������ˏo���Ă��āA���ʂł͂������炳��ɐ��ɊK�i���z�u����Ă���A ���̂��߃G���g�����X�̃I�[�_�[����̕����ɐU��ăt�@�T�[�h�ɓ������o�Ă���B �����Ƃ��o���b�N�I�ȗʊ��Ɖ^�����O�ςɋ�����������B |

  |
|
|---|---|
|
�N���C�X�g�E�`���[�`�́A�����Z�̋���̒��ŁA(���������̂�5����)�ł�����ŁA�������ꂽ����ł���B �Ƃɂ����X�P�[�����A�����h���̒ʏ�̋�������|�I�ɗ��킵�Ă���A�܂����̑傫���ɋ��������B �܂���d�̏�ɁA����ȃ��F�l�V�A���E�E�C���h�E(�����̍L���J�����ɃA�[�`���˂���A���e�̊J�����ɂ͔݂̂���3�A�̊J�����ŁA �Z�����I�̌��z���ɏ��߂Č�����̂ŁA�Z�����A�[�i���邢�̓Z�����A���E���`�[�t�Ƃ��Ă��)�̃��`�[�t�A �����Ă��̏�ɕǏ�̗��ʂ��̂��Ă���B �����čŏ㕔�ɂ̓S�V�b�N���v�킹��듃������B �^�N�V�[��d�b�{�b�N�X�̃T�C�Y�Ɣ�r����Ƃ悭����Ǝv�����A�Ƃɂ����֑�ϑz���I�ɑ傫���B ���͂��̃N���C�X�g�E�`���[�`�����Ă��炻�̖��͂ɜ߂����A�l�̓z�[�N�X���[�A����������D���ɂȂ��Ă��܂����B ��ɃL���b�X���E�n���[�h��v���j�����������Ǝv�����̂��N���C�X�g�E�`���[�`����������ł���B ���������邱�Ƃ��o���Ȃ������̂Ŏʐ^�ł݂邵���Ȃ����A���̃N���C�X�g�E�`���[�`�͓������͋����^���ɂ��ӂ�Ėʔ������ł���B �D�Z���g�E�����[�E�E�[���m�X������܂��@�A�A�Ɠ����悤�ɒ��ň͂܂ꂽ�����`�����S�ɂȂ��Ă���B 3�{1�g�̃R�����g���I�[�_�[�������̍����������x���Ă���A���̐����`�̕������㕔���O���ɓˏo���āA���~�`�̍������`�����Ă���B ���ʂ��܂��ς���Ă���B���ʂ͕Ǐ�ʼn����������X�e�B�P�C�V����(�e�ΐ�)���{����Ă���A�엧�ʂɂ͐[�����A�㉺�̑�������A �k���ʂɂ́A�O�̃j�b�`������B �ǂ���ɂ���͂�A�ʏ�̔�ኴ�o���傫�ȃz�[�N�X���[�A���L�̃L�[�X�g�������Ă��ĕ\����������߂Ă���B �E�u���[���Y�E�x���[�̃Z���g�E�W���[�W����́A�Z�̋���̒��ł���Ӗ��ŃN���C�X�g�E�`���[�`�̎��ɖʔ����B |
�܂����o�[�g�E���F���`�����[�����A
�g���z�̑��l���ƑΗ����h�̒��ł��̋���ɂ��ė��ҋ���(�{�[�X�E�A���h)�̍��ŐG��Ă���B �g�u���[���Y�x���[�̃Z���g�E�W���[�W����̔j���̂��������ƕ��ʂ̑S�̂̂���������́A��k�������������Ƃ�A�����̓�������ѓ��A�����̓��w(�Ւd���܂�)�A �����̃o���R�j�[�̌`��Ȃǂ���́A����Ƃ͒������鎲�������̔�d�������Ċ�������B �Η��I�ȗv�f�ƕό`���ꂽ�ʒu�̌̂ɁA���̋���ɑO�㍶�E�̈قȂ闆���^���ʂƁA ��̑Γ��Ȏ������M���V���\�����ʂ̂ǂ�������\�����Ă���B ����ȕ~�n�ƕ��ʂ̏̌��ʁA�����̑Η���(�R���g���f�B�N�V����)�́A �����Ə����ȍ\���ɂ����Ă݂͂��Ȃ��L�����Ƌْ���L���Ă���̂��B�h ������̓|�[�e�B�R�̂���쑤�ł��邪�A���̂��鐼���ɂ��������Ƃ�K�v���������ƃz�[�N�X���[�A�͔��f���A�����̒Z�������q�̌����Ƃ��āA �����̔��~���ɍՒd���Ƃ����B ���斯�͂̂��ɕs�ւ�������1781�N�k���ɍՒd���ڂ������C�A�E�g�ɕύX�����B�]���Ă��̎����̓��̉��̓����͕����ꂽ�B ���̗�Ɠ����悤�ɂ�͂蒆�S�̐����`�������������痧����āA�������`�����Ă���B���̓��̒i��̃s���~�b�h�̌`�������듃���A �y�f�B�����g��������̏�ɂ̂��Ă���B �����ɂ̓W���[�W�ꐢ�̑�������B ���Ƃ��Ƃ͂��̑��Ƀ��C�I���ƃ��j�R�[��������Ă����炵�����A�̂��Ɏ�菜���ꂽ�B ���̐듃�����́A���[�\���E���Ƃ�����̌ꌹ�ƂȂ����n���J���i�b�\�X�̉��A�}�E�\���X�̕�̕����}���A���̂܂܃f�U�C���̌���ɂ��Ă���B �܂��Ƀz�[�N�X���[�A�̍l�Êw�I�����ւ̊S����̉��������̂ł���B �Ñネ�[�}�A�N���X�g�t�@�[�E�����A�����ăS�V�b�N���l�I�ȃo���b�N�̎���ō��������A�z�[�N�X���[�A�Ǝ��̍����i�ł���B �����Z�̋����́A �z�[�N�X���[�A�̒m�I��ƂƂ��Ă̌��z�������Ƃ̊y�������`����Ă���B |


 |
|
|---|---|
|
�S�D�L���b�X���E�n���[�h�̃��[�\���E�� �@1712�N�ɃL���b�X���E�n���[�h�̓@�ق̎d���͈ꎞ���f���A�J�[���C�����̋����͒뉀�̕��Ɉڂ����B �܂����@���u���ɂ��e���v���E�I�u�E�t�H�[�E�U�E�E�B���Y(�l����)�́A�p���f�B�I�v�̗L���ȃ��B���E�A�������R(���g���_)���x�[�X�ɂȂ��Ă���B ���g���_���x�[�X�ɂ������z�́A�p���ɂ͂��̑��ɂ��R�����E�L�����x���v�ɂ��~�A���[�X(1723)�A�o�[�����g�����ɂ��A�`�Y�E�B�b�N�E�n�E�X(1725���H)������B �����̂��������ɂȂ����A�p���f�B�I�́u���z�l���v�̉p���ɂ�����|��o�łƂ����傫�Ȏ������A1715�N�ɋN���Ă���B ���̃e���v���͌��ǁA 1726�N�̃��@���u���̎��̌�A�z�[�N�X���[�A�ɂ�芮�����ꂽ�B �����Ă���3�N��A1729�N�ɂ́A�z�[�N�X���[�A�̐v�ɂ��J�[���C�����ƉƑ��̂��߂̕�A ���[�\���E���̌��݂��X�^�[�g����B�z�[�N�X���[�A�A68�̎��ł���B�������͂�u���z�l���v�̃C�^���A�̐�B�ɔ͂��Ƃ��Ă���B ���Ȃ킿�u���}���e�v�̉~�`�_�a�e���r�G�b�g�ł���B | ���̌����ɂ��ẮA���̊Ԋu����������Ƃ����o�[�����g�����̔ᔻ�����������A ���̋������������[�\���E���ɁA�߂Â��������ْ�����^���Ă���ƁA�l�͊������B �������Ƃ��������A�����������̗v���̈���Ǝv���B �����́A�����h���̘Z�̋���Ɠ����悤�Ƀh�[���̉��̍���(�N���A�X�g�[���[)����̌�����������ł���B �z�[�N�X���[�A�����[�\���E���̊��������邱�Ƃ͂ł��Ȃ������B�`�Y�E�B�b�N�E�n�E�X�̊K�i�ɂ�������̊K�i�́A�o�[�����g�����̗F�l�ł��������J�[���C�����̋`���̑��q�A ���r���\�����ɂ����̂ł���B �z�[�N�X���[�A�́A�����ĖK��邱�Ƃ̂Ȃ������A���[�}�ւ̋������ۂ�����A�ÓT��`���z�̂��܂��܂Ȍ��T��m�I��疗y���Ȃ���A �Ǝ��̗͓����A�ʊ����������āA�p�����z�Ɉ�̋P������������������B �L���b�X���E�n���[�h�A���[�\���E���A�����ău���j���A�N���C�X�g�E�`���[�`�A ���z�������тɈ�ꂽ�����̌��z�́A�p�����z�j�̋��ȏ��̒�����A����P���A�����o���Ă���B |

 |
|
|---|---|
| QUERINI-STAMPALIA FOUNDATION �N�F���[�j�E�X�^���p�[���A�̕��� -Carlo Scarpa�i1908-1978�j ��̂Ђ�̏�ŋP���A��̂悤�ȃN�F���[�j�E�X�^���p�[���A�̒���B ���[���b�p�̒뉀�̒�Ƃ��Ă̓`���I�\���v�f������A ���̂����� �X�J���p�̉��߂ƁA �����Ă����炭���{�뉀�̉e������������~�j�`���A�̐��m�뉀�B �����ăX�J���p�̌��z�Ɍ������Ȃ��g���h�B ����̐��̗���̍s��������ɁA���嗝�́A��̐������� �� ���˂���ג������ʂ̋P���A���炫�炵�������Ȑ��̗���B ���ƌ��A���ƐA���Ɨ̂Ԃ��荇���B ���Ƃ�������B �i�ς낷38�@9106�j |
 |
